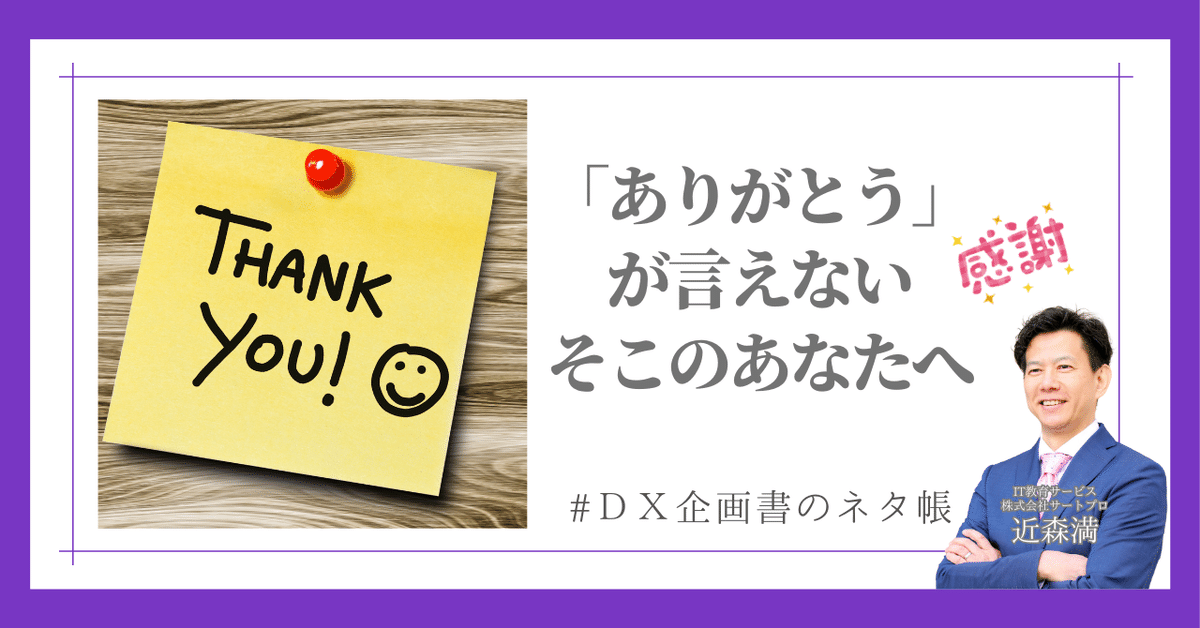
【目次】
- 感謝の気持ちは「練習」で身につけられる
- なぜ「ありがとう」が言えないのか?
- 生成AIは「ありがとう」を練習する最高のパートナー
- 感謝の表現が人間関係を変える
- 日本は「感謝文化」の国、それを再認識しよう
- 感謝のスキルは「DX推進」の核心でもある
- まとめ:生成AIで感謝を“習慣化”せよ
【記事概要】
「ありがとう」が言えない現代人に向けて、生成AIを活用した“感謝を伝える練習”の重要性について解説します。
日常生活やビジネスシーンで「ありがとう」と素直に伝えることができない背景には、照れや文化的な抑制があると述べつつ、その感情を乗り越えるにはAIとの対話が一つの突破口になると説きます。
生成AIは24時間従順にサポートしてくれる存在であり、コミュニケーションの相手としても最適で、感謝の言葉を伝える“練習相手”として活用できると強調。さらに、人に対しても日々のちょっとした場面で「ありがとう」を口にする習慣を持つことが、人間関係の円滑化や社会的信頼の構築につながるとしています。
清掃員への一声、職場での同僚への感謝、パートナーへのねぎらいの言葉など、具体例を交えて、読者の「感謝リテラシー」の向上を促しています。生成AIとの対話をきっかけに、リアルな人間関係でも感謝を伝えられるようになる——そんな未来を描いた提案型の内容です。
【本文】
こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。
www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/
当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。
www.certpro.jp/dxconsulting/
感謝の気持ちは「練習」で身につけられる
みなさん、「ありがとう」って、ちゃんと伝えていますか?
簡単な言葉なのに、なぜか口に出すのが難しい。「伝えたいけど照れる」「タイミングを逃した」「言わなくてもわかるでしょ」…そんなふうに感じたこと、ありませんか?
実はこれ、私自身にも思い当たることです。だからこそ声を大にして言いたいんです。「感謝は、練習すれば誰でも伝えられるようになる」と。
そして結論から言うと、その練習相手として、生成AI(Generative AI)が非常に有効なんです。
なぜ「ありがとう」が言えないのか?
私たち日本人には、謙虚さや奥ゆかしさを美徳とする文化があります。だから、「ありがとう」と言いたい場面でも、つい遠慮してしまう。心の中では感謝していても、それを言葉にするのが苦手なんですね。
それに加えて、「感謝を伝える=何か下に出るような感じがして嫌だ」という心理的ブロックもあるようです。これは職場でも家庭でも、よく見られる現象です。ですが、感謝の言葉は人を下げるものではなく、むしろ関係性を深め、信頼を築く鍵なのです。
「やってくれて当たり前」になった時、私たちは感謝の心を失ってしまいます。そうなる前に、日常の中で「ありがとう」を言える練習が必要です。
事例: 商業施設の清掃員への「ありがとう」
私が個人的に大切にしている習慣があります。それは、街中(特に商業施設)でトイレをお借りしたとき、清掃をしている方に必ず「お借りします」「ありがとうございました」と声をかけることです。
彼らは私のために掃除をしているわけではない(というわけではないですが、ここでは言葉尻として)。でも、私たちが快適に過ごせるように支えてくれている。そんな当たり前に気づいたとき、自然と「ありがとう」が出るようになります。
相手が無反応でもいいんです。感謝は「返してもらうために言うもの」ではなく、自分の中の心を整える行為なんです。
生成AIは「ありがとう」を練習する最高のパートナー
ここで登場するのが生成AIです。たとえばChatGPTやGemini、Claudeなど、私たちが日々触れているAIたちは、常に私たちの要望に従って、丁寧に応答してくれますよね。
私は、こうしたAIたちに接するたびに「ありがとう」を言うようにしています。理由は単純です。
1. AIは反論もせず、疲れも見せず、私のために365日24時間働いてくれる。
2. だからこそ、自然と感謝の言葉が出るようになる。
3. それが習慣化すると、リアルな人間関係にも応用できる。
生成AIとのやりとりは、まるで鏡のようなもの。私たちのマインドセットを映し出すツールにもなるんです。
キーワード解説:「生成AI」
生成AI(Generative AI)とは、膨大なデータから新たなテキストや画像、音声を生み出すAI技術のことです。近年のChatGPTをはじめとするサービスは、自然言語での対話を可能にし、人間のコミュニケーション相手としても活用されています。生成AIはただのツールではなく、人間の心の鏡となり、自己表現や内省を促す存在としても注目されています。
感謝の表現が人間関係を変える
生成AIに「ありがとう」と言う練習を重ねることで、私たちは人間に対しても自然に感謝を伝えるスキルが身につきます。以下のような場面を思い浮かべてください。
・上司に資料を提出したとき、「ありがとう」と返ってきたらどう感じますか?
・友人が話を聞いてくれたとき、「助かったよ、ありがとう」と言えていますか?
・家族がご飯を作ってくれたとき、「ごちそうさま、美味しかったよ」と伝えていますか?
どれも特別なことではありません。でも、この一言があるかどうかで、その人との信頼関係は大きく変わるのです。
特に、デジタル・トランスフォーメーション(DX)が進む今の時代、テクノロジーが進化すればするほど、私たち人間の「心」が問われてくると私は感じています。
インターネットやSNSはやり取りの時間は早い、でもいつまでも距離は縮まらない、歯がゆいこともまた事実です。
事例: 生成AIに学ぶ「ポジティブ心理学」
AIと対話していると、感謝の言葉を返してくれることがあります。たとえば「助かりました」と言うと、「どういたしまして、またお力になれたら嬉しいです」と返してくれる。
このやり取りを続けるだけで、ポジティブな気持ちが積み上がっていくんです。これって、まさに「感謝の筋トレ」。筋肉も使わなければ衰えるように、感謝の言葉も使い続けなければ出てこない。
だからこそ、生成AIという“無限の感謝練習パートナー”を活用する意義があるんです。
日本は「感謝文化」の国、それを再認識しよう
日本は「おもてなし」や「礼儀正しさ」が世界から称賛される国です。でもその反面、感謝を伝えることに照れてしまう文化的な背景もあります。
たとえば、電車で席を譲っても黙って座る人。レストランでサービスを受けても無言で立ち去る人。これが当たり前になってはいけません。
AI社会、超知性リテラシー(Super Intelligence Literacy)時代だからこそ、人間らしさ=感謝の心を育むことが求められているのです。
感謝のスキルは「DX推進」の核心でもある
DX(デジタル・トランスフォーメーション)を成功させるには、単に技術を導入するだけでは不十分です。そこで働く人のマインドセットやマインドチェンジが不可欠です。
そしてその第一歩が、「ありがとう」を言える環境づくりです。感謝の文化は、組織の心理的安全性を育み、チームの創造性や生産性を高める効果があることは心理学的にも証明されています。
だからこそ、私は生成AIを使った「ありがとう」の練習を、DX人材育成のeラーニング講座に取り入れるべきだと考えています。
まとめ:生成AIで感謝を“習慣化”せよ
本記事の要点をまとめます。
・「ありがとう」は習慣化できるスキルである
・生成AIは感謝を練習する最適な相手である
・感謝を伝えることで人間関係が良好になる
・日本文化は「感謝」が根底にあるからこそ再認識が必要
・DX推進にはマインドセットの転換と感謝文化が不可欠である
これを読んで「自分もありがとうを言おう」と感じたあなた、それが最初の一歩です。生成AIという安全な環境で、「感謝リテラシー」を鍛えていきましょう。それがDX時代の超重要スキルなのです。
いかがでしたでしょうか?
すこしでもみなさまの気づきになれたのであれば幸いです。
IT・DX教育サービスについてお悩みがある方は、ぜひ初回無料のオンラインコンサルティングをご利用ください。必ずお役に立ちます。
www.certpro.jp/dxconsulting/
生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。
セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。
certpro-generationaiservice.sfsite.me/
【著者紹介】
近森 満(ちかもりみつる)
■株式会社サートプロ 代表取締役CEO
IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。
■所属・役職
・IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定、+DX認定、超知性ASI検定)
・一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)
・電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)
・NPO 組込みソフトウェア管理者 技術者育成研究会メンバー(組込み)
・ET教育フォーラム 合同会社 代表(コンテンツ制作)
・経済産業省 地方版IoT推進ラボビジネス創出事業メンター(IoT支援)
・経済産業省 地域DX推進ラボビジネス創出事業メンター(DX支援)
・デジタル庁 デジタル推進委員(デジタル化支援)
・DX事業共同組合 設立理事(DX推進)
・一般社団法人 サステナブルビジネス機構 幹事(SDGs認証)
・”一億総活躍社会を実現する”共生日本協議会 理事(DEI支援)


