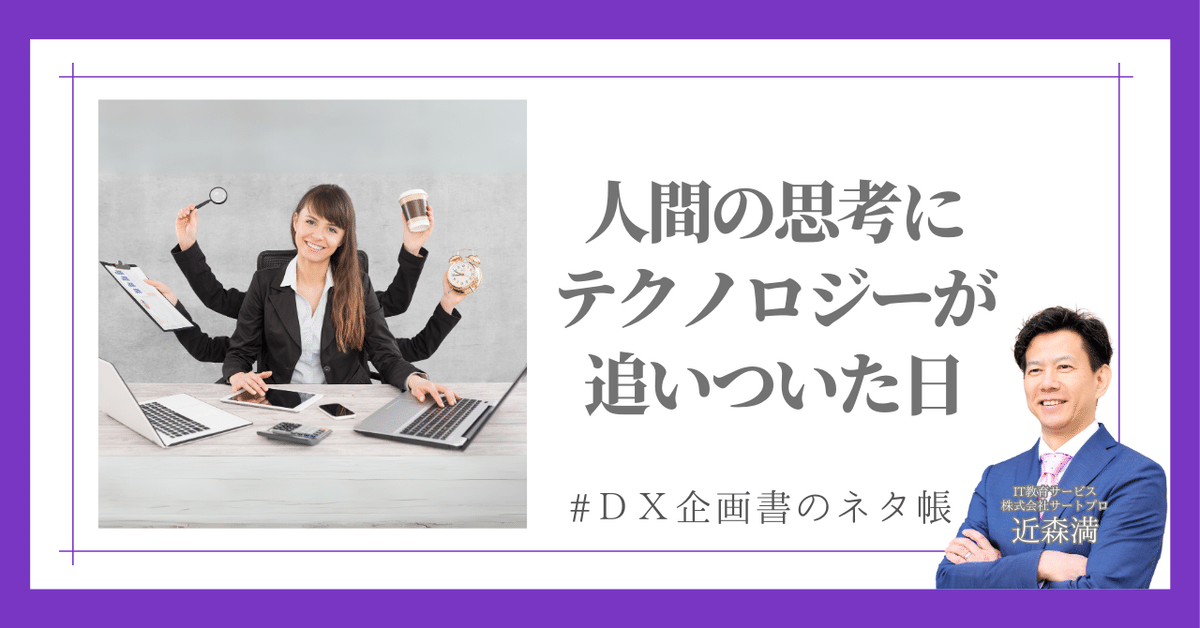
【目次】
- 思考と現実のギャップがついに埋まった
- AIという“拡張装置”の衝撃
- スキル・トランスファー理論が現実に
- 1億総ディレクター時代と創造性の再定義
- AI時代のマインドセットと未来像
- テクノロジーの社会インフラ化と創造の速度革命
- まとめ:創造性を活かすための新しい前提
【記事概要】
生成AIの登場により、人間の思考とテクノロジーの間にあった「ギャップ」が劇的に縮まった今、私たちは新たな時代の入り口に立たされています。
本稿では、「思っているのにできなかったこと」が、いかにして生成AIによって可能になりつつあるかを、近森満自身の草サッカー経験やビジネス現場の事例と重ねて語ります。頭で描いたアウトプットが瞬時に具現化されるという“アウトプット革命”の到来。
そしてそれがもたらす自由と速度、生産性の変化。それでもなお必要な「人間の創造性」や「足で稼ぐ」実践知の重要性とは?創造性を武器にしたAIとの共創、そして新しい働き方・学び方を模索する読者に向け、実践的なヒントと警鐘を織り交ぜて語られた内容を、お伝えします。
【本文】
こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。
www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/
当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。
www.certpro.jp/dxconsulting/
思考と現実のギャップがついに埋まった
生成AIが本格登場したことで、これまで私たちが
「頭では描けているけど、現実にはできなかった」
ことが、次々と可能になっています。私はこれを、
人間の思考にテクノロジーが追いついた瞬間
だと表現しています。
誰でもスポートをしていて経験があるかと思います。サッカーでフェイントや見事なゴールシーンを頭でイメージできても、体がついてこないという経験をしたことはありませんか?
あるいは、仕事の作業現場、表計算ソフトのExcelを前に「こういう資料が作れれば完璧」とイメージできても、関数やフォーマット作業に手間取り、時間を浪費したことがあるでしょう。
それが今、生成AIを使えば、自分の頭の中にあるイメージを言語化するだけでアウトプットが得られる、くらいになっています。
これはまさに”アウトプット革命”です。
AIという“拡張装置”の衝撃
私自身、子どものサッカーチームでミニゲームに加わるとき、頭では三苫選手のようなフェイントができる気がしても、現実の動きはまるで追いついていません(笑)。この「知覚−行動ギャップ」こそ、人間の本質的な課題です。
同じことがビジネスでも言えます。資料作成やアイデア出し、学習設計など、頭の中では完璧な完成形を描けても、それを現実化するには訓練・知識・時間・お金が必要でした。
ところが、生成AIはこのギャップを一気に縮めました。思考→言語→成果物、というプロセスが“言葉にする”だけで成立してしまうのです。
「魔法の玉手箱」「打ち出の小槌」とも言える存在。それが生成AIです。
事例: フェイントとExcelのジレンマ
・サッカーで描いた「フェイントしてゴール」の理想像
・Excelで構想した「完璧な報告書」
いずれも、「頭の中にはあるのに、実行が難しい」。これが人間の限界でした。しかし、生成AIを使えば、「そのゴールイメージ」を言葉にすることでアウトプットが得られます。これは創造の民主化です。
スキル・トランスファー理論が現実に
教育心理学の世界では「スキル・トランスファー理論」という概念があります。学習した知識を異なる場面に応用するためには、「媒介」が必要だという考えです。では、その媒介は何か?
私は、生成AIこそが媒介の役割を担っていると考えています。自分の中にある知識や構想を言葉で表現することで、それがコードになったり、スライドになったり、文章になったりする。これは、これまで専門家しかできなかったことです。
1億総ディレクター時代と創造性の再定義
いまや、誰もがAIを活用することで「ディレクション」できる時代です。アイデアを言葉にしてAIに投げれば、成果物が返ってくる。これは1億総ディレクター時代の到来を意味します。
ただし注意点もあります。過信は禁物です。生成AIのアウトプットを鵜呑みにしてしまえば、現実との乖離が新たな問題を生む可能性もあります。足を使って情報を集める、他者と議論して裏を取る、といった「人間的な営み」があって初めてAIは有効に機能するのです。
事例: 「足で稼ぐ」スキルの重要性
営業で「足で稼ぐ」とは、実際に顧客のもとへ足を運び、情報を得て、信頼を積み上げていくこと。今もこの力が失われてはいけません。
生成AIで得た情報をそのまま使っても、それはまだ「情報」であって「知識」でも「知恵」でもありません。それを文脈に応じて活用し、行動につなげる力が、これからの人間に求められるリスキリングの要素です。
AI時代のマインドセットと未来像
技術的にはすでに人間の思考速度を追い越しつつある生成AI。しかし、だからこそ大切なのがマインドセットの転換=マインドチェンジです。
「AIをどう使い倒すか?」という視点ではなく、「AIをどうパートナーとして位置づけるか?」という視点に変えていく必要があります。
それは、AIを“使役する道具”ではなく、共創する相棒とする考え方。そして、テクノロジーを前提とした新しい働き方、学び方、遊び方、創り方へと移行する覚悟です。
テクノロジーの社会インフラ化と創造の速度革命
今後、生成AIは資料作成やスケッチ、ビジネスアイデア創出、学習支援などあらゆる領域で人間の拡張装置=外部脳として社会に浸透します。
それは、パソコンやスマホと同様に、「使えるのが当たり前」になることを意味します。つまり、生成AIは社会のインフラになります。
「読み・書き・そろばん」 → 「読み・書き・生成AI」
この変化は単なる効率化ではなく、創造プロセスそのものを高速化するという点で本質的です。想像→設計→実行→成果、のサイクルが飛躍的に短縮されます。
まとめ:創造性を活かすための新しい前提
今回の話の本質は、創造性とテクノロジーの融合が不可避な時代において、我々は何を学び直す必要があるのか?という問いです。
AIは私たちの想像力をカタチにする道具ですが、それを使いこなすには、超知性リテラシー、プロンプト設計スキル、批判的思考といった「新しいスキルセット」が必要です。
そして何よりも、自分の考えを言葉にして他者と共有する力=アウトプット力が問われる時代になっているのです。
これからのDX推進において、生成AIは単なるツールではありません。共創のパートナーであり、思考と行動の橋渡し役であることを、企画書の前提として盛り込んでいきましょう。
いかがでしたでしょうか?
すこしでもみなさまの気づきになれたのであれば幸いです。
IT・DX教育サービスについてお悩みがある方は、ぜひ初回無料のオンラインコンサルティングをご利用ください。必ずお役に立ちます。
www.certpro.jp/dxconsulting/
生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。
セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。
certpro-generationaiservice.sfsite.me/
【著者紹介】
近森 満(ちかもりみつる)
■株式会社サートプロ 代表取締役CEO
IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。
■所属・役職
・IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定、+DX認定、超知性ASI検定)
・一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)
・電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)
・NPO 組込みソフトウェア管理者 技術者育成研究会メンバー(組込み)
・ET教育フォーラム 合同会社 代表(コンテンツ制作)
・経済産業省 地方版IoT推進ラボビジネス創出事業メンター(IoT支援)
・経済産業省 地域DX推進ラボビジネス創出事業メンター(DX支援)
・デジタル庁 デジタル推進委員(デジタル化支援)
・DX事業共同組合 設立理事(DX推進)
・一般社団法人 サステナブルビジネス機構 幹事(SDGs認証)
・”一億総活躍社会を実現する”共生日本協議会 理事(DEI支援)


