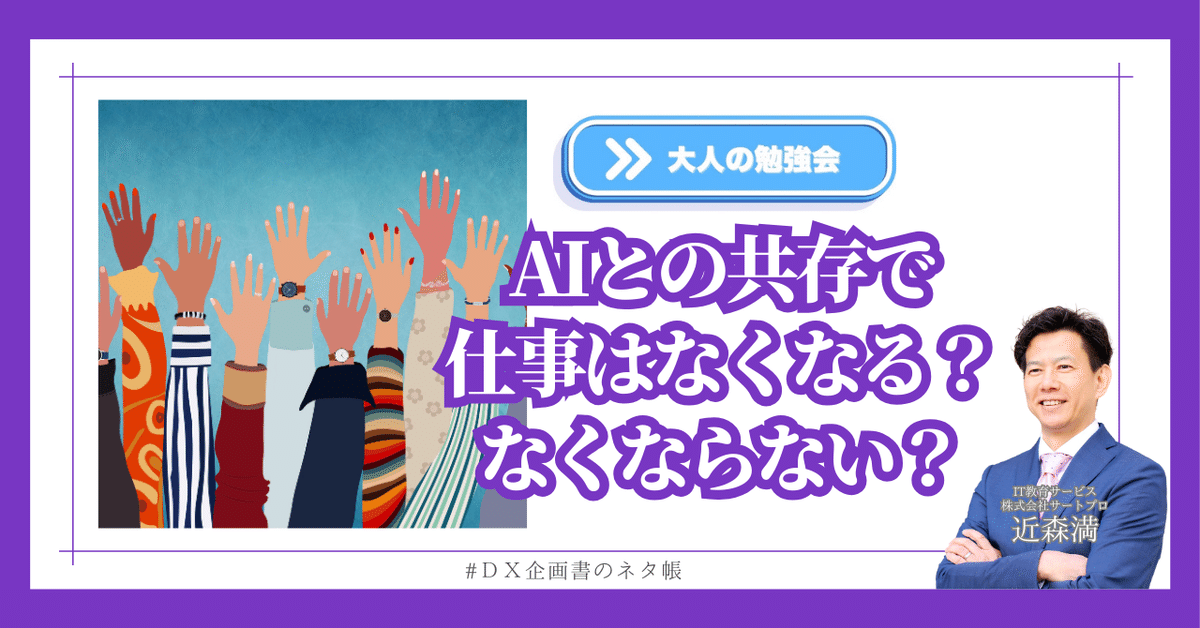
【記事概要】
AIとの共存は、私たちの仕事を本当に奪ってしまうのか?そんな問いに対し、「仕事はなくならない」と力強く語る近森満氏。今回の勉強会では、AI時代における働き方の変容と可能性について、馬車から自動車への変化を例にとりながら、「なくなるのは仕事ではなく“業務”や“作業”である」という視点を提示。営業職の役割や、IT・AIが代替できない人間ならではの価値にも言及し、変化に適応するためのマインド・トランスフォーメーションの重要性を説きます。
単に恐れるのではなく、共存するためのリスキリングとキャリアシフトをどう捉えるかが、AI時代における未来の働き方を左右する。この記事では、生成AIやDX推進を見据えた「仕事の未来」のヒントを、具体的かつ実践的に探っていきます。
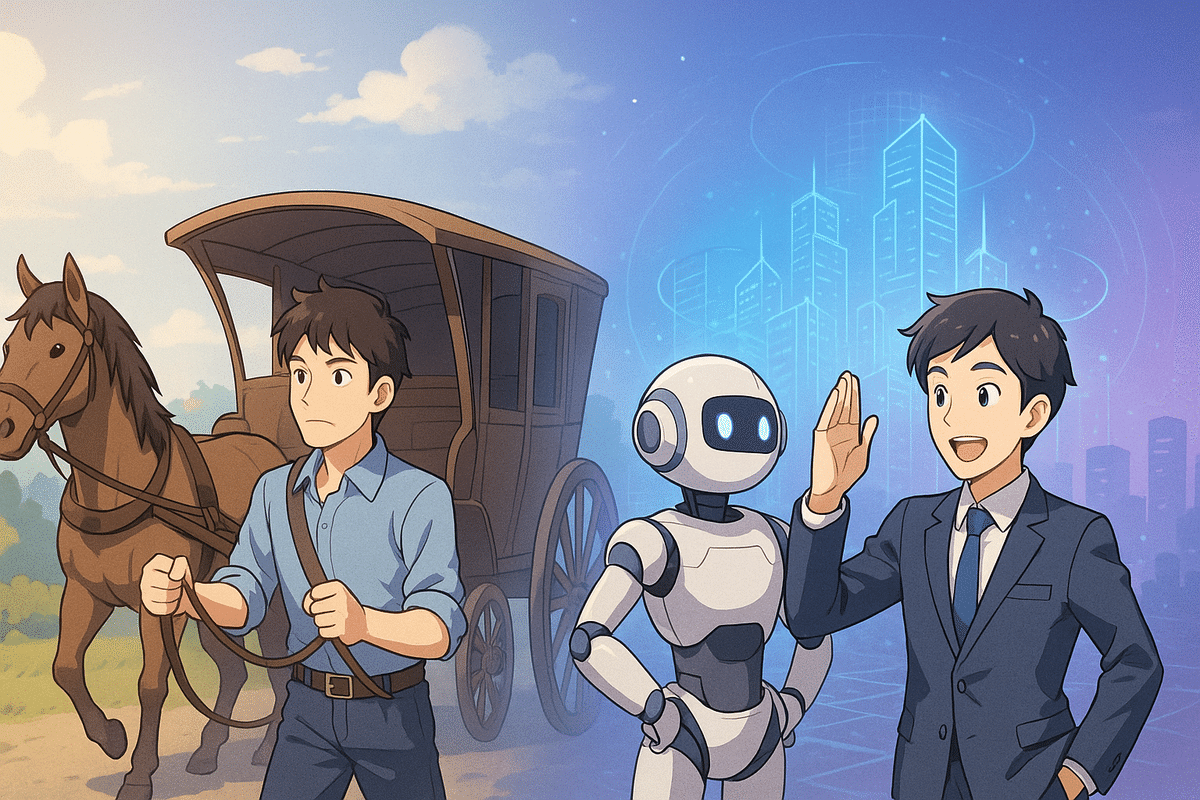
【著者情報】
こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。
www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/
当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。
www.certpro.jp/dxconsulting/
AIで仕事はなくなる?という幻想
「AIが進化したら、人の仕事はなくなる」と、そんな不安を抱える人は多いかもしれません。
しかし、結論から言うと「仕事はなくならない」のです。なくなるのは、今までの“業務”や“作業”のやり方です。
私たちは今、デジタル三兄弟と呼ばれる3つの波に直面しています。
それは
「デジタイゼーション(Digitization)」
「デジタライゼーション(Digitalization)」
「デジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation)」の3つ。
このプロセスの中で、アナログな作業がデジタル化され、やがて業務の全体像が再構築されます。
「じゃあ、それによって仕事がなくなるのでは?」という懸念はもっともですが、そこで止まってはいけません。
馬車と自動車の例に見る“仕事の本質”
ここで、少し歴史をさかのぼってみましょう。かつて「馬車」が交通の主役だった時代がありました。
その時代、自動車が開発されたとき、多くの人がこう言ったそうです。
「馬車の仕事はなくならないよ」「自動車なんて信用できない」
しかし、今どうでしょう?街中で馬車を見かけることは、ほとんどありません。
事例: 馬車から自動車へ―“役割”は変わる
馬を育てる人、馬車を整備する人、馬車を運転する人たちの“作業”は、確かに姿を消しました。
でも、「移動手段を提供する」という“目的”は消えませんでした。
結果として、タクシー運転手やガソリンスタンドなど、新しい仕事が生まれたのです。
つまり、「役割は変わるが、本質的な仕事は形を変えて続いていく」ということ。
これはAIにも同じことが言えます。
AIによってなくなるのは「作業」や「業務」
生成AIの登場によって、ルーティン業務は確かに自動化されていきます。
たとえば:
・納期の調整 → チャットボットやRPA
・情報共有 → CRMや顧客ポータル
・データ分析 → BIツールやAI解析
これらは「業務の自動化」です。
でも、「人が行うべき仕事」は、まだまだ数多く残っています。
たとえば営業職。電話連絡や納期調整はシステムに置き換えられても、顧客との信頼関係構築や交渉・提案はAIに任せるわけにはいきません。
“仕事”とは何か?定義から考える
そもそも「仕事」って何でしょうか?
私はこう考えます。
「誰かの課題を解決し、対価を得る行為」
つまり、価値提供の対価としてお金や信頼を得ること。
逆に言えば、価値提供ができる限り仕事は生まれ続けるのです。
では、どうやって価値を提供するか?
それが今、「マインド・トランスフォーメーション」というキーワードで問われています。
事例: 窓ふきの少年たち
海外では、信号待ちしている車に勝手に水をかけて窓ふきをして「チップちょうだい」と言ってくる子どもたちがいます。
これは“勝手に作業した”ことへのチップ要求であり、「依頼されていない仕事」の典型例です。
ここからわかるのは:
・価値を感じた人が対価を払う
・文化やルールで「それは仕事かどうか」が決まる
この視点はAI時代の「仕事の本質」を考えるうえで非常に重要です。
参考:AIに奪われにくい職業
こちらの記事、AIに奪われにくい職業の話が参考になります。
デジタルとの共存が生む“新しい仕事”
では、AIと共存することでどんな新しい仕事が生まれるのでしょうか?
代表的なものを挙げてみましょう:
・プロンプトエンジニア:
AIに最適な指示を出す職種
・AI活用コンサルタント:
業務プロセスをAIで最適化する人材
・生成AI教育者:
企業向けにAIリテラシーを教える講師
・マインド・トランスフォーメーション支援者:
社員の意識変革を支援するファシリテーター
つまり、新しいスキルセットに応じた仕事はどんどん増えているのです。
「なくなる仕事リスト」に怯える前に
「10年後になくなる仕事」という記事を見て、不安になる人は多いでしょう。
でも大事なのは、「その仕事の目的と価値」に着目すること。
・単にデータを入力するだけの作業 → AIに置き換えられる
・データからインサイトを引き出す思考 → AIでは不完全
この差を見極めるには、自分自身の「仕事の中にある“人間性”や“創造性”」を可視化することが重要です。
事例: 営業の変化と進化
たとえば営業職。
従来は飛び込みや電話が中心でしたが、今は顧客がWebで自分で情報を集められます。
それでも営業はなくなっていません。なぜなら、「人を動かす力」はAIには代替できないからです。
AIは「面倒くさがり屋の人類」が生んだモンスター
ちょっと笑える話をします。
AIって、実は「面倒なことをやりたくない人間」が生んだ“モンスター”なんですよね(笑)。
・めんどくさい計算 → コンピューター
・面倒な仕分け作業 → RPA
・めんどくさい資料作成 → 生成AI
でも、そのおかげで私たちは「もっと人間らしい仕事」に集中できるようになったとも言えます。
「苦労=価値」ではない時代が来ているのです。
人間にしかできないことを見つめなおす
では、人間にしかできないことって何でしょう?
・感情の理解と共感
・文脈を汲んだ判断
・暗黙知の伝承
・未来を創造する力
これらはAIには真似できません。
だからこそ、“人間にしかできないこと”に仕事を寄せていく努力が必要なのです。
まとめ:AI共存時代のマインドチェンジ
AIと共存する未来、それは仕事の終わりではなく、「仕事の再定義」の始まりです。
「作業」にしがみつくのではなく、
「価値提供の本質」を見極め、
新しいスキルとマインドを育てることが、AI時代を生き抜くカギとなります。
未来を恐れるのではなく、未来に向けて“自分の中の変化”を楽しみましょう。
いかがでしたでしょうか?
「仕事がなくなる」と漠然と不安を感じていた方も、「なくなるのは“作業”や“業務”」という視点に立てば、今できることが見えてくるはずです。
大切なのは、自らのキャリアを自分で“設計しなおす”覚悟と行動。
それこそが、AI時代の生存戦略です。
IT・DX教育サービスについてお悩みがある方は、ぜひ初回無料のオンラインコンサルティングをご利用ください。必ずお役に立ちます。
www.certpro.jp/dxconsulting/
生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。
セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。
certpro-generationaiservice.sfsite.me/
キーワードの解説
DX推進
デジタル・トランスフォーメーション(DX)とは、企業や社会がデジタル技術を活用して業務プロセスやビジネスモデルを根本的に変革することを指します。単なるIT導入ではなく、組織のマインドセットや文化を含めた変革が求められます。DX推進では、既存の業務を効率化するだけでなく、新しい価値提供を創出することが重要です。
生成AI
生成AI(Generative AI)とは、文章や画像、音声などのコンテンツを自動生成する人工知能技術のこと。ChatGPTやMidjourney、DALL·Eなどが代表例です。従来のAIがルールに基づいて動作していたのに対し、生成AIは膨大なデータから学習し、創造的な出力が可能です。特にビジネスの自動化・効率化・コンテンツ制作の分野で活用が急拡大しています。
マインド・トランスフォーメーション
単にスキルを変えるのではなく、価値観や考え方、働き方そのものを根本から変えるプロセスを指します。DXやAI導入が進む現代では、「業務が変わる」ことよりも「人の意識が変わる」ことが成否を分ける要素となります。自ら学び、自ら変化する力、すなわち適応力を育むことが、AI時代を生き抜くための“人間力”です。
【著者紹介】
近森 満(ちかもりみつる)
■株式会社サートプロ 代表取締役CEO
IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。
■所属・役職
・IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定、+DX認定、超知性ASI検定)
・一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)
・電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)
・NPO 組込みソフトウェア管理者技術者育成研究会 メンバー(組込み)
・ET教育フォーラム合同会社 代表(コンテンツ制作)
・経済産業省地方版IoT推進ラボ ビジネス創出事業メンター(IoT支援)
・経済産業省地域DX推進ラボ ビジネス創出事業メンター(DX支援)
・デジタル庁デジタル推進委員(デジタル化支援)
・DX事業共同組合 設立理事(DX推進)
・一般社団法人日本サステナブルビジネス機構 幹事(SDGs認証)
・”一億総活躍社会を実現する”共生日本協議会 理事(DEI支援)
・アジャイル開発技術者検定試験コンソーシアム 事務局長(Agile検定)
・一般社団法人国際サイバーセキュリティ協会 事務局長(IACS認定)


