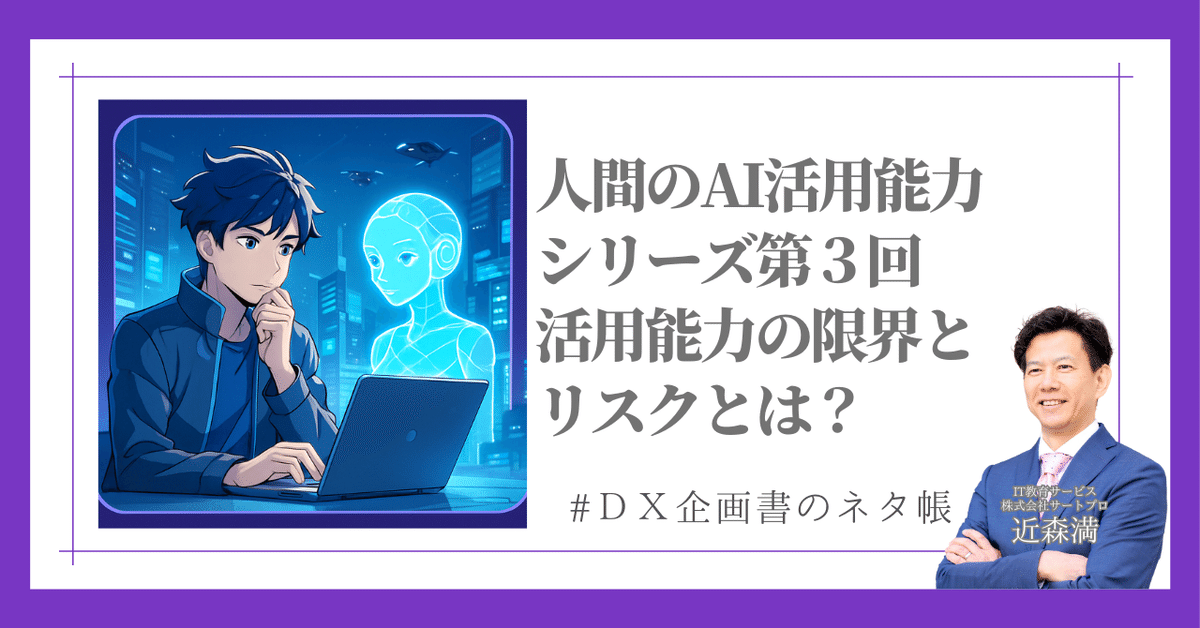
【目次】
- 活用能力が進化する時代の落とし穴
- IQは本当に進化しているのか?
- 「Google効果」が思考力を奪う?
- 技術の進化が人間の「手」を奪う
- テクノロジーに“任せすぎる社会”の先にあるもの
- 「再定義」すべきは、私たち自身
- 成長には限界があるが、視点は進化できる
- 限界を知ることが、活用の第一歩
- まとめ:AI時代の“活用能力”再定義戦略
【記事概要】
人間のAI活用能力シリーズの第3回となる今回は、「人間の活用能力の限界とリスク」に焦点を当て、否定的な視点から深掘りしていきます。これまでAIの進化を肯定的に捉え、その恩恵について語ってきた一方で、今回は逆に“AIに任せすぎる”ことによって生じる人間の能力低下や依存リスク、社会的格差の拡大といったネガティブな側面に注目します。
リバース・フリン効果として知られるIQの低下傾向や、便利さの裏に潜む「思考力・記憶力」の衰退、さらには人間の技術スキルや経験が失われる危険性についても実例を交えて解説。加えて、自動化が進む中での人間の“再定義”や自己のあり方の問い直しも提起されます。
生成AIやAGI時代の幕開けに際し、私たちがどのようにテクノロジーと向き合い、自らの活用能力を保ち、社会で役立つ存在であり続けるためには何が必要なのかを、リアルな視点とともに考察します。

【著者情報】
こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。
www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/
当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。
www.certpro.jp/dxconsulting/
活用能力が進化する時代の落とし穴
生成AIの登場以降、AIを“使いこなす力”を高めることが、多くの人にとって日常的なテーマとなってきました。確かに、私自身もChatGPTのようなAIを業務に取り入れ、作業の効率化やアイデア創出に役立てています。人間のAI活用能力は、ある意味で人生を先取りするような力にもなりうるでしょう。
しかし今回は、その“活用能力”の裏側にある限界とリスクについて、否定的な視点からあえて深掘りしたいと思います。便利さに慣れすぎた私たちは、果たして本来持つべき「思考力」や「判断力」を失っていないでしょうか?
IQは本当に進化しているのか?
一部の研究では、人類のIQは20世紀に入ってから上昇を続けてきたとされています。これは「フリン効果」と呼ばれる現象です。しかし近年、このフリン効果に“逆回転”が起きているという「リバース・フリン効果」が指摘されています。特に先進国ではIQの平均値が低下傾向にあるというデータもあるのです。
事例: 言語力・数的推論の低下傾向
このリバース・フリン効果では、特に「言語力」や「数的推論能力」が下がっているという指摘があります。その背景には、テクノロジーによって人間の“脳を使う機会”が減っていることが影響している可能性があります。
記憶する必要がない。計算も検索もツール任せ。いつの間にか私たちは“考えなくていい人間”になってしまっているのかもしれません。
参考:リバース・フリン効果とは
20世紀を通じて観測されていたIQの平均スコア上昇(フリン効果)に反して、近年一部の先進国でIQが低下し始めている現象です。特に若年層でその傾向が強く、原因としては教育格差の拡大、栄養状態や社会環境の悪化、さらにはスマートフォンや検索エンジンへの依存により記憶力や思考力を使う機会が減少していることが挙げられます。知識そのものよりも“情報の場所”を記憶する傾向が強まるなど、現代人の知的活動の質の変化が影響していると考えられています。
名前はこの現象を研究したニュージーランドの政治学者ジェームズ・R・フリンに由来しています。
「Google効果」が思考力を奪う?
Googleに代表される検索エンジンや、AIによる答えの自動生成によって、私たちは“情報そのもの”よりも“情報の場所”を覚えるようになってきました。これは「Google効果」とも呼ばれています。
確かに便利です。しかし、物事を覚える、考える、深めるというプロセスがなくなってしまえば、人間の知性はテクノロジーに代替されるだけでなく、退化していく可能性すらあるのです。
技術の進化が人間の「手」を奪う
AIによる自動翻訳や自動運転。こうした技術は、人間が学ばなくてもよい世界をもたらします。「語学を学ばなくても翻訳がある」「運転免許を取らなくても自動運転がある」。確かに効率的ですが、その先には“技術の衰退”というリスクも潜んでいます。
事例: 航空業界での自動操縦とスキル低下
航空機の自動操縦技術の発達によって、パイロットが危機的状況で判断・操作する能力が低下しているという報告があります。これは「任せすぎることの代償」と言えるかもしれません。
テクノロジーに“任せすぎる社会”の先にあるもの
自動化やAI活用の拡大は、私たちの生活を便利にする一方で、「人間らしさ」や「自分で考える力」を徐々に奪っていきます。情報を調べるのではなく、出力された答えを“選ぶだけ”の存在になってしまったら、それはもう“使う”ではなく“使われている”のかもしれません。
「再定義」すべきは、私たち自身
ここで重要なのは、人間が自らを再定義するという視点です。テクノロジーが進化する時代において、「私はどんなスキルを持ち」「どこに価値を提供できるのか」という視点を忘れてはなりません。
変化が激しい時代に、「変わらない自分」でいることはリスクでしかありません。むしろ、「何を変えるか」「何を変えないか」を主体的に選び取る必要があります。
成長には限界があるが、視点は進化できる
人間の能力には限界があります。私自身、年齢や経験とともにスキルの向上速度が落ちてきたことを感じています。だからこそ、テクノロジーを横に置く“並走型”の活用が必要なのです。
AIを“外部脳”として活用し、アウトプットの質を高めることで、自己の成長を支援する。それが現代の“活用能力”の本質ではないでしょうか。
限界を知ることが、活用の第一歩
活用能力には限界がある。しかし、限界を知ることこそが、真の活用能力の出発点だと私は考えています。自分にできること、できないこと。それを見極めてテクノロジーと役割分担をする。それが“人間とAIの共生”に必要なマインドセットです。
事例: 検定制度を通じたスキルの可視化
私が関わっている「+DX認定」や「IoT検定」は、スキルを数値や資格で“見える化”する仕組みです。これは、単なる資格取得ではなく、変化に対応する力=適応力を測る取り組みそのものです。
まとめ:AI時代の“活用能力”再定義戦略
生成AIやAGI(汎用人工知能)が進化する時代、人間の役割はますます問い直されます。企業にとっては、社員の“AI活用能力”をいかに育て、かつ“依存にしない設計”をするかが重要な戦略になります。
“便利さの裏にあるリスク”に目を向け、「活用とは何か?」を改めて問い直すこと。それこそが、真のデジタル・トランスフォーメーションに求められる企画視点なのです。
いかがでしたでしょうか?
すこしでもみなさまの気づきになれたのであれば幸いです。
IT・DX教育サービスについてお悩みがある方は、ぜひ初回無料のオンラインコンサルティングをご利用ください。必ずお役に立ちます。
www.certpro.jp/dxconsulting/
生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。
セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。
certpro-generationaiservice.sfsite.me/
―――
全5回エピソード:
【人間のAI活用能力 第1回】AIの進化と人間の“活用能力”とは何か? 〜定義と歴史的背景〜
【人間のAI活用能力 第2回】“活用能力”は進化しているのか? 〜肯定的な視点とその根拠〜
【人間のAI活用能力 第3回】“活用能力”の限界とリスクとは? 〜否定的な視点に基づく考察〜
【人間のAI活用能力 第4回】AIと人間は融合するのか? 〜シンギュラリティに関する専門家の見解〜
【人間のAI活用能力 第5回】 最終回 人間の未来と“活用能力”のゆくえ 〜可能性と課題を見据えて〜
―――
【著者紹介】
近森 満(ちかもりみつる)
■株式会社サートプロ 代表取締役CEO
IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。
■所属・役職
・IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定、+DX認定、超知性ASI検定)
・一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)
・電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)
・NPO 組込みソフトウェア管理者 技術者育成研究会メンバー(組込み)
・ET教育フォーラム 合同会社 代表(コンテンツ制作)
・経済産業省 地方版IoT推進ラボビジネス創出事業メンター(IoT支援)
・経済産業省 地域DX推進ラボビジネス創出事業メンター(DX支援)
・デジタル庁 デジタル推進委員(デジタル化支援)
・DX事業共同組合 設立理事(DX推進)
・一般社団法人 サステナブルビジネス機構 幹事(SDGs認証)
・”一億総活躍社会を実現する”共生日本協議会 理事(DEI支援)
・アジャイル開発技術者検定試験コンソーシアム 事務局長(Agile検定)


