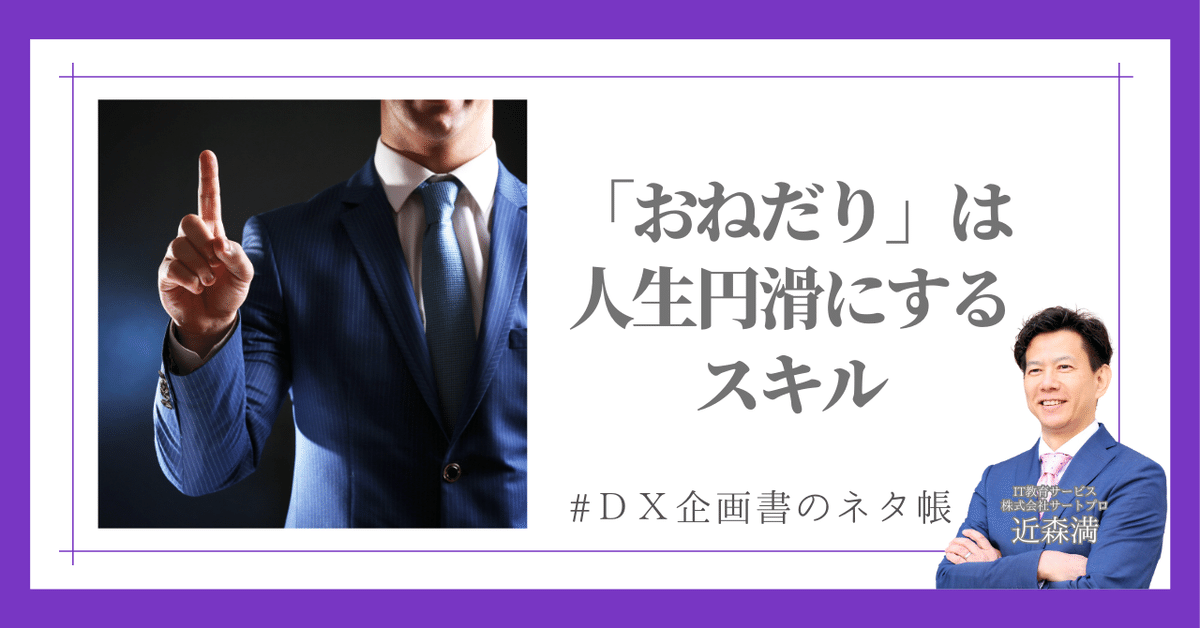
【目次】
- 「おねだり上手は人生上手」
- ギブアンドテイクの本質を見直す
- お願いが下手な人の「思い込み」という壁
- 「おねだり」のスキルはDX時代の必須能力
- お願い力を育てる3つのコツ
- お願いできる人は信頼される人
- まとめ:お願いできる人が強い理由
【記事概要】
「おねだり上手は人生上手」
この一見甘えた言葉には、実は人間関係やキャリア形成、さらにはDX時代における重要なビジネススキルが隠されています。
本記事では、近森満が語る「おねだりできる人=頼れる人」がいかにして信頼を築き、人生をうまく進めているか、その心理と行動の秘密を深掘りします。
ギブアンドテイクの本質、お願いが下手な人の心理構造、そしてお願い上手になるための実践的なコツまで、具体的なエピソードやたとえ話を交えてわかりやすく解説。さらに生成AI時代におけるマインドセットの変革や、リスキリングとの関係性も掘り下げます。
キャリアアップを目指すビジネスパーソン必読の内容です。
【著者情報】
こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。
www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/
当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。
www.certpro.jp/dxconsulting/
「おねだり上手は人生上手」
「お願いできる人」は、なぜか人生もうまくいく——そんな印象を受けたことはありませんか?頼るのが苦手、甘えてはいけない、そんな風に自分を律している人も多いでしょう。けれども、実は「おねだり上手」はただの甘え上手ではなく、極めて高いコミュニケーション能力と信頼構築力を持つ賢い人だということが、近森満の語りから浮かび上がってきます。
お願い上手になるためには、単に「何かをねだる」のではなく、相手の心地よさや信頼感に着目した深い人間理解と自己認識が必要です。そしてこれは、ビジネスシーンにおける交渉や人材育成、DX推進の現場でも応用できる極めて実践的なスキルなのです。
ギブアンドテイクの本質を見直す
「ギブアンドテイク」の概念はよく耳にしますが、ここにある心理的なダイナミズムをどこまで理解しているでしょうか?
近森が紹介するアダム・グラントの「ギバー/テイカー/マッチャー理論」によれば、与える人(ギバー)、受け取る人(テイカー)、そしてそのバランスを取る人(マッチャー)の3タイプに人間は分類されるといいます。
特筆すべきは、「お願いできる人=テイカー」であるにもかかわらず、周囲の人に「ギバーとしての行動」を促す不思議な力を持っているという点です。そのカギとなるのが、信頼と人間関係の文脈構築です。
事例: クレクレタコラと「お願い力」の違い
日本の古いテレビ番組『クレクレタコラ』のように、ひたすら何でも「ちょうだい、ちょうだい」と要求するだけでは、当然嫌われます。しかし、お願い上手な人は、断れない魅力や「助けてあげたくなる」雰囲気を自然に纏っています。それは単なる甘えではなく、相手の心を動かす技術なのです。
お願いが下手な人の「思い込み」という壁
一方で、お願いが下手な人には共通する心理的特徴があります。
・迷惑をかけると思ってしまう
・自分でやるべきだと思い込んでいる
・断られるのが怖い
この三重苦により、「お願いをする前」にすでに失敗してしまっているのです。お願いする前の段階で自ら壁を作ってしまう。これが、成長や人間関係構築の妨げになっていることは明らかです。
「おねだり」のスキルはDX時代の必須能力
おねだり=頼ること。それは、協働性・信頼性・柔軟性というキーワードと深く結びついています。
生成AIやAGI(汎用人工知能)が台頭し、人間の業務領域が変容する中で、他者との連携や柔らかな思考の持ち主がますます重視されています。その象徴が「頼れる人=お願い上手な人」なのです。
事例: 行政の窓口で「お願いできる人」になる
たとえば行政窓口では、市民からお願いされたことを受け入れるのが役割です。初対面でもお願いしやすい相手の代表格ですが、そこでも「信頼関係ができているかのような話し方」ができる人は、自然と協力を引き出します。
お願い力を育てる3つのコツ
①タイミングを見極める
お願いするのに適した時間、相手の状態、自分の準備状況を把握しましょう。
②感情を込めすぎない
「迷惑かも」「断られたら怖い」などの感情に飲み込まれないように注意が必要です。
③必ず感謝を伝える
お願いを受け入れてもらったら「ありがとう」は鉄則。信頼関係を構築・強化する最大の要素です。
この3つを意識するだけでも、驚くほどコミュニケーションの質が変わります。
お願いできる人は信頼される人
お願い上手な人は「信頼されているからお願いできる」のではなく、「お願いすることで信頼を育てている」のです。
相手に頼ることで、その人の専門性や誠実さを認め、「あなたを信じている」というメッセージを伝えることができます。
つまり、おねだりは信頼関係を広げる行動でもあるのです。
まとめ(企画書のネタ):お願いできる人が強い理由
本記事の要点は以下のとおりです:
・お願い上手は信頼構築の名手
・お願い下手は先回りして自己否定してしまう
・「お願い力」はDX人材に不可欠なスキルセット
・タイミング・感情の扱い・感謝がカギ
・おねだり=信頼の表現
人にお願いすることは、単なる依存ではなく自己成長と信頼関係構築の戦略的行為であるという視点を持ちましょう。
お願いできる自分を育てる。
それは、デジタル時代を生き抜く新しいマインドセット=超知性リテラシーともいえるかもしれません。
「お願いする=甘える」と考えず、「お願いする=信頼の証」と捉えなおしましょう。
1回断られてもいいじゃないですか。まずは小さなお願いから始めてみること。それが行動の第一歩です。
人生は、お願いで動き出す。
あなたも今日、誰かにひとつだけ、お願いしてみませんか?
「もうひとこえ!」こんなキーワードもおねだりの一つかもしれませんね。
いかがでしたでしょうか?
すこしでもみなさまの気づきになれたのであれば幸いです。
IT・DX教育サービスについてお悩みがある方は、ぜひ初回無料のオンラインコンサルティングをご利用ください。必ずお役に立ちます。
www.certpro.jp/dxconsulting/
生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。
セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。
certpro-generationaiservice.sfsite.me/
【著者紹介】
近森 満(ちかもりみつる)
■株式会社サートプロ 代表取締役CEO
IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。
■所属・役職
・IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定、+DX認定、超知性ASI検定)
・一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)
・電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)
・NPO 組込みソフトウェア管理者 技術者育成研究会メンバー(組込み)
・ET教育フォーラム 合同会社 代表(コンテンツ制作)
・経済産業省 地方版IoT推進ラボビジネス創出事業メンター(IoT支援)
・経済産業省 地域DX推進ラボビジネス創出事業メンター(DX支援)
・デジタル庁 デジタル推進委員(デジタル化支援)
・DX事業共同組合 設立理事(DX推進)
・一般社団法人 サステナブルビジネス機構 幹事(SDGs認証)
・”一億総活躍社会を実現する”共生日本協議会 理事(DEI支援)


