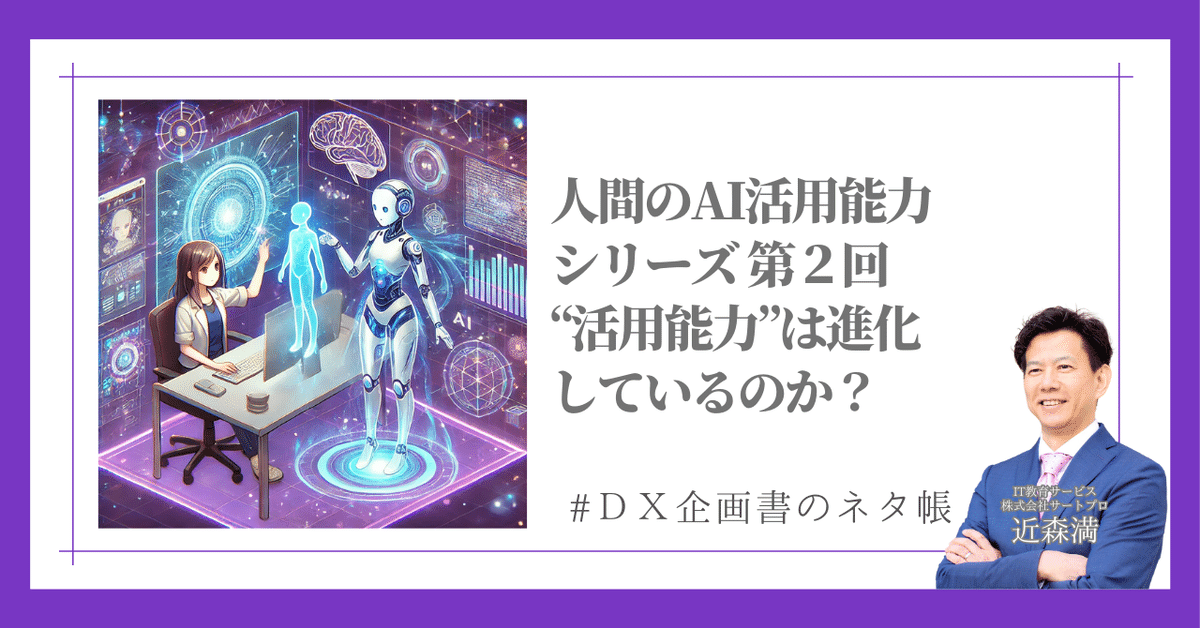
【目次】
- AIは進化し続ける、では人間はどうか?
- “活用能力”はAIを生み、活かす人間の力
- 火を味方につけた知性の歴史
- AIとの協働で“人間はより成長できる”
- 知識へのアクセスが“万人の力”を引き出す
- 人間は“欲求”によって進化する
- AIと共存するための“マインドセット再定義”
- まとめ:人間の進化はAIとの共創にある
【記事概要】
生成AIの発展を背景に、「人間の活用能力は本当に進化しているのか?」という問いが生まれています。本稿では、近森満が肯定的な視点からこのテーマに迫ります。
AIは飛躍的な速度で成長しているものの、その発展を支えているのもまた人間です。火や道具の使用に始まり、現代では生成AIを「道具」として活用し、創薬や将棋、英語学習など様々な領域で人間はAIとの協働によって自己の可能性を広げています。
また、教育の普及やインターネットによる知識アクセスの民主化が、個人の学習能力や問題解決能力を飛躍的に向上させていることも紹介されます。人間の“活用能力”は、知識と技術を組み合わせ、AIとともに未来を切り拓く進化の原動力として、いま再定義されようとしています。
【著者情報】
こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。
www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/
当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。
www.certpro.jp/dxconsulting/
AIは進化し続ける、では人間はどうか?
生成AIが爆発的に進化し、日々新しい技術やサービスが登場する現代。
AIが語られる時、「これからの人間はAIに置き換えられるのではないか?」という不安がつきまといます。しかし、その問いに対し私はあえて肯定的にこう言います。
「人間の活用能力は、今もなお進化し続けている」と。
テクノロジーの進化に触れれば触れるほど、人間の可能性もまた広がっている。今回は、その「進化」を支える根拠と、活用能力の本質について掘り下げていきます。
“活用能力”はAIを生み、活かす人間の力
AIの進化の源泉を辿れば、それを作り出し育てているのは紛れもなく人間自身です。どんなに賢いAIであっても、その背後には人間の創意と試行錯誤がある。そして、今私たちが手にしている生成AIは、始まりに過ぎません。
まだまだ“Day 1”、日々が革新の連続です。
AIがどれだけ賢くなっても、それを“使う力”、つまり「活用能力」こそが人間の優位性なのです。火を起こし、道具を発明し、社会を築いてきたように、人類は技術との共進化を遂げてきました。
この“活用する力”こそが人間の本質であり、デジタル・トランスフォーメーション(DX)時代の要でもあります。
火を味方につけた知性の歴史
火を扱えるのは人間だけです。
それは単に便利だからではなく、「火を制御できる」と理解した知性があったからこそ。
火を見て恐怖や敵と捉えるのではなく、利用価値を見出し、活用する力を人間は持っていたという証明です。
この「活用能力」は、現代においてはAIやデータにも当てはまります。
AI=恐れるものではなく、活かすもの。このマインドチェンジが、新たな時代の人材像を形作るキーワードです。
事例:IQの上昇と“人間の知の進化”
IQスコアは20世紀を通じて世界的に上昇してきました。これは“フリン効果”と呼ばれ、教育の普及や社会の複雑化への適応の結果です。知的な問題解決能力が向上し続けている証拠であり、活用能力が進化している裏付けとも言えます。
AIとの協働で“人間はより成長できる”
AIと人間がタッグを組んだとき、驚くべき成果が生まれます。
たとえばチェスの世界では、人間とAIの混成チームが、AI単体や人間単体のプレイヤーよりも高い勝率を出した例があります。
つまり、AIを“使いこなせる人間”こそが最強なのです。
この考え方は将棋界でも実証されています。
藤井聡太さんのような「デジタルネイティブ ✕ 棋士」は、AIとの壁打ちによって常に自己の戦術をアップデートしており、まさにAIとの共進化の象徴的存在です。
キーワード解説:「AIエージェント」
AIエージェントとは、人間の代わりにタスクを実行するAIです。近年ではチャットボットや仮想アシスタント、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)との組み合わせなどが一般化しています。
ただし、AIエージェントの力を最大化できるかどうかは「人間の活用能力」にかかっていることを忘れてはいけません。
何を目的に、どのように使うか。人間の判断と設計があって初めて、AIは力を発揮します。
知識へのアクセスが“万人の力”を引き出す
AIだけでなく、インターネットやオンライン講座、オープンデータベースなど、誰もが専門情報にアクセスできる時代になりました。
以前は専門家にしか扱えなかった研究論文などの学術情報も、今では誰でも学べる時代です。
生成人工知能を活用すれば、「小学生にもわかるように説明して」とプロンプトを入力するだけで、複雑な情報が一気にわかりやすくなるのです。
事例:英語学習におけるAIの壁打ち活用
私自身も英語学習でAIと“壁打ち”をしてみましたが、非常に効果的でした。発音チェック、言い換え練習、瞬間英作文など、多様な練習が可能です。
AIが苦手を分析し、最適な練習メニューを提案してくれるこの仕組みは、まさに活用能力の進化を象徴しています。
人間は“欲求”によって進化する
なぜ人間は成長できるのか?
それは「欲求」という内的動機があるからです。もっと知りたい、理解したい、うまくなりたい——この欲求が学びを駆動します。
この「欲求喚起 × テクノロジー」の構造こそ、人間がAI時代においても成長し続ける理由です。
そしてその先にあるのは、「AIとの共創」です。人間とAIが互いの得意分野を活かし、協働で価値を生むチームとして新たな成果を出す未来です。
AIと共存するための“マインドセット再定義”
変化に適応するには、考え方そのものを見直す必要があります。
かつて「メールを使わない社会」など想像できなかったように、AIを使わないという選択肢は、今後ますます非現実的になります。
したがって、「AIを使わない」のではなく、「どう使いこなすか」を考える時代です。
事例:「使わない選択」がもたらす機会損失
生成AIを使わないというだけで、ライバル企業より何倍も非効率な作業を強いられる可能性があります。実際に、提案書、議事録作成、語学翻訳、技術調査など、AI活用で工数が1/10になったというケースも増えています。
「使わない」はリスク、活用することが“競争優位”になる時代です。
まとめ:人間の進化はAIとの共創にある
人間の活用能力は、進化しています。そしてその進化は、AIと“敵対”するのではなく、協働することによってより高まるものです。
デジタル技術がツールとして高度化すればするほど、
「それをどう使うか」「何のために使うか」が問われます。
人間の脳は、無限の思考を生み出すだけでなく、新しいツールとの連携によって新たな知恵を生み出す可能性を持っています。
AIはすでに「ただの道具」ではなく、「共に創るパートナー」です。
この視点を持つことこそが、超知性時代におけるDX人材の核となる“活用能力”なのです。
いかがでしたでしょうか?
すこしでもみなさまの気づきになれたのであれば幸いです。
IT・DX教育サービスについてお悩みがある方は、ぜひ初回無料のオンラインコンサルティングをご利用ください。必ずお役に立ちます。
www.certpro.jp/dxconsulting/
生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。
セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。
certpro-generationaiservice.sfsite.me/
―――
全5回エピソード:
【人間のAI活用能力 第1回】AIの進化と人間の“活用能力”とは何か? 〜定義と歴史的背景〜
【人間のAI活用能力 第2回】“活用能力”は進化しているのか? 〜肯定的な視点とその根拠〜
【人間のAI活用能力 第3回】“活用能力”の限界とリスクとは? 〜否定的な視点に基づく考察〜
【人間のAI活用能力 第4回】AIと人間は融合するのか? 〜シンギュラリティに関する専門家の見解〜
【人間のAI活用能力 第5回】 最終回 人間の未来と“活用能力”のゆくえ 〜可能性と課題を見据えて〜
―――
【著者紹介】
近森 満(ちかもりみつる)
株式会社サートプロ 代表取締役CEO
IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。
一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)
電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)
IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定+DX認定)
ET教育フォーラム 合同会社 代表(コンテンツ制作)
経済産業省 地方版IoT推進ラボビジネス創出事業メンター(IoT支援)
経済産業省 地域DX推進ラボビジネス創出事業メンター(DX支援)
デジタル庁 デジタル推進委員(デジタル化支援)
DX事業共同組合 設立理事(DX推進)
DX企画書のネタ帳をはじめた人「DXの鍛え方 伝道師」とは?「DXの道を切り開く伝道師、その人物と使命に迫る」【近森満:自己紹介:2024年版】|#DX企画書のネタ帳


