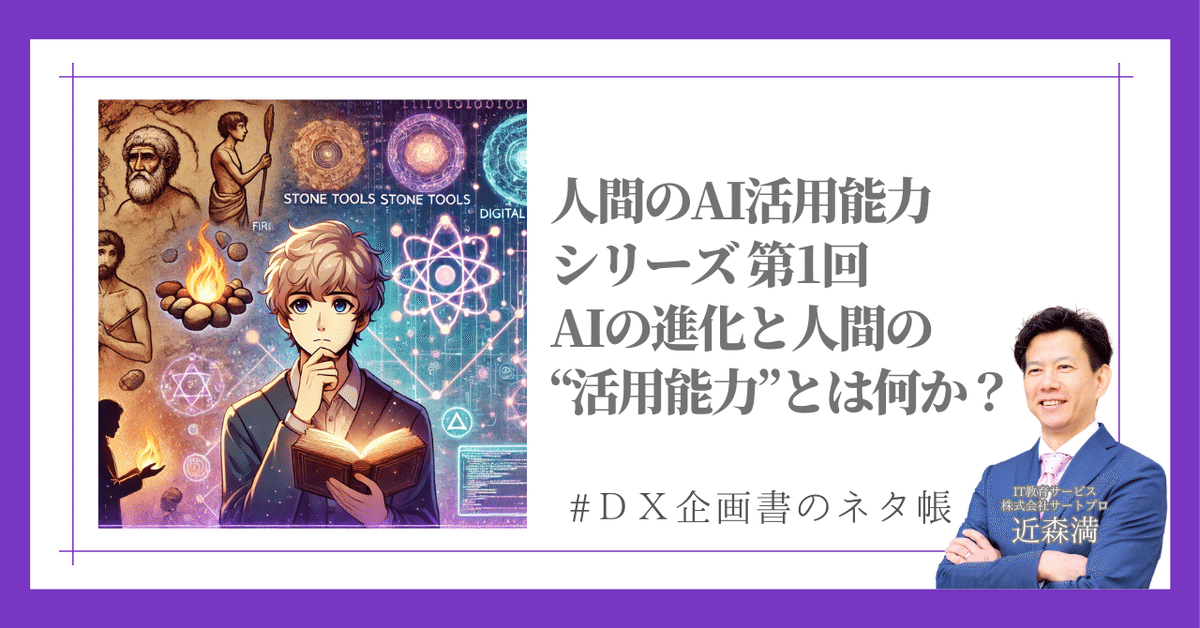
【目次】
- AIと“活用能力”の接点を見直す時代
- シンギュラリティと超知性ASIの予言
- 人間の“活用能力”の定義と本質
- 人間は進化する“活用力の集合体”である
- DX時代における“活用能力”の新たな解釈
- “活用能力”の鍵を握るのは、テクノロジーではなく人間自身
- 事例: テクノロジーと教育がもたらす社会的変革
- まとめ:“活用能力”とは次世代のリーダーシップの核
【記事概要】
生成AIの進化が加速する現代社会において、人間の“活用能力”とは何かを問い直す本稿は、AI時代の新しいスキル観と人間の進歩の本質に迫ります。
第1回では、レイ・カーツワイル氏の提唱したシンギュラリティ(技術的特異点)や、孫正義氏が語るAGI・ASIといった超知性AIへの展望を踏まえ、テクノロジーの進化がいかに人間の知性や社会構造に影響を与えてきたかを俯瞰。人類が火や石、言語、文字といった「道具」をいかに活用し進歩してきたか、そしてその能力が現在のデジタル・トランスフォーメーション(DX)にも連続していることを、多角的な視点から解説します。
「人間の活用能力」とは、単なるスキルではなく、知識、道具、環境を駆使して課題を乗り越える能力であり、その歴史的背景を踏まえた現代的意義を明らかにします。
【本文】
こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。
www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/
当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。
www.certpro.jp/dxconsulting/
AIと“活用能力”の接点を見直す時代
今、私たちはAIの進化の只中にいます。とくに2022年11月にChatGPTが登場して以降、生成AIの技術は想像を超えるスピードで進化を遂げています。音声、画像、テキスト、動画を組み合わせた「マルチモーダルAI」や、高度な分析・検索を実現する「ディープリサーチAI」、そして日々の業務をサポートする「AIエージェント」などが次々と登場しています。
こうした現代のテクノロジーの加速を受けて、私たちは今一度、「人間の活用能力」とは何か?という問いを立てる必要があります。これは単なるスキルや知識の話ではありません。環境、道具、そして情報を活かし、自分の人生や社会の課題を解決していく力そのものです。
シンギュラリティと超知性ASIの予言
レイ・カーツワイル氏が提唱した「シンギュラリティ(技術的特異点)」という言葉は、AIが人間の知能を超える時点を意味します。彼は「2045年には人間の知能とAIが融合し、知能は百万倍になる」と語り、AIの進化がもたらす変化を予見しました。
また、日本では孫正義氏が「AGI(汎用人工知能)」から「ASI(超知性人工知能)」の進化を提言し、その世界が目前に迫っていると述べています。私たちはこれらの未来予想に触れるたびに、テクノロジーに対する驚きと同時に、人間は何をすべきかという本質的な問いを突きつけられるのです。
事例: テクノロジーの“道具化”が意味するもの
たとえば、電車に乗るプロセスを考えてみましょう。駅で切符を買い、改札を通って乗車し、目的地に到着して改札を出る──これはすでに「プロセス化された活用能力」の一例です。
AIも同様に、設定された目的に向かって適切に利用できれば、人間の意思決定や行動の補助的存在として強力な「道具」になり得るのです。
人間の“活用能力”の定義と本質
私たちがいう「活用能力」とは、単なる知識や知能の多寡ではなく、知識・スキル・環境・道具を組み合わせて、問題解決や価値創造を行う力です。
この能力は、「学習力」「記憶力」「推論力」といった知的機能だけでなく、AIや道具、他者との協働によって拡張されてきました。
つまり、「活用能力」は、人間の知的活動にとどまらず、社会的知性や文化的資本と結びつくものでもあるのです。
人間は進化する“活用力の集合体”である
人類の歴史を振り返ると、火の使用、石器の発明、文字の登場、印刷技術の開発といったイノベーションは、すべて「活用能力」の表れです。そして言語と文字の発展は、人類が知識を蓄積し、世代を超えて共有する手段を得たことを意味します。
こうした知識の累積と共有によって、人間社会は飛躍的な進歩を遂げてきました。東京タワーからスカイツリーへの進化もまた、過去世代の知恵と技術を土台に、新たな課題を高度に解決した結果です。
事例: “累積的文化進化”と知識の爆発
1900年には人類の知識量が100年で倍増していました。しかし1945年には25年、1980年代にはわずか1年で倍増するようになったという試算があります。
現在では生成AIの登場で、日々指数関数的に知識が増加している時代に突入しています。
DX時代における“活用能力”の新たな解釈
このような進化を背景に、「デジタル・トランスフォーメーション(DX)」は単なるIT化ではなく、人間の活用能力の拡張と再定義の試みであると言えるでしょう。AIは知識を蓄積・分析し、人間に代わって創造も行える存在となりつつあります。
しかし、だからこそ人間に求められるのは、「何を目的に道具を活用するのか」「社会や他者との協働でどんな価値を創出するのか」といったマインドセットの変革です。
“活用能力”の鍵を握るのは、テクノロジーではなく人間自身
近代以降の科学技術の発展、産業革命に始まる生産力の向上、コンピューターによる計算能力の飛躍など、すべては「人間の活用能力」を後押しするものでした。しかし、それらの“道具”をどう活かすかは、最終的に人間の意志にかかっています。
教育や社会制度、情報インフラの整備により、私たちは世界規模でリテラシーを向上させ、87%以上の成人が読み書き可能となった現代。これは、活用能力が人類全体に浸透しつつある証拠です。
事例: テクノロジーと教育がもたらす社会的変革
インターネットとデジタル技術の普及により、私たちは地球の裏側の情報にもリアルタイムでアクセスできるようになりました。
こうした情報環境は、人間の興味や学習意欲と結びつき、“学びたい”という本能を瞬時に満たす新しい社会を形成しています。
まとめ:“活用能力”とは次世代のリーダーシップの核
これからの時代、活用能力こそが次世代のリーダーシップの核になります。AIに任せるべきタスクと、人間が担うべき価値創出の領域を見極める力。道具を使いこなすだけでなく、それを社会や人のために活かすビジョンを持つこと。
この力は、教育やスキルだけでは育ちません。「変化に適応する力」「チームと協働する姿勢」「倫理や目的意識」といった、超知性リテラシーとも呼べる新たな人間力が、今まさに問われています。
いかがでしたでしょうか?
すこしでもみなさまの気づきになれたのであれば幸いです。
IT・DX教育サービスについてお悩みがある方は、ぜひ初回無料のオンラインコンサルティングをご利用ください。必ずお役に立ちます。
www.certpro.jp/dxconsulting/
生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。
セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。
certpro-generationaiservice.sfsite.me/
―――
全5回エピソード:
【人間のAI活用能力 第1回】AIの進化と人間の“活用能力”とは何か? 〜定義と歴史的背景〜
【人間のAI活用能力 第2回】“活用能力”は進化しているのか? 〜肯定的な視点とその根拠〜
【人間のAI活用能力 第3回】“活用能力”の限界とリスクとは? 〜否定的な視点に基づく考察〜
【人間のAI活用能力 第4回】AIと人間は融合するのか? 〜シンギュラリティに関する専門家の見解〜
【人間のAI活用能力 第5回】 最終回 人間の未来と“活用能力”のゆくえ 〜可能性と課題を見据えて〜
―――
【著者紹介】
近森 満(ちかもりみつる)
株式会社サートプロ 代表取締役CEO
IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。
一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)
電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)
IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定+DX認定)
ET教育フォーラム 合同会社 代表(コンテンツ制作)
経済産業省 地方版IoT推進ラボビジネス創出事業メンター(IoT支援)
経済産業省 地域DX推進ラボビジネス創出事業メンター(DX支援)
デジタル庁 デジタル推進委員(デジタル化支援)
DX事業共同組合 設立理事(DX推進)
DX企画書のネタ帳をはじめた人「DXの鍛え方 伝道師」とは?「DXの道を切り開く伝道師、その人物と使命に迫る」【近森満:自己紹介:2024年版】|#DX企画書のネタ帳


