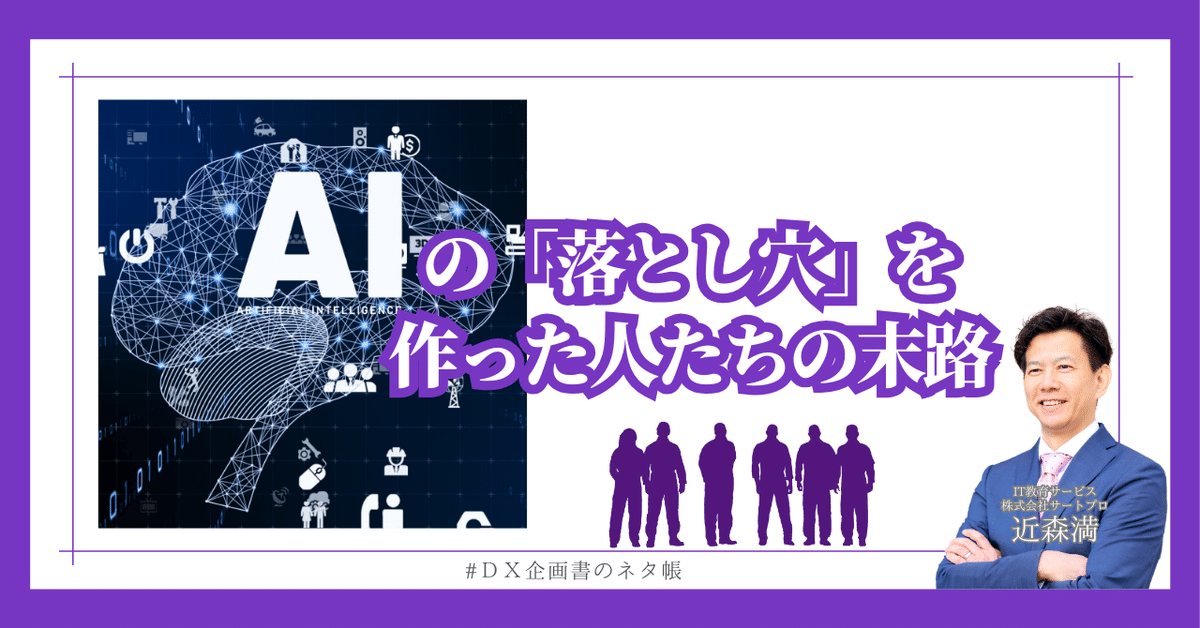
【記事概要】
「AIでなんかやれ」と丸投げする上司、そして“中身が伴わないAI企業”が迎える末路──そんな現代のAI社会に潜む「落とし穴」について、DX教育の専門家・近森満と構成作家の堀内崇氏が語る前編・後編の2部構成のエピソードです。前編では、生成AIをただのバズワードとして使い、現場を混乱させる“他人任せ”なマネジメントの問題を中心に展開。後編では、実際に粉飾決算や人力業務をAIと偽っていたAI企業「オルツ」の事例を紹介し、AIリテラシーの重要性、そして我々が陥りやすい「情弱ビジネス」の罠について深堀りしています。
また、近森満自身の体験談として、マイナンバーカードを使ったパスポート申請の事務的混乱や、AIを活用しているはずのサービスの実態を見極めることの難しさも赤裸々に語られます。
本記事では、生成AI時代に求められる「判断軸」や「マインドセットの重要性」を軸に、「超知性AI」「リテラシー」「騙されないための視点」などの視点から深く掘り下げていきます。企業のDX推進担当者や、AIをビジネスで活用しようとする全てのビジネスパーソンに向けた、思考のトリガーとなる必読の内容です。
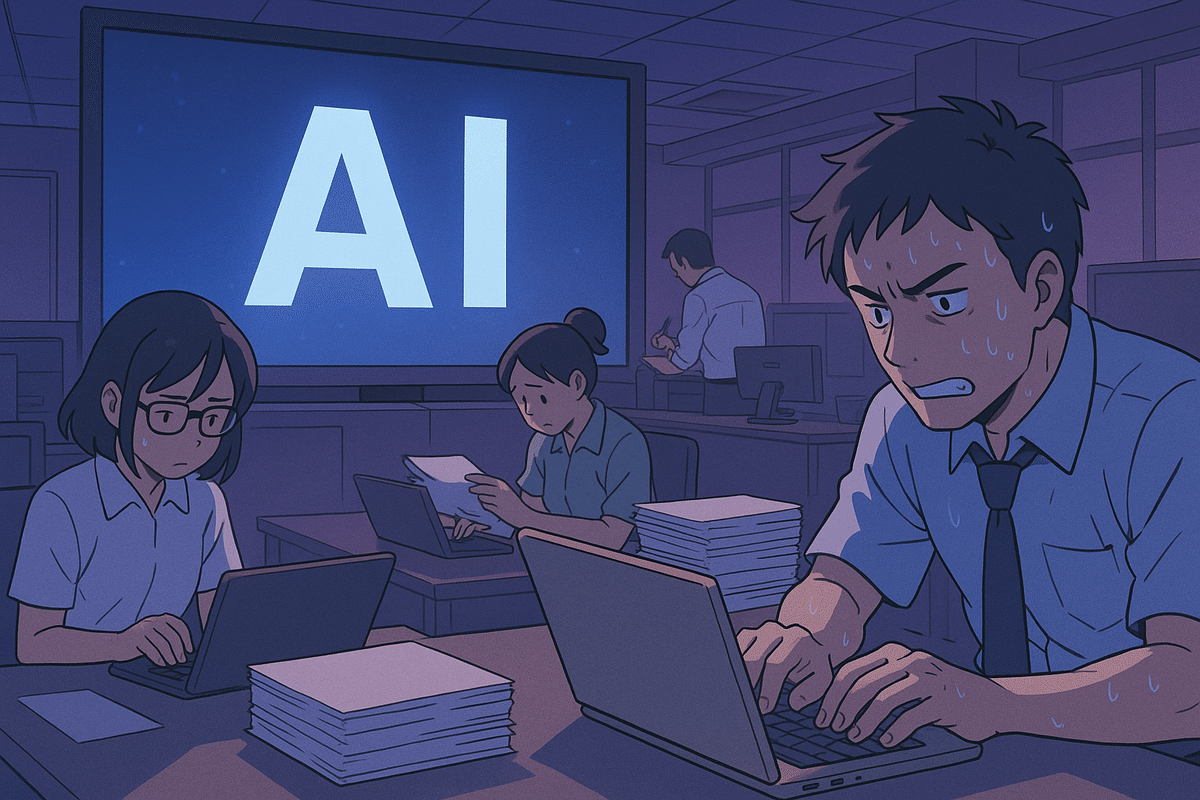
【著者情報】
こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。
www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/
当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。
www.certpro.jp/dxconsulting/
AI活用ブームの「熱」と「穴」
生成AIが登場してからというもの、多くの企業がこぞって「AIを活用せよ」という号令を発するようになりました。しかし、**「AIでなんかやれ」**とだけ部下に丸投げする上司が急増しているのが現場の実情です。
あるポッドキャスト番組「テックリードFM」でも取り上げられたように、AIに対する理解も戦略もなく、他人任せで無責任な指示を出す経営層の姿が散見されるようになりました。これは、まさに「インターネット黎明期のFAXおじさん」再来とも言える現象です。
AIというテクノロジーに可能性を感じてはいるものの、それを自ら試さず、現場の若手に押し付ける。そして、自分では何も学ばず成果だけを求める。そんな構図が、現場のモチベーションを奪い、組織のイノベーションを止めてしまうのです。
逃げるマネジメントと変われない組織
近森自身も、かつて同じような体験をしたことがあります。ワープロや表計算が出てきた頃、上司から「これ、やっておいて」と、IT活用を丸投げされた経験です。
それはIT活用への理解を放棄し、進化を他者に委ねる「逃げの姿勢」に他なりません。この姿勢は、現在の生成AI時代においても変わっていないどころか、より顕在化しています。
事例: 社長がデジタル嫌いな企業
コンサルティングに入った企業で、社長は「DXやりたい」と言いながら、ミーティング中は世間話ばかり。話をデジタルに持っていこうとすると、目をそらす。その結果、現場だけが苦しむ形になっていました。近森満の経験です。
「よし、なんとかやっといてくれ」と言われた担当者の苦悩は計り知れません。ビジョンなきDX、指示なきマネジメントは、組織全体の信頼感を損ないます。
AI企業「オルツ」に見る本当の“落とし穴”
AIをビジネスの看板にしていた企業「オルツ」が、粉飾決算・循環取引・実体のないAIプロダクトなどで問題になった事件は記憶に新しいでしょう。
特に衝撃だったのは、「AI議事録」として売り出していたサービスが、実は人力で議事録を作成していたという点です。つまり、表ではAIを掲げながら、裏では人が黙々と文字起こしをしていたのです。
これは、ユーザーへの誤認を狙ったブランディングと資金調達であり、投資家や顧客を欺く形になっていました。
事例: Sansanとの対比
コロナ禍を経てさらに事業拡大をし、松重豊さんを起用したCMでも話題になった名刺管理サービスで知られる「Sansan」も、初期は名刺を海外の作業者が手作業で入力していました。しかし、Sansanはその運用を正直に明示していた点が大きく異なります。徐々にAI化を進め、現在では高度なOCRと自然言語処理によって精度を高めています。
透明性と進化の姿勢の違いが、企業の信頼性を大きく分けるのです。
情報弱者を食い物にする「情弱ビジネス」
このような“実態のないAIビジネス”が通用してしまう背景には、AIリテラシーの欠如があります。
見た目がそれっぽい、AIと書いてある、話題になっている、それだけで飛びついてしまう人がいる。そして、売る側もそれを狙って、「AIっぽさ」だけを強調する。
この構造は、古くは「水素水」や「EM菌」、そして今では「NFT」「Web3」にも通じる“バズワード消費”です。
リテラシーの正体とは?マインドセットの問題
ここでいう「AIリテラシー」とは、単に技術を知っているかどうかではありません。自分の目で確かめる姿勢、思考の軸を持っているかどうかが問われているのです。
「みんなが使ってるから」「話題になってるから」ではなく、自分で触り、試し、検証する。その経験がなければ、いくら最新のキーワードを知っていても、それは知識ではなく“うわさ”でしかありません。
このようなマインド・トランスフォーメーション(意識の変革)こそが、真のリテラシーの第一歩なのです。
事例: パスポート申請の“闇”
近森がマイナンバーカードを使ってパスポート申請をした際、ステータスが「手続き中」のまま何ヶ月も動かない。アプリでも、マイナポータルでも、何の通知も来ない。最後に解決したのは「電話」でした。
最先端のテクノロジーよりも、最もアナログな手段が最も強力だったという皮肉な現実。これもまた、テクノロジーと現実の乖離を示す好例です。
まとめ:AI時代を生き抜く「超知性リテラシー」
AIが発展すればするほど、私たちには新たなリテラシー、つまり「超知性リテラシー」が求められます。
これは、生成AIやAGIのような新技術に振り回されず、「自分自身の知性で判断できる力」です。企業であれ個人であれ、外部に丸投げせず、自分の意志と軸を持って向き合う力が必要なのです。
マインドチェンジでは足りない。マインド・トランスフォーメーションが求められているのです。
AIは魔法でも、万能薬でもありません。しかし、正しく向き合い、使いこなせば、ビジネスもキャリアも劇的に進化します。
「お前らAIでなんかやれ」ではなく、「私たちがAIと共に何を成し遂げるか」。この意識の転換こそが、DX推進における最大の鍵です。
いかがでしたでしょうか?
すこしでもみなさまの気づきになれたのであれば幸いです。
IT・DX教育サービスについてお悩みがある方は、ぜひ初回無料のオンラインコンサルティングをご利用ください。必ずお役に立ちます。
www.certpro.jp/dxconsulting/
生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。
セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。
certpro-generationaiservice.sfsite.me/
キーワードの解説
生成AI(Generative AI)
生成AIとは、テキスト、画像、音声、動画などのコンテンツを自動で生成できるAI技術のことを指します。ChatGPT、Midjourney、DALL·E、Stable Diffusionなどが代表的な事例です。企業の業務効率化やクリエイティブ支援、教育分野まで多岐にわたる分野で導入が進んでいます。一方で、その「使いどころ」や「リスク管理」の判断には高度なリテラシーが求められるようになっています。
情弱ビジネス
情報弱者(情弱)を対象にしたビジネスモデルで、実態が不透明または誤認を誘う商材・サービスが特徴です。AI業界では「AIを使っている」と謳いながら、実は中身は人力や汎用ツールに頼っているケースもあります。見た目や話題性に流されず、本質を見抜く判断軸=リテラシーが重要とされます。
マインド・トランスフォーメーション(Mind Transformation)
単なる知識の更新や考え方の柔軟性(マインドチェンジ)にとどまらず、自らの行動や価値観を根本から変革する思考プロセスのこと。生成AI時代においては、このマインド・トランスフォーメーションこそが、個人・組織を次のレベルへ導く鍵とされています。使うだけではなく、何をどう使うかを主体的に設計・判断する力が求められます。
【著者紹介】
近森 満(ちかもりみつる)
■株式会社サートプロ 代表取締役CEO
IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。
■所属・役職
・IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定、+DX認定、超知性ASI検定)
・一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)
・電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)
・NPO 組込みソフトウェア管理者技術者育成研究会 メンバー(組込み)
・ET教育フォーラム合同会社 代表(コンテンツ制作)
・経済産業省地方版IoT推進ラボ ビジネス創出事業メンター(IoT支援)
・経済産業省地域DX推進ラボ ビジネス創出事業メンター(DX支援)
・デジタル庁デジタル推進委員(デジタル化支援)
・DX事業共同組合 設立理事(DX推進)
・一般社団法人日本サステナブルビジネス機構 幹事(SDGs認証)
・”一億総活躍社会を実現する”共生日本協議会 理事(DEI支援)
・アジャイル開発技術者検定試験コンソーシアム 事務局長(Agile検定)
・一般社団法人国際サイバーセキュリティ協会 事務局長(IACS認定)


