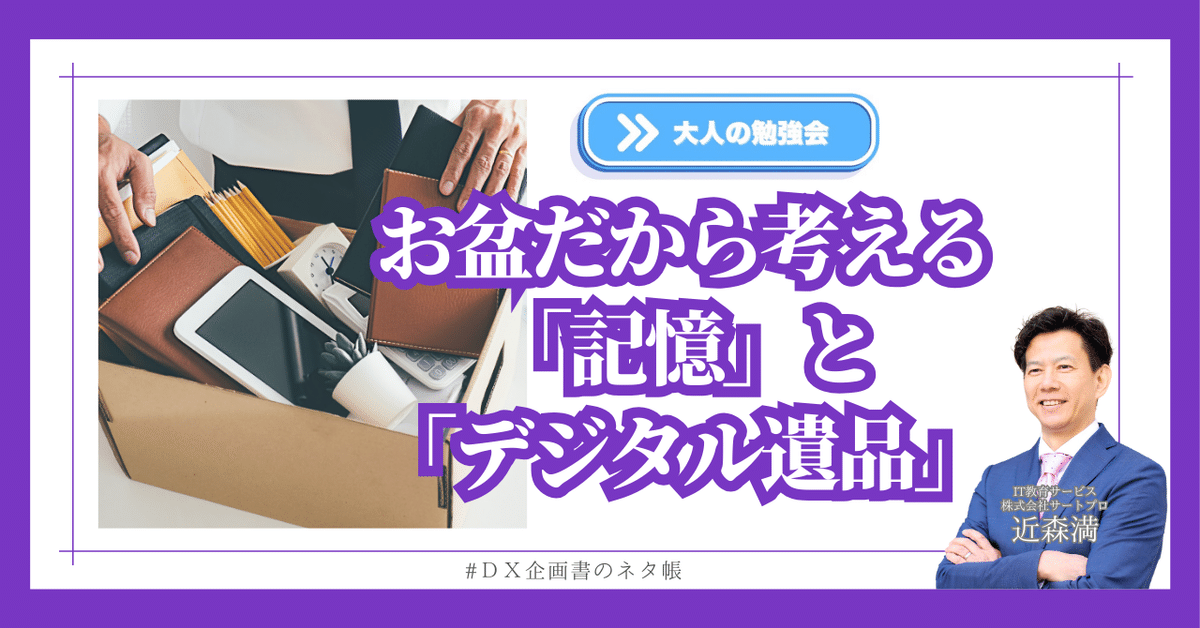
【記事概要】
お盆だからこそ向き合いたい「記憶」と「デジタル遺品」について考える機会です。本稿では、近森満が大人の勉強会で語った内容をもとに、個人と家族が今すぐ整えるべき実務とマインドを整理いたします。
鍵となるのはデジタル遺品管理の三原則「アカウント・パスワードの安全保管」「本人意思の明文化(何を残すか)」「家族への引き継ぎ方法の決定」です。クラウド時代においては、写真や動画、サブスクリプション、業務アカウントが家庭内で重なり合い、放置すると課金やアクセス不能のリスクが高まります。高齢の親の端末やノートに散在する情報、仕事と私用が交差するデータ、家族共有クラウドの見えにくさを断捨離と棚卸しで可視化し、継承フローを文書化することが重要です。
DX推進や生成AI活用の視点から見ても、個人の「記録」は将来の学習資産であり、家族間や組織間の情報連携はマインドチェンジの実践になります。お盆の数日間に、一覧化・意思表明・引き継ぎの三点セットを小さく始め、継続的にアップデートする行動計画に落とし込むことをおすすめします。
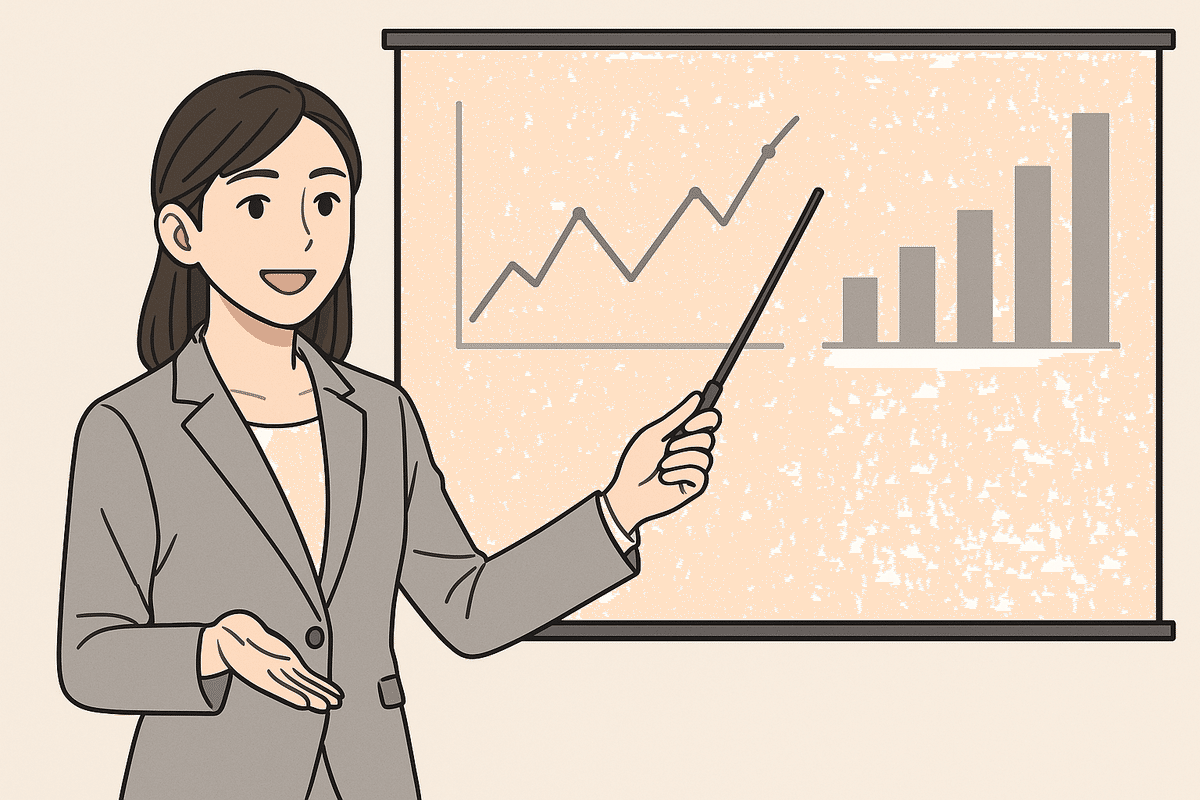
【著者情報】
こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。
www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/
当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。
www.certpro.jp/dxconsulting/
お盆に考える「記憶」と「デジタル遺品」
お盆という時期は、故人を偲び、記憶と向き合う時間です。しかし現代に生きる私たちにとって、もう一つ考えなくてはならないテーマがあります。それが「デジタル遺品」。スマホやクラウドに眠る写真、動画、SNSアカウントやサブスクリプション契約。これらは整理されないまま放置すると、本人だけでなく家族も困惑する資産となります。
お盆だからこそ、物理的な遺品整理と同じように「デジタルの棚卸し」を始めるタイミングだと考えます。
デジタル遺品管理の三原則
私が提唱するのは、デジタル遺品管理の三原則です。
①アカウントとパスワードの安全保管
②本人意思の明文化(どのデータを残すか)
③家族への引き継ぎ方法を決めること
この3つを意識するだけで、デジタル遺品は「混乱の種」から「家族の資産」に変わります。
事例: 高齢の親のパソコンとスマホ
私の母もかつてはパソコンやスマホを活用していましたが、年齢を重ねると次第に利用が減り、どこにどのデータが残っているのか把握が難しくなりました。パソコンのIDやパスワードが分からなければ、大切な写真に二度とアクセスできなくなります。そこで私は母と一緒に、ノートに書き残し、データの所在を共有しました。時間はかかりましたが、これが後々の安心につながりました。
データの断捨離とクラウド活用
ハードディスクやSDカードにデータを詰め込む時代から、クラウドに集約する時代へ。今ではiCloud、Google Drive、Amazon Cloudなどを使えば膨大な容量を確保できます。
しかし便利さの裏に落とし穴があります。
クラウドに保存しても、家族がIDとパスワードを知らなければ、データは「存在していても見えない遺品」と化してしまいます。
事例: サブスクリプションの継続課金
私自身、生成AIの利用で複数のサブスク契約を抱えています。本人が意図せず亡くなった場合でも課金は続き、家族にとって負担になります。だからこそ「解約手順」や「継続の意思」を明文化しておくことが重要です。これはデジタル断捨離の一部であり、未来の安心への投資でもあります。
デジタル遺品と家族コミュニケーション
デジタル遺品の整理は「人に言いにくい話題」ですが、家族で共有することが不可欠です。なぜなら、デジタル資産は個人だけでなく家族全員に影響するからです。
クラウドで共有していた写真や動画も、家族が知らなければ消失同然。逆に共有と申し送りをしておけば、思い出は家族で引き継がれていきます。
事例: 長男としての役割
私は三兄弟の長男として「兄貴が整理してくれる」と期待される立場でした。実際、銀行口座や公共料金の名義変更と同じように、デジタル資産の管理も担うことになりました。ここで痛感したのは「一人で抱え込まず、家族みんなで共有する仕組み」が必要だということです。
DX推進とデジタル遺品の接点 H2段落
一見、DX推進や生成AIの話とは別に思えるかもしれません。しかし私はこう考えます。
デジタル遺品の整理は 「個人におけるDX」 です。
・スキルセット:IDやパスワード管理、クラウド利用スキル
・マインドセット:家族とデータを共有する姿勢
・マインドチェンジ:デジタルを資産と捉え、残すものと捨てるものを選ぶ
これはDXの基本原則と同じです。
また、デジタル3兄弟(AI・クラウド・IoT)とマインド3姉妹(学び直し・共有・変革意識)を組み合わせることで、個人も「小さなDX」を実践できます。
まとめ:お盆を「デジタルの棚卸し」の起点に
お盆という静かな時間を、デジタル遺品と向き合う「棚卸し」の機会にしてみませんか?
・IDとパスワードを安全にまとめる
・残すデータと捨てるデータを選ぶ
・家族にどう引き継ぐか話し合う
この3つを一度に完璧にやる必要はありません。小さく始め、継続して更新することが重要です。
デジタル社会に生きる私たちにとって、これは「未来の家族への贈り物」であり、自分自身の安心でもあります。
いかがでしたでしょうか?
すこしでもみなさまの気づきになれたのであれば幸いです。
IT・DX教育サービスについてお悩みがある方は、ぜひ初回無料のオンラインコンサルティングをご利用ください。必ずお役に立ちます。
www.certpro.jp/dxconsulting/
生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。
セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。
certpro-generationaiservice.sfsite.me/
キーワードの解説
デジタル遺品
故人が残したパソコン・スマホ内のデータ、クラウド上の写真や動画、SNSアカウント、ネット銀行口座、サブスク契約などの総称。これらは適切に管理されなければ家族がアクセスできず、金銭的・精神的負担になる。整理の三原則は「安全保管」「意思の明文化」「引き継ぎ方法」である。
DX推進
DX(デジタル・トランスフォーメーション)は単なるIT化ではなく、組織や社会の仕組みをデジタル技術で変革すること。人材育成やマインドセットの転換が重要であり、個人にとっては「生活や資産のDX」としてデジタル遺品整理も含まれる。
マインドチェンジ
変化の激しい社会で、新しい技術や価値観を受け入れる姿勢を指す。デジタル遺品管理のように「残す・捨てる」を主体的に判断することは、マインドチェンジの実践そのものである。
【著者紹介】
近森 満(ちかもりみつる)
■株式会社サートプロ 代表取締役CEO
IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。
■所属・役職
・IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定、+DX認定、超知性ASI検定)
・一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)
・電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)
・NPO 組込みソフトウェア管理者技術者育成研究会 メンバー(組込み)
・ET教育フォーラム合同会社 代表(コンテンツ制作)
・経済産業省地方版IoT推進ラボ ビジネス創出事業メンター(IoT支援)
・経済産業省地域DX推進ラボ ビジネス創出事業メンター(DX支援)
・デジタル庁デジタル推進委員(デジタル化支援)
・DX事業共同組合 設立理事(DX推進)
・一般社団法人日本サステナブルビジネス機構 幹事(SDGs認証)
・”一億総活躍社会を実現する”共生日本協議会 理事(DEI支援)
・アジャイル開発技術者検定試験コンソーシアム 事務局長(Agile検定)
・一般社団法人国際サイバーセキュリティ協会 事務局長(IACS認定)


