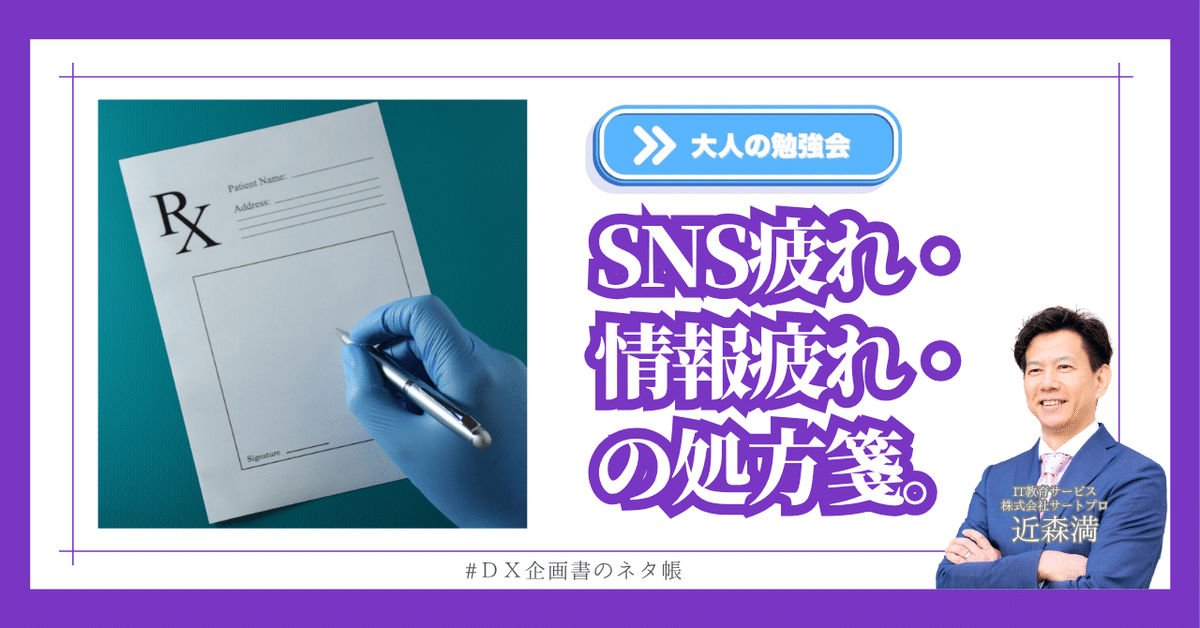
【記事概要】
SNSやニュースを日常的に追い続けることで生じる「SNS疲れ」「情報疲れ」は、脳の認知負荷を高め、集中力の低下や精神的ストレスを引き起こします。
本稿では、その原因を認知負荷理論の観点から解説し、デジタルデトックスや情報ダイエットの実践方法を提案します。具体的には、SNSやニュース閲覧を1日30分以内に制限、通知オフ設定やフォロー整理、朝晩のデジタル断食などで情報接触量をコントロール。
さらに、五感を使うアナログな趣味(散歩・ギター・読書等)で脳をリフレッシュし、アウトプット中心の学び(発信・共有・対話)で情報を定着させます。DX推進やデジタル人材育成においても、この習慣化はマインドセット改革と生産性向上の両立に直結します。
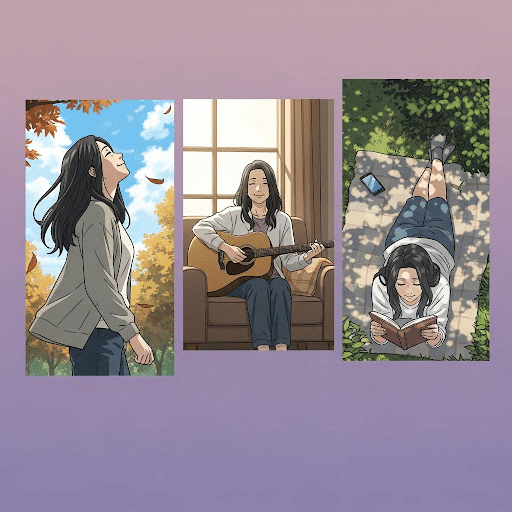
【著者情報】
こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。
www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/
当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。
www.certpro.jp/dxconsulting/
なぜ私たちはSNSや情報に疲れてしまうのか
「朝から晩までスマホと向き合っているのに、なぜか満たされないし疲れている」——多くの方が感じるこの現象こそが、SNS疲れ・情報疲れです。
情報化社会の現代では、最新のニュースやトレンドを追うことは当たり前の行動になりました。しかし、人間の脳が同時に処理できる情報量には限界があります。心理学の認知負荷理論(Cognitive Load Theory)によれば、過剰な情報摂取は作業記憶を圧迫し、集中力や判断力を低下させます。
SNSや動画プラットフォームは、人の注意を引くために情報を“濃縮”して提供します。TikTokやYouTubeショートのような短尺動画は、10秒から1分という短い時間に大量の刺激を詰め込み、視覚や聴覚を連続的に占有します。その結果、脳は休む暇なく情報を処理し続け、いわば「脳の塩分過多状態」に陥るのです。
情報疲れを生む3つのメカニズム
①認知資源の消耗
SNSやネットニュースからの過剰情報は、集中力の低下と精神的疲労を引き起こします。特にプッシュ通知によって、作業が頻繁に中断されると再集中まで時間がかかり、生産性が著しく低下します。
②感情的ストレス
ネガティブニュースや他者比較を誘発する投稿は、自己肯定感を削り、無意識に心を消耗させます。
③身体的負担
長時間のスマホ利用による首・肩のこり、視神経の疲れも情報疲れの一因です。いわゆる「スマホ首」は、持続的な身体疲労を蓄積します。
仮想:ある大手IT企業のエンジニアチーム
開発本部では、Slack・メール・社内SNSといった複数の連絡手段が常時稼働し、エンジニアは「常時接続状態」に置かれていました。そこで人事本部長が中心となり、
・全社Quiet Hours(通知停止時間)の設定
・社内SNSは1日2回のみチェック
・ネガティブな外部ニュースの共有は「週1回のまとめ配信」に集約
を実施。結果、3か月で「業務中の集中ブロック確保時間」が平均1.6倍に伸び、心理的疲労度スコアも改善しました。
脳を守るための「情報ダイエット」5つの習慣
①SNS・ニュースの閲覧時間を1日30分以内に制限
情報摂取の“量”を決めることが、認知負荷軽減の第一歩です。
②通知オフ・フォロー整理
無意識に開いてしまうトリガーを減らします。特に就寝前と起床後の通知は脳を休ませるために遮断。
③朝と夜のデジタル断食
朝の15分、夜寝る前の1時間はスマホ・PCから離れる時間を設定します。
④五感を使うアナログ趣味
散歩、読書、楽器演奏、料理、園芸など、物理的活動を通じて脳をリフレッシュします。
⑤アウトプットを伴う学び
情報は発信・共有・対話によって定着します。勉強会や社内Wikiで小さな発表を習慣化しましょう。
事例:私の「ギター式デジタルデトックス」
私自身、ギターを弾く時間を“強制的スマホ休憩”にしています。両手を使うため物理的にスマホが触れられず、演奏中は集中して音に没入できます。若い頃は「ギターばかり弾いてないで勉強しろ」と言われたものですが、今や「スマホ見てないでギター弾け」という感覚です。
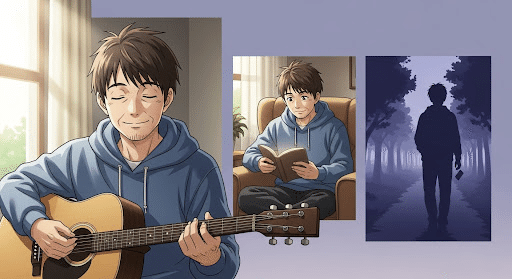
今日からできる実践ステップ
①通知を一括オフにして、1日2回だけチェックする時間を決める
②就寝1時間前はスマホを別室に置く
③朝の15分はニュースやSNSを見ず、深呼吸や散歩に充てる
④週3回は五感を使う趣味を予定に組み込む
⑤学んだことを300文字で社内やSNSに発信
これらを3週間続ければ、情報疲れの軽減と集中力の回復を体感できるはずです。
まとめ:情報との距離感を再設計する
SNS疲れは避けられない宿命ではありません。情報接触をコントロールし、アウトプット中心の学びに切り替えることで、脳と心に余白が戻ります。これはDX推進やデジタル人材育成においても重要な要素です。デジタル3兄弟(データ・クラウド・AI)とマインド3姉妹(好奇心・共創・寛容)をバランスよく育てることが、マインド・トランスフォーメーションの第一歩です。
情報疲れを感じたら、まずは“減らす”ことから始めましょう。そして減らした時間で、自分の声や考えを外に出してください。それが自分を守り、成長させ、周囲にも良い影響を与えます。今日から、あなたの「情報ダイエット」を始めてみませんか?
いかがでしたでしょうか?
すこしでもみなさまの気づきになれたのであれば幸いです。
IT・DX教育サービスについてお悩みがある方は、ぜひ初回無料のオンラインコンサルティングをご利用ください。必ずお役に立ちます。
www.certpro.jp/dxconsulting/
生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。
セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。
certpro-generationaiservice.sfsite.me/
キーワードの解説
認知負荷理論(Cognitive Load Theory)
認知負荷理論は、人間の作業記憶には限界があり、過剰な情報や複雑な課題は学習や作業効率を下げるという心理学理論です。負荷には「内在的負荷(課題の難しさ)」「外在的負荷(不要な情報や手順)」「関連的負荷(学習促進に役立つ負荷)」の3種類があります。SNSやニュースの過剰摂取は外在的負荷を増やし、集中力低下や精神的疲労の原因になります。情報整理や提示方法の工夫で外在的負荷を減らすことが、効率的な学習や業務遂行につながります。
デジタルデトックス
デジタルデトックスとは、一定時間スマホやPCなどのデジタル機器から離れ、心身を休ませる習慣です。短時間でも脳のリフレッシュや睡眠の質向上、ストレス低下が期待できます。完全に断つのではなく、朝晩の15〜60分や就寝前のスマホ別室など「区切り時間」を設ける方法が現実的で継続しやすいです。ビジネス現場では、集中作業時間の確保やチーム全体のパフォーマンス向上にも直結します。
マインド・トランスフォーメーション
マインド・トランスフォーメーションは、個人や組織が環境変化に適応するための意識改革です。単なるスキル習得ではなく、価値観や思考パターンそのものを柔軟に変えることを目指します。DX推進では、デジタル3兄弟(データ・クラウド・AI)とマインド3姉妹(好奇心・共創・寛容)の両輪で、変化に対応できる組織文化をつくることが不可欠です。情報疲れ対策やデジタルデトックスも、この意識改革の一環として位置づけられます。
【著者紹介】
近森 満(ちかもりみつる)
■株式会社サートプロ 代表取締役CEO
IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。
■所属・役職
・IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定、+DX認定、超知性ASI検定)
・一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)
・電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)
・NPO 組込みソフトウェア管理者技術者育成研究会 メンバー(組込み)
・ET教育フォーラム合同会社 代表(コンテンツ制作)
・経済産業省地方版IoT推進ラボ ビジネス創出事業メンター(IoT支援)
・経済産業省地域DX推進ラボ ビジネス創出事業メンター(DX支援)
・デジタル庁デジタル推進委員(デジタル化支援)
・DX事業共同組合 設立理事(DX推進)
・一般社団法人日本サステナブルビジネス機構 幹事(SDGs認証)
・”一億総活躍社会を実現する”共生日本協議会 理事(DEI支援)
・アジャイル開発技術者検定試験コンソーシアム 事務局長(Agile検定)
・一般社団法人国際サイバーセキュリティ協会 事務局長(IACS認定)


