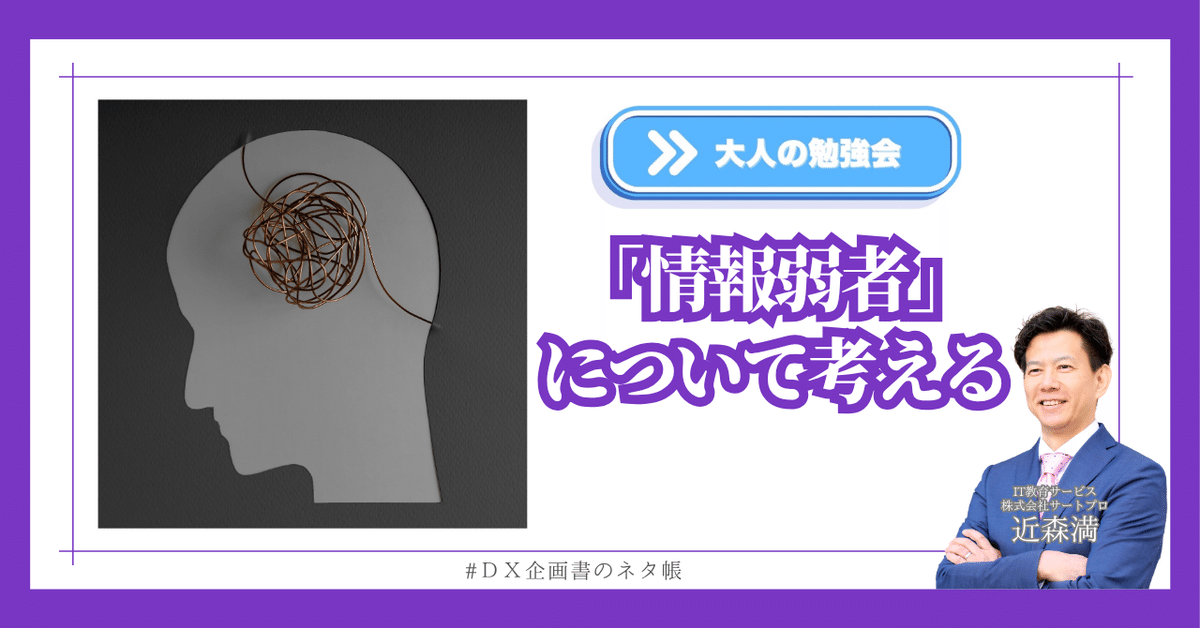
【記事概要】
この記事は、「情報弱者」というテーマを夏休み特別企画として多角的に掘り下げた内容です。近森満氏は、SNSやネットビジネスにおける「情報弱者」の一般的なイメージから話を始め、企業や個人が高額コンテンツやサービスを購入する背景、そこに潜む価値判断と自己責任の重要性を説きます。
さらに、投資や株、海外サービスの早期導入などのビジネス事例を交え、情報をいかに仕入れ、優位性を築くかを解説。自らの不得意分野や失敗談を交えながら、「誰もがある分野では情報弱者になる」ことを認め、その上で生成AIを活用してバイアスを減らし、判断軸を磨く方法を提案します。
最後に、学び方を学び、自分なりの判断基準を持つことが情報格差を超える鍵であるとし、読者に主体的な行動を促す構成になっています。
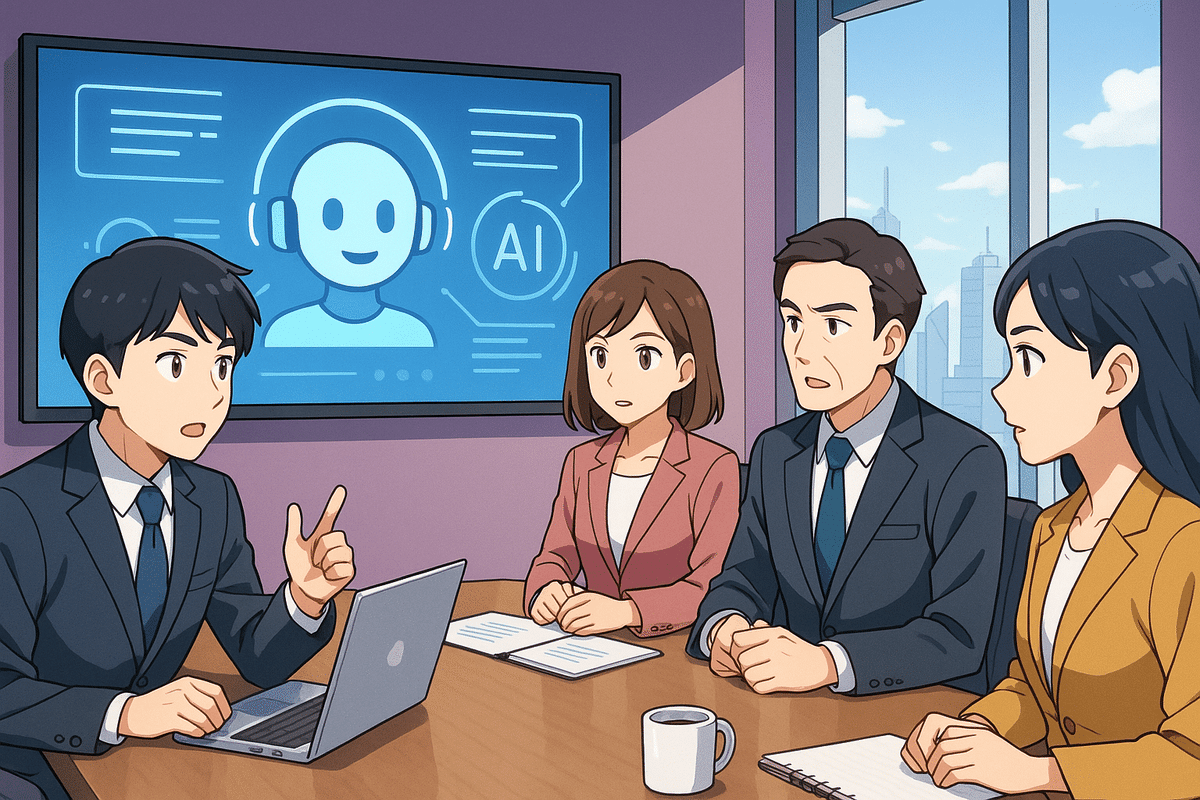
【著者情報】
こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。
www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/
当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。
www.certpro.jp/dxconsulting/
情報弱者とは何か
私たちが日常的に使う「情報弱者」という言葉は、しばしばSNSやネットニュースで目にします。多くの場合、
・SNS広告に反応して不要な商品やサービスを購入してしまう人
・ネット詐欺に遭いやすい人
・リテラシーの低いユーザーを指すイメージが強いでしょう。
しかし、私はこう考えます——「情報弱者は特定の層だけではなく、誰もがある場面では情報弱者になる」。
つまり、どんなに経験豊富なビジネスパーソンでも、自分の不得意分野や未経験領域では情報の見極め力が弱くなるのです。
興味を引く視点:情報を買う心理
多くの人が、自己成長やビジネスのために情報を「購入」します。
Eラーニングの講座、オンラインサロン、数十万〜百万円規模のビジネス教材など。
第三者から見れば「高すぎる」「中身が薄い」と思えるコンテンツでも、当事者は「これで自分を変えられる」と信じ、行動します。本屋で買った本を積読する現象の“高額版”とも言えます。
重要なのは、その購入が自己判断か、他者に丸め込まれた結果かです。自分で調べ、試し、納得してお金を払うなら自己責任ですが、「勧められたから」「雰囲気で」では、リスクが高まります。
事例: 高額コンテンツ購入の是非
ある企業が海外の最新マーケティングツールを日本市場で独占契約。初期費用は高額でしたが、早期導入により競合優位性を獲得し、結果的に投資を上回る利益を得ました。
一方で、後発参入した別企業は、同じツールを高額で導入したものの、既に市場は飽和。顧客獲得が進まず、投資回収できませんでした。
同じツール購入でも、情報の仕入れ時期と判断基準で明暗が分かれる典型例です。
情報弱者の構造
情報弱者が生まれる背景には、以下の3要素があります。
①情報格差:
情報へのアクセス環境やネットワークの差。
②リテラシー不足:
情報の真偽や価値を見抜くスキル不足。
③判断軸の欠如:
自分なりの意思決定基準を持っていない。
私は会計や投資分野は不得意です。そのため、金融商品の話が来ても、自分で深く検証しない限りは手を出さないポリシーを持っています。この「得意不得意の自覚」こそが、情報弱者にならないための第一歩です。
事例: 弱い分野での失敗と学び
若い頃、私は高額な絵画をローンで購入しました。今思えば市場価値なんか考えてなくて、部屋に飾ることで精神的な支えとなり、結果的には自分の判断軸を鍛える経験になりました。
一度や二度の失敗は、情報選別力を育てる肥料になります。
MICHAEL DAVID WARD
この方の作品です。いまなら生成AIでも…
生成AI時代の情報リテラシー
生成AIは365視点で物事を検証し、認知バイアスを指摘し、代替案を提示してくれます。人間同士の会話では批判に感情的反応をしがちですが、AIからの指摘は感情を刺激しにくく、冷静に受け止められます。
「AIに頼ると脳が退化する」という意見もありますが、私は逆だと考えます。適切に使えば、判断材料を増やし、思考の幅を広げるツールとなります。
行動を促す:判断軸を持つ
情報弱者から脱却するには、
・自分の得意・不得意分野を明確にする
・納得できるまで情報を検証する
・他者の意見を鵜呑みにせず、必ず一次情報に触れる
・生成AIや専門家の視点を活用してバイアスを補正する
これらを習慣化することです。お金を払うか否かは、その結果として自分が納得できるかどうかで決めましょう。
まとめ:情報格差を超える力
情報弱者であることは恥ではありません。誰もがある分野では弱者になります。重要なのは、その事実を認め、判断軸を磨き続けること。
学び方を学び、自分の頭で考え、行動する——これが情報格差を超える唯一の方法です。
いかがでしたでしょうか?
すこしでもみなさまの気づきになれたのであれば幸いです。
IT・DX教育サービスについてお悩みがある方は、ぜひ初回無料のオンラインコンサルティングをご利用ください。必ずお役に立ちます。
www.certpro.jp/dxconsulting/
生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。
セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。
certpro-generationaiservice.sfsite.me/
キーワードの解説
情報弱者
「情報弱者」とは、情報の入手や判断において不利な立場にある人を指します。これは単にネットリテラシーが低い人だけでなく、専門外の分野では誰もがなり得ます。情報弱者の特徴として、一次情報を確認せずに他者の意見や広告を鵜呑みにする、真偽の検証スキルが低い、判断軸を持たないなどがあります。克服するには、自分の得意不得意の把握、情報源の多角化、検証の習慣化が重要です。
生成AI
生成AI(Generative AI)は、学習したデータを基に文章・画像・音声などの新たなコンテンツを生成する人工知能です。ChatGPTや画像生成AIなどが代表例で、文章作成、要約、分析、アイデア創出など幅広く活用できます。特に判断の補助や認知バイアスの指摘に有効で、情報弱者からの脱却をサポートします。適切な質問設計(プロンプトエンジニアリング)により、質の高い出力が得られます。
判断軸
判断軸とは、物事を選択・評価する際の基準や優先順位のことです。情報選別や意思決定において、この軸が明確であれば感情や一時的な雰囲気に流されにくくなります。判断軸は経験、専門知識、価値観などから形成され、自己責任の範囲で意思決定するための土台となります。生成AIや専門家の意見を活用しつつ、自らの判断軸を更新し続けることが重要です。
【著者紹介】
近森 満(ちかもりみつる)
■株式会社サートプロ 代表取締役CEO
IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。
■所属・役職
・IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定、+DX認定、超知性ASI検定)
・一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)
・電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)
・NPO 組込みソフトウェア管理者技術者育成研究会 メンバー(組込み)
・ET教育フォーラム合同会社 代表(コンテンツ制作)
・経済産業省地方版IoT推進ラボ ビジネス創出事業メンター(IoT支援)
・経済産業省地域DX推進ラボ ビジネス創出事業メンター(DX支援)
・デジタル庁デジタル推進委員(デジタル化支援)
・DX事業共同組合 設立理事(DX推進)
・一般社団法人日本サステナブルビジネス機構 幹事(SDGs認証)
・”一億総活躍社会を実現する”共生日本協議会 理事(DEI支援)
・アジャイル開発技術者検定試験コンソーシアム 事務局長(Agile検定)
・一般社団法人国際サイバーセキュリティ協会 事務局長(IACS認定)


