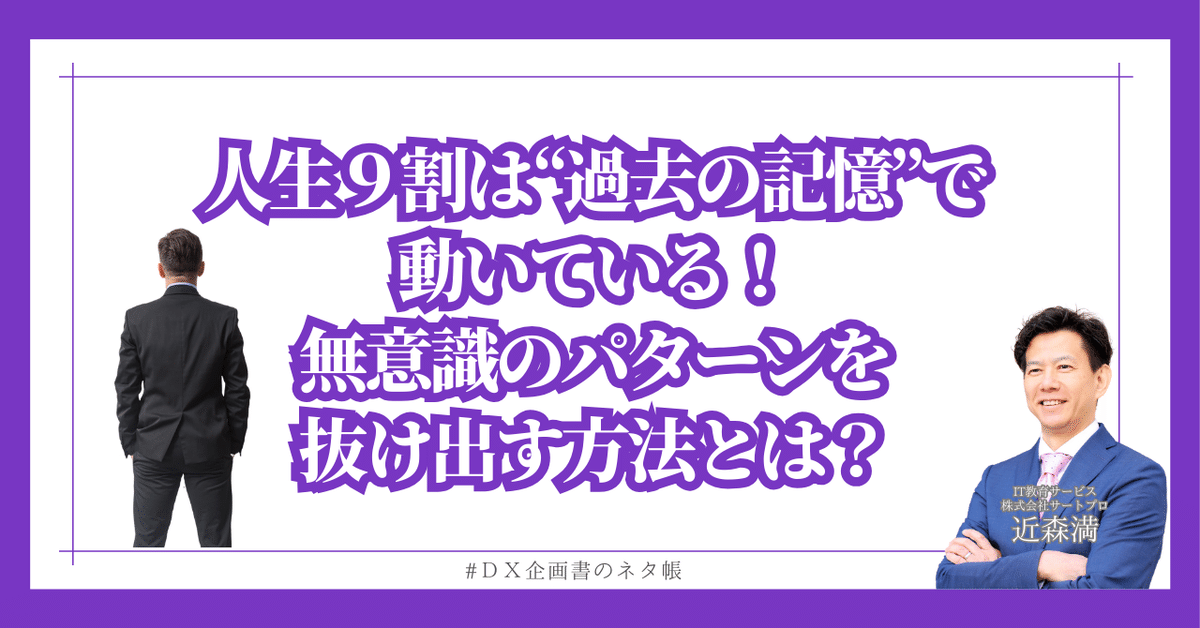
【記事概要】
この記事では、「人生の9割は過去の記憶で動いている」という視点から、無意識の習慣や思考のパターンが私たちの行動をどのように形作っているのかを掘り下げます。
近森満氏は、生成AIやDX推進の現場経験を交えながら、人間の脳がエネルギーを節約するために過去の経験を優先し、新しい選択を避けがちになるメカニズムを説明。
その上で、過去の枠から抜け出すための三つの問い
①今の自分が本当に望んでいることか?
②それは昔の正解ではないか?
③一度もやったことのない選択肢はないか?
を提示します。
また、残りの「1割の未来」を意識的に選択することで、新たな可能性を開く重要性を強調。生成AIの限界と活用法、マインドトランスフォーメーションの必要性にも触れ、読者に自己理解と自己対話を通じた行動変容を促します。
【著者情報】
こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。
www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/
当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。
www.certpro.jp/dxconsulting/
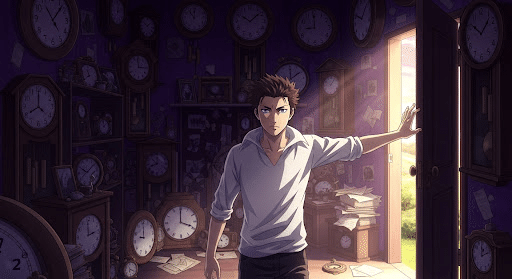
人生の9割は「過去の記憶」で動いているという事実
日々の行動や意思決定の大半は、実は過去の経験や記憶に基づいています。これは心理学的には「スキーマ理論」と呼ばれ、脳はエネルギー節約のために自動反応を優先する傾向があります。炊飯器のスイッチを押すとき、ご飯の炊き方をいちいち考えないのと同じように、ビジネスや生活の多くの選択も無意識のうちに過去のパターンに沿って行われているのです。
生成AIやAIエージェントが生活に浸透する現代では、時間短縮や生産性向上が容易になりましたが、同時に「過去のやり方」に固執する人も少なくありません。そこには安全志向や安心感もありますが、それが変化の足かせになることも多いのです。
なぜ人は過去の枠から抜け出せないのか
人間の脳は変化よりも安定を好みます。特に過去の成功体験や「正解」と信じたやり方は、脳内に強固な回路として定着します。これが「無意識の習慣」となり、新しい選択肢を検討するエネルギーを惜しむ原因です。
脳の省エネモードは、ある意味では効率的ですが、急速に変化する社会やDX推進の現場では、それが成長の阻害要因になります。
事例: ギターマガジンの購読習慣
長年続けてきた雑誌購読。毎月買うのが習慣になり、「買わないと過去の積み重ねが無駄になる」と感じてしまう。この心理は「サンクコスト効果」とも呼ばれ、過去の投資に縛られる典型例です。
この行動を振り返り、「今の自分が本当に望んでいることなのか?」と問うことで、無意識の習慣に気づくきっかけになります。
過去のパターンを打破する三つの問い
近森氏は、自らの経験と心理学的知見から、過去の枠を抜け出すための三つの問いを提案します。
①これは本当に今の自分が望んでいることか?
習慣や惰性で選んでいないかを確認する。
②それは昔の正解ではないか?
当時は正解だったが、今は状況が変わっている可能性を疑う。
③一度もやったことのない選択肢はないか?
意図的に未経験の選択を試すことで、思考の幅を広げる。
残りの「1割の未来」をどう活かすか
仮に人生の9割が過去の記憶で動いているとしても、残りの1割は「未来の選択」に使えます。この1割こそ、変化を生み出す突破口です。
未来はまだ何も決まっておらず、「今、この瞬間の選択」によって形作られます。だからこそ、ここでの行動が将来の10割になる可能性を秘めています。
生成AIと「過去の知識」
生成AIは、膨大な過去のデータを組み合わせて新しい文章やアイデアを提示します。一見新しいように見えても、そのほとんどは既存知識の再構成です。
したがって、AIを過信せず、自分自身が主体的に取捨選択し、オリジナルの発想を加えることが重要です。企業活用では、AIを「思考補助ツール」として最大限に活かすことがポイントになります。
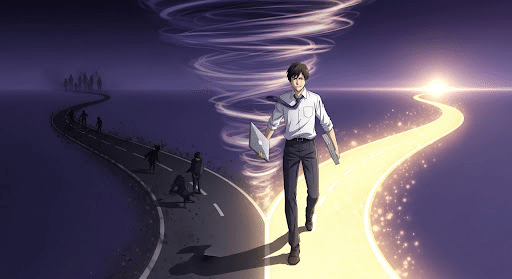
事例: DX推進プロジェクトでのAI活用
ある製造業のDXプロジェクトでは、AIが過去の生産データを解析して最適化案を提案しました。しかし、現場の作業員の暗黙知を反映させなかったため、提案が現実に即していなかった。このケースでは、人間の経験とAIの分析を融合させることで初めて成果が出ました。
マインド・トランスフォーメーションの重要性
過去からの無意識な行動パターンを変えるには、単なるスキルアップではなく「マインドセットの変革」が必要です。
近森氏が提唱する「マインド三姉妹」—マインドシフト、マインドチェンジ、マインドトランスフォーメーション—は、そのプロセスを体系化した考え方です。
まとめ:自己理解と自己対話が変化の起点
自分の行動の9割が過去の記憶に基づくことを理解し、その枠から抜け出すための問いを持ち続けることが、人生とキャリアを再設計する第一歩です。DX推進やAI時代においては、この柔軟性こそが最大の競争力となります。
いかがでしたでしょうか?
すこしでもみなさまの気づきになれたのであれば幸いです。
IT・DX教育サービスについてお悩みがある方は、ぜひ初回無料のオンラインコンサルティングをご利用ください。必ずお役に立ちます。
www.certpro.jp/dxconsulting/
生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。
セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。
certpro-generationaiservice.sfsite.me/
キーワードの解説
スキーマ理論
スキーマ理論とは、人間の思考や行動が過去の経験や記憶に基づく「枠組み(スキーマ)」によって自動化されるという心理学的モデルです。脳は膨大な情報を効率よく処理するために、既存のスキーマを参照して判断や行動を行います。これにより意思決定のスピードは上がりますが、新しい選択肢や変化を拒みやすくなるという副作用があります。DXやイノベーションの現場では、このスキーマに気づき、意識的に破ることが重要です。
マインド・トランスフォーメーション
マインド・トランスフォーメーションとは、価値観や思考の枠組みを根本から変える意識改革のプロセスです。近森氏の提唱する「マインド三姉妹」—マインドシフト(視点の転換)、マインドチェンジ(行動習慣の変更)、マインドトランスフォーメーション(根本的変革)—の最終段階にあたります。特に生成AIやDX推進時代では、技術やスキルだけでなく、このマインドの進化が持続的成長のカギとなります。
サンクコスト効果
サンクコスト効果とは、既に投資した時間・お金・労力を惜しむあまり、合理的な判断ができなくなる心理現象です。例えば、長年購読している雑誌を「今までの努力が無駄になる」と感じて買い続けることなどが該当します。過去の投資に縛られず、現在と未来の価値を基準に意思決定することが、変化と成長を促進します。
【著者紹介】
近森 満(ちかもりみつる)
■株式会社サートプロ 代表取締役CEO
IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。
■所属・役職
・IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定、+DX認定、超知性ASI検定)
・一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)
・電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)
・NPO 組込みソフトウェア管理者技術者育成研究会 メンバー(組込み)
・ET教育フォーラム合同会社 代表(コンテンツ制作)
・経済産業省地方版IoT推進ラボ ビジネス創出事業メンター(IoT支援)
・経済産業省地域DX推進ラボ ビジネス創出事業メンター(DX支援)
・デジタル庁デジタル推進委員(デジタル化支援)
・DX事業共同組合 設立理事(DX推進)
・一般社団法人日本サステナブルビジネス機構 幹事(SDGs認証)
・”一億総活躍社会を実現する”共生日本協議会 理事(DEI支援)
・アジャイル開発技術者検定試験コンソーシアム 事務局長(Agile検定)
・一般社団法人国際サイバーセキュリティ協会 事務局長(IACS認定)


