
【記事概要】
生成AIやAIエージェントを活用し、人間が全ての業務を抱え込むのではなく、適切に「任せる」ことで生産性を高める「70%ルール」と「タスク分離思考」の重要性を解説。
中小企業支援やDX推進現場での経験をもとに、経営者と現場のデジタル活用ギャップ、マインドトランスフォーメーションの必要性、成果共有のためのデータ活用方法を提示。AIの得意分野を見極め、議事録作成・情報収集・資料作成など繰り返し業務を委ねることで、人間は感情理解や人間関係構築など本来の強みを発揮できる環境を整えるべきと説く。
また、完璧を求めずたたき台としてAIを活用し、最終判断や文化的ニュアンス調整は人間が担うべきと提案。AIとの共存共栄を前提に、役割再定義と時間創出の戦略が今後の競争優位を決めるとまとめる。
【著者情報】
こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。
www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/
当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。
www.certpro.jp/dxconsulting/
いっそAIに任せた方がいい?
AI技術、とりわけ生成AIやAIエージェントの発展によって、「人間がやるべきこと」と「AIに任せるべきこと」を改めて考え直す時代が来ています。中小企業や自治体のDX推進を支援する中で感じるのは、経営者が掲げるデジタル化の方向性と現場の実務レベルでのデジタル活用には大きなギャップがあるという現実です。
多くの場合、経営者は「DXを進めたい」と口にしますが、現場では紙やアナログの業務プロセスが根強く残っています。パソコンやクラウドを使ってはいるものの、生成AIの導入はまだ遠い存在——そんな企業は少なくありません。
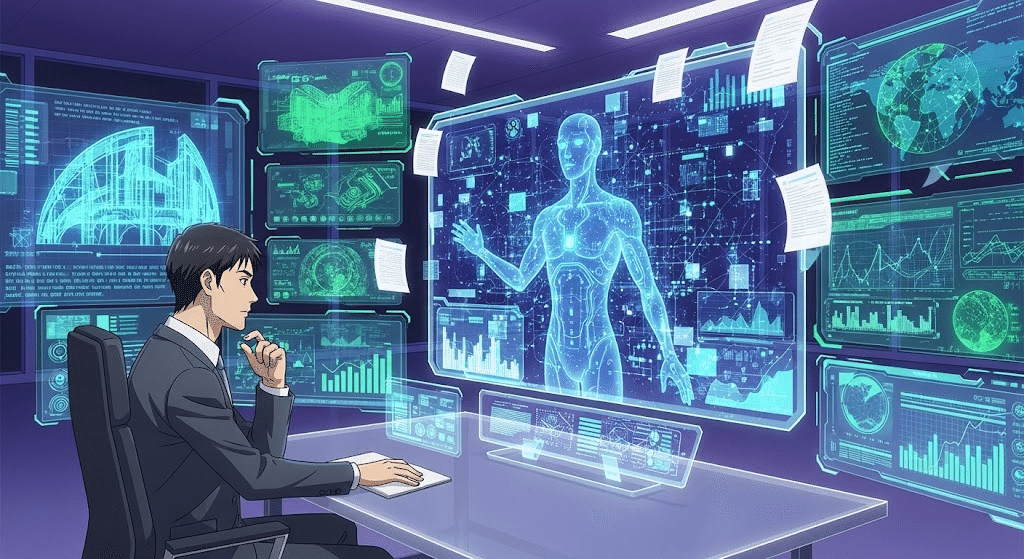
船頭多くして船進まず——マインド・トランスフォーメーションの必要性
DX推進において最初の壁となるのは技術導入ではなく「意識変革」です。マインドトランスフォーメーション、つまりマインドセットの転換こそが第一歩です。経営者が率先して変わろうとする姿勢は不可欠ですが、現場側には「今のやり方で迷惑はかかっていない」という慣習意識が根強くあります。
この停滞を打破するには、「変えないと誰かが困る」という状況設定と、それを後押しする仕組みが必要です。さらに、成果を共有するためのデータ可視化も欠かせません。日々の業務では変化を実感しづらくても、月単位・年単位での進捗や売上への貢献を数値として示すことで、社員の主体性を引き出せます。
事例: 研修事業の長期的視点
私の会社でも、研修や人材育成事業は年度や担当者の異動によって急に止まることがあります。そのため、単年度の売上責任だけでなく、長期的な成長を意識し、数値共有や成果指標を設定することで事業継続のモチベーションを保っています。
AIに任せる70%ルール
AI活用のカギは、「自分でやった方が早い」と感じるタスクであっても、70%の精度でAIがこなせるなら思い切って任せることです。生成AIはすでに議事録作成、情報収集、メールドラフト、テンプレート作成などの領域で高精度な成果を出せます。人間がやらなくても良い定型作業を手放すことで、本来注力すべき創造的・戦略的業務に時間を割けます。
タスク分離思考の実践
タスク分離思考とは、業務を「人間がやるべき領域」と「AIが担える領域」に切り分ける発想です。判断基準はシンプルで、「想像・判断・人間関係構築」が必要な仕事は人間、それ以外はAIに任せます。例えば、会議資料の要約やオンライン情報収集はAIに、最終的な意思決定や微妙な言葉遣いの調整は人間が担当します。
事例: プレゼン資料作成の分業
私はプレゼン資料作成の際、見出しや構成案はChatGPTで作り、中身の文章はClaudeで肉付けし、ビジュアル要素はGeminiや画像生成AIに任せています。AIごとの得意分野を見極め、適材適所で組み合わせることが効率化のコツです。
これもマルチモーダルのなせる技ですが、AIエージェントが発達すると、この分業も必要なくなるかもしれません。
AI活用の心構え——完璧を求めない
AIを活用する際は、完璧な成果を一発で期待するのではなく、たたき台として使う姿勢が重要です。指示は明確にし、期待値を設定した上で、最終調整は自分で行う。これは人に仕事を任せる場合と同じで、最後の5%〜10%は自分の色を加える工程だと割り切れば、スピードと質のバランスが取れます。
人間にしかできない仕事を再定義する
AIが苦手とするのは感情理解や文化的文脈の把握です。社内外の微妙なニュアンスや人間関係の調整、状況判断は人間の強みです。この「ラストワンマイル」を担うために、自分の時間を確保する——そのためにAIへ業務を委譲するのです。
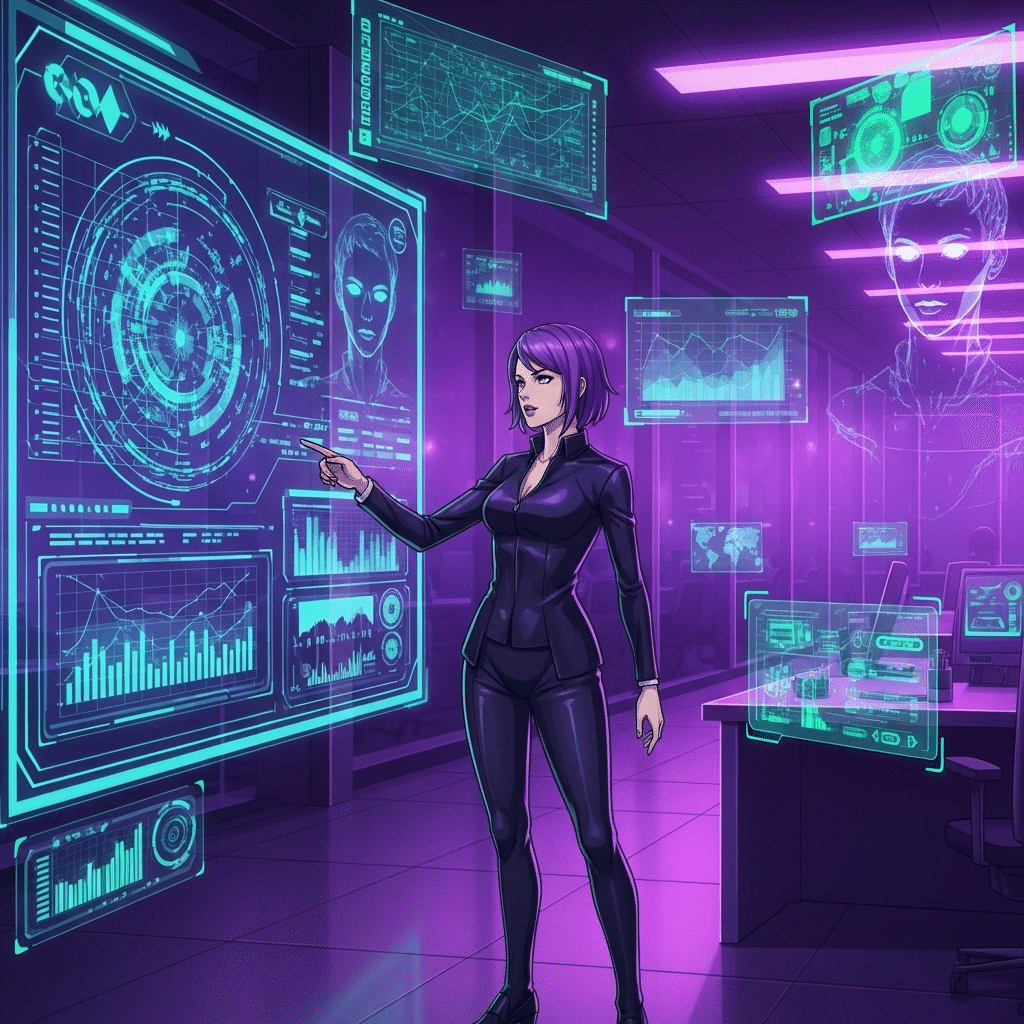
まとめ:AIと共存しながら競争優位を築く
AIは人間の集大成であり、しかも優秀な人材を何人も雇うのと同じ効果を持ちます。だからこそ、AIを恐れるのではなく、積極的に雇い入れる感覚で活用すべきです。AIと共存し、役割を再定義し、自分の強みを最大限発揮できる環境を作ることが、これからの競争優位の源泉になります。
いかがでしたでしょうか?
少しでもみなさまの気づきになれたのであれば幸いです。
DX推進担当者の育成やIT教育研修でお悩みがあれば、ぜひ初回無料のコンサルティング「DX推進人材教育プログラム」にご応募ください。かならずお役に立ちます。
www.certpro.jp/dxconsulting/
生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。
セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。
certpro-generationaiservice.sfsite.me/
【キーワードの解説】
・生成AI
自然言語処理や画像生成などの技術を活用し、人間の指示に応じて文章・画像・音声・プログラムコードなどを生成するAIの総称。ChatGPTやClaude、Geminiなどが代表例。定型業務やクリエイティブ作業の効率化、企画立案の支援など、ビジネス全般に応用が広がっている。
・マインドトランスフォーメーション
単なるスキル習得にとどまらず、仕事の進め方や価値観そのものを変革すること。DX推進では、経営者から現場まで全員が「変化を受け入れるマインドセット」を持つことが重要。
・タスク分離思考
業務を人間が行うべき領域とAIが担える領域に明確に分ける考え方。判断・創造・人間関係構築など感性が求められる部分は人間が担当し、情報整理や定型処理などはAIに委譲することで、生産性と創造性を両立させる。
【著者紹介】
近森 満(ちかもりみつる)
■株式会社サートプロ 代表取締役CEO
IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。
■所属・役職
・IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定、+DX認定、超知性ASI検定)
・一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)
・電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)
・NPO 組込みソフトウェア管理者技術者育成研究会 メンバー(組込み)
・ET教育フォーラム合同会社 代表(コンテンツ制作)
・経済産業省地方版IoT推進ラボ ビジネス創出事業メンター(IoT支援)
・経済産業省地域DX推進ラボ ビジネス創出事業メンター(DX支援)
・デジタル庁デジタル推進委員(デジタル化支援)
・DX事業共同組合 設立理事(DX推進)
・一般社団法人日本サステナブルビジネス機構 幹事(SDGs認証)
・”一億総活躍社会を実現する”共生日本協議会 理事(DEI支援)
・アジャイル開発技術者検定試験コンソーシアム 事務局長(Agile検定)
・一般社団法人国際サイバーセキュリティ協会 事務局長(IACS認定)


