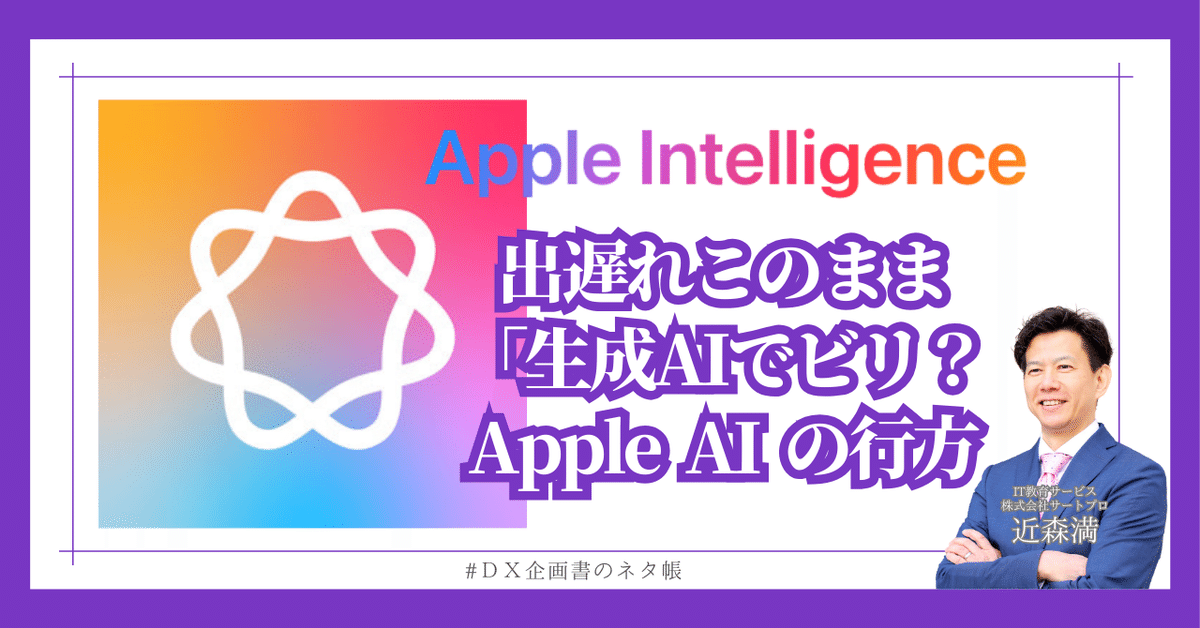
【記事概要】
今回のテーマは「出遅れたAppleはこのまま生成AIビリになってしまうのか?」です。Appleはこれまで革新的な製品で私たちの生活に驚きを与えてきましたが、生成AI分野ではOpenAIやGoogle、Microsoftなどに比べ後れを取っているという指摘があります。
番組では、過去のSiri導入やApple Intelligence発表を振り返りつつ、なぜ同社が生成AI競争で静観しているのかを分析。背景にはプライバシー保護を重視したオンデバイス処理方針や、過去のApple Mapsの失敗回避などがあるとされています。
さらに、パープレキシティ(Perplexity)の買収検討や、AI搭載製品の将来像にも触れ、単純な生成AI競争ではなく「生活や体にフィットする」独自価値の創出こそがAppleの真骨頂だと論じます。最終的には、Appleが生成AIレースから降り、他社と連携しながら独自の世界観を築くという選択肢も提示。ユーザーの期待と現実のギャップを整理しつつ、今後の巻き返しや全く新しい市場創出の可能性について展望します。

【著者情報】
こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。
www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/
当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。
www.certpro.jp/dxconsulting/
Appleの生成AI“出遅れ”は本当か?
生成AIの世界では、OpenAI、Google、Microsoft、Metaなどが次々と新機能を発表し、競争は激化しています。その一方で、Appleの動きは静かです。2024年に発表されたApple Intelligenceは一定の注目を集めましたが、ChatGPTやGeminiのように市場を沸かせるインパクトはまだ感じられません。過去のSiriの登場時のような「生活にフィットする驚き」をユーザーが待ち望む中で、「Appleはこのまま生成AIビリになるのでは?」という声も出始めています。
※この記事を音声配信した時点では、Apple IntelligenceをMACパソコン上でしか触っていませんでした。現在はiPhone16を所持しており、Apple Intelligenceを使うことができています。

参考:オケサンマさんのnote
なぜAppleは慎重なのか
背景には、Appleが長年掲げてきたプライバシー重視の哲学があります。ユーザーデータをクラウドに集めず、端末内で処理を完結させるオンデバイス処理を優先しており、これが生成AIの深い機能実装を遅らせている要因です。さらに、過去にApple Mapsを拙速にリリースして批判を浴びた経験から、未完成の技術を市場に投入するリスクを避けたい意向もあります。
事例: Apple Mapsの教訓
2012年、AppleはGoogle Mapsから独自マップに切り替えましたが、欠落や誤情報が多く、世界中から批判されました。この「失敗の記憶」は、生成AI戦略にも慎重さを植え付けています。
参考:CNET Japanの考察
競合との差
GoogleはGemini、OpenAIはChatGPTを軸にマルチモーダル化やコード生成などの新領域を開拓中。MicrosoftはCopilotをOfficeやWindowsに統合し、日常業務の中にAIを自然に組み込んでいます。これに対しAppleは、生成AI単体ではなく、既存のエコシステムや製品体験に深く融合させる方向を模索していると見られます。
パープレキシティ買収の可能性
最近では、AI検索プラットフォーム「Perplexity」の買収検討が報じられています。もし実現すれば、強力な検索機能と生成AIの知見をApple製品に統合でき、独自のApple流AI体験を創出できる可能性があります。ユーザーの質問に正確かつ整理された情報を返すPerplexityの強みは、AppleのUI/UX哲学と親和性が高いと考えられます。
参考:アップルがPerplexity買収に向け協議–AI戦略強化の一手となる可能性(ZD Netの記事)
事例: 他社によるAI人材争奪戦
Metaが数十億円規模で優秀なAIエンジニアを引き抜くなど、生成AI分野では人材獲得競争が激化。Appleも本格参入するなら人的リソースの確保は必須です。
「降りる」という選択肢
番組内では、「生成AIレースから降りてしまえばビリにはならない」というユニークな提案も出ました。Appleはハードウェア設計や世界観づくりに注力し、AIは他社と連携して取り入れる戦略です。過去の成功も、必ずしも自社開発にこだわらず、優れた技術を取り込みApple流に昇華させる手法から生まれています。
新市場の創出とAIの役割
真のAppleらしさは、既存市場を驚かせる新カテゴリー創出にあります。脳波を読み取って思考を即座に言語化するデバイスや、生活習慣を先回りして支援する“秘書型AI”など、生活や身体に自然に溶け込む体験を提案できれば、生成AI分野でも他社にない価値を示せます。
事例: 身体拡張型AIのビジョン
たとえば朝起きる前にMacが自動で起動し、今日のスケジュールを最適化、集中を乱すアプリをブロックする。これほど生活に密着すれば、単なる「生成AI」ではなく「生活の一部」として愛用されるでしょう。
まとめ:Appleはどこへ向かうのか
Appleがこのまま生成AI競争の後塵を拝するのか、それとも既存市場を超える新しい体験を提供するのかは、今後1〜2年で明らかになります。単純な機能競争ではなく、「生活にフィットする体験」というAppleらしさを貫くかどうかが鍵です。
いかがでしたでしょうか?
すこしでもみなさまの気づきになれたのであれば幸いです。DX推進担当者の育成やIT教育研修でお悩みがあれば、ぜひ初回無料のコンサルティング「DX推進人材教育プログラム」にご応募ください。かならずお役に立ちます。
ではまた。
www.certpro.jp/dxconsulting/
生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。
セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。
certpro-generationaiservice.sfsite.me/
【キーワードの解説】
生成AI(Generative AI)
生成AIとは、テキスト・画像・音声・動画などの新しいコンテンツを自動生成する人工知能技術です。大量の学習データをもとにパターンを学び、与えられた指示や質問に応じてオリジナルのアウトプットを生み出します。ChatGPTやGoogle Geminiのように自然言語処理能力を高めたモデルは、検索や文章作成、コード生成、翻訳、要約など多岐にわたる用途に活用されています。企業では業務効率化や新規サービス開発の基盤技術として導入が進み、競争優位性を左右する重要要素になっています。
オンデバイス処理
オンデバイス処理は、ユーザーのスマートフォンやPCなど端末内でデータを処理する方式です。クラウドにデータを送信せずに完結するため、通信遅延を減らし、プライバシーやセキュリティを強化できます。Appleはプライバシー重視の姿勢からこの方式を推進しており、生成AI機能もできる限り端末内で動作させる方向を取っています。これはユーザー信頼の確保に有効ですが、AIモデルの規模や機能面で制約が生じやすいという課題もあります。
Apple Intelligence
Apple Intelligenceは、Appleが自社デバイスに搭載する生成AI機能群の総称です。Siriの進化形として自然言語理解を強化し、文章要約、文章生成、画像編集、アプリ連携などを行います。他社AIとの差別化ポイントは、ユーザーデータをクラウドに集約せずオンデバイス処理を優先することと、Apple製品間の緊密なエコシステム統合です。現時点では市場を驚かせるほどの新機能は少ないものの、今後のアップデートや新製品との組み合わせで進化が期待されています。
【著者紹介】
近森 満(ちかもりみつる)
■株式会社サートプロ 代表取締役CEO
IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。
■所属・役職
・IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定、+DX認定、超知性ASI検定)
・一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)
・電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)
・NPO 組込みソフトウェア管理者技術者育成研究会 メンバー(組込み)
・ET教育フォーラム合同会社 代表(コンテンツ制作)
・経済産業省地方版IoT推進ラボ ビジネス創出事業メンター(IoT支援)
・経済産業省地域DX推進ラボ ビジネス創出事業メンター(DX支援)
・デジタル庁デジタル推進委員(デジタル化支援)
・DX事業共同組合 設立理事(DX推進)
・一般社団法人日本サステナブルビジネス機構 幹事(SDGs認証)
・”一億総活躍社会を実現する”共生日本協議会 理事(DEI支援)
・アジャイル開発技術者検定試験コンソーシアム 事務局長(Agile検定)
・一般社団法人国際サイバーセキュリティ協会 事務局長(IACS認定)


