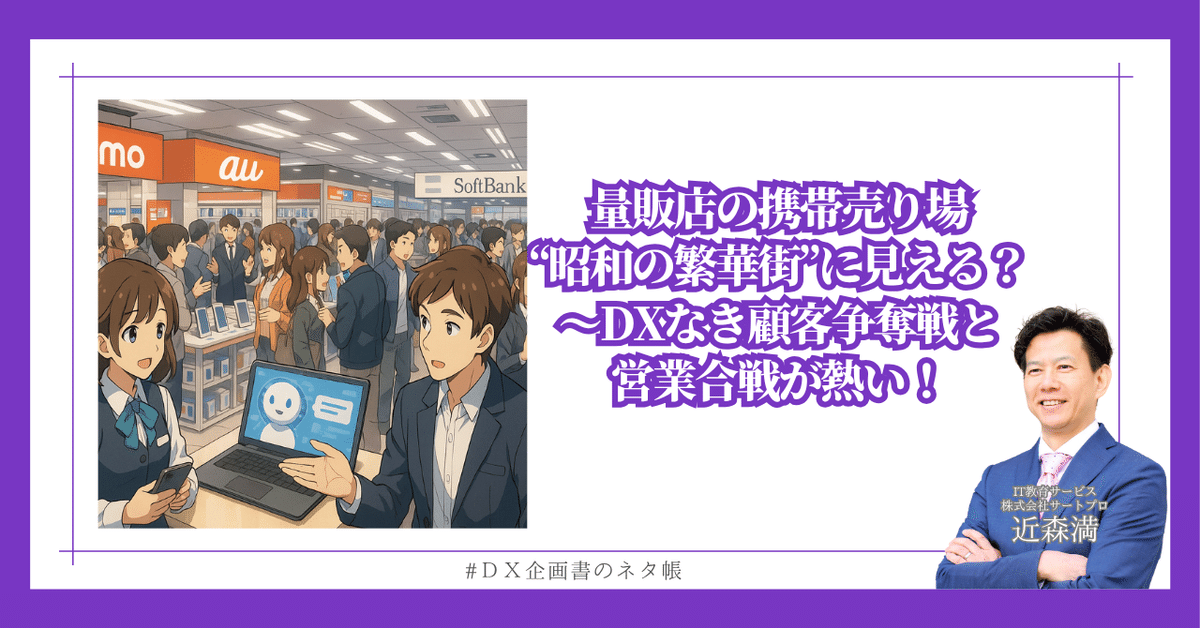
【記事概要】
量販店の携帯電話売り場が「昭和の繁華街」のように見える――そんな現象に遭遇した私が、携帯キャリア契約を通じて体感した“営業戦争のリアル”をレポートします。近森満自身や家族のスマートフォン契約を乗り換える過程で、大手量販店の1階を占めるキャリアブースの“異様な熱気”に触れました。池袋の某大型電機店では、キャリアのスタッフが30人以上も配置され、来店者に猛烈な勢いで声をかけてくる様子は、まるでかつての繁華街で繰り広げられた客引きのよう。
生成AIが進化し続ける一方で、こうした“人の熱量”による営業現場は、今もなお圧倒的な存在感を放っているのです。この現象を通じて、AIがまだ介入できない“営業”という領域の本質や、多国籍化が進む都市部の接客現場のリアルを深掘りし、DX推進における人間の役割を再考する一助とします。
【著者情報】
こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。
www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/
当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。
www.certpro.jp/dxconsulting/
スマホの契約変更から始まった“違和感”の正体
先日、私は長年使っていたソフトバンクのスマホからドコモのahamoプランへと契約を切り替えました。6月末でahamoの旧プランが終了するということで、ちょっとした駆け込みでしたが、「これはいい!」と思える内容だったので迷わず切り替えを決断。
さらに、手元に余っていた番号を活かして格安プラン(たしかirumo?)への切り替えも検討しましたが、うまくいかず、仕方なく別の番号でソフトバンク新規→MNPでドコモへ、という“二段ジャンプ”を実施しました。
まあ、こんなことをするのも、常時”生成AIを回せる端末”がもう1台欲しかったからなんです。
私はiPhoneとAndroidの2台持ちをしていて、iPhoneは日常使い、Androidは生成AIなどの実験用途と決めているんですね。
このように、スマホの契約や買い替えは、デジタル人材としての私にとっては“日常的なリスキリング”でもあるわけです。
池袋の量販店で目撃した「接客の昭和」
そして、事件(?)は息子のスマホ契約変更の付き添いで起こりました。
「父さん、池袋のY電機に行くから、ちょっと来てくれない?」
と頼まれて向かったその店の1階フロアは、見渡す限り“携帯電話の契約ブース”に占拠されていたのです。
およそ昭和の繁華街、あるいは戦国時代の城下町さながら。
大手キャリア3社(ドコモ、ソフトバンク、au)に加えて、ワイモバイルやUQモバイル、さらには格安ブランドまで所狭しとブースが並び、それぞれが自陣営の兵をズラリと並べ、まるで「こっちの陣営が得だよ!」と口説き落とさんばかりの勢いで声をかけてきます。
一歩ブースに近づこうものなら、「お探しの機種ありますか?」「お子さまの契約ですか?」「番号そのまま乗り換え可能ですよ!」と、矢継ぎ早にセールストークが飛び交う。
正直、営業力の物量戦ってやつですね。しかも、人件費をかけた“リアル営業”。
これ、生成AIではまだ再現できない領域だと、改めて実感しました。
人が作る“熱”と“空気感”はAIに任せられない
量販店の1階フロアに、あれだけの人数がいて、なおかつすべてのテーブルに客が座っている光景――これは相当なインパクトです。
その様子は、夜の繁華街で呼び込みの兄ちゃん姉ちゃんに囲まれるような感覚にも似ていて、まさに“昭和の営業文化”が現代にタイムスリップしてきたような錯覚すら覚えました。
もちろん、現場のスタッフは多国籍。
中国系、東南アジア系、中東系と、多様なルーツを持つ人たちが、流暢な日本語で熱心に接客しているのです。
これはまさに“多国籍接客力”とも言うべきもので、日本社会の変化も映し出していると感じました。
そしてここがポイントなのですが――
このような営業合戦に、生成AIはまだ入ってきていない。
もちろん、各社の裏側では生成AIによるプラン提案支援やFAQ自動応答などの仕組みが入っている可能性は高いですが、目の前の「いらっしゃいませ!」「この機種がいま一番人気です!」という生身のコミュニケーションには、やはり“人間の熱量”が必要なのです。
事例: キャリアブースに集結する“人間力”営業戦略
特筆すべきは、「人間一人に一契約」というマンツーマン対応が前提であるということ。
それゆえ、常に人手が必要であり、その場での判断力、提案力、機転、そして人当たりの良さ――そういったものが総合的に求められる。
つまり、ここには“デジタルスキル”ではなく“対人スキル”の戦場が広がっていたのです。
この状況は、DX文脈では逆説的ですが、だからこそ学びになる。
「この営業体験は、どうやったらAIや自動化に変換できるのか?」
「そもそも、変換するべきなのか?」
「“人の存在”が持つ説得力や安心感を、DX時代にどう位置づけるべきか?」
そんな問いが浮かび上がってきます。
“昭和的な営業”の意味を問い直す
今回の量販店体験を通して、私はある意味で“ノスタルジー”すら感じました。
私が若い頃、秋葉原や渋谷のラジオ会館で見かけたガジェット販売員たち。
道端で手渡されたチラシ、対面での価格交渉、雑談まじりの説得――
あれは、AI時代の今でも、ある種の“人間らしい営業体験”として価値があるのではないかと。
もちろん、オンラインでの契約やeSIMの普及によって、物理的な店舗の存在意義は縮小しつつあります。
しかし、こうした“熱気のある売り場”は、教育現場や人材育成のヒントにもなりうるのです。
教育現場が学ぶべきは“営業現場”のリアリティ
私は教育事業をしていますが、今回のような現場を見て思いました。
「研修やeラーニングで、人間の“情熱”や“臨機応変な対応力”をどう伝えるのか?」
たとえば、AIチャットボットに対するプロンプトエンジニアリングは高度なスキルですが、目の前の顧客の反応を見ながら言葉を変える営業トークのほうがよほど難しい場面もある。
つまり、「AIにできること」と「人間にしかできないこと」を再整理し、人材育成プログラムに組み込んでいく必要があるのです。
そしてこれは、超知性AI時代における“超人間力リテラシー”と言ってもいいかもしれません。
まとめ:AI時代の“人間の価値”再考
今回の話は、携帯電話の契約ひとつから、DX文脈における人材戦略の再定義にまでつながりました。
昭和的な営業の本質、それは「人を惹きつける力」。
デジタルで効率化される世界の中でも、人間の“熱量”はやはり無視できないのです。
教育現場においても、企業のDX推進現場においても、
「この熱をどう伝えるか」「この対応力をどう育てるか」
そこに、私たち教育事業者の役割があるのだと再認識しました。
キャリア契約の現場からDX人材教育まで――これが“現場視点のDX企画書”です。
いかがでしたでしょうか?
すこしでもみなさまの気づきになれたのであれば幸いです。
IT・DX教育サービスについてお悩みがある方は、ぜひ初回無料のオンラインコンサルティングをご利用ください。必ずお役に立ちます。
www.certpro.jp/dxconsulting/
生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。
セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。
certpro-generationaiservice.sfsite.me/
【キーワードの解説】
生成AI
生成AI(Generative AI)とは、文章・画像・音声・映像などのデータを学習し、新たなコンテンツを創造するAI技術です。ChatGPTやMidjourney、DALL·Eなどが代表例です。DX推進においては、カスタマーサポートや商品提案、教育支援など様々な場面で活用されていますが、記事で触れた携帯売り場のような“人間の熱量”を要する領域では、まだ限界も存在します。
DX(デジタル・トランスフォーメーション)
DXとは、デジタル技術を活用して業務プロセスやビジネスモデルを変革し、企業競争力を向上させる取り組みを指します。単なるIT導入ではなく、マインドセットの変革や組織文化の更新が不可欠です。本記事では、対面営業の現場から“人間の力”の再定義がDXにおいて重要であることを提起しています。
多国籍人材・多様性対応力
現代の都市型販売現場では、外国籍の販売員や多様な文化背景を持つ顧客が混在するため、「多国籍対応力」は重要なスキルとなっています。これは単なる語学力にとどまらず、文化的背景の理解や非言語コミュニケーションの感性などを含みます。今後のDX推進における“現場リテラシー”として注目されています。
【著者紹介】
近森 満(ちかもりみつる)
■株式会社サートプロ 代表取締役CEO
IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。
■所属・役職
・IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定、+DX認定、超知性ASI検定)
・一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)
・電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)
・NPO 組込みソフトウェア管理者技術者育成研究会 メンバー(組込み)
・ET教育フォーラム合同会社 代表(コンテンツ制作)
・経済産業省地方版IoT推進ラボ ビジネス創出事業メンター(IoT支援)
・経済産業省地域DX推進ラボ ビジネス創出事業メンター(DX支援)
・デジタル庁デジタル推進委員(デジタル化支援)
・DX事業共同組合 設立理事(DX推進)
・一般社団法人日本サステナブルビジネス機構 幹事(SDGs認証)
・”一億総活躍社会を実現する”共生日本協議会 理事(DEI支援)
・アジャイル開発技術者検定試験コンソーシアム 事務局長(Agile検定)
・一般社団法人国際サイバーセキュリティ協会 事務局長(IACS認定)


