
【記事概要】
生成AIの登場によって、IT業界はその根幹から変革を迫られています。本稿では、近森満氏が語る「生成AIとIT業界の未来」について、音声配信第1802回の内容をもとに深掘りしていきます。
エンジニアが日々抱えるストレスやメンタル不調の原因に着目し、生成AIがそれらを軽減する可能性を示唆。また、AIによるコーディング支援が業務効率を大きく向上させることで、人間が本来注力すべき創造的な仕事へとシフトする未来像を提示します。さらに、エンジニアが減るのではなく、むしろITを理解し活用できる人材が今後増加していくとの展望も語られました。
本記事は、AI時代におけるエンジニアのキャリアとマインドセットの再構築、さらにはIT業界全体の構造転換へのヒントを提供します。
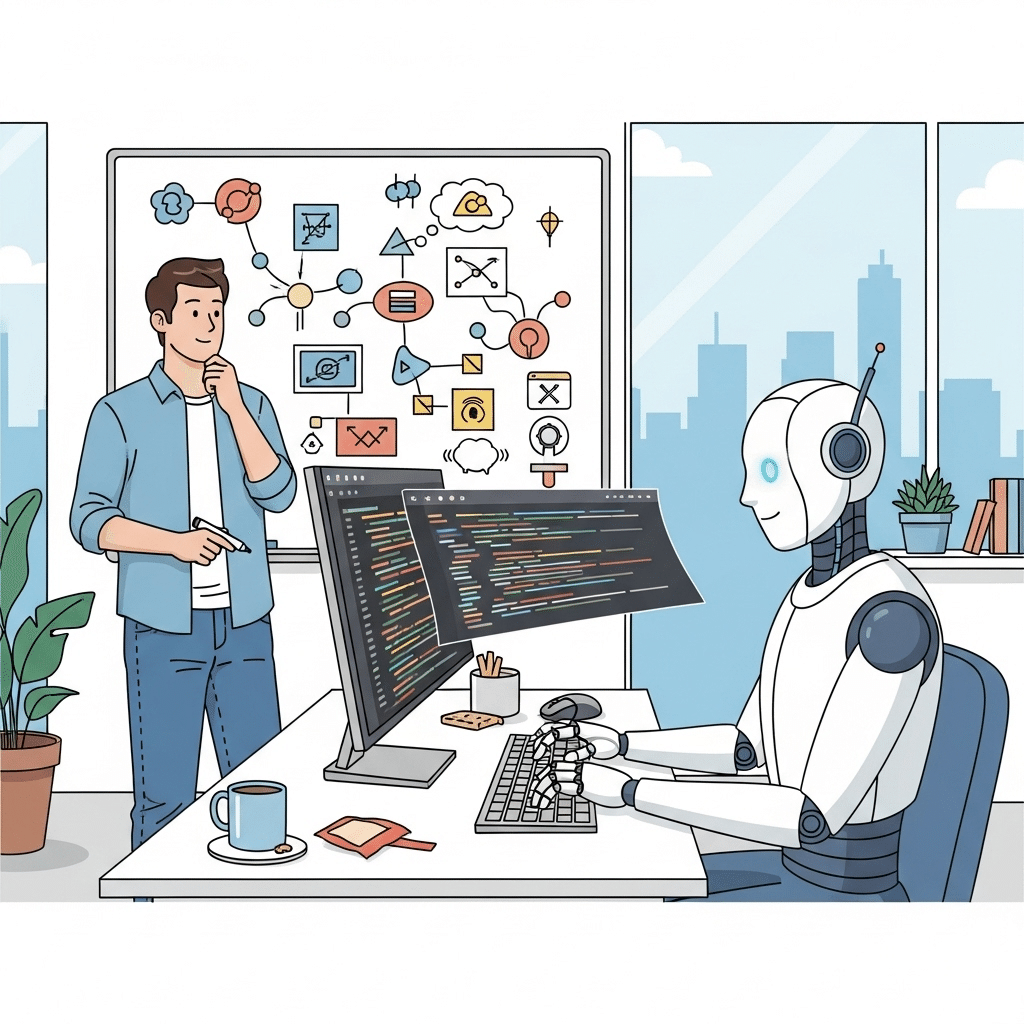
【著者情報】
こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。
www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/
当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。
www.certpro.jp/dxconsulting/
生成AIが切り開く“仕事の地平線”
生成AI(Generative AI)が私たちの働き方に与えるインパクトは、想像以上に大きいものがあります。特にIT業界においては、その影響は表面的なツールの進化ではとどまらず、業界構造の根底からの再編を促すものとなりつつあります。
私自身、IT業界に身を置いて40年を超え、今も現役でデジタル人材の育成に携わっています。その中で強く感じるのは、生成AIによって“エンジニアの役割”が変わりつつあるという現実です。
かつては、要件定義から設計、コーディング、テストまで、全て人の手で行っていた開発工程。これが今では、「設計」や「要件定義」の“隙間”すらAIが補完してくる時代になってきました。つまり、1から10まで人間が行っていた作業のうち、2〜9は生成AIが担う未来がすぐそこにあるのです。
「守る」ためのAI仕事術
生成AIの真価は、「人間の代替」ではなく「人間の支援」にあります。これは、単なる効率化だけでなく、人間のメンタルを守るという側面からも注目すべきポイントです。
IT業界、とくにソフトウェア開発の現場では、精神的に疲弊するエンジニアが多いことが課題として挙げられます。なぜか?
それは、「わかってもらえない苦しさ」「技術の不透明さ」「責任の押し付け構造」に起因するものが少なくありません。
例えば、社内システムの不調が発生した際、ユーザー側からは「とにかく早く直してくれ」とプレッシャーがかかる。その背景にある複雑なネットワーク構造や、外部要因の影響などは理解されにくい。それでも、「すぐやってくれ」と要求されてしまう――このストレスが積み重なり、メンタルを病む要因にもなっているのです。
しかし、ここに生成AIを活用すればどうでしょう。
障害分析の自動化、エラー解決支援、ドキュメント作成補助など、AIが“支える”役割を果たすことで、エンジニアは孤立から脱却できます。
デジタルネイティブではなくても、活躍できる未来
音声配信を毎日1,800回超えで実践してきた身として思うのは、「デジタルネイティブじゃなくても、AIを使いこなせる時代が来ている」ということです。
私自身、PCを触らない日はないほどデジタルに依存した生活をしていますが、それでも“デジタルネイティブ”とは言えない世代です。それでも、「話す」ことで情報を発信し続け、「触れ続ける」ことで新しいテクノロジーを自分の言葉に変換して伝えています。
生成AIも同じです。
最初は戸惑い、敷居が高く感じても、日々の業務の中で「AIに聞いてみよう」「下書きをAIに任せてみよう」といった小さな試みを重ねることで、自分の“分身”のような存在に変わっていきます。
これが、“自分を守るAI仕事術”です。
IT業界が変わる3つの構造転換
今、生成AIの登場によって、IT業界は以下のような3つの構造転換期を迎えています。
① 手作業→AI自動化:コーディングは“ゼロから書かない”時代へ
AIによるコード自動生成は、もはや実用段階に入っています。GitHub CopilotやChatGPTの活用により、プロトタイピングや修正提案はAIに任せることができ、エンジニアは“思考と設計”に集中できる環境が整ってきました。
② IT人材の再定義:マインドセットとマインドチェンジの時代
プログラムを書くことだけがITスキルではなくなっています。AIを活用しながらビジネスに適応する“超知性リテラシー”や、データドリブンな意思決定が求められます。
③ 顧客対応から共創へ:ストレスの源泉から“共感”へ
ユーザーとの関係性も変わります。AIがFAQ対応や一次サポートを担い、エンジニアは“問題の本質”に向き合う余裕が生まれ、対話力や共創力が重要になってきます。
事例: ITサポート部門の“生成AI導入による劇的改善”
ある中堅製造業のIT部門では、社内ヘルプデスク対応に追われていた2名のエンジニアが、ChatGPTベースのFAQボットを導入。結果、対応件数は週300件→80件に減少し、本来の業務である社内システム改修やセキュリティ強化に時間を投下できるようになりました。
AIが変えるのは「人の数」ではなく「人の質」
よく「AIでエンジニアが減るのでは?」という声を聞きますが、私は逆に“ITを理解できる人”は今後さらに増えていくと考えています。
なぜなら、生成AIをはじめとした新しいツール群が“ITの壁”を取り払ってくれるからです。専門知識がなくても、適切なプロンプト(指示)を与えれば、AIはエンジニアのように答えてくれます。そしてその結果から学び、「理解する力」が高まっていくのです。
つまり、AIによって「技術人材の裾野」が広がるのです。
まとめ:生成AIは、IT業界を「より人間らしくする」
生成AIはIT業界を機械的にするのではなく、むしろ「人間らしくする」ためのツールです。人間が本来持つべきクリエイティビティ、共感、判断、対話といった力に集中するための“余白”を、AIが作ってくれるのです。
この“余白”を活用し、新たなキャリアパスを設計することこそ、DX推進時代における真の「人材戦略」と言えるのではないでしょうか。
いかがでしたでしょうか?
すこしでもみなさまの気づきになれたのであれば幸いです。
IT・DX教育サービスについてお悩みがある方は、ぜひ初回無料のオンラインコンサルティングをご利用ください。必ずお役に立ちます。
www.certpro.jp/dxconsulting/
生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。
セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。
certpro-generationaiservice.sfsite.me/
【キーワードの解説】
生成AI(Generative AI)
生成AIとは、テキスト、画像、音声、コードなどを自動で“生成”する人工知能のことです。代表的なツールにChatGPTやMidjourney、GitHub Copilotなどがあります。特にIT業界では、コード補完、テストケース生成、文書化などに活用されており、開発工数の削減や作業の質的向上に大きく貢献しています。また、エンジニア以外の職種でも、業務効率化や企画立案支援に使われています。
超知性リテラシー
超知性リテラシーとは、AGI(汎用人工知能)やASI(超知能)など、現在のAIを超える知性と共に生きるために必要な能力を指します。単なるツール操作スキルではなく、AIとの協働、倫理的判断、意思決定支援など、社会的・心理的スキルも含まれます。AI時代において「信頼できる情報を見極め、活用する力」として、教育現場や企業研修でも注目されています。
マインドセット/マインドチェンジ
マインドセットは「思考の型」、マインドチェンジは「その型を意図的に変える行為」です。AI時代の変化に対応するには、既存の“できる・できない”の価値観や、上下関係に基づいたコミュニケーションスタイルを見直し、柔軟で探索的な姿勢を育むことが重要です。生成AIの活用においても、まずは“試してみる”ことがマインドチェンジの第一歩とされています。
【著者紹介】
近森 満(ちかもりみつる)
■株式会社サートプロ 代表取締役CEO
IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。
■所属・役職
・IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定、+DX認定、超知性ASI検定)
・一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)
・電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)
・NPO 組込みソフトウェア管理者技術者育成研究会 メンバー(組込み)
・ET教育フォーラム合同会社 代表(コンテンツ制作)
・経済産業省地方版IoT推進ラボ ビジネス創出事業メンター(IoT支援)
・経済産業省地域DX推進ラボ ビジネス創出事業メンター(DX支援)
・デジタル庁デジタル推進委員(デジタル化支援)
・DX事業共同組合 設立理事(DX推進)
・一般社団法人日本サステナブルビジネス機構 幹事(SDGs認証)
・”一億総活躍社会を実現する”共生日本協議会 理事(DEI支援)
・アジャイル開発技術者検定試験コンソーシアム 事務局長(Agile検定)
・一般社団法人国際サイバーセキュリティ協会 事務局長(IACS認定)


