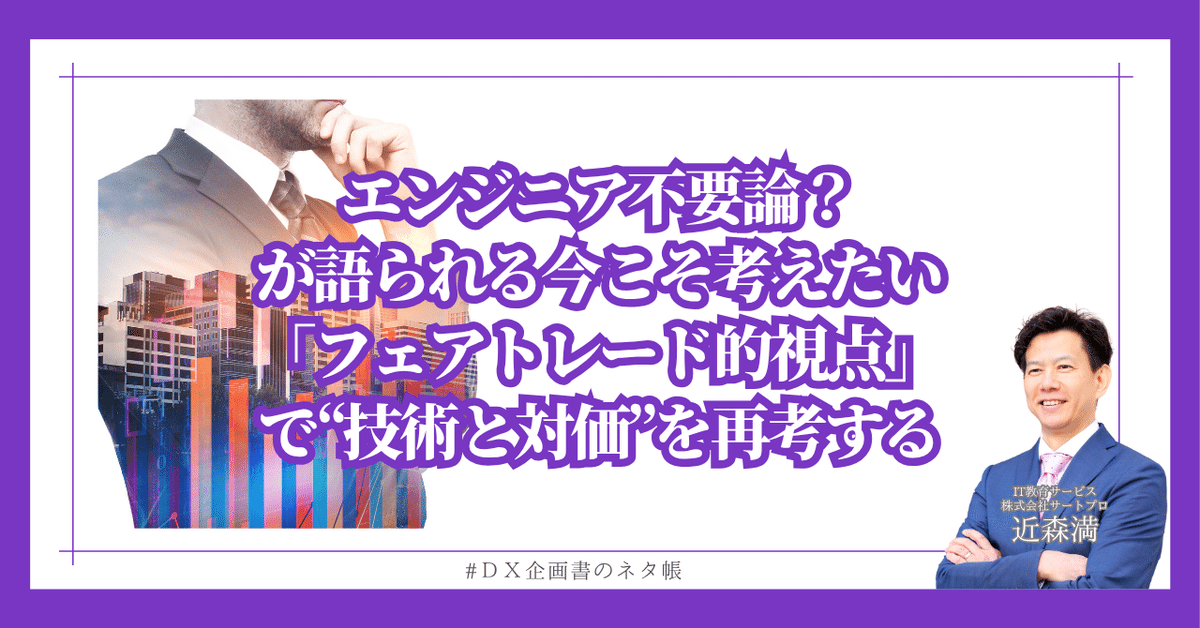
【記事概要】
生成AIの進化により、エンジニア不要論が再燃しています。しかし本当にエンジニアは不要なのでしょうか?
本記事では、IT教育とDX推進に取り組む筆者・近森満が、フェアトレードの思想をヒントに、「技術と対価のバランス」や「エンジニアの価値の再定義」について語ります。技術者を部品のように扱うのではなく、その個性や成長を支援する仕組みづくりが不可欠であり、プロフェッショナルへの道筋を整えることが企業にとっても重要です。
AIに補完される時代だからこそ、人間の創造性や社会実装力を育むための「公正な仕組み」が必要です。単なる労働力ではなく、知的資産としてのエンジニア育成が求められる今、企業と個人の両面からのマインドセット変革が急務です。本稿は「エンジニアの自立と共創の価値」を再認識し、未来の技術社会の担い手に求められるスキルと姿勢について考察します。
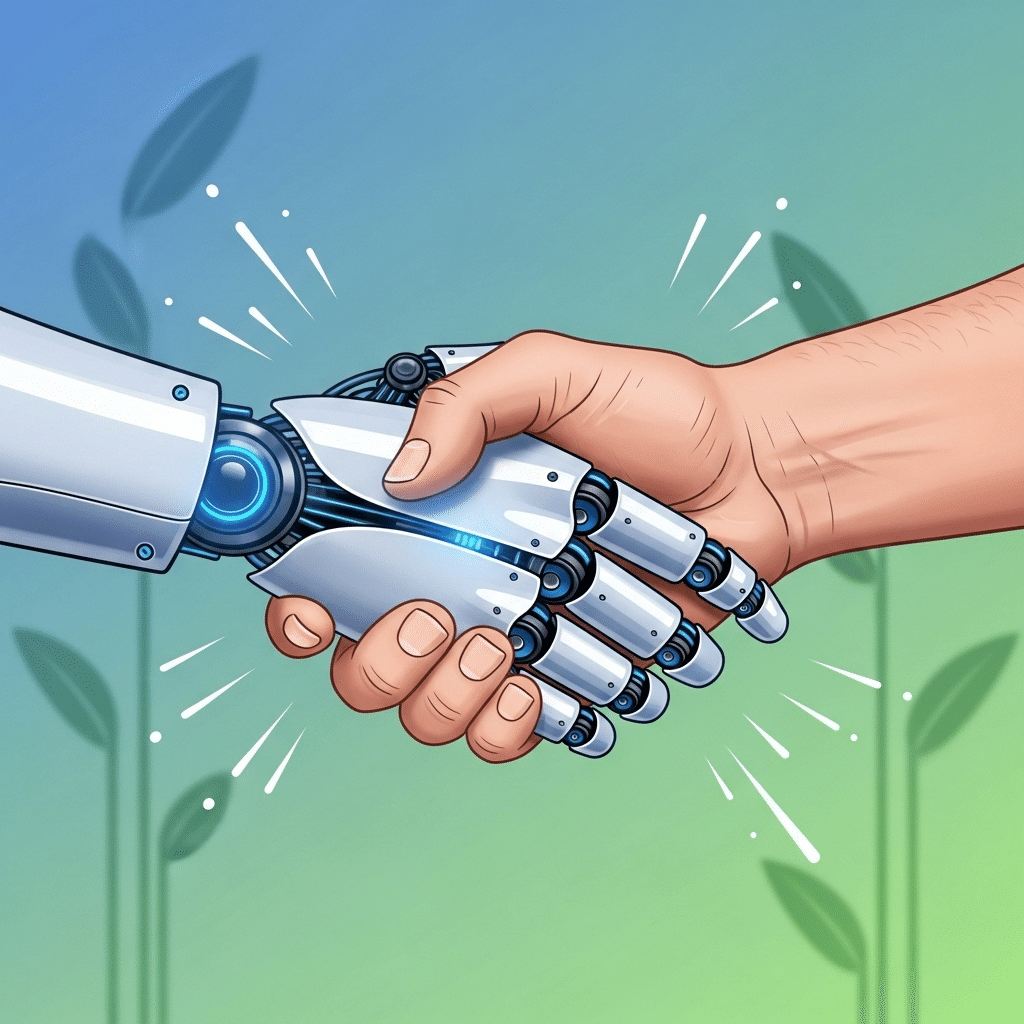
【著者情報】
こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。
www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/
当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。
www.certpro.jp/dxconsulting/
エンジニア不要論の時代に「技術の意味」を問い直す
近年、「生成AIによって初級エンジニアはもう不要なのでは?」という言説がネットや企業内で飛び交っています。まるで、エンジニアの価値が自動化によって無効化されたかのように。それはまるで、大量生産された機械部品の中に不良品が混ざっていたら、その部品が悪いと言われるのと同じ論理です。
ですが、人は機械部品ではありません。一人ひとりが唯一無二の個性を持ち、単なる「稼働時間」では測れない創造性や文脈理解力を内包しています。だからこそ、失敗や非効率の原因を「人」のせいにするのではなく、仕組みや制度設計のあり方を再設計すべきなのです。
その観点から今回私は、エンジニアの仕事や報酬のあり方を「フェアトレード(公正取引)」の思想から見直してみたいと思います。
フェアトレードに学ぶ、価値交換の再定義
フェアトレードとは、発展途上国の小規模生産者に対して、搾取されない価格で農産物や工芸品などを取引し、持続可能な生活と経済発展を支援する考え方です。つまり、「正当な価値を、正当な対価で交換しよう」という仕組みです。
このフェアトレードの文脈を、エンジニアやIT業界に応用して考えてみたらどうなるでしょうか?
発注側(企業)と受注側(エンジニアやベンダー)が、技術力という「知的労働」に対して、正当な報酬や教育機会を提供できているのか。特に、生成AIの登場によって「自動化で事足りる部分」が増える今、エンジニアの“時間労働”ではなく、“価値提供”に焦点を当てる必要があります。
事例: 技術者の時間価値 vs. 知的資産価値
たとえば、胡椒やカカオなどの一次生産物は、原産地では1円で買い叩かれ、先進国の市場では100倍の価格で販売されています。生産者にはその利益が還元されていません。エンジニアリングの世界でも同じような構造が起きていないでしょうか?
ソースコードはAIが自動生成できても、それを「どのように活用し、どう社会に実装するか」という設計力や倫理観は、人間の知性でしか担保できません。ここにこそ、エンジニアの真の「価値源泉」があるのです。
成長と評価が循環する「仕組み」をつくる
私は「制度設計屋」を自称しています。技術者として始まり、教育者として、そして今は仕組みを設計する側に立っています。その理由は、人間の成長や挑戦を支えるには、「適切な仕組み」こそが最重要だからです。
AIがどれほど進化しようとも、「人間は感情を持ち、学習し、成長する存在」であるという事実は変わりません。だからこそ、プロの技術者が初級者を育成できるような時間軸や環境設計が必要なのです。
事例: バックエンドは書けてもフロントは自信がない技術者
ある開発者が素晴らしいバックエンドのAPIを設計できたのに、フロントエンドの実装には不安を感じていたそうです。でも、生成AIの助けを借りて自分でもフロントを構築できたことで、「エンジニアとして一歩踏み出せた」と言っていました。
これは「AIの助けがあったからこそ、知的資産に自信を持てた」好例です。AIが補完することで、人間の成長意欲が引き出される――これが持続可能な「共創社会」への第一歩なのです。
マインドセットの転換がカギ
しかし、そのためには私たち一人ひとりがマインドチェンジをしなければなりません。
「時間を切り売りする労働」から、「知的資産としての価値創出」へ。
「言われたことをやる」から、「仕組みを考え、巻き込む」へ。
「評価されるのを待つ」から、「自ら環境を選び、自分を評価する」へ。
これらの変化は、単なるスキルチェンジではなく、マインドセットの書き換えを意味します。
エンジニアのキャリアパス再考:4つのフェーズ
エンジニアの成長は、大きく4つのフェーズで捉えることができます。
労働者:
時間を提供し、指示を受けてタスクをこなす段階
専門職:
特定のスキルでプロとして価値提供する段階
プロデューサー:
仕組みや制度を設計し、他者を巻き込む段階
共同経営者・意思決定者:
パートナーとして責任と利益を共有する段階
企業が求めるべきは、単に「使える人材」ではなく、この4つのフェーズをスムーズに移行できるよう支援する環境と制度です。そうして初めて、エンジニアは「不要」ではなく「不可欠」な存在になり得るのです。
離職率低下=フェアトレードの成果
意外に思うかもしれませんが、この「フェアトレード的な仕組みづくり」は、企業にとっての重要なKPIである「離職率の低下」に直結します。
エンジニアが「正当に評価され、報酬が得られ、学ぶ機会がある」と感じれば、わざわざ転職しようとは思いません。それは「信頼資本」として企業に蓄積されるのです。
・スキルに見合った報酬
・健全な労働環境
・教育機会とスキルアップの道筋
・成果と貢献が認められる文化
これらすべてが揃ってこそ、フェアトレード的な職場環境が実現されるのです。
結論:「エンジニア不要論」は問いの立て方が間違っている
結局、「エンジニア不要論」が間違っているのではなく、「問いの立て方」が誤っているのです。
必要なのは「エンジニアがどのように成長すれば、社会に価値を提供できるのか」という問い。
その答えは、「仕組み」と「教育」にあります。そしてそれを実現するのは、企業の制度設計力と、個人のリスキリング意欲の両輪です。
まとめ:エンジニアの価値に公正な評価を与える制度づくり
企業に求められるのは、**「プロを囲い込み、初級を切り捨てる」のではなく、「全員をプロへと育てる土壌をつくる」**こと。
個人に求められるのは、**「指示を待つエンジニア」から「意思を持ち仕組みをつくるエンジニア」**への変化。
技術の民主化と生成AIの進化が加速する今こそ、フェアトレード的な視点で技術と報酬の仕組みを再構築する絶好のタイミングなのです。
いかがでしたでしょうか?
すこしでもみなさまの気づきになれたのであれば幸いです。
IT・DX教育サービスについてお悩みがある方は、ぜひ初回無料のオンラインコンサルティングをご利用ください。必ずお役に立ちます。
www.certpro.jp/dxconsulting/
生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。
セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。
certpro-generationaiservice.sfsite.me/
【キーワードの解説】
フェアトレード(Fair Trade)
フェアトレードとは、開発途上国の生産者に対し、公正な価格で取引を行う仕組みや運動のことを指します。搾取的な商習慣を避け、生産者が持続的に生活できるような経済的自立を支援する考え方です。これをIT業界に応用すると、「エンジニアに正当な報酬と成長機会を提供する仕組み」へと展開できます。つまり、時間やコード量ではなく、その人の創造性や設計力などに正当な対価を与えることが、現代の「技術フェアトレード」のあり方です。
エンジニア不要論
近年、生成AIの進化により「プログラムはAIが書くもの」とする言説が目立つようになりました。初級エンジニアの役割が不要になるという「エンジニア不要論」は、その象徴的な現象です。しかし実際には、AIでは担えない「文脈理解」「要件定義」「セキュリティ設計」などの領域で、エンジニアは依然として不可欠な存在です。必要なのは“エンジニア不要”ではなく、“エンジニアの役割再定義”なのです。
マインドセット/マインドチェンジ
マインドセットとは、ある対象に対して固定的に持つ思考の枠組みを指します。これを柔軟に変化させることを「マインドチェンジ」と言います。エンジニアのキャリアにおいても、「時間を売る人材」から「知的資産を創る人材」へのシフトは、マインドセットの転換なくしては成り立ちません。自らを評価する主体となり、学び続け、成長を自らデザインする思考が求められています。
【著者紹介】
近森 満(ちかもりみつる)
■株式会社サートプロ 代表取締役CEO
IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。
■所属・役職
・IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定、+DX認定、超知性ASI検定)
・一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)
・電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)
・NPO 組込みソフトウェア管理者技術者育成研究会 メンバー(組込み)
・ET教育フォーラム合同会社 代表(コンテンツ制作)
・経済産業省地方版IoT推進ラボ ビジネス創出事業メンター(IoT支援)
・経済産業省地域DX推進ラボ ビジネス創出事業メンター(DX支援)
・デジタル庁デジタル推進委員(デジタル化支援)
・DX事業共同組合 設立理事(DX推進)
・一般社団法人日本サステナブルビジネス機構 幹事(SDGs認証)
・”一億総活躍社会を実現する”共生日本協議会 理事(DEI支援)
・アジャイル開発技術者検定試験コンソーシアム 事務局長(Agile検定)
・一般社団法人国際サイバーセキュリティ協会 事務局長(IACS認定)
【音声配信】
※音声収録のポッドキャストではテキストには載っていない㊙話も。
ぜひ、ものは試しに聴いてみてください。
🎙️『近森満のDX企画書のネタ帳』は毎日配信中!


