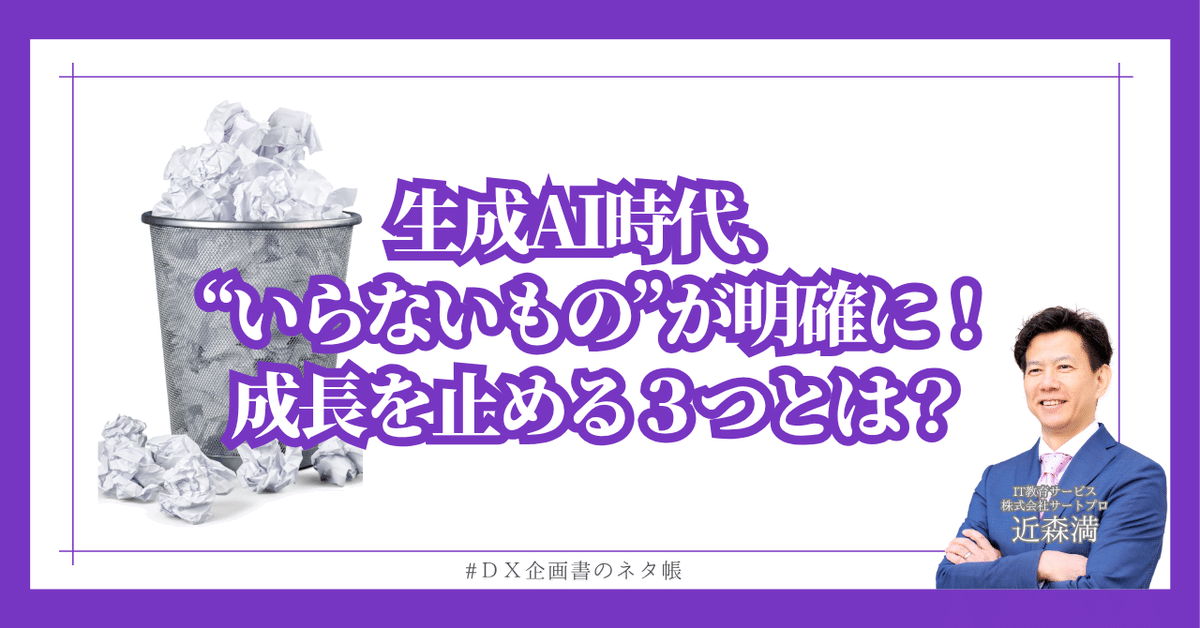
【記事概要】
生成AI時代、私たちは何を捨て去るべきか?
本記事では、IT教育サービスと生成AI実装を推進する株式会社サートプロ代表・近森満氏が、「生成AI時代にいらないもの」として語った3つの思考・行動パターンについて深堀りしていきます。
第一に、「代案なき批判」は不要と断言。AIが即座に代案を提示できる時代に、否定のみの意見は組織や個人の価値を下げる行為になりつつあります。
第二に、「目的のない対話」は意味を失ってきており、情報が溢れる現代では、価値のある対話とは「何を話すか」より「何を生み出すか」が鍵となると説きます。
第三に、「不安のアピール」、すなわち「自信がないからできません」という表明は意味を持たず、むしろ「小さくやる勇気」こそが重要であると近森氏は語ります。
これらの考察は、生成AIが当たり前に存在する社会における「行動の再定義」を促すものです。AIを単なるツールとしてではなく、共に働くパートナーと見なし、変化に順応するマインドセットと実践力を持つことが求められているのです。
AI時代において必要なのは、建設的な思考・対話・行動。この記事では、近森氏の具体的なたとえ話やユーモアを交えた解説とともに、それらをどのように実践していけばよいのかを提案します。
DX推進に携わるすべての方にとって、必読の内容です。
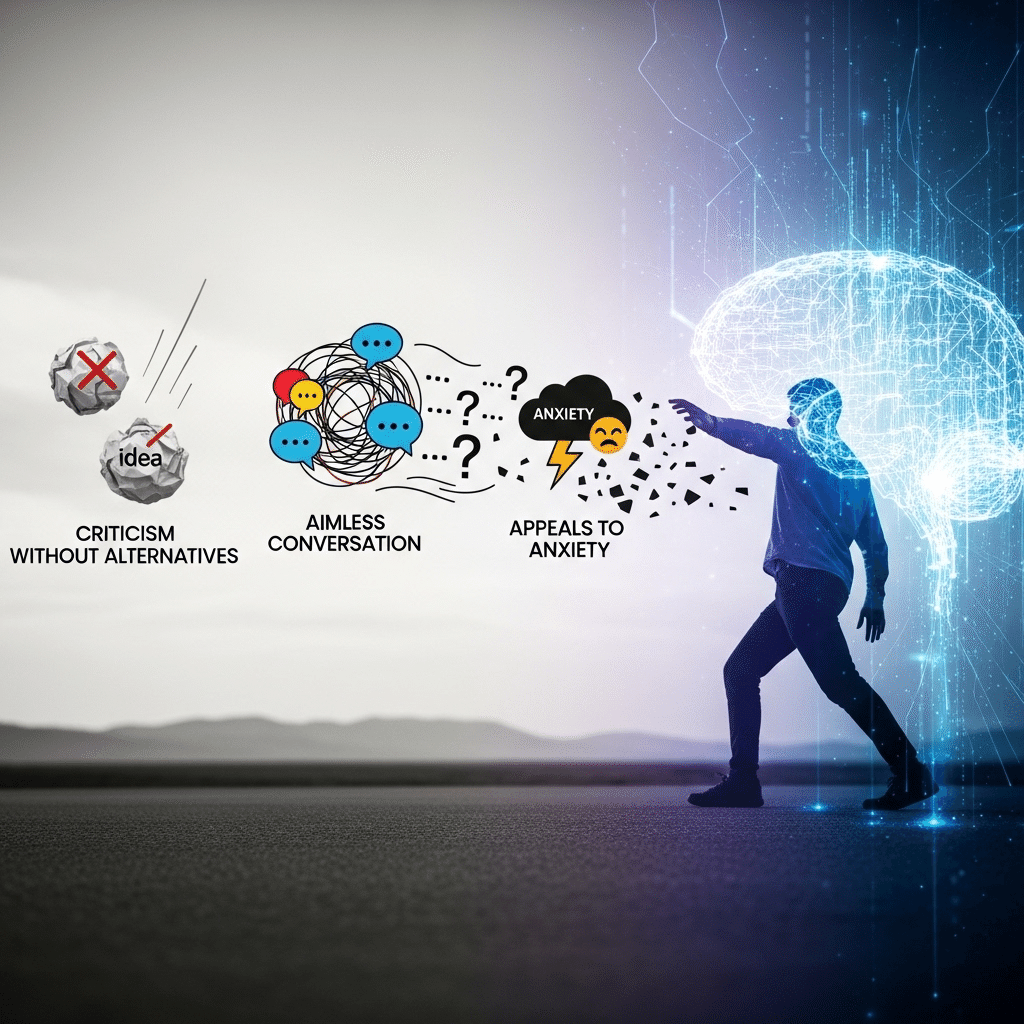
【著者情報】
こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。
www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/
当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。
www.certpro.jp/dxconsulting/
AIとともに進む時代、「人」に求められるものが変わった
2020年代以降、ChatGPTをはじめとする生成AIの爆発的な普及は、働き方だけでなく、思考や行動の前提条件すら変えつつあります。
私は今、「これはもう、いらないな」と確信を持って言える思考や習慣が、明確になってきたと感じています。それは以下の3つです。
①代案なき批判
②目的のない対話
③自信のなさのアピール
この3つは、これまでの組織社会の中では「あるある」として許容されてきた部分があるかもしれません。ですが、生成AIという“外部脳”を持つ人類にとって、それらはもはや足枷でしかありません。
それでは一つひとつ見ていきましょう。
「代案なき批判」はもう通用しない
かつての日本社会は「批判力」に価値があるとされていました。「それは違う」と言える人は「頭が切れる」と評価されることすらありました。
ですが、生成AIは反論されても代案を即座に提示できます。
「その企画はダメだ」と言えば、AIはこう返します。
「では、以下の代案を5つ提示します」
…圧倒的なスピードと多様性をもって。
つまり今、「反対だけする人」は代案も出せない無責任な人として、評価が下がっていきます。
そして何より重要なのは、「代案を出せないこと」そのものが悪いのではありません。
代案を出そうとしない姿勢が、問題なのです。
生成AI時代の価値は、“提案力”と“構築力”にシフトしています。
##「目的のない対話」は、時間の浪費になる
「雑談が大事」と言われた時代もありました。実際に、アイスブレイクや信頼構築のために、ちょっとした無駄話は役立ちます。
しかし今は違います。
目的なき対話は、AIによる前提情報分析と代替が可能になったことで、価値を失いつつあるのです。
近年、会議の在り方も問われています。「その会議、本当に必要?」という声はあらゆる企業で聞かれます。
目的がなければ、AIがサマリを出しておしまいでいい。わざわざ人間が集まる理由がないのです。
では、これからの対話に必要なものは何か?
それは**「問い」と「ゴール」です。**
問いのある対話は、思考を進化させます。
ゴールのある対話は、アクションを生み出します。
この変化に気づいているかどうかが、DX推進の鍵を握るのです。
事例: AIを活用した企画会議の進化
あるIT企業では、プロジェクト開始前に「AIにアジェンダをつくらせる」という取り組みを行っています。人間同士の会話の出発点が、すでにAIが集めたインサイトから始まる。結果として、会議の生産性は約1.5倍に向上しました。
これはつまり、「対話の再定義」です。
##「自信がない」のアピールは、意味がない
3つ目は「自信がないからできません」という“言い訳”です。
率直に言えば、これはやらない理由探しに過ぎません。
むしろ、「小さくやってみる勇気」こそが評価される時代になっているのです。
不安があるならAIに聞けばいい。
経験がなくても、まずは試してみればいい。
苦手なら、他人に頼ればいい。
今は、「やらない理由」ではなく、**「どうやって一歩踏み出すか」**が問われているのです。
事例: 文才がない私が、文章を書き始めた理由
私自身、「文章力に自信がない」とよく公言していました。でも今、それは言いません。生成AIが下書きを作ってくれるからです。
それでも、文章を世に出すという行為は自分の責任です。
ですから、最後は自分の手で整えて、自分の意志として発信する。
こうした「AIとの協働」が当たり前になってきた今、自信の有無に振り回される必要はないのです。
デジタル時代に必要なマインドセットとは?
以上の3点、「代案なき批判」「目的のない対話」「不安のアピール」は、すべて人間の内側のクセに関係するものです。
これらを捨てることは、**マインドセットの刷新=“思考のアップデート”**に他なりません。
AI時代の人材に求められるのは、「万能な能力」ではありません。
むしろ、「足りない部分を外部に委ね、必要な行動だけに集中する」というメタスキルです。
AIとともにある働き方:再定義の時代
今、私たちは仕事の定義を再構築する必要があります。
「考えること」=自分だけがやるべきことではなくなった。
「情報を集める」=AIに任せられる。
「実行する」=ツールが代替可能。
では、何が残るのか?
それは、**「構想すること」「人を動かすこと」「意志を持つこと」**です。
こうした行動様式の再定義こそが、生成AI時代におけるDX推進人材に求められるスキルセットなのです。
まとめ:行動の再定義とマインドの刷新
・代案なき批判は、もういらない
・目的のない対話も、もはや意味がない
・不安を表明することより、まずはやってみる勇気が大切
この3つの不要論は、単なる思考ではありません。生成AIというパートナーと共にある時代の“行動様式の再設計”に他なりません。
組織において、リーダーとして、個人として。
このアップデートを受け入れることで、DX推進のスピードも質も、格段に高まるのです。
いかがでしたでしょうか?
すこしでもみなさまの気づきになれたのであれば幸いです。
DX推進担当者の育成やIT教育研修でお悩みがあれば、ぜひ初回無料のコンサルティング「DX推進人材教育プログラム」にご応募ください。かならずお役に立ちます。
IT・DX教育サービスについてお悩みがある方は、ぜひ初回無料のオンラインコンサルティングをご利用ください。必ずお役に立ちます。
生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。
セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。
certpro-generationaiservice.sfsite.me/
【キーワードの解説】
生成AI(Generative AI)
文章や画像、音声、プログラムコードなどを人間の代わりに「創造する」AI技術のこと。ChatGPTやMidjourneyなどが代表例。人間の言語や発想を模倣しつつ、新しいコンテンツを生成する能力があるため、従来の検索型AIやルールベースの自動化とは一線を画す。ビジネスの企画提案、文章生成、画像デザイン、教育支援などあらゆる分野で応用されている。
建設的対話(Constructive Dialogue)
単なる意見交換ではなく、目的と進展を前提とした対話のあり方。何を話すかではなく、何を生み出すかを重視する。DX推進の現場では、ゴールから逆算した議論とアクションプラン策定が求められる場面で特に有効。会議の価値を最大化するためのマインドセットとも言える。
マインドセット/マインドチェンジ
思考や行動の前提となる無意識の価値観や判断軸を指す。「マインドセットの再構築」は、DXやAI導入の初期段階で最大のボトルネックとなる。変化を受け入れ、自らアップデートする姿勢(マインドチェンジ)が求められる。
【著者紹介】
近森 満(ちかもりみつる)
■株式会社サートプロ 代表取締役CEO
IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。
■所属・役職
・IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定、+DX認定、超知性ASI検定)
・一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)
・電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)
・NPO 組込みソフトウェア管理者技術者育成研究会 メンバー(組込み)
・ET教育フォーラム合同会社 代表(コンテンツ制作)
・経済産業省地方版IoT推進ラボ ビジネス創出事業メンター(IoT支援)
・経済産業省地域DX推進ラボ ビジネス創出事業メンター(DX支援)
・デジタル庁デジタル推進委員(デジタル化支援)
・DX事業共同組合 設立理事(DX推進)
・一般社団法人日本サステナブルビジネス機構 幹事(SDGs認証)
・”一億総活躍社会を実現する”共生日本協議会 理事(DEI支援)
・アジャイル開発技術者検定試験コンソーシアム 事務局長(Agile検定)
・一般社団法人国際サイバーセキュリティ協会 事務局長(IACS認定)


