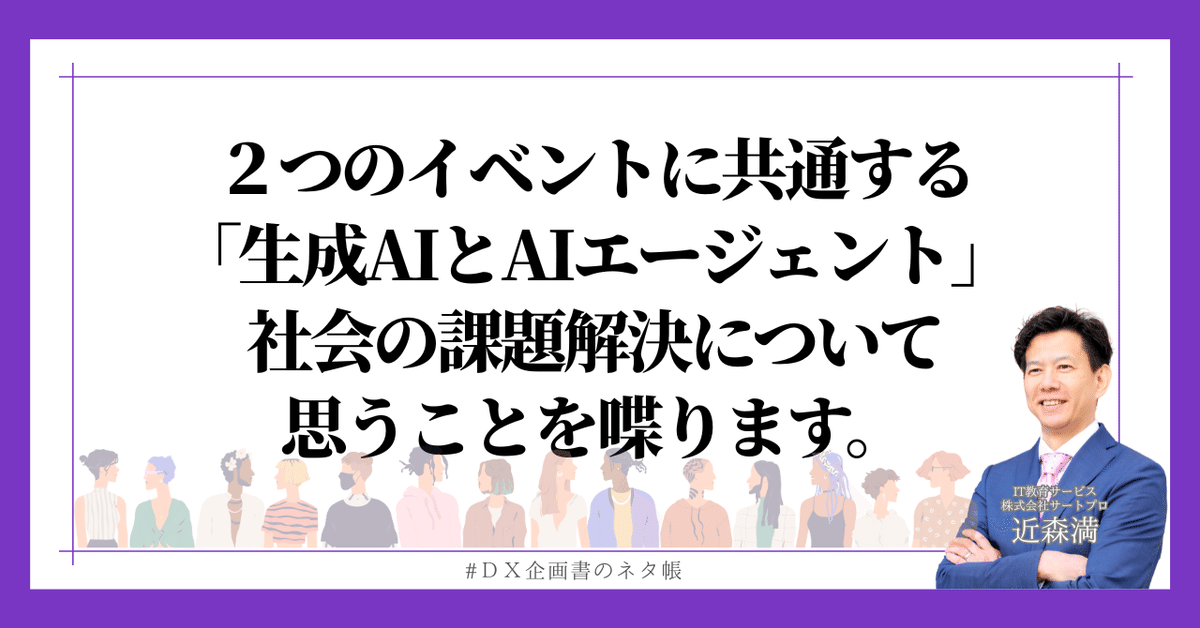
【記事概要】
2025年6月某日、私、近森満は2つの重要なイベントに参加しました。ひとつは自治体向けセミナー、もうひとつはCopilotのハンズオンイベントであり、いずれも「生成AI」と「AIエージェント」に焦点を当てたものでした。自治体向けセミナーでは、近森満が講師の一人として生成AIの社会実装に向けた地域課題の共有と解決を探り、Copilotの体験会では、参加者としてAIツールの実用性とユーザーの習熟度のギャップを痛感しました。
近森自身もCopilotやAIエージェントの実装に苦戦しながらも、参加者の対話や助言から新たな学びを得ています。特に、GitHub CopilotやCursorなどの開発支援AIの可能性に触れ、今後のDX推進におけるヒントと課題を探求しています。本記事では、近森満の体験と気づきをもとに、AI技術の現場活用のリアルを共有し、デジタル人材育成のヒントを提示します。
【著者情報】
こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。
www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/
当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。
www.certpro.jp/dxconsulting/
生成AIと自治体課題のリアル
2025年6月18日、私は2つのまったく異なるシーンで「生成AIとAIエージェント」という同じテーマに向き合っていました。
午前中は、自社サートプロが主催した自治体職員向けのセミナー。大阪府でIoTを推進していた辻野さん、埼玉県中小企業診断協会の山田副会長、そして中小企業診断士の横田さんという、心強い専門家3名とともに、自治体が抱える観光課題をテクノロジーでどう解決できるかというテーマで意見を交わしました。
最後のパネルディスカッションのモデレーターを務めながら、第1部で自分自身が話したのは約30分。生成AIの事例や社会実装の道筋について触れながら、「自治体こそ、生成AIの力で観光DXを一気に推進すべき」と強調しました。
だが本音を言えば、自治体職員の多くが生成AIに距離を感じている。これは企業以上に情報統制や稟議の壁があること、予算決裁の構造が硬直的であることが背景にあります。
観光の一例ですが、生成AIを使えば、プロモーション素材の自動生成や地域名産品のコピーライティング、SNS投稿案の自動出力など、多くの業務を軽減できる。にも関わらず、その可能性に触れようとする姿勢がまだ浸透していないのが現状です。
セミナー終了後、参加者から「生成AIをどこから学んでいいか分からない」との声を多くいただきました。ここに、まさに“教育格差”という課題が潜んでいます。
Copilot体験会で感じた温度差
同じ日の夜18時半、私はもう一つのイベントに参加しました。全国ソフトウェア協同組合連合会(通称:ジャスパ)主催のCopilotハンズオンイベントです。
このイベントでは、Copilotの基本的な使い方をみんなで体験し、どう活用するかをディスカッションする形式が取られました。参加者は30名ほどで、リアル会場に20人、オンラインが10人という構成。私は委員会メンバーの立場で参加しつつ、むしろ学びにきた感覚でした。
会場ではお酒も提供されていましたが、私はいつも通りソフトドリンク。無糖紅茶を飲みながら、周囲の様子を観察していたのですが、驚いたことがありました。
「Copilotを日常業務で使っていますか?」という問いに、手を挙げた人がほとんどいなかったのです。
MicrosoftのCopilotといえば、ExcelやWord、PowerPointと親和性が高く、Office365の環境さえあればすぐに使えるもの。エンジニアだけでなく、業務系ユーザーにも広がるはずのツールです。しかし、実際は「ログインできなかった」「認証アプリが連携していない」といった理由でうまく使えていない方が多数。
私自身も例外ではなく、イベント中にログインを試みたものの、機種変更したiPhoneの認証アプリが機能せず、結局操作できずじまいというオチでした。
こうした「触りたいけど触れていない」という現場のギャップ。それこそが今の生成AI時代の課題です。
事例: Jasper主催「Copilotってどうよ」イベント参加体験
イベントの後半では、3チームに分かれてディスカッションを行い、「Copilotはどう活用できるのか?」というテーマでそれぞれが意見を交わしました。
私が属したチームでは、ある女性開発者が印象的な発言をしていました。「GitHub Copilotが、ディレクトリ構成からコード補完まで、まるでバディのように振る舞ってくれる」と。その方の上司が研究開発部門のプロフェッショナルで、普段からAIエージェントをフル活用しているとのこと。
この話を聞いたとき、私は本当に「負けた」と思いました。AIツールを単なる「おまけ機能」ではなく、「業務のパートナー」として扱うこの姿勢。まさにマインドセットの違いです。
CopilotやChatGPTのようなツールは、使ってみないとその真価がわかりません。だからこそ、気軽に試す“場”をいかに設けるかが今後の大きな鍵になると強く感じました。
開発現場でのAIツール活用の実態
技術者の中でも、AIツールに対する活用度には大きな個人差があります。
ある会社では、全社員にChatGPTの有料アカウントを支給している一方、別の企業では、無償版をこっそり使っているだけというケースも。特に中小企業では、AIツール導入の決裁すら下りないことも多く、個人ベースでの利用にとどまっているのが現実です。
実際、Copilotをメインで使っているという人はまだ少数。生成AIツールの多くは「習熟する前に飽きられてしまう」というリスクを抱えているため、企業として継続的な活用支援を行う仕組みが不可欠です。
とくに、以下の2点が重要です。
・AIツールを活用した成果の“見える化”
・マニュアルではなく、“ナレッジベースの共有”
この2つが揃わなければ、CopilotやAIエージェントは「すごそうだけど自分には関係ない」技術で終わってしまいます。
GitHub CopilotとAIエージェントの可能性
イベント終了後、ある開発会社のプロフェッショナルと懇親会で話す機会がありました。
その方が特に推していたのが、GitHub Copilot、Cursor、WindSurfといったAIエージェントの活用です。彼はこう語っていました。
「どれもログインさえできればすぐ使える。まずは触ることが重要です」
そして彼が勧めてくれたのが「エージェントモード」。このモードを使えば、対話しながらコードを自動生成することができ、ビジュアルで出力も得られるため、初心者にもわかりやすいとのこと。
私は思わず「目からウロコ」でした。ログインはしたものの、眺めて終わっていた自分を恥じ、すぐに試してみたくなったのです。
事例: 優秀な女性開発者とCopilot活用法
先述した女性開発者との会話では、具体的にどのようにCopilotを使っているかも教えてもらいました。
・ディレクトリ構成の提案
・ルーティングや認証のコード自動生成
・テストコードの自動補完
「まるで、優秀な後輩が隣で助けてくれているようです」
そう彼女は語っていました。彼女の上司はさらに進んで、独自のAIエージェントをカスタマイズして社内展開しているそうです。
ここで重要なのは、「人材育成」としてのAI活用。彼女のような若手がAIを積極的に取り入れているからこそ、組織としてのDXが前進しているのです。
Cursor、WindSurf、GitHub Copilotの比較検討
それぞれのツールの特性は以下の通りです:
・GitHub Copilot:定額制、信頼性高、Visual Studio Codeとの親和性◎
・Cursor:UIが直感的、非エンジニアでも扱いやすい
・WindSurf:柔軟なエージェント設計が可能、カスタマイズ性◎
どれか一つに絞る必要はなく、業務用途に応じて“使い分け”が鍵となります。私も、まずはWindSurfを本格的に触ってみようと心に決めました。
まとめ:AIツールは使ってこそ意味がある
CopilotもChatGPTも、ただ「知っている」だけではDXにはなりません。使ってみて初めて分かる驚きと課題があり、そこにこそ人材育成や教育支援の余地があります。
・「自社で生成AIはどう導入すべきか?」
・「使いこなせる人材をどう育てるか?」
・「教育現場でどう教えるべきか?」
この3つの問いに向き合うことで、真のDX推進が見えてくるのです。
だからこそ、まずは“触ってみる”ことから始めましょう。AIツールは、眺めているだけでは何も起きません。
私は今回の2つのイベントを通じて、自分がまだまだAI活用に遅れを取っていることを痛感しました。
けれど、だからこそ言えることがあります。「今からでも、遅くない」。
AIは“超知性”と呼ばれる時代に突入しましたが、その本質は“使う人間のマインド”にかかっています。
私自身、これからもAIエージェントを学び、皆さんに実体験として伝えていきます。
いかがでしたでしょうか?
すこしでもみなさまの気づきになれたのであれば幸いです。
DX推進担当者の育成やIT教育研修でお悩みがあれば、ぜひ初回無料のコンサルティング「DX推進人材教育プログラム」にご応募ください。かならずお役に立ちます。
www.certpro.jp/dxconsulting/
生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。
certpro-generationaiservice.sfsite.me/
【キーワードの解説】
生成AI(Generative AI)
生成AIとは、既存のデータから新しい情報を創り出すAI技術のことです。代表的な例にChatGPTやMidjourney、GitHub Copilotがあります。生成AIは文章、画像、コード、音声など多様なアウトプットが可能で、コンテンツ制作や業務効率化に活用されています。特にDX推進においては、従来の業務プロセスに“創造性”を持ち込む力として注目されており、人材育成や教育、商品企画、自治体施策など幅広い分野で導入が進んでいます。
AIエージェント(AI Agent)
AIエージェントとは、特定のタスクを自律的に遂行するAIのことです。ユーザーと対話しながら指示を受け取り、必要なアクションを判断・実行する機能を持ちます。代表的なツールにはCursor、WindSurfなどがあり、開発業務の補佐、業務自動化、パーソナルアシスタントなどに活用されています。今後はAGI(汎用人工知能)やASI(超知性AI)への進化が予測される中、AIエージェントはその前段階の実用フェーズとして注目されます。
Copilot(コパイロット)
Copilotは、Microsoftが提供するAI支援ツールで、主にプログラミング支援やOffice製品との統合で使われています。Visual Studio CodeやGitHubに統合されたGitHub Copilot、Microsoft 365向けのCopilot for Officeなどがあります。自然言語での入力に対してコード生成や文章提案、資料作成支援などを行うため、非エンジニアにも導入のハードルが低い点が魅力です。多くの企業で業務効率化やナレッジ共有に活用が始まっています。
【著者紹介】
近森 満(ちかもりみつる)
■株式会社サートプロ 代表取締役CEO
IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。
■所属・役職
・IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定、+DX認定、超知性ASI検定)
・一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)
・電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)
・NPO 組込みソフトウェア管理者技術者育成研究会 メンバー(組込み)
・ET教育フォーラム合同会社 代表(コンテンツ制作)
・経済産業省地方版IoT推進ラボ ビジネス創出事業メンター(IoT支援)
・経済産業省地域DX推進ラボ ビジネス創出事業メンター(DX支援)
・デジタル庁デジタル推進委員(デジタル化支援)
・DX事業共同組合 設立理事(DX推進)
・一般社団法人日本サステナブルビジネス機構 幹事(SDGs認証)
・”一億総活躍社会を実現する”共生日本協議会 理事(DEI支援)
・アジャイル開発技術者検定試験コンソーシアム 事務局長(Agile検定)
・一般社団法人国際サイバーセキュリティ協会 事務局長(IACS認定)
【音声配信】
※音声収録のポッドキャストではテキストには載っていない㊙話も。
ぜひ、ものは試しに聴いてみてください。
🎙️『近森満のDX企画書のネタ帳』は毎日配信中!


