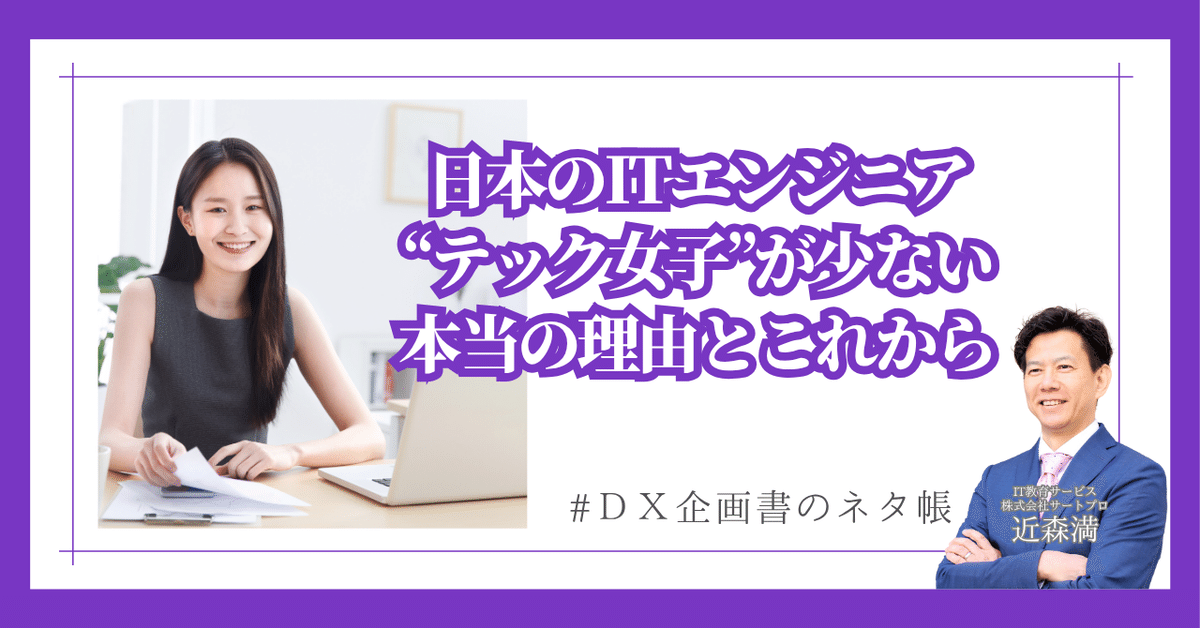
【記事概要】
「ITエンジニアにおける女性比率はなぜ2割未満なのか?」という疑問を切り口に、近森満が日本のIT業界における女性エンジニアの現状、背景、課題を掘り下げます。
OECD加盟国における比較、総務省・パーソル等の調査結果から、女性比率が約18.8%に留まり、技術職に限るとさらに低い実態が明らかに。背景には大学進学段階でのSTEM分野の女性比率の低さがあり、教育機会の不足と職場環境の問題が絡み合います。
しかしながら、IT職への定着率やスキル習得における満足度の高さ、出産・育児後の復職意欲やフリーランスとしての活躍など、女性ならではのポテンシャルも指摘されます。今後は女性の参入促進、STEM分野での支援、経営層のマインドセット改革、そしてメンタルケア支援の必要性が急務です。女性の声が届くケア体制構築と、企業の支援制度の活用が鍵となるでしょう。
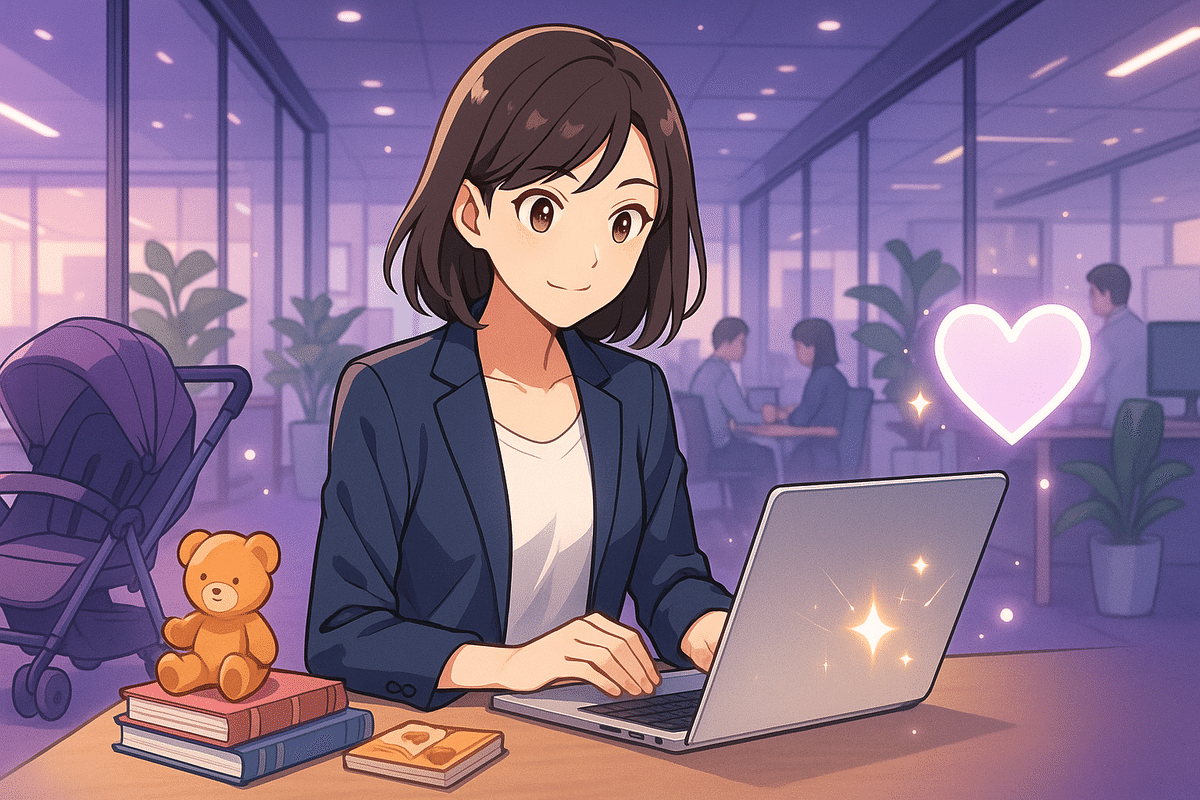
【著者情報】
こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。
www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/
当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。
www.certpro.jp/dxconsulting
はじめに
日本のIT業界における女性エンジニア比率の現状とその背景、課題、そして今後の方向性について、30年以上IT業界に関わってきた経験と調査結果を交えてお伝えします。
日本のITエンジニアにおける女性の割合はOECD加盟33カ国中17位で、約18.8%。総務省やパーソルの調査でも、技術職に限れば10%前半という低水準です。一方で、入職後のIT職における満足度や習得意欲、出産育児後の復職やフリーランスとしての活躍意欲は高く、ポテンシャルは充分。にもかかわらずなぜ基盤数が伸びないのか。大学・専門学校のSTEM分野への進学率、職場環境の整備、経営層の意識改革、メンタルヘルス支援の体制といった複合的要因が絡まり合っています。
本記事では、日本が抱える「ITエンジニアにおける“テック女子”不足」の構造をAIDA(Attention—Interest—Desire—Action)の流れで整理し、政策的観点・企業施策・現場実践の三階層から、具体的な対応策を提示します。
現状把握:実態データに見る“テック女子”の姿
OECD比較から見える日本の位置付け
OECD加盟33カ国で、日本は女性エンジニア率17位、全体の約18.8%。OECD平均の20.6%を下回ります。総務省によれば、技術職に限るとさらに低く、10%台前半とみられます。この数値の低さから、日本の“テック女子”基盤がいかに脆弱かが浮き彫りになります。
パーソルなど国内調査による分析
人材系大手パーソルによる調査では、ITエンジニア全体に占める女性の割合は約16%。STEM分野の大学・専門学校における女性学生比率の低さもあり、「将来の母集団」がそもそも少ない状況です。
入職後の“ギャップ”とポテンシャル
一方で、IT職に就いた女性の中には、「仕事のやりがい」や「スキル習得の満足度」を高く評価する人が多いという傾向があり、参入後の定着や成長の可能性は充分と捉えられています。また、結婚や出産後に独立やフリーランスへ転身する事例も多く、新しい働き方を起点としたキャリア形成が進みつつあります。
参考:
・総合人材サービス企業ヒューマンリソシア社による調査では、ITエンジニア全体における女性の割合は18.8%。OECD加盟国33カ国中17位、OECD平均の20.6%を下回っています
https://www.athuman.com/news/2025/22544/?utm_source=chatgpt.com
・総務省の集計では、IT業界全体の女性の割合は約20%程度。そのうち技術職に就く女性エンジニアは10%台前半という見解もあり、技術者に限ると更に低い可能性があります
https://master-key.co.jp/media/women-engineers-shortage-reasons/?utm_source=chatgpt.com
・人材系大手パーソルの調査では、約16%とやや低めの数字が示されています
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001019.000016451.html?utm_source=chatgpt.com
背景分析:なぜ女性エンジニアが伸びないのか?
教育段階における“STEM女子”の課題
・高校・大学・専門学校などで、STEM分野の女性進学率が低い現状。
・入学者の偏りが母集団を縮小。将来的なIT人材供給源が少なくなる。
・理由として、「理系=男の世界」「女性に不向き」といった固定観念と無自覚な偏見が存在。
職場環境とキャリア構築のネック
・結婚・出産・育児といったライフイベントによって、企業を離れざるを得ない構造。
・男性中心の職場文化では、女性特有のメンタルヘルスケアニーズに対応しづらく、異なる視点のケア体制が不十分。
・女性同士のコミュニティやメンター制度の欠如が心理的障壁を高めています。
希望の兆し:ポテンシャルの高さと復職意欲
“働く満足度”の高さが示す可能性
IT分野で働く女性たちからは、スキル習得や業務内容への満足度が高いという声が多く聞かれます。これは「やりがい」「自立性」「変化対応力」が活きる領域であることの証です。近年では、出産後もITスキルを活かしてフリーランスや業務委託で復職する女性も増加傾向にあります。
出産・育児とキャリアの両立
結婚・出産後に一度職場を離れた女性が、再びIT職に戻ってくるには、職場環境の整備が必要です。柔軟な勤務形態やリモートワークの普及は、女性に限らず全社員の多様な働き方を支援します。国の助成金制度や企業の雇用継続施策を活用することが、“辞めさせない支援”となるのです。
具体策:増やすためのステップと環境整備
教育:STEM分野へのアプローチ
・中高生からの理系進学支援とロールモデル提示
・高専・大学・専門学校での女子学生向けキャリア支援プログラム
・女性教員・女性講師の登用で心理的障壁を下げる環境構築
組織:職場におけるマインドセット変革
・経営層・人事に対する意識改革研修の導入
・「女性だから」ではなく、「多様性の中の一人として」扱う文化の醸成
・メンタルケアやライフイベント支援の制度整備と共有
社会:政策と世論による後押し
・SDGs目標5「ジェンダー平等」達成に向けた産学官連携
・職場復帰を支援する専門相談窓口・リスキリング講座の拡充
・IT業界団体による女性技術者ネットワーク支援
事例: 産休復帰支援を強化する中堅SIer企業の取り組み
関東圏の中堅SIer企業では、育児中社員専用の業務支援チームを設置。時短勤務やリモートワーク、保育補助制度の整備だけでなく、メンタリング制度とキャリア相談サービスを導入。結果として復職後3年以内の離職率を2割改善し、社内の技術者コミュニティでも女性がリーダー職に就く事例が続出している。
展望:超知性AI時代の“テック女子”戦略
生成AIやAGI、ASIといった超知性の時代に突入しつつある今、単なる技術力だけでなく、感性・共感力・倫理的判断が重視されるようになっています。こうした領域で、女性の能力が際立つ場面も増えるでしょう。
“男性社会のIT”から、“多様性が駆動するイノベーション”へ。
この転換を推進する上で、今こそ女性の積極的な参入と持続的支援が求められているのです。
女性エンジニアの比率を上げるべき理由
世界に目を向けると、日本の女性エンジニアの比率はOECD加盟国の中でも中位に留まり、OECD平均を下回る18.8%にとどまっています。つまり、私たちは他国と比べて、まだまだ「女性が活躍するIT環境」を整備しきれていないのが現実です。
その原因は、実はもっと手前の段階――STEM分野に進学する女性の数がそもそも少ないという、“入り口の構造的な問題”に根ざしています。理工系進学を目指す女性が少なければ、当然その先のキャリアパスも限定され、エンジニアとして社会に出る女性の母数自体が増えません。
一方で、いったんIT職に就いた女性たちの声に耳を傾けると、「仕事の満足度が高い」「スキルアップを実感できる」「できるなら長く続けたい」といった、前向きな反応が多く聞かれます。また、結婚や出産といったライフイベントを経ても、復職を希望する人や、フリーランスとして再びスキルを活かす人も増えているのです。
つまり、私たちは「なぜ女性がIT業界に少ないのか?」という問いの答えを、“資質”ではなく“環境”に求める必要があります。教育機会の拡充、職場の柔軟性、そしてジェンダーに対する無意識の偏見を乗り越えるためのマインドセットの刷新。こうした努力によって、まだ開かれていない可能性の扉が、静かに、しかし確実に開いていくのです。
そしてこの変化は、単に“女性のため”という話に留まりません。多様な視点を持つメンバーが協働するチームほど、創造力と革新性を生み出すことができる。DXやAIが求めるのは、まさにこの多様性から生まれる知性です。女性エンジニアの比率を上げることは、日本が技術立国として未来を切り拓いていくための、大切な“戦略”なのです。
いかがでしたでしょうか?
すこしでもみなさまの気づきになれたのであれば幸いです。
IT・DX教育サービスについてお悩みがある方は、ぜひ初回無料のオンラインコンサルティングをご利用ください。必ずお役に立ちます。
www.certpro.jp/dxconsulting/
生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。
セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。
certpro-generationaiservice.sfsite.me/
【著者紹介】
近森 満(ちかもりみつる)
■株式会社サートプロ 代表取締役CEO
IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。
■所属・役職
・IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定、+DX認定、超知性ASI検定)
・一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)
・電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)
・NPO 組込みソフトウェア管理者技術者育成研究会 メンバー(組込み)
・ET教育フォーラム合同会社 代表(コンテンツ制作)
・経済産業省地方版IoT推進ラボ ビジネス創出事業メンター(IoT支援)
・経済産業省地域DX推進ラボ ビジネス創出事業メンター(DX支援)
・デジタル庁デジタル推進委員(デジタル化支援)
・DX事業共同組合 設立理事(DX推進)
・一般社団法人日本サステナブルビジネス機構 幹事(SDGs認証)
・”一億総活躍社会を実現する”共生日本協議会 理事(DEI支援)
・アジャイル開発技術者検定試験コンソーシアム 事務局長(Agile検定)
・一般社団法人国際サイバーセキュリティ協会 事務局長(IACS認定)


