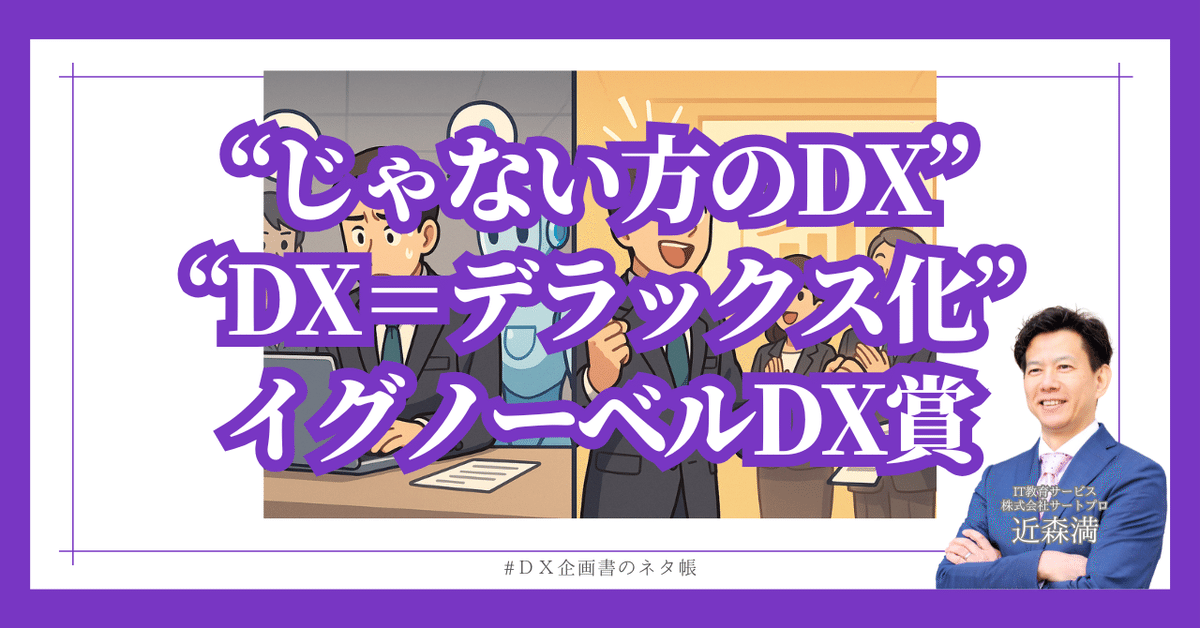
【記事概要】
DX推進って、本当に変革できてますか?
「うちはまだまだDXできていないよ」「いや、そもそもデジタルすら手つかずで…」──こんな声が日本の企業からよく聞こえてきます。デジタル・トランスフォーメーション(DX)とは、単なるIT導入やツール刷新ではなく、価値観や業務プロセス、組織文化そのものを変える“変容”のこと。それにも関わらず、多くの企業では「X(変革)」が置き去りにされた「デラックス(見せかけ)DX」が横行しているのが現実です。
本記事では、生成AIやAGI時代における真のDXの意味を再確認し、変われていない改革=“XできてないDX”をユーモアを交えて振り返ります。会議がオンライン化しただけ、ツールを入れて満足している、そんな「イグノーベル賞級」なあるある事例を紹介しつつ、真に価値あるDXとは何かを再考する機会を提供します。
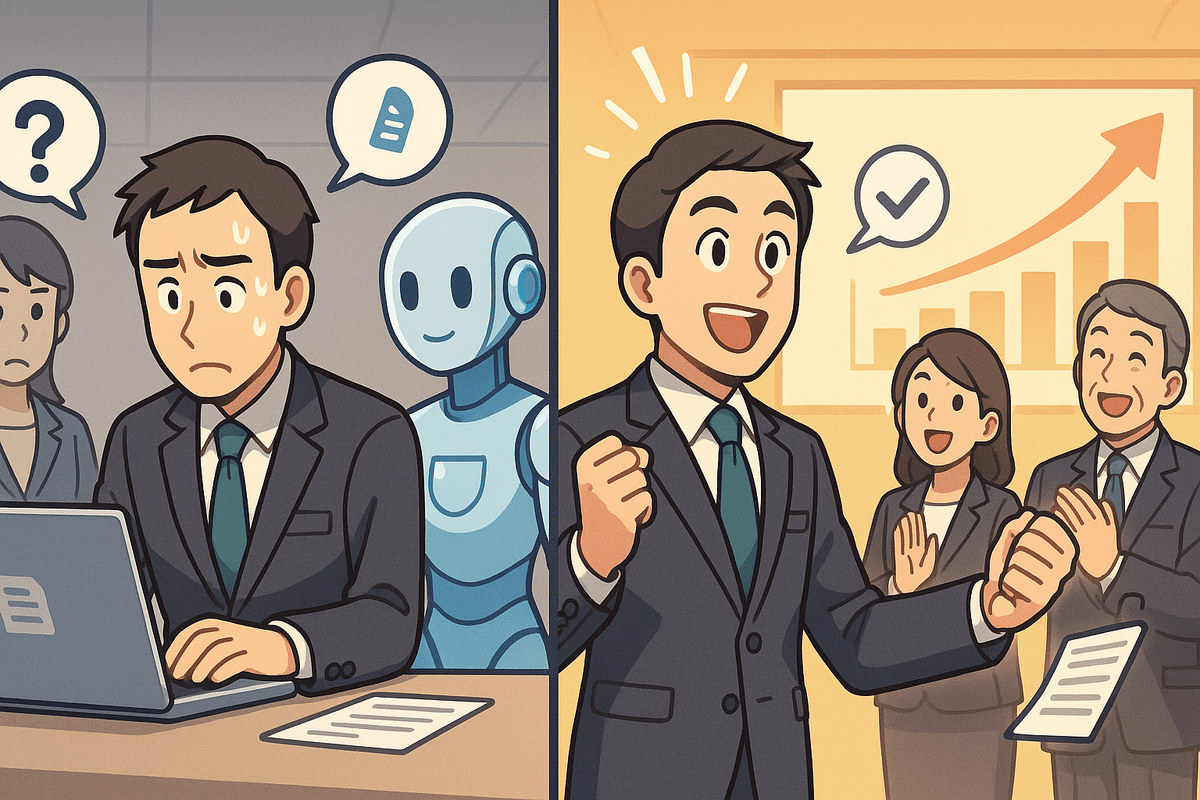
【著者情報】
こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。
www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/
当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のコンサルティングを提供しています。
DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。
www.certpro.jp/dxconsulting/
DXは変革なのに、なぜか“飾り”になっていないか
今でこそ日本中が「DX!DX!」と声高に叫んでいますが、「うちはまだデジタルすらできていないよ」という企業、実は少なくありません。それどころか、Faxをやっと撤廃できた程度で、「DX化しました!」と胸を張ってしまっているケースも散見されます。
そもそもDXとは「デジタル・トランスフォーメーション」の略。デジタル(Digital)は道具にすぎず、変えるべきは“X”──すなわちTransformation(変容)の部分です。業務プロセスを変える、意思決定の速度を変える、顧客価値の定義すら変える。DXとはそういう意味での根本的な変革なのです。
にもかかわらず、表面的なツール導入だけで満足してしまう企業が多い。いわば「DX=デラックス」化してしまっている状態です。
“XできてないDX”が生む、企業の迷子たち
ある日、こんな話を聞きました。
「御社、DXやってますか?」と聞くと、「もちろんやってますよ。会議を全部オンラインにしたし、Google Workspaceも導入したんですよ」。
──いや、それ、ただの“デジタルツールの導入”ですよね?トランスフォーメーションは、どこ行った??
“X”が抜けたDX=できてないDX。そんな企業が増えています。
たとえばExcelをクラウド保存するようになっただけで「我が社もDX!」。紙の書類をスキャンしてPDF化しただけで「ペーパーレス完了!DX完了!」──そう言ってしまうと、「DXってなんだっけ?」と問い直したくなりますよね。
先日とある会議で有識者の方々とお話をしたことをヒントに、この状態を私は“イグノーベルDX賞”と呼ぶことにしました。実用性はさておき、思わず笑ってしまう。だが、笑っていられない。そんな見せかけの改革こそ、今の日本企業が抱える深刻な課題です。
※あとで界隈の方々からお咎めがないか心配ですw
“デジタル化”と“DX”は違うもの。道具と意志のズレ
多くの企業が“デジタル化”の第一歩を踏み出したのは事実です。
たとえば:
・デジタイゼーション(Digitization):
紙をPDF化する、手書きのデータをデジタル化する。
・デジタライゼーション(Digitalization):
業務フローにデジタルを取り入れる。Excelで管理していたデータをクラウドに移行し、分析し始める。
しかし、それでもDXにはまだ至っていません。DXとは、こうした取り組みの“先”にある、思考と行動の変容です。AIや外部データと連携しながら、これまでの事業そのものを根本から見直す。再定義する力が問われるのです。
「ツールは入れた。でもXしてない」…それ、病気です
私はこれを「デジタル装飾症候群」と呼ぶことにします。
デジタルの服を着ただけで、変わった気になってしまっている。つまり、クラウドやチャットツールなどのITツールを導入したことだけで「改革できた!」と満足してしまっているのです。でも、肝心な“変容”はまったく起こっていない。
それはあたかも、メイクを変えただけで中身を磨かないままの“外見先行主義”のようなものです。中身=組織文化や価値観が変わらなければ、本質的なDXは実現できません。
事例: 「デジタル化しました。でも…」
ある企業では、営業部門にタブレットを配布し、「これでペーパーレス!DX推進です!」と社内報で大きく発表。しかし実際は、PDFで営業資料を見せるだけで、行動も判断もまったく変わっていませんでした。
──結局、デジタルを“紙の代替物”としてしか使っていないんです。それではXしていないDXです。
※ペーパーレスは環境に優しく、SDGs的にはいい感じになってきましたね。
“ビヨンドDX”の世界を見据えて:変革し続ける力
「DXが終わったら何があるの?」という質問に、私はこう答えます。
「ビヨンドDX」なんてない(ことはないけど)、常にトランスフォーメーションし続けるしかないんです。
未来は、フィジカルとバーチャルが融合し、さらにAIが社会の判断を支援する時代。つまり、WX=融合×変容のような世界です。トランスフォーメーションは“完了”するものではなく、永続的に続くものだと理解する必要があります。
余談ですが…
ダブルエックスというと旧車のトヨタにセリカダブルエックスという車種がありました。スープラの前ですね、懐かしい。

それでも“笑えるDX”でいい。でも、笑われるDXはもうやめよう
「まだうちなんか笑っちゃうくらいDXできてないですよ」という自虐が許されるのは今のうち。数年後には、その笑いも「イグノーベルDX賞」のように皮肉を込めた風刺に変わっていくでしょう。
とはいえ、失敗を笑い飛ばせるマインドセットは、変革の入口としては悪くありません。問題は、それを“気付き”に変えられるかどうかです。
真のDXとは、“Xする覚悟”を持つこと
では、何が「本当のDX」なのか?
・顧客価値の再定義:顧客にとって何が本当に価値なのかを見直す
・意思決定の高速化:稟議書3回の反抗ではなく、デジタルで“秒で決断”
・組織文化の変革:トップが変革の先頭に立つ覚悟を持つ
・職の再設計:社長含め、自らのポジションを賭けてでも変革を実行する
事例: 「稟議書ではんこを押すため回覧する文化」からの脱却
ある中堅企業では、稟議が通るまでに最短でも2週間。現場は当然、提案や改善を諦めがちに。しかし、グループウェアの導入と意思決定のロール再設計により、「24時間以内で決済完了」が可能に。
「早く決めることが正義」という価値観に切り替えた瞬間、社員の動きも変わったのです。
大体ですね、これに生産性がありますかね?
お辞儀ハンコのルール:
・若い順に左側から
申請者(若い順)が右側、上司や承認者が左側になるように押印します。
・上司は左側
上司や承認者は、申請者よりも左側に押印します。
・左にお辞儀
印鑑の向きを左斜めに傾けて押印します。これは、上司や承認者に対してお辞儀をするように見えることから「お辞儀ハンコ」と呼ばれます。
…そりゃあ、私も古い人間ですから過去やりましたが、今となっては何だったんでしょうね。
脱却せねば、とHITACHIさんも言っています。
「いま、やらなきゃ」生成AI時代の“待ったなしDX”
生成AIやAGI(汎用人工知能)、そしてその先のASI(超知性)など、時代の進化は止まりません。これらのテクノロジーが次々に登場し、意思決定のスピードはますます加速していきます。
「やるなら今。いつやるの?今でしょ。」という言葉が、もはや冗談ではなく切実なメッセージになってきているのです。
悩んでいる暇があったら、まず一歩踏み出す。生成AIに聞いて判断する時代に、人間が1週間悩んでどうするのか──そんな“変革の機会損失”こそ、DXが解決すべき課題です。
まとめ:“イグノーベルDX賞”から“静かなDX”へ
今回のテーマを一言でまとめると、「デジタルな見せかけに満足するな。Xできていないなら、笑われる前に変われ。」です。
面白いエピソードやイグノーベル的なDX事例に笑いながらも、「じゃあ、うちはどうだ?」と問い直す。そこから生まれる一歩こそが、真のDXのはじまりです。
派手にアピールしなくてもいい。静かに、確実に、変化を積み重ねることが、企業としての生存戦略になります。
いかがでしたでしょうか?
すこしでもみなさまの気づきになれたのであれば幸いです。
IT・DX教育サービスについてお悩みがある方は、ぜひ初回無料のオンラインコンサルティングをご利用ください。必ずお役に立ちます。
www.certpro.jp/dxconsulting/
生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。
セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。
certpro-generationaiservice.sfsite.me/
キーワードの解説
DX(デジタル・トランスフォーメーション)
DXとは「Digital Transformation」の略で、単なるデジタル化ではなく、デジタル技術を活用してビジネスモデルや業務プロセス、組織文化などを根本から変革する取り組みを意味します。IT導入やツール刷新と混同されがちですが、DXの本質は「人・組織・価値観の変容(Transformation)」にあります。企業が持続的に競争力を維持し、社会の変化に適応していくための戦略的プロセスとして注目されています。
イグノーベルDX賞
「イグノーベル賞」は、“人を笑わせ、そして考えさせる”風刺的なノーベル賞ですが、本記事ではこれをもじって、形だけのDXに満足してしまう企業・事例を揶揄する「イグノーベルDX賞」という表現が登場します。デジタルツールの導入だけで満足し、真の変革が伴っていない状態を可視化し、考え直すためのユーモラスな提案です。笑いと学びを兼ね備えたDXのメタファーとして機能します。
Transformation(変容)
DXのXにあたる「トランスフォーメーション」は、単なる改善や変更ではなく、抜本的な“変容”を意味します。これは「業務フローの自動化」「ツール導入」ではなく、ビジネスモデルや価値提供の再構築、組織文化の改革、人材の意識変革などを含む、本質的な再定義です。DXの中核はこの“変容”にあり、それを実現するためのリーダーシップと意志決定のスピードが問われます。
【著者紹介】
近森 満(ちかもりみつる)
■株式会社サートプロ 代表取締役CEO
IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。
■所属・役職
・IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定、+DX認定、超知性ASI検定)
・一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)
・電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)
・NPO 組込みソフトウェア管理者技術者育成研究会 メンバー(組込み)
・ET教育フォーラム合同会社 代表(コンテンツ制作)
・経済産業省地方版IoT推進ラボ ビジネス創出事業メンター(IoT支援)
・経済産業省地域DX推進ラボ ビジネス創出事業メンター(DX支援)
・デジタル庁デジタル推進委員(デジタル化支援)
・DX事業共同組合 設立理事(DX推進)
・一般社団法人日本サステナブルビジネス機構 幹事(SDGs認証)
・”一億総活躍社会を実現する”共生日本協議会 理事(DEI支援)
・アジャイル開発技術者検定試験コンソーシアム 事務局長(Agile検定)
・一般社団法人国際サイバーセキュリティ協会 事務局長(IACS認定)


