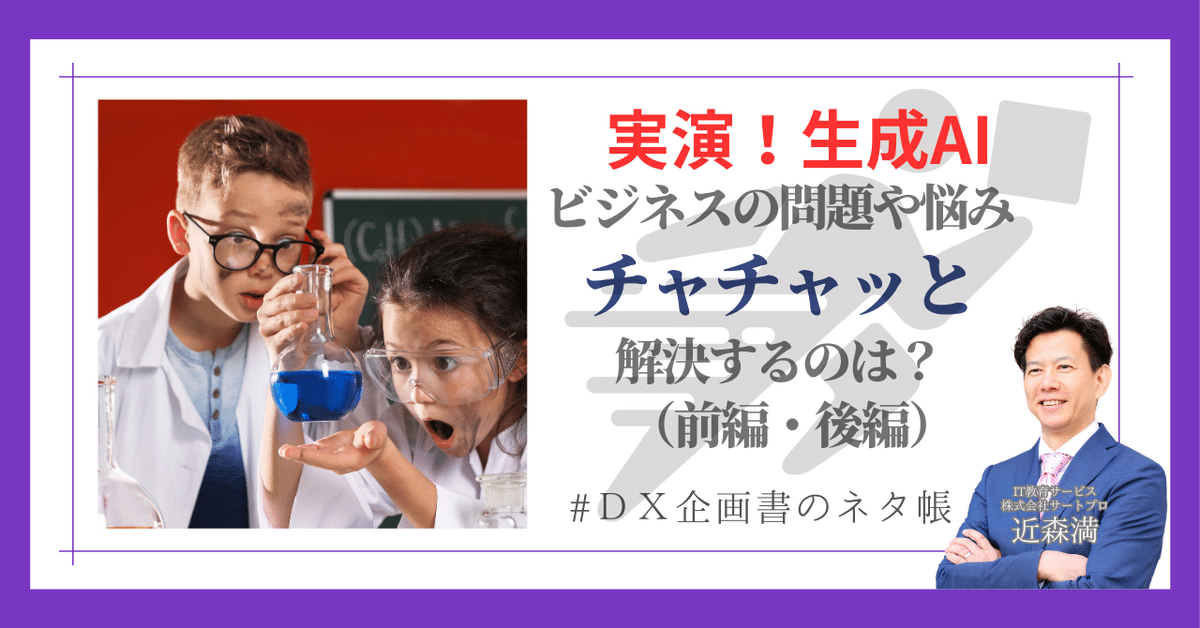
目次
- 生成AIが「チャチャッと解決」してくれる時代?
- 複数AIで同一プロンプトを検証してみた
- 生成AIの回答結果発表
- 「育てたAI」は、育てた通りに応える
- シンギュラリティ後の未来はユートピア?ディストピア?
- 超知性リテラシーと人間の役割とは?
- 他者との比較が生む気づきと実験の価値
- まとめ:AIに頼る時代、人は“問い”を鍛えよ
【記事概要】
生成AIの進化は、もはや実験や研究段階を超え、日常のビジネスにおいて“当たり前のツール”として認識されるようになっています。そんな中、AI・IoT教育サービスのサートプロ近森満と構成作家の堀内崇がパーソナリティを務めるポッドキャスト番組「DX企画書のネタ帳」では、生成AIを活用した「ビジネス課題の即時解決」について、複数の生成AI(ChatGPT、Gemini、Felo、Grok)を実際に使って比較検証を行う実験的対談が実施されました。
本記事では、その前後編にわたる対談内容を再構成し、生成AIのアウトプットの違いや、ユーザーごとの使い方・育て方の影響、さらには生成AIの未来におけるユートピア/ディストピアの可能性に至るまでを多角的に掘り下げます。「答えが違う」ことにどう向き合うか、「正しさ」よりも「深掘りする力」が問われる時代のリテラシーとは?ビジネスパーソン、特にDX推進担当者や人材育成に携わる方に向け、AI時代の企画書に役立つ“行動につながるネタ”をお届けします。
【本文】
こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。
www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/
当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。
www.certpro.jp/dxconsulting/
生成AIが「チャチャッと解決」してくれる時代?
今、巷で大きな注目を集めているのが「生成AI」。ビジネスシーンでの活用がますます進む中、よく耳にするのが「AIに聞けばチャチャッと答えてくれるよね?」というフレーズです。昭和風のCM風アニメを話題に、AIがラブレターや社内文書まで瞬時に“無難な”回答を出してくれる様子に多くの人が驚きを覚えています。
参考:もしも昭和40年代にChatGPTのCMが放送されていたら
(かねひさ和哉さんのYouTube)
しかし、「本当にそれだけでいいのか?」という問いも同時に浮かびます。AIは“正しそうな答え”を出してくれるけれど、それが常に“最適解”とは限りません。では、AIに頼る前に私たちが持つべき姿勢とは?
複数AIで同一プロンプトを検証してみた
事例: 採用に応募が来ない理由をAIに聞いてみた
今回は製造業の採用課題を題材に、ChatGPT、Gemini、Feloという3つの生成AIに同じプロンプトを投げて、その応答内容を比較してみました。
1)当社は製造業、大手企業の子会社で金属加工を扱っている50名の会社です。製造職で何度も求人広告を出しているが、応募が全然来なくなった。なぜ?
ChatGPTの回答は、求人市場の構造変化、求人広告の内容設計、採用ブランディングの重要性などを網羅的に箇条書き。近森満が使ったChatGPTは「コンサルティング的視点で360度アプローチを提示」する傾向があり、他方、堀内崇が使ったGPTは「採用広報の具体例を中心に、実務的アドバイスをテーブル形式で整理」していました。
GeminiはGoogle由来だけあり、広く検索知見を元にした答え。Feloは日本国産AIだけあって、回答が近森と堀内でほぼ一致。まるで国語の模範解答のようでした。
これ、実はAIの“記憶”の差や、ユーザーの“育て方”に依存しているんです。
生成AIの回答結果発表
1)当社は製造業、大手企業の子会社で金属加工を扱っている50名の会社です。製造職で何度も求人広告を出しているが、応募が全然来なくなった。なぜ?
堀内ChatGPT:
chatgpt.com/share/67fe21c1-0540-8004-b7a5-1a3998d25c42
近森ChatGPT:
chatgpt.com/share/67fe2201-41c0-8011-9dad-8f3fa46282d9
堀内Gemini:
g.co/gemini/share/ac78a10292b5
近森Gemini:docs.google.com/document/d/1_bz3oazi4W0kXe91QtJAzHIJ5QReh0GtUXLEHnBr7dM/edit?usp=sharing
堀内Felo:
felo.ai/search/iYzzyaj5zLg4JVJB4EoJQ4?invite=2m2ga4pLvwDW5
近森Felo:
felo.ai/search/4h3NFJgaH9UP3jGW6ZWxrG
2)10年後の2035年ごろ、シンギュラリティが来てAIは人間を超えるらしいですが、ユートピアになりますか?もしデストピアだとして解決策はありますか?
堀内ChatGPT:
chatgpt.com/share/68003480-f868-8004-aff2-47578ca993e5
近森ChatGPT:
chatgpt.com/share/67fe313c-b2c0-8011-9ae9-5a77ef094e7e
堀内Gemini:
g.co/gemini/share/a7fd6b4ea7b8
堀内Felo:
felo.ai/search/YFQEhHo68pNGXzCuxY4hct?invite=2m2ga4pLvwDW5
3)会社にChatGPTの有償プランを使いたいと言いたいけど、どうしたらよいものか、上司への提案内容をください。上司は否定的です。
堀内ChatGPT:
chatgpt.com/share/6810caed-01dc-8004-a7d1-b583a4ff4797
堀内Felo:
felo.ai/search/a48DXQkbvc6yDsW8ZLEjku?invite=2m2ga4pLvwDW5
「育てたAI」は、育てた通りに応える
事例: ChatGPTが出す答えに現れる「使用者のクセ」
ChatGPTはユーザーごとの使用履歴やプロンプト傾向を記憶しており、近森満がよく使う“全角括弧+箇条書きスタイル”で返答を出します。堀内崇はテーブル形式を好むため、AIもそれに従うようになっていました。
これはつまり、「使い手のクセ」がAIの応答に現れるということ。これは非常に重要な気付きです。どんなに中立なAIであっても、学習データや利用者のインタラクションによって“バイアス”は生じます。
AIに使われるのではなく、AIを育てる意識が求められています。
シンギュラリティ後の未来はユートピア?ディストピア?
事例: 2035年、AIは人間を超えるのかという問いへの各AIの回答
もうひとつの実験テーマは、「シンギュラリティが訪れた2035年、AIは人間を超えるのか?それはユートピアかディストピアか?」という哲学的かつ社会的な問い。
ChatGPT(4.0と4.5)、Gemini、Felo、そしてGrokを使って回答を収集しました。
結果はというと、ユートピア視点では「医療や教育の発展」「労働からの解放」「イノベーションの加速」、ディストピア視点では「監視社会」「仕事の消失」「格差の拡大」といったリスクを示すもので、構成や文体はAIごとに異なるも、総論的な結論は似通っていたのが印象的でした。
これはまさに「模範解答を出す」国産AI(Felo)と、「問い返すことで掘り下げを促す」Grokの設計思想の違いを象徴しています。
超知性リテラシーと人間の役割とは?
ここで登場する重要キーワードが「超知性リテラシー」。つまり、AI(特にAGI:汎用人工知能やASI:超知性AI)の時代において、人間としてどう情報を咀嚼し、判断し、問いを深掘りできるかという新しいリテラシーの必要性です。
AIは“即答”を得意としますが、“なぜ?”という本質への問いかけや、“どこまで信用するか”の判断は人間にしかできません。
単に「正しい答えをAIに求める」ことから、「複数の答えを比較し、仮説を立てて検証する力=掘り下げ力」が、DX推進人材に求められています。
他者との比較が生む気づきと実験の価値
AIの回答が異なることは、エラーではなく発見の種です。
堀内崇が語ったように、「違いがあるから面白い。比較こそが新しい問いを生み出す」という視点は、まさに生成AI時代の“行動指針”になるべきマインドセットです。
これはビジネスの場においても同じで、「正解」ではなく「納得解」「自社に合った答え」を導く姿勢が、デジタル・トランスフォーメーションの本質であり、人材育成の核でもあります。
まとめ:AIに頼る時代、人は“問い”を鍛えよ
生成AIが当たり前のように企画や文章を出してくれる時代。
でも、それを「どう評価し」「どう行動に変えるか」は、人間の解釈と判断の力に委ねられている。
だからこそ、AIを複数使って比較し、問いを掘り下げる力が“差”を生みます。
AIは情報を出す、行動するのは人。
DX推進において、問う力を鍛え、「問いの設計者」になることが、これからの時代のビジネスリーダーに求められています。
いかがでしたでしょうか?
すこしでもみなさまの気づきになれたのであれば幸いです。
IT・DX教育サービスについてお悩みがある方は、ぜひ初回無料のオンラインコンサルティングをご利用ください。必ずお役に立ちます。
www.certpro.jp/dxconsulting/
生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。
セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。
certpro-generationaiservice.sfsite.me/
【著者紹介】
近森 満(ちかもりみつる)
■株式会社サートプロ代表取締役CEO
IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。
■所属・役職
・IoT検定制度委員会事務局長(IoT検定、+DX認定、超知性ASI検定)
・一般社団法人 IT職業能力支援機構理事長(Android資格)
・電気・電子系技術者育成協議会副理事長(E検定)
・NPO 組込みソフトウェア管理者技術者育成研究会メンバー(組込み)
・ET教育フォーラム合同会社代表(コンテンツ制作)
・経済産業省地方版IoT推進ラボビジネス創出事業メンター(IoT支援)
・経済産業省地域DX推進ラボビジネス創出事業メンター(DX支援)
・デジタル庁デジタル推進委員(デジタル化支援)
・DX事業共同組合設立理事(DX推進)
・一般社団法人サステナブルビジネス機構幹事(SDGs認証)
・”一億総活躍社会を実現する”共生日本協議会理事(DEI支援)
・アジャイル開発技術者検定試験コンソーシアム 事務局長(Agile検定)
DX企画書のネタ帳をはじめた人「DXの鍛え方 伝道師」とは?「DXの道を切り開く伝道師、その人物と使命に迫る」【近森満:自己紹介:2024年版】|#DX企画書のネタ帳


