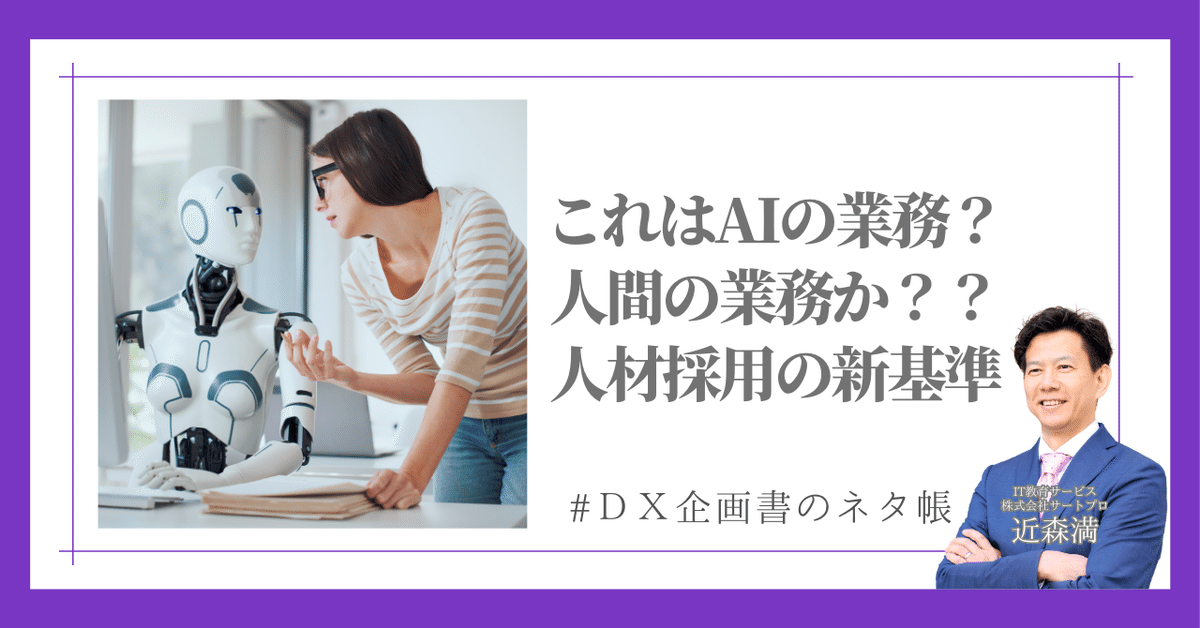
【目次】
- Shopifyの衝撃的な経営方針と“採用よりAI”という選択
- 採用は「AIにできないこと」に絞る時代へ
- ビヨンドDX:もはや「導入」ではなく「前提」の時代
- 日本企業はこの潮流にどう向き合うべきか?
- AIを活用できる人材が企業の未来を左右する
- まとめ:採用よりAIという概念をどう活用するか
【記事概要】
AI時代の働き方改革における衝撃的な経営判断として、カナダ発のEC企業Shopifyが提示した新たな人材採用の基準が話題となっています。同社CEOが全社員に向けて発したのは、「その仕事はAIにできない理由をまず証明せよ」という強いメッセージ。この指針のもと、AIに置き換え可能な業務はAIに任せ、人的リソースはAIでは代替不可能な付加価値の高い業務に集中させるというポリシーが全社方針として示されました。
この記事ではShopifyの革新的な取り組みがどのようにDX(デジタル・トランスフォーメーション)と人材戦略に影響を与えるかを深掘りします。AGIやASIといった超知性AIの登場を見据えた時代に、企業が採るべき働き方の方針、採用基準の在り方、そして教育・研修の方向性について、豊富な実例とともに解説していきます。
マインドセットの転換と生成AIの活用を前提にした「ビヨンドDX」な思考が求められるいま、経営者や人材開発担当者が押さえるべき新基準とは何か?ECとAIの共存から見える未来の働き方と、その鍵を握るマインドチェンジ、スキルチェンジについて整理します。
【著者情報】
こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。
www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/
当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のオンラインによるコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。
www.certpro.jp/dxconsulting/
Shopifyの衝撃的な経営方針と“採用よりAI”という選択
今、AI時代の働き方に新たな問いが投げかけられています。その中心にあるのが、ECプラットフォーム「Shopify」が全従業員に示したメッセージ、「その仕事はAIにできない理由を述べよ」という一文です。
《参考》ShopifyのCEO「採用よりAI」 人手代替、社員に突きつけ(日本経済新聞)
これは単なる効率化の話ではありません。人材採用の基準が「AIで代替できないことがあるか否か」という視点に移行しているのです。チームが人員や予算の増加を要求する場合、その業務がAIにできない理由を先に示すという前提条件が、公式なポリシーとして示されました。
Shopifyはかねてより、業務効率とコスト意識に厳しい姿勢を見せており、過去には会議にかかる人件費を可視化するツールを導入。30分の会議で最大1,600ドル(約22万円)ものコストがかかっていることを示し、不要な会議の削減を推進してきました。
この姿勢が今回の採用戦略にも現れており、「AIで代替できるのに人を雇うのは無駄」という明快なロジックを貫いています。
採用は「AIにできないこと」に絞る時代へ
ShopifyのCEOトビアス・リュトケ氏が全社に向けて発した書簡には、「付加価値の高い仕事こそ人間が担うべきだ」という強いメッセージが込められています。人間の採用にはコストがかかる。であれば、採用に先立ってまずはAIで代替できるかを徹底的に検証すべき。
その背景には、今や業務の多くが生成AIやAIエージェントによって処理可能となり、業務構造そのものが変化しつつあるという現実があります。Shopifyでは、AIが処理可能なタスクは積極的にAIに任せ、人間には「創造性」「戦略性」「判断力」「対話力」といった、AIでは代替し得ない領域を任せるという役割分担を徹底しています。
これはまさに「マインドチェンジとスキルチェンジ」の体現であり、AI時代における働き方のプロトタイプとも言えるでしょう。
ビヨンドDX:もはや「導入」ではなく「前提」の時代
AIを使いこなすことが前提となる今、企業のDX(デジタル・トランスフォーメーション)は“アフター”や“ビヨンド”のフェーズに入っています。
今までのように、「DXを導入しましょう」という段階はすでに終わり。AIを使うのは当然。どのように活かすかが問われているのです。
Shopifyのように、生成AIを前提に業務設計を行う姿勢は、AIエージェント間の連携や、AGI(汎用人工知能)、さらにその先のASI(超知性)を見据えた高度なマネジメント戦略に通じています。今後の企業活動は、AIによる業務の標準化と、人による価値創出が明確に分かれる世界になるでしょう。
事例: Shopifyが採用基準にAI前提を導入した背景
Shopifyがこの方針に至った背景には、カナダという先進的なテック文化と、グローバル市場での競争があります。特にコロナ禍以降、リモートワークとデジタル化が一気に進んだこともあり、「採用=スキルの担保」から「採用=AIとの連携スキルの担保」へとシフト。ここに“AIと共存する働き方”のヒントがあります。
日本企業はこの潮流にどう向き合うべきか?
この動きに対し、日本の企業はどう応えるべきでしょうか?
まず求められるのは「超知性リテラシー」の育成です。これは単なるITスキルではありません。AIを理解し、適切に業務へ導入し、他者との協働や倫理面も配慮しながら活用できる力です。
また、リスキリング(学び直し)も不可欠です。従来の業務がAIに置き換わる中で、企業は社員に「AIを使って何ができるか」を再学習させる必要があります。退職金を払って人を手放すより、AIとの協働スキルを育てるほうが生産的です。
この点で、経営者は「採用より教育」にシフトすべきだと私は考えます。
事例: QRコード技術の無償公開に見る社会的連携 H3段落
QRコードを開発したデンソーウェーブ社が特許使用料を取らず、社会全体で技術を共有するスタンスを取ったように、AIの活用においてもオープンな連携が必要です。現在、Anthropic社のClaudeが発表した「MCP(Multi-Agent Communication Protocol)」など、AIエージェント間の接続を促すプロトコルが台頭しており、“誰もが共通基盤の上でつながる”世界が現実化しつつあります。
AIを活用できる人材が企業の未来を左右する
これから求められるのは、AIを「使えるかどうか」ではなく、「使いこなせるかどうか」。
そして、AI時代における人材の価値は、ゼロからイチを生み出す創造的な力、そして決断を下す意思の強さです。
私たちは、「AIが主役の社会」で人間がどのように存在感を示すかという問いに直面しています。その中で、マネジメントや教育の在り方も抜本的に変えていく必要があるでしょう。
まとめ:採用よりAIという概念をどう活用するか
「この仕事はAIにできない理由があるか?」という問いは、今後の採用や人材育成、業務設計において強力なフィルターとなるはずです。
この視点を活かしたDX企画書としては、以下のような柱が考えられます:
・全業務のAI代替性評価(AIアセスメントマップの導入)
・採用戦略の再構築(AI基準による採用フィルター)
・リスキリング戦略(生成AI活用トレーニング+超知性リテラシー教育)
・AIと連携する人材配置最適化(AI×HRM構想)
AIと共にある働き方を前提とした人事戦略こそが、企業成長の核心になる時代が来ています。
私たちが変化を恐れていては、変化のスピードに追いつけません。
企業が今こそ考えるべきは、「AIと共に生きる」というマインドセットと、それを前提にした組織設計です。
あなたの会社でも、「採用する前にAIでできるか?」という問いを投げかけてみてください。
このシンプルな質問が、組織全体の視座を大きく変えるきっかけになるはずです。
いかがでしたでしょうか?
すこしでもみなさまの気づきになれたのであれば幸いです。
IT・DX教育サービスについてお悩みがある方は、ぜひ初回無料のオンラインコンサルティングをご利用ください。必ずお役に立ちます。
www.certpro.jp/dxconsulting/
生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。
セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。
certpro-generationaiservice.sfsite.me/
【著者紹介】
近森 満(ちかもりみつる)
株式会社サートプロ 代表取締役CEO
IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。
一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)
電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)
IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定+DX認定)
ET教育フォーラム 合同会社 代表(コンテンツ制作)
経済産業省 地方版IoT推進ラボビジネス創出事業メンター(IoT支援)
経済産業省 地域DX推進ラボビジネス創出事業メンター(DX支援)
デジタル庁 デジタル推進委員(デジタル化支援)
DX事業共同組合 設立理事(DX推進)
DX企画書のネタ帳をはじめた人「DXの鍛え方 伝道師」とは?「DXの道を切り開く伝道師、その人物と使命に迫る」【近森満:自己紹介:2024年版】|#DX企画書のネタ帳


