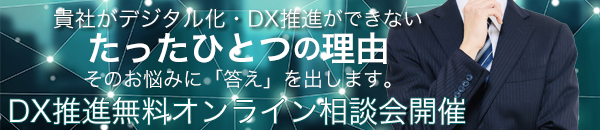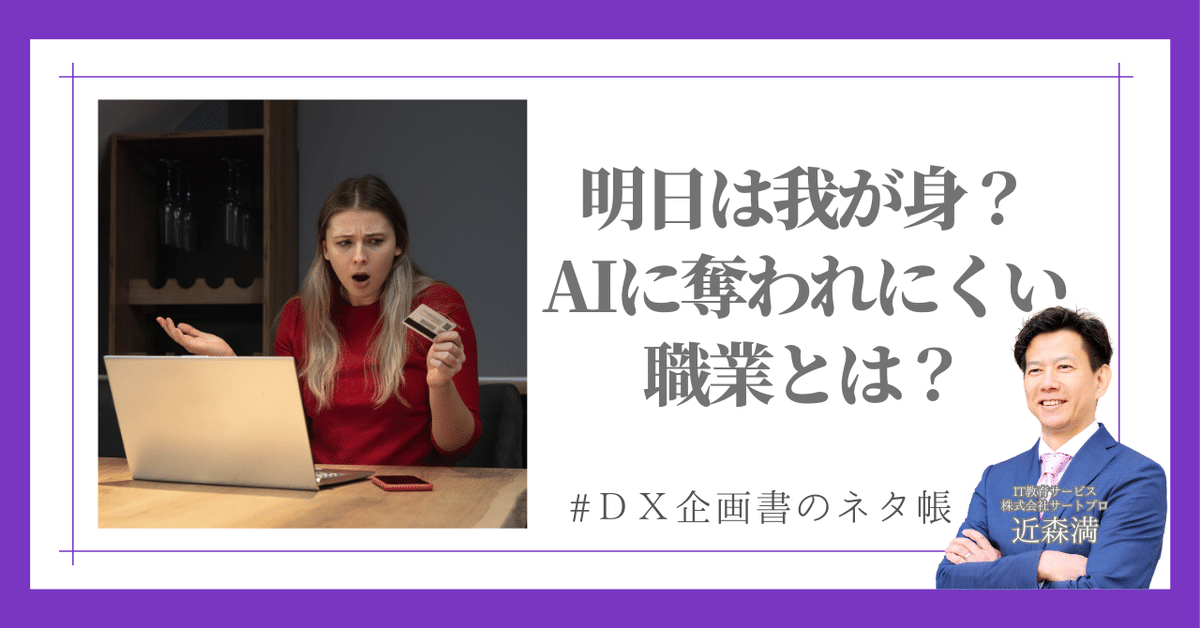
【記事概要】
「AIに奪われにくい」とされた職業が、真っ先に生成AIの影響を受ける──そんな“予想外の逆転現象”が現実となりつつあります。
AIの進化は、私たちの働き方に大きな変化をもたらしています。すでに事務処理やデータ分析といった「定型業務」はAIに置き換えられつつあり、「自分の仕事は大丈夫だろうか?」と不安を感じる人も多いでしょう。しかし、すべての仕事がAIに奪われるわけではありません。むしろ、人間ならではのスキルを活かせる職業や資格は今後さらに価値が高まります。
2015年に野村総合研究所が発表した「AIによる代替可能性レポート」では、一般事務やデータ入力といった定型作業が高リスク、ライターやアーティストといった創造的職業は安全とされていました。
しかし実際には、生成AIの進化により、文章・画像・音声といったクリエイティブ領域がいち早く代替対象となり、フリーライターやWeb制作者は新たな競争環境に直面しています。
本記事では【2025年版】として「AIに取られない仕事と資格」をランキング形式で解説し、「仕事がなくなる」のではなく「業務の中身が再構築される」という構造的変化を明らかにしながら、職業観の再定義やリスキリングの重要性、そしてAGI・ASI時代を見据えた人間ならではの価値について考察します。
AIと共存する働き方のヒントを、あなたのキャリア設計に活かしてください。
この記事でわかること
・AIに奪われる職業とは?2025年最新リスト付き
・AIに代替されやすい・されにくい仕事の違い
・AIに奪われないスキルと今後求められる働き方
・AI時代に有利な資格と選び方
・自分の仕事がAIに取られないためにできること
【著者情報】
こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。
www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/
社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のオンラインによるコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。
www.certpro.jp/dxconsulting/
AIに奪われる職業の“予想外”な現実
2015年、野村総合研究所が発表したレポートに「日本の労働人口の49%がAIやロボットによって代替可能になる可能性がある」と記されました。調査対象となった601の職業がそれぞれ代替確率で評価され、多くの人々がそのリストに注目しました。
中でも「AIに奪われにくい」とされていたのは、ライターやカメラマン、アーティストといった“創造性が求められる職業”。これらは、AIでは模倣が難しいと考えられてきたからです。
しかし現実には、真っ先に影響を受けたのはその“創造的職業”でした。生成AIが高精度な文章や画像を作れるようになり、Webライターやデザイナーなどの領域で「人間の代替」が始まったのです。特にフリーランスライターの間では、仕事の単価が下がるなどの“実害”も報告されています。
一方で、近年の調査では、一般事務職やデータ入力職、カスタマーサポートといった「エントリーレベルのホワイトカラー職」が、想定以上にAIの影響を受けていることが判明しています。米Upworkの報告では、2023年末からフリーランスの“AI対応事務職”案件数が減少傾向にあり、報酬も約5%低下したというデータがあります。
つまり、かつて「安全」とされていた仕事ほど、実は“最初に代替されるリスク”を抱えていた──これが、生成AI時代の最大の逆転劇なのです。
引用元リンク:
・野村総合研究所レポート
「日本の労働人口の49%が人工知能やロボット等で代替可能に」
www.nri.com/content/900037164.pdf
・Yahoo!ニュース記事
「AIに奪われる職業」10年前の予想が大外れと話題に 編集者は悲鳴「1人で何でもできてしまう時代」
news.yahoo.co.jp/articles/534e3d81c3229eb2f23c7da5a3ae10d5972d5ed2
「仕事が奪われる」は本当か?
このテーマで最も誤解されやすいのが、「職業そのもの」が消えてしまうという感覚です。
実際には、“職業”ではなく、その中に含まれる「業務」や「作業」単位でAIによる代替が進んでいるのが実情です。AIの登場以前から、単純な手作業や定型処理業務はコンピュータに代替されてきた歴史があります。生成AIの進化も、その延長線上にあると考えるのが自然です。
例えば「事務職」という職種が消えるわけではありませんが、その中の「データ入力」「定型報告書の作成」などは真っ先にAIが得意とする分野です。一方で「顧客の感情に寄り添う対応」や「複雑な例外処理への判断」など、人間ならではの判断力や共感力が求められる部分は依然として人の役割です。
事例:一般事務・医療事務・受付係
これらはAI代替可能性が高い職種としてリストに挙げられています。しかし、実際の現場では自動化が進んでも“人間の存在が完全に不要になる”というわけではありません。
たとえば、受付にタブレットが設置されていても、利用者が操作に戸惑ったり、想定外の問い合わせがあった場合は、やはり人の助けが必要です。医療事務にしても、保険の複雑な条件や患者対応には経験的な判断が欠かせない局面があります。
このように、AIはあくまで“効率化の補助輪”であり、人間の業務を完全に代替するには至っていない。むしろ、AIと人が協働することで新たな仕事の在り方が生まれているとも言えるでしょう。
AIに奪われる職業とは?【2025年最新版】
これまで「AIによって最も代替されやすい」とされてきた職種には、以下のようなものが挙げられます。
| 職種 | 代替されやすい主理由(タスク特性) | 置き換える/補助する技術例 |
人間が残る価値・場面
|
データ入力 |
定型・反復・ルール明確/判断の自由度が低い | OCR、RPA、フォーム自動入力、LLMによる構造化 |
例外データの判断、対面確認、機微情報の扱い、業務設計
|
製パン作業員 |
計量・成形・焼成など工程が標準化しやすい | 製造ライン自動化、ロボットアーム、画像検査AI、需要予測 |
高付加価値の手仕事、味・食感の最終調整、新商品開発、接客体験
|
製本作業員 |
断裁・綴じ・梱包など反復工程が中心 | 自動製本機、画像外観検査、AGV/AMR搬送、スケジューラ |
特装・小ロットの手加工、品質トラブルの現場判断、段取り替え最適化
|
タクシー運転者 |
経路選択と運転がルール化・データ化しやすい | 自動運転(ADAS/HDマップ)、最適配車アルゴリズム、運賃ダイナミクス |
高度な接客、観光案内・多言語対応、悪天候・障害時対応、リスク判断
|
IC生産オペレーター |
クリーンルームでの装置監視・条件設定が標準化 | MES/APC、装置ロボット化、予知保全AI、統計的工程管理 |
異常時切り分け、設備立上げ・歩留まり改善、工程改善の仮説立案
|
銀行窓口係 |
定型手続・照合業務が多い/ルール明確 | モバイルバンキング、eKYC、チャットボット、セルフ端末 |
高齢者・法人の複雑相談、相続・資産運用提案、信頼形成・説明責任
|
一般事務員 |
文書作成・集計・日程調整など定型処理が中心 | RPA、LLMアシスタント、予定調整自動化、テンプレ生成 |
部門間調整、例外処理、暗黙知の翻訳、企画・要件定義・品質管理
|
これらの職種に共通するのは、特別な判断や創造力を必要とせず、秩序的・反復的な作業で構成されている点です。定型処理に強いAIやロボットとの親和性が高く、自動化が技術的には可能とされてきました。
しかし、実際にはこうした職種がすぐに淘汰されているわけではありません。たとえば「タクシー運転者」は自動運転技術の進展が注目されていますが、現在もドライバーの人手不足が叫ばれ、業界はむしろ人材確保に苦労している状態です。
これはAI導入における“インフラと制度整備”の課題や、“人間ならではの接客対応”の必要性が関係しています。また、都市部と地方部ではテクノロジー受容の速度も異なるため、全国一斉に「明日から全自動へ」などというシナリオは現実的ではないのです。
つまり、「代替される可能性が高い」という指摘と、「すぐに現場が変わる」という現実にはタイムラグがあります。人の生活や社会構造の変化には段階があるという、極めて人間的な要素がここにも表れているのです。
2025年版:AIに代替される可能性が高い職業リスト
現在も自動化が進んでおり、2025年以降にさらにAIによる代替が進むと考えられる職業には以下が挙げられます。
| 職種 | 代替されやすい主理由(タスク特性) | 置き換える/補助する技術例 |
人間が残る価値・場面
|
データ入力・チェック業務 |
定型・反復処理が中心、誤差検出もルール化可能 | RPA、OCR、生成AIによる自動入力・検証 |
イレギュラー対応、業務設計やプロセス改善、データの解釈
|
工場の軽作業員 |
単純作業やライン作業は自動化しやすい | ロボットアーム、画像認識AI、協働ロボット(コボット) |
多品種少量生産、段取り替え、手作業による品質調整
|
銀行・役所窓口係 |
定型手続・本人確認・書類処理が多い | オンライン申請、eKYC、セルフ端末、AIチャット相談 |
高齢者やデジタル弱者対応、複雑・例外的案件の相談、信頼形成
|
タクシー・トラック運転手 |
経路選択・運転がデータ化・自動化しやすい | 自動運転(ADAS、AI配車)、配送ドローン、物流自動化 |
緊急時対応、顧客接客、特殊配送(高額貨物・狭路運転など)
|
カスタマーサポート |
FAQ対応や標準問い合わせはAIが高速処理可能 | チャットボット、音声AI、FAQ自動生成 |
感情対応、複雑なクレーム処理、関係構築、提案型サポート
|
レジ係(無人化店舗) |
会計・決済フローが単純化しやすい | セルフレジ、AI画像認識、キャッシュレス決済、Amazon Go型店舗 |
高齢者サポート、接客・商品提案、サービス体験の提供
|
不動産事務、法務補助、簡易翻訳 |
書類作成・検索・照合などルーチン要素が強い | 契約自動生成AI、リーガルテック、AI翻訳(DeepL等) |
交渉力、契約リスク判断、文化的背景理解、顧客に寄り添う説明
|
このような職業は共通して、「定型処理」「反復作業」「判断基準が明確」という特徴を持ち、AIやロボットに代替されやすい業務構造を持っています。
AIに奪われにくい仕事が真っ先に影響を受けた理由
かつて「AIに奪われにくい」とされた職業の中には、フリーライター、ブロガー、ジャーナリストなど、創造性や人間の感性を必要とするクリエイティブ職が含まれていました。理由は明確で、「文章を書く」「情報を取材する」「人の心を動かす」といった作業は、AIには難しいと考えられていたからです。
しかしその予想は、生成AI(Generative AI)の登場によって覆されました。ChatGPTに代表されるような大規模言語モデル(LLM)の進化により、人間が1時間かけて書いていた文章が、数十秒で整然とアウトプットされるようになったのです。
しかも、それが読みやすく、SEOにも強い。こうして、記事作成やブログコンテンツといった領域は、真っ先に生成AIによる“侵食”を受けました。
事例:フリーライターの実態
実際に、1ヶ月に1本の記事を仕上げていたライターが、生成AIの支援を得ることで、1週間に1冊の書籍レベルのコンテンツを制作できる──そんな“生産性の爆上がり”が現実となりつつあります。
ただしこれは、構成力やリサーチ能力、校正スキルを兼ね備えた“プロフェッショナルな書き手”に限られた話でもあります。AIと協業できるスキルがなければ、かえって市場競争に取り残されてしまうリスクがあるのです。
たとえば、米Upworkの報告では、AI登場以降、フリーランスライターの受注数は前年比で約2%減少し、報酬単価も5.2%ダウンしたという実データがあります。これは“量産が可能になった”ことによる供給過多の影響と考えられています。
つまり、代替されにくいとされた職種が、最初に価格競争に晒された──これが生成AI時代の皮肉とも言える“逆転現象”なのです。
キーワード解説:生成AI
生成AI(Generative AI)とは、テキスト、画像、音声、動画などの“新たなコンテンツ”を自動生成するAI技術のことです。代表例には、文章生成を得意とするChatGPT、画像生成のDALL·E、音声生成のVoiceboxなどがあります。
とくに大規模言語モデル(LLM:Large Language Model)の発展により、人間が書いたかのような自然な文章、構成力のあるレポート、さらにはコードや企画書までを生成できるようになりました。
この技術革新により、これまで人間固有の能力とされていた“創作”領域が、AIによって再構築されつつあります。
AIの代替可能性を“業務単位”で見よう
AI時代において、最も重要なのは「職業名」だけで未来を語るのではなく、その職業に含まれる“業務”や“タスク”ごとにAIとの関係性を見極める視点です。
たとえば、「ライター」という職業がAIに代替されると言っても、その全ての仕事がAIに任せられるわけではありません。ライターの仕事には、以下のように多様なタスクが含まれています。
| タスク | AIが得意とする部分 |
人間が担う価値・AIが苦手な部分
|
| 情報収集・リサーチ | Web検索の自動化、要約、トレンド分析、関連情報の抽出 |
情報の真偽確認、一次情報の裏取り、社会的文脈や空気感の理解
|
| 現地取材やインタビュー | 文字起こし、録音データの自動要約 |
相手の感情を読み取る、質問の臨機応変な切り替え、信頼関係の構築
|
| 原稿構成と執筆 | 文章生成、見出し作成、ロジック整理、SEOキーワード最適化 |
読者層に合わせたトーン調整、ストーリーテリング、創造的な表現
|
| 校正・校閲 | 誤字脱字検出、文法チェック、用語統一 |
文脈に応じたニュアンス調整、表現の美しさ・リズム感、倫理的判断
|
| 企画立案やクライアントとの折衝 | データを基にした企画提案、過去実績からの分析 |
クライアントの意図や背景の把握、信頼構築、対人関係スキル
|
この中で、生成AIが強みを発揮するのは「構成支援」「文章生成」などの特定業務です。一方で、人間の感性や空気を読む力が求められる“取材・インタビュー”や“文脈に合わせた表現調整”“倫理的判断”などは、まだAIが苦手とする領域です。
この構造は、ライターに限らず多くの職業に共通しています。たとえば、営業職なら「顧客データの管理」はAIが得意ですが、「信頼関係を築く対話」や「空気を読む提案」は人間にしかできません。
つまり、“職業が奪われる”というより、“業務が再構築される”という視点こそが、AI時代に必要なマインドセットなのです。
これは悲観すべきことではありません。むしろ、人間がAIと共創し、自らの価値を再定義していくチャンスでもあるのです。
クリエイティブ職の未来はどうなる?
これまで「AIには難しい」とされていた分野の代表格が、クリエイティブ職です。アートディレクター、映画監督、イラストレーター、ナレーター、音楽プロデューサーなど、芸術性や感性、センスが求められる職業はAIの進出が難しいとされてきました。
ところが現在、音声・映像・画像制作の分野でも、生成AIの進化が加速しています。実際に以下のような実用例が既に登場しています。
| クリエイティブ職タスク | AIが得意とする部分 |
人間が担う価値・AIが苦手な部分
|
| 映像編集(映画・動画制作) | 自動カット提案、色補正、音声同期、不要シーンの検出 |
物語性の演出、観客心理を読む編集、感情を揺さぶるリズム設計
|
| ナレーション・音声制作 | 高精度の合成音声、自動字幕生成、多言語変換 |
声のニュアンス・温度感、物語を伝える抑揚や間、ライブ感の演出
|
| イラスト・広告ビジュアル制作 | DALL·EやMidjourneyによる試作、背景生成、複数案の即時出力 |
ブランドイメージに沿った調整、独自スタイルの確立、細部へのこだわり
|
| 音楽制作(BGM・効果音) | 自動作曲、ジャンル模倣、テンポ合わせ、効果音生成 |
曲のコンセプト設計、感情を動かすメロディの創出、文化的文脈の表現
|
| シナリオ・構成(YouTubeや広告) | ストーリーの骨組み提案、トレンドデータをもとにした自動生成 |
読者や視聴者に刺さる物語設計、文化的背景や社会性の反映、倫理的配慮
|
| アートディレクション・監督業 | 複数パターンの生成や検証、アイデア出し支援 |
アイデアの選択・取捨選択、作品全体の統一感、メッセージ性の演出
|
こうした技術により、これまでプロの手を必要としていた工程が“部分的に自動化”されてきているのです。これはクリエイターにとって、単なる脅威ではなく「ルーティンをAIに任せ、本来の創造力に集中する」機会でもあります。
とはいえ、生成AIはあくまで「候補を出す存在」です。最終的に「どのアイデアを選び、どう仕上げるか」という判断は、依然として人間の感性に依存します。
AIが生み出す“平均的な美しさ”では物足りない──それが人間の欲望です。AIにより表現の幅が広がっても、「この作品が好きだ」と人々の心に刺さるかどうかは、やはり人間のセンスや意図に委ねられる部分なのです。
未来のクリエイティブ職は、「手を動かす職業」から「AIと共創し、選び、演出する監督者」へと進化していくでしょう。
事例: 俳優とCM業界
実写の俳優を使わず、AIが生成したキャラクターでCMを作る事例も増えています。しかし、視聴者の“好感度”や“信頼性”を得るには、やはり人間らしさが重要であるという声も根強いのが現状です。
職業観の再定義と“変化する勇気”
AIの進化が加速する現在、働く人々に突きつけられているのは「仕事がなくなる恐怖」ではなく、“自分の職業観そのものを問い直す必要”です。
これまでの日本社会では、「終身雇用」や「一つの職能を磨き続けること」が美徳とされてきました。しかし、その延長線上には「この仕事しかできない」という不安も生まれています。
たとえば、何十年も同じ業務に従事してきた人が、ある日突然「AIで代替できるようになりました」と言われたとき、どうするか──。それは決してその人の価値がなくなったわけではありません。ただ、社会や技術の変化に対して、自分の働き方を再構築するタイミングが訪れただけなのです。
重要なのは、「この道一筋だったのに奪われた」と嘆くのではなく、「じゃあ次は何ができるか?」と柔軟に切り替える“変化する勇気”です。これは、年齢に関係なく、あらゆる職種の人に求められているマインドセットです。
キーワード解説:マインドセットとリスキリング
マインドセットとは、物事の捉え方や思考のクセを指します。特に変化の激しい現代においては、「これまでのやり方に固執しない柔軟性」こそが生存戦略です。
そして、その柔軟な心構えのうえに築かれるのがリスキリング(Reskilling)=学び直しです。たとえば、AI時代には「文章生成」よりも「プロンプト設計」が重要になるように、スキル構成そのものが再定義されつつあります。
「自分は技術職じゃないから関係ない」では済まされない時代。IT、AI、デジタルの基本リテラシーは、全職種にとっての“新しい常識”になろうとしています。
学び直す意志があれば、何歳からでもキャリアは再構築できる──その前提に立つことが、AI時代を生き抜く第一歩なのです。
AIに奪われにくい仕事・資格とは?
逆に、AIに奪われにくい仕事には次のような特徴があります。
・創造性や発想力が求められる(クリエイティブ職)
・多様な人間関係に基づく判断が必要(マネジメント・教育・医療)
・現場対応力・身体性を要する(介護・建設・保守)
代表的な「AIに取られにくい資格」
| カテゴリ | 資格 |
AIが代替しにくい理由・特徴
|
| 国家資格 |
看護師 |
患者の身体や感情に直接寄り添うケア、緊急時の判断力、共感を伴うコミュニケーションが不可欠
|
| 国家資格 |
保育士 |
子どもの発達段階に応じた対応、感情の理解、遊びや学びを通じた人間的な成長支援
|
| 国家資格 |
臨床心理士 |
心理面の深い傾聴や対話を通じて支援、倫理的判断と人間関係の信頼性が必要
|
| 国家資格 |
社会福祉士 |
高齢者や障害者の生活支援、制度活用の助言、相談者の状況に応じた柔軟対応
|
| 専門技能 |
電気工事士 |
高度な安全性確保、現場ごとに異なる設備環境への対応、精密な手作業
|
| 専門技能 |
建築士 |
法規制や構造設計への理解、美的感覚と機能性を両立させた提案力
|
| 専門技能 |
測量士 |
地形や現場環境の読み取り、誤差を考慮した判断、災害・特殊環境での柔軟対応
|
| 対人関係 |
キャリアコンサルタント |
個人の価値観や感情に寄り添いながらキャリア形成を支援、信頼関係が前提
|
| 対人関係 |
中小企業診断士 |
経営者との対話を通じた課題抽出、状況に応じた戦略提案、人間的な交渉力
|
| 教育関係 |
教員免許 |
学習者ごとの理解度や感情に合わせた指導、やる気を引き出す関わり方
|
| 教育関係 |
学習支援関連の民間資格 |
個別ニーズに対応した支援、学習意欲の促進、柔軟なコミュニケーション
|
特に“人に寄り添う”職業は、今後ますます価値を持つと見られています。
AGI・ASI時代に備えて
現在は生成AI(Generative AI)が話題の中心ですが、その先にはAGI(汎用人工知能:Artificial General Intelligence)、そしてASI(超知性AI:Artificial Super Intelligence)という未来像が待ち受けています。
AGIとは、人間と同等、あるいはそれ以上の幅広い知的能力を持つAIのこと。ASIはそれをさらに超え、人間のすべての知的活動を凌駕する能力を持つ存在を意味します。
これらが実現すれば、単なる業務の自動化にとどまらず、戦略立案、政策形成、倫理判断など、これまで人間だけが担っていた領域にもAIが進出する可能性があります。
そうした時代において重要になるのは、「自分は何ができるか」という機能的なスキルよりも、「自分はどんな価値を提供できるか」という存在意義の再定義です。
とくに重要になるのは、以下のような“非構造的スキル”です:
・倫理的判断
・共感力・対人理解
・文脈に応じた意思決定
・多様性への感受性
・創造的なストーリーテリング
これらは数値化や形式化が難しく、AIによる完全代替が困難とされています。
つまり、「超知性の時代」に生き残る人材とは、あえて“非効率”を引き受け、人間らしさを武器にできる存在なのです。
AGIやASIに備えるということは、未来の技術的脅威に怯えることではありません。むしろ、今こそ人間にしかできない価値を見つめ直し、そこに磨きをかける絶好のタイミングなのです。
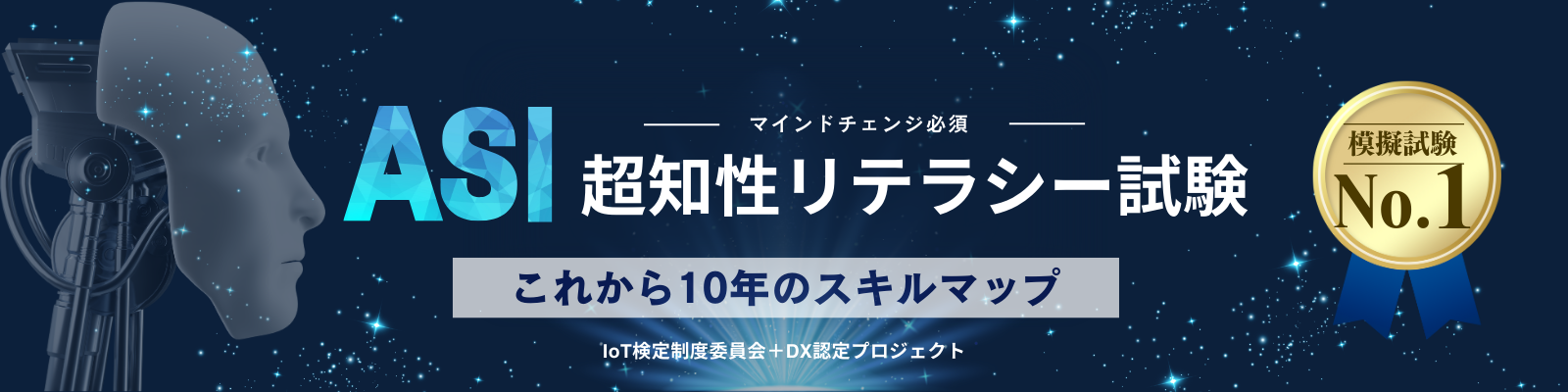
まとめ:仕事は「なくなる」のではなく「進化する」
ここまで見てきたように、AI、特に生成AIの急速な進化は、職業の構造や価値基準に大きな変化をもたらしています。
かつて「安全」とされた仕事が真っ先に代替され、「代替されやすい」とされた仕事が意外に残っている──この逆転現象が示すのは、「仕事そのものが消える」のではなく、「仕事の中身が変わる」という現実です。
重要なのは、業務のうちAIが得意とする部分はAIに委ね、自分は“人間にしかできない価値提供”に集中すること。つまり、「自分の仕事が何か」ではなく、「自分は何に価値を生み出せるか?」を問い直す時代なのです。
この視点の転換こそが、AI時代、そして将来のAGI・ASI時代を見据えたキャリア設計の出発点となります。
変化は脅威ではなく、再構築と進化のチャンス。あなた自身のスキルセット、マインドセット、職業観を柔軟に“アップデート”していくことが、これからの10年における最強の生存戦略です。
いかがでしたでしょうか?
すこしでもみなさまの気づきになれたのであれば幸いです。
当社は資格や検定の立ち上げを得意としています。
IT・DX教育サービスについてお悩みがある方は、ぜひ初回無料のオンラインコンサルティングをご利用ください。必ずお役に立ちます。
www.certpro.jp/dxconsulting/
生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。
セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。
certpro-generationaiservice.sfsite.me/
【著者紹介】
近森 満(ちかもりみつる)
■株式会社サートプロ 代表取締役CEO
IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。
■所属・役職
・IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定、+DX認定、超知性ASI検定)
・一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)
・電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)
・NPO 組込みソフトウェア管理者技術者育成研究会 メンバー(組込み)
・ET教育フォーラム合同会社 代表(コンテンツ制作)
・経済産業省地方版IoT推進ラボ ビジネス創出事業メンター(IoT支援)
・経済産業省地域DX推進ラボ ビジネス創出事業メンター(DX支援)
・デジタル庁デジタル推進委員(デジタル化支援)
・DX事業共同組合 設立理事(DX推進)
・一般社団法人日本サステナブルビジネス機構 幹事(SDGs認証)
・”一億総活躍社会を実現する”共生日本協議会 理事(DEI支援)
・アジャイル開発技術者検定試験コンソーシアム 事務局長(Agile検定)
・一般社団法人国際サイバーセキュリティ協会 事務局長(IACS認定)
DX企画書のネタ帳をはじめた人「DXの鍛え方 伝道師」とは?「DXの道を切り開く伝道師、その人物と使命に迫る」【近森満:自己紹介:2024年版】|#DX企画書のネタ帳