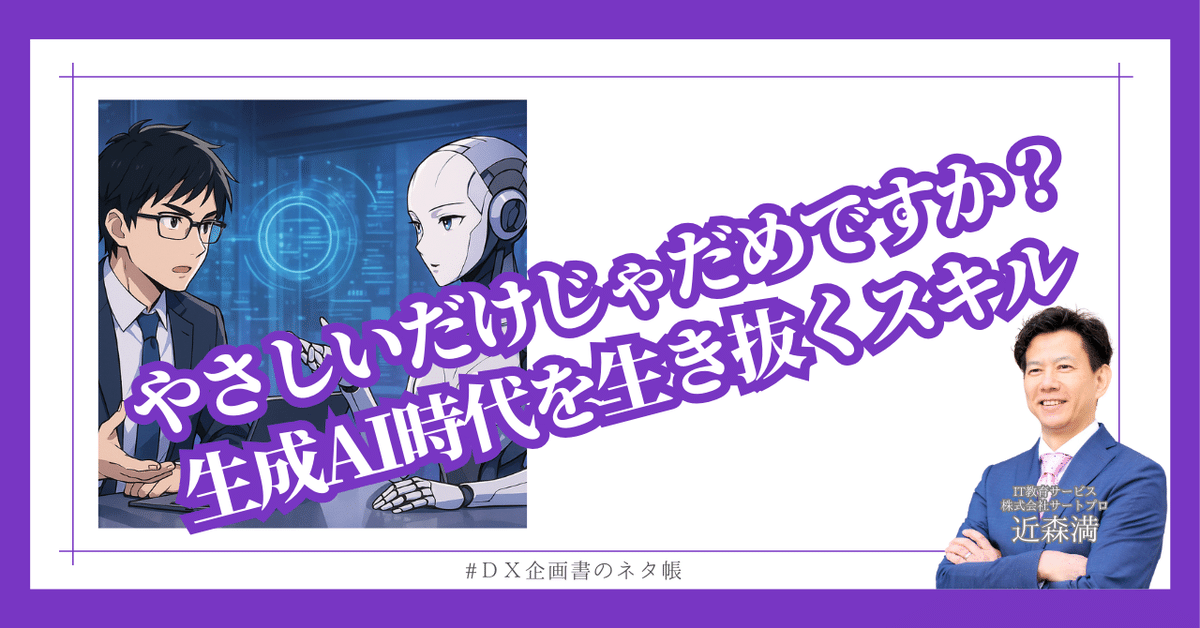
【記事概要】
生成AIが身近な存在となりつつある現代社会。私たちがAIを活用していく上で必要となるのは、単なる優しさではなく、「しつこさ」と「冷徹さ」を併せ持つマインドセットです。
本記事では、近森満氏がポッドキャストで語った内容を元に、生成AIとの効果的な向き合い方や、その中で求められる思考の変革「マインド・トランスフォーメーション」について詳しく解説します。Copilotのような“副操縦士”から、対等な“知的パートナー”へと進化するAI。その進化に対応するには、人間側も「何を求めるのか」を明確にし、曖昧さを排除しながら、時には自分自身に冷徹になる必要があります。
本記事では、AIにしつこく問い続ける姿勢と、AIの中立的な回答を鵜呑みにせずに判断する冷静さの両立が、これからのビジネスパーソンにとって不可欠であることを、事例を交えながら紹介します。
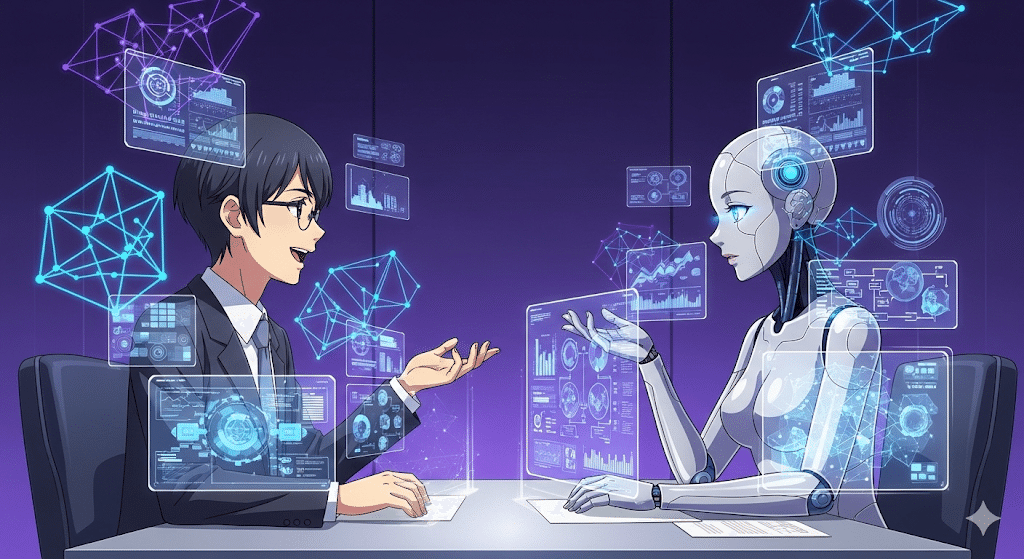
【著者情報】
こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。
www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/
当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。
www.certpro.jp/dxconsulting/
優しさだけではAIと向き合えない
「AIにやさしく接しましょう」とよく言われます。でも本当にそれだけで良いのでしょうか?
今、生成AIが急速に進化し、私たちの生活やビジネスのあらゆる場面に入り込んできています。
それに伴い、人間の側にも新しい思考や行動が求められるようになっています。そのひとつが、「しつこさ」と「冷徹さ」です。
特に「冷徹さ」と聞くと、ネガティブな印象を持つ方が多いでしょう。
「冷たい人」「共感がない」「とっつきにくい」など…。
しかしここで言う冷徹さとは、人間味を捨てるという話ではありません。むしろ、AIと共存するためのマインドセットのひとつとして、自分自身とテクノロジーの関係性を問い直す“冷静さ”のことを指しています。
この「冷徹さ」と「しつこさ」をセットで持つことが、今後のAI時代における「生きる力」になっていくのです。
Copilotから対等な知的パートナーへ
かつて、AIは「副操縦士=Copilot」として、私たち人間の補佐役に過ぎませんでした。
たとえば、Microsoftの「Copilot」は、その名の通り「副操縦士」として、操作の補助や確認を行ってくれました。
しかし、今日の生成AIはどうでしょうか? すでに知識や分析力においては私たちを凌駕する存在となり、私たちと「対等に議論」するレベルにまで進化しています。
この変化により、私たち自身が判断する主体であることがより強く求められるようになりました。
AIがいくら正確な情報を返してきても、「その結論で本当にいいのか?」と最後にジャッジを下すのは人間です。
事例: ChatGPT-4oとChatGPT-5の性格の違い
近森氏は、ChatGPTの過去バージョンのGPT-4oと現在のGPT-5との違いについても触れています。
「4oはちょっと人間味があった。一方で新しいバージョン5は冷たい。寄り添ってくれない。」
これは、新しいAIが“中立性”と“冷徹な情報処理”を追求している証拠とも言えるでしょう。
ユーザーの共感を優先するのではなく、ファクトベースで大量の情報を圧倒的なスピードで返す。そこに「優しさ」はないのかもしれません。
ですが、それは“AIが冷たい”というよりも、人間側の感情を投影しているだけなのです。
だからこそ、「AIの返答に感情を読み取る」のではなく、「冷徹に事実を読み解く力」が人間には求められます。
しつこさ=AI時代の“交渉術”
では「しつこさ」とは何か?
これは、生成AIを使いこなす上で不可欠な“粘り強さ”と“具体性”のことです。
生成AIに問いかけると、非常に優秀な回答を返してくれるように見えます。しかし、それは「こちらの意図を100%正確に汲み取った結果」ではなく、曖昧な指示に対してそれらしく整った回答を出しているだけの場合も多いのです。
だからこそ必要なのが、「違う、そうじゃない!」と繰り返し伝え、
“AIに自分の意図を理解させるしつこさ”なのです。
事例: ChatGPTに何度も同じ質問をする
ある質問に対し、AIから望んだ答えが得られなかったとします。
このとき、「もういいや」とあきらめるのではなく、「具体的にどこが違うのか」「どの視点で欲しいのか」をしつこく5回でも10回でも伝え直す。
その反復の中でAIの理解度も上がり、期待に応えられる回答が返ってくるようになるのです。
これはまさに、プロンプトエンジニアリングの本質でもあります。
しかも近年のGPTは、長期記憶を持つことで、利用者の性格や傾向を学習するようになっていますので、結果的に将来のアウトプットはあなたの欲しいものになります。
AIに対する冷徹さと自己に対する冷徹さ
生成AIと付き合う上で、冷徹さは二方向に求められます。
①AIに対する冷徹さ
②自分自身に対する冷徹さ
AIに対しては、「AIの答えを鵜呑みにしない」「裏取りをする」「5回確認する」など、情報を疑う目が必要です。
AIの出す答えには、“信頼できるものもあれば、間違っているもの”もあります。
一方で、自分自身に対しても「本当に自分が欲しかった情報は何か?」と問い直す必要があります。
AIに明確な指示ができない=自分の思考が曖昧である、という可能性もあるのです。
この「自己への冷徹さ」は、時に痛みを伴う現実と向き合う勇気でもあります。
情と理のハイブリッド:新時代のマインドセット
AI時代の人間に求められるのは、「情」と「理」のハイブリッドです。
・情(しつこさ): 相手を理解し、何度も粘り強く伝える努力
・理(冷徹さ): 事実に基づき、感情を切り離して判断する力
この両輪を回せることが、AIを使いこなすスキルセットであり、マインド・トランスフォーメーション(思考の変革)の核心でもあります。
分断社会とマインドの格差
近森氏は、AI活用の分野において、今後「分断」が進むと警告します。
・積極活用派(毎日使い倒す)
・選択的活用派(必要なときだけ使う)
・拒否派(AIは信用できない)
こうした心理的な壁は、テクノロジーの格差ではなく、マインドセットの格差=“マインドデバイド”に他なりません。
この格差を乗り越えるためには、「使えるかどうか」ではなく、「どう使うべきか」「なぜ使うのか」という目的意識が必要です。
マインド・トランスフォーメーションからDX推進へ
マインドチェンジの先にあるのが、マインド・トランスフォーメーションです。
そしてそれは、企業のDX推進とも直結します。
・自分の中にある「古い価値観」を見つけて
・テクノロジーとの共生を受け入れ
・情報を取捨選択し、冷徹に判断し
・何度でも問い直すしつこさを持ち
このマインドセットこそが、「生成AI時代のビジネスパーソン」に求められる新しいスキルとなるでしょう。
まとめ:AI時代の思考法は“優しさ+冷徹さ”
やさしさだけでは、AI時代を生き抜けない。
その本質は、相手(AI)と自分の限界を理解し、「行動を続けるしつこさ」と「情報に向き合う冷徹さ」の両立にあります。
これは人間らしさを失うことではなく、むしろより深い人間理解と知性を磨くプロセスです。
いかがでしたでしょうか?
すこしでもみなさまの気づきになれたのであれば幸いです。
DX推進担当者の育成やIT教育研修でお悩みがあれば、ぜひ初回無料のコンサルティング「DX推進人材教育プログラム」にご応募ください。かならずお役に立ちます。
ではまた。
www.certpro.jp/dxconsulting/
キーワードの解説
マインド・トランスフォーメーション
マインド・トランスフォーメーションとは、単なる知識やスキルの習得にとどまらず、個人や組織の価値観・判断基準・思考習慣を根本から見直し、デジタル時代に適応するための「思考の進化」を指します。従来のマインドチェンジが「変化を受け入れる姿勢」であるのに対し、トランスフォーメーションは「変化を生み出す原動力」へと自分をシフトさせることが目的です。DX推進においては、マインド・トランスフォーメーションの有無が組織の成否を分ける重要な鍵となります。
生成AI
生成AI(Generative AI)とは、テキストや画像、音声、動画などのデータをもとに、新たなコンテンツを自動生成するAI技術の総称です。代表的な例にはChatGPTやGemini、Claudeなどがあり、プロンプト(命令文)に応じて人間のような自然な文章を返すことができます。近年ではビジネス・教育・行政など幅広い分野で活用が加速しており、情報収集・分析・意思決定・創造活動に革命をもたらしています。
冷徹さ
本稿で語られる「冷徹さ」とは、他人やAIに対して非情になるという意味ではなく、「感情に流されず、事実をもとに判断する思考態度」を意味します。生成AIの出す回答に共感や温かさを求めすぎると、判断を誤るリスクが高まります。冷徹さとは、自己のバイアスを排し、「今本当に必要な情報は何か?」を見極める力のことです。生成AI時代において、優しさと冷徹さのバランスを保つことが、持続可能な成長には欠かせません。
【著者紹介】
近森 満(ちかもりみつる)
■株式会社サートプロ 代表取締役CEO
IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。
■所属・役職
・IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定、+DX認定、超知性ASI検定)
・一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)
・電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)
・NPO 組込みソフトウェア管理者技術者育成研究会 メンバー(組込み)
・ET教育フォーラム合同会社 代表(コンテンツ制作)
・経済産業省地方版IoT推進ラボ ビジネス創出事業メンター(IoT支援)
・経済産業省地域DX推進ラボ ビジネス創出事業メンター(DX支援)
・デジタル庁デジタル推進委員(デジタル化支援)
・DX事業共同組合 設立理事(DX推進)
・一般社団法人日本サステナブルビジネス機構 幹事(SDGs認証)
・”一億総活躍社会を実現する”共生日本協議会 理事(DEI支援)
・アジャイル開発技術者検定試験コンソーシアム 事務局長(Agile検定)
・一般社団法人国際サイバーセキュリティ協会 事務局長(IACS認定)


