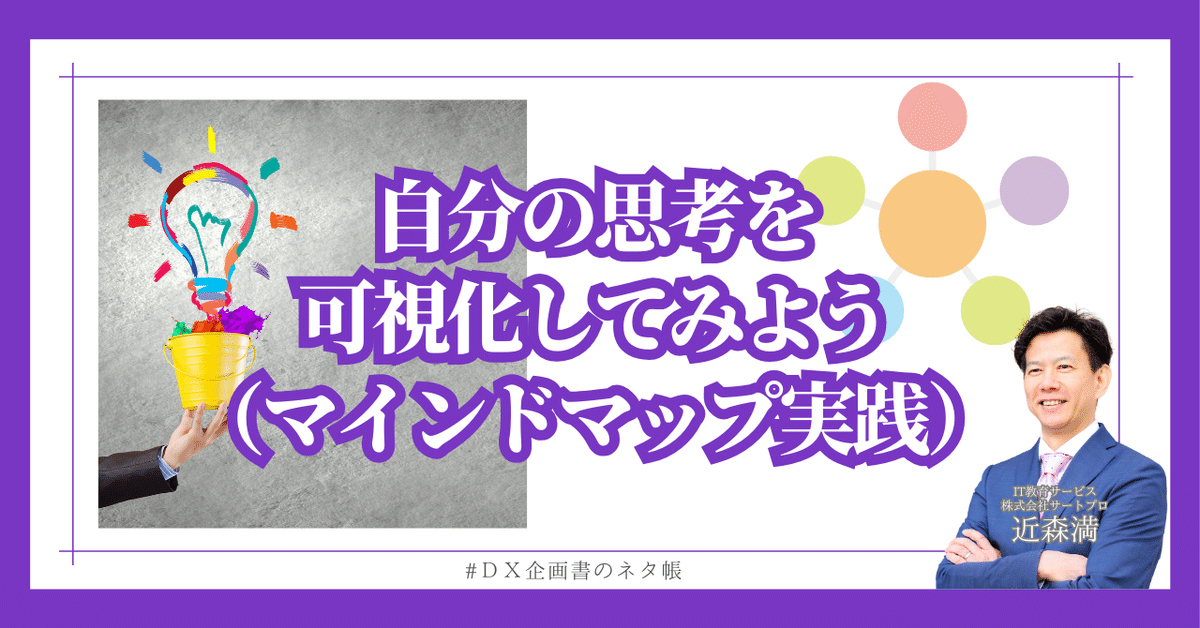
【記事概要】
本記事は、大人の勉強会「最終回」で語られた「自分の思考を可視化する」方法、特にマインドマップ実践の意義を深掘りします。
近森満氏の20年以上にわたる実践経験を背景に、マインドマップの基本ルールや効果、さらには大谷翔平選手の「マンダラート」活用事例なども紹介。単なる図解法ではなく、思考の整理、未来設計、行動計画の強力なツールとしての活用可能性を描きます。
さらに生成AIやGoogleの「NotebookLM」との連携といった最新トレンドにも触れ、デジタル時代における“思考の見える化”の重要性を解説します。学びを止めないための実践方法、日常生活や仕事にどう応用するかまでを体系的に整理。読後には、あなた自身がマインドセットを可視化し、行動へと落とし込む第一歩を踏み出せるよう設計された記事です。
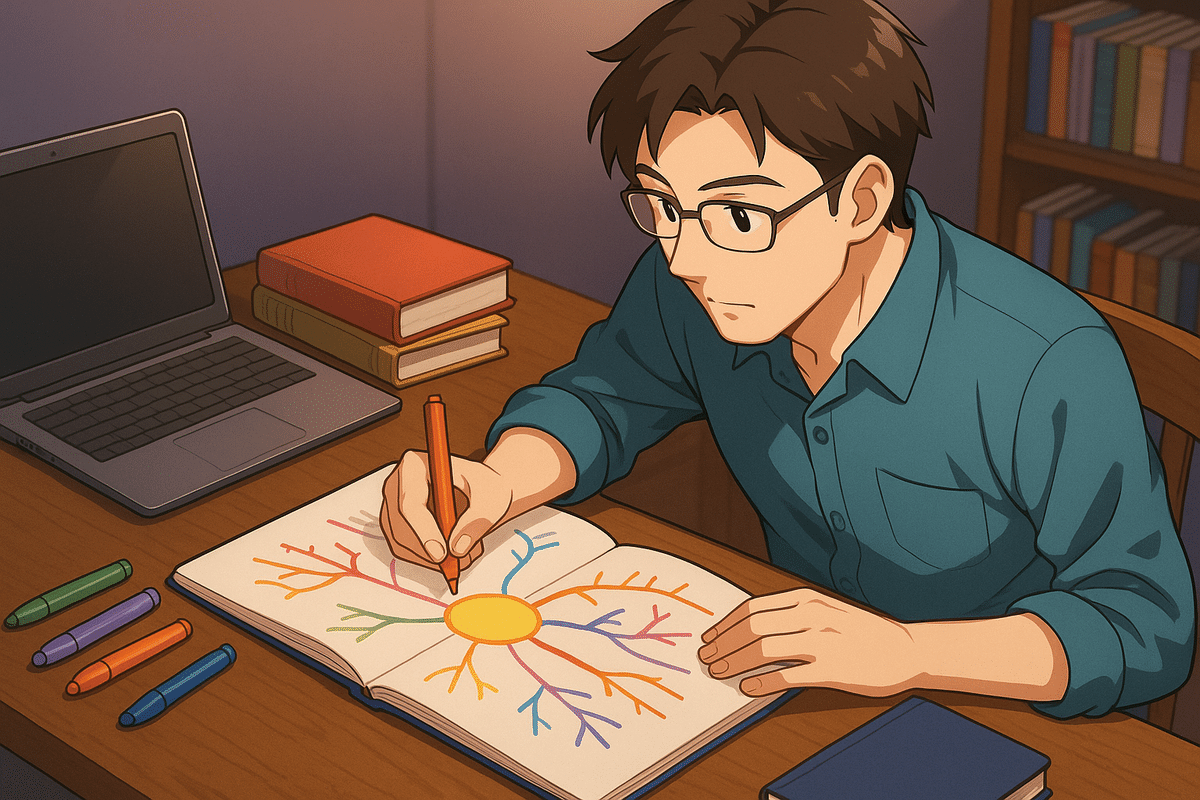
【著者情報】
こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。
www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/
当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。
www.certpro.jp/dxconsulting/
学びを止めない大人の勉強会
8月のお盆や夏休みの暑い時期、誰しも気が散ったり、だるさで仕事に向き合いたくない日もあるでしょう。私自身も例外ではありません。そんな中でも「学びを止めない」という姿勢を保つために始めたのが、この大人の勉強会でした。約20回にわたる配信を通じて、皆さんと一緒に成長を考え、実践してきました。
学びを続けるための工夫は、形式を変えることにも表れています。これまで何年も続けた音声配信を、今回は「大人の勉強会」という視点で共有スタイルに変えたのもその一つです。子供たちが夏休みに勉強するように、大人にも学び直しやリスキリングの機会が必要です。
思考を可視化する力とは
最終回のテーマは「自分の思考を可視化する」こと。これを実現する代表的な方法がマインドマップです。中心にキーワードを置き、放射線状に連想を広げるこの手法は、思考の流れを整理し、行動計画へと落とし込む強力なツールです。
大谷翔平選手が高校生時代に「マンダラート」を活用し、自らの夢を具現化したエピソードは有名です。中心のマスに大目標を据え、周囲に具体的な行動を配置していくことで、夢を現実に近づけました。マインドマップも同じく、放射思考を可視化する点で共通しています。
事例: UMLとマインドマップ
2000年頃、日本ではUML(統一モデリング言語)がそれまでバラバラであった記述言語を一つにまとめ、結果、ソフトウェア開発現場で流行しました。当時、私もマインドマップを設計段階のアイデア整理に活用するいろいろな現場を見ました。機能要件やサービスのイメージを放射状に描き出すことで、システム開発の全体像が明確になり、効率的に進めることができました。絵を添えたり、カラフルな色使いが特徴なマインドマップなので、単なる「遊び」に見られることもありましたが、実際には右脳と左脳を刺激し、発想を広げる実践的な方法だったのです。
マインドマップの基本ルール
効果的なマインドマップには基本的なルールがあります。
①テーマを中央に置く
②枝ごとにキーワードを一つ書く
③色やイラストを交えて連想を広げる
④階層構造で整理する
最初から完璧を目指す必要はありません。大切なのは量を出すこと。思いついたらすぐに書き出し、必要に応じて修正すればよいのです。文章でまとめるよりもキーワードで書く方が発想が途切れず、自然と新しいアイデアが生まれます。
思考の可視化がもたらすメリット
なぜ思考を可視化する必要があるのか。理由はシンプルです。
アイデアは放っておくと散らばり、形になりません。マインドマップにすることで、中心となる目的が見え、メリットや市場性、リスクを整理できます。これにより行動計画を立てやすくなります。
例えば新規事業を構想する際も、マインドマップを使えばアイデアの全体像を俯瞰でき、方向性を見失わずに済みます。
事例: 年始の目標設定
私は毎年、年初にマインドマップで「今年の目標」を描いています。家族・仕事・趣味・チャレンジなどのカテゴリを中心から広げ、具体的に行動に落とし込む。これにより、1年の指針が明確になり、モチベーション維持にも役立ちます。
AI時代におけるマインドマップの価値
近年は生成AIやGoogleの「NotebookLM」のようなツールでもマインドマップが自動生成されます。しかし、本来の意義は「自分の頭の中を可視化する」ことにあります。AIによる整理は便利ですが、自分の手で描くことで思考が深まり、右脳と左脳のバランスを刺激できます。
最新ツールを活用して補助的に整理するのも良いですが、まずは自分で書き出してみることが重要です。
マインドマップ実践のすすめ
思考の可視化は、職場での業務改善だけでなく、プライベートにも役立ちます。趣味の計画や家族との未来設計など、多様な場面で活用できます。
ただし注意点もあります。マインドマップを理解していない人に見せると「落書き」に見えることも。共有する相手を選びつつ、自分自身の思考整理のために積極的に活用しましょう。
まとめ:思考の可視化で未来を描く
マインドマップは単なる図解ではなく、自己成長のための武器です。未来設計、行動計画、学びの振り返りにおいて、思考を整理することで次の一歩を踏み出せます。
行動を始めなければ何も変わりません。まずは1枚、自分のテーマを書き出してみてください。
いかがでしたでしょうか?
すこしでもみなさまの気づきになれたのであれば幸いです。
IT・DX教育サービスについてお悩みがある方は、ぜひ初回無料のオンラインコンサルティングをご利用ください。必ずお役に立ちます。
www.certpro.jp/dxconsulting/
生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。
セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。
certpro-generationaiservice.sfsite.me/
キーワードの解説
マインドマップ
トニー・ブザン氏が提唱した思考整理の手法。中心にテーマを置き、放射線状に連想を広げる。言語情報と非言語情報を組み合わせることで、記憶定着やアイデア発想を助ける。ビジネスや教育現場だけでなく、個人の生活目標にも活用可能。
思考の可視化
頭の中の抽象的な思考を図解やキーワードで外に出し、整理すること。アイデアを散逸させず、目的と方向性を明確にする。行動計画や問題解決を促進するだけでなく、チーム共有の基盤にもなる。
リスキリング
新しい時代の変化に適応するための「学び直し」。既存のスキルをアップデートし、DX推進や生成AIの活用といった新しい課題に備える。企業にとっては人材育成の鍵であり、個人にとってはキャリアを切り拓く手段となる。
【著者紹介】
近森 満(ちかもりみつる)
■株式会社サートプロ 代表取締役CEO
IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。
■所属・役職
・IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定、+DX認定、超知性ASI検定)
・一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)
・電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)
・NPO 組込みソフトウェア管理者技術者育成研究会 メンバー(組込み)
・ET教育フォーラム合同会社 代表(コンテンツ制作)
・経済産業省地方版IoT推進ラボ ビジネス創出事業メンター(IoT支援)
・経済産業省地域DX推進ラボ ビジネス創出事業メンター(DX支援)
・デジタル庁デジタル推進委員(デジタル化支援)
・DX事業共同組合 設立理事(DX推進)
・一般社団法人日本サステナブルビジネス機構 幹事(SDGs認証)
・”一億総活躍社会を実現する”共生日本協議会 理事(DEI支援)
・アジャイル開発技術者検定試験コンソーシアム 事務局長(Agile検定)
・一般社団法人国際サイバーセキュリティ協会 事務局長(IACS認定)


