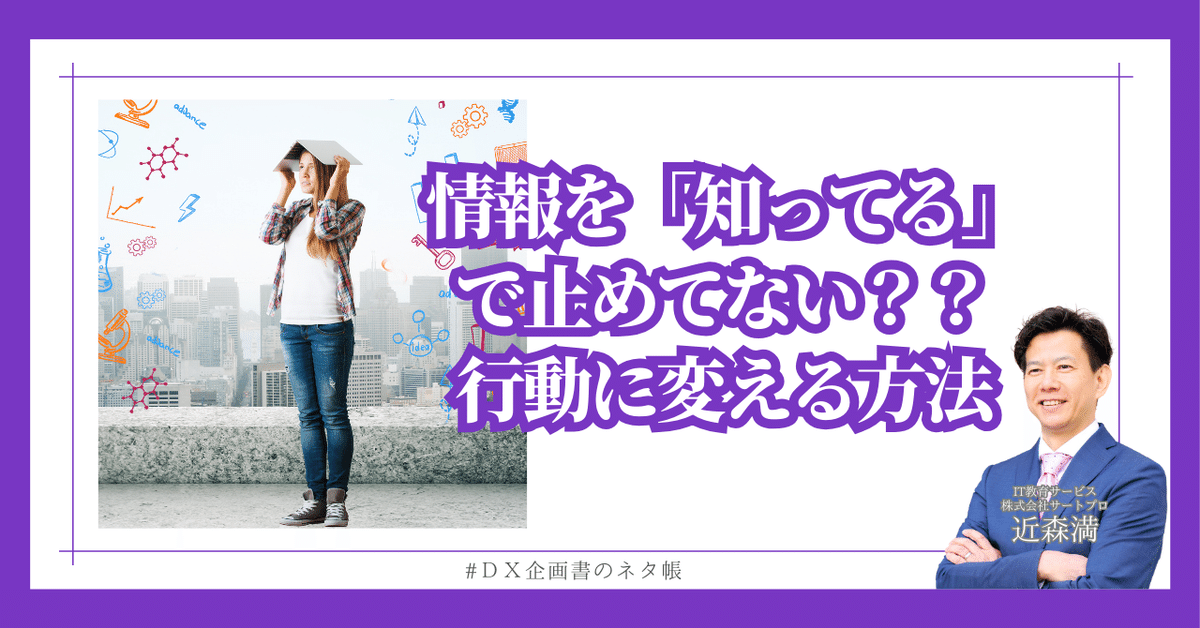
【記事概要】
「知っている」ことに満足してしまい、行動に移せない――そんな悩みを抱えるビジネスパーソンに向けて、IT・DX人材育成のプロである近森満が、情報を行動に変えるための具体的な方法を提案します。
本エピソードでは、情報過多の現代における「インプット症候群」や、「知行合一(ちこうごういつ)」という東洋思想を背景に、アウトプット力を鍛える3つのステップ(人に話す、書く、小さく試す)をわかりやすく解説。
また、行動を促進するための環境構築術(タスクの小分け、締切、仲間との共有など)や、知識の採算化=成果につなげる考え方まで掘り下げます。リモートワークで孤立しがちな現代人にとって、自らアウトプットの場を作り、学びを習慣化する重要性が再確認できる内容です。行動を後回しにしがちな人、自分の知識を活かしきれていないと感じている人にとって、気づきと背中を押すヒントが満載の回となっています。
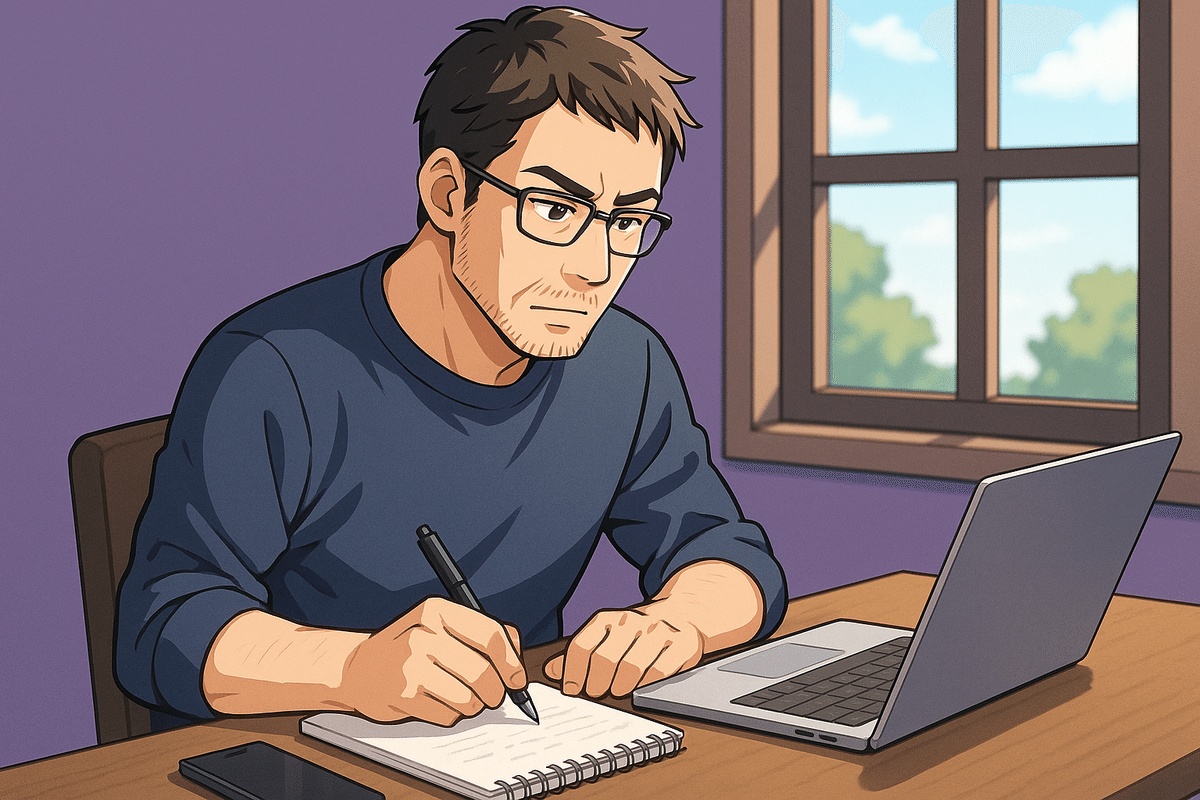
【著者情報】
こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。
www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/
当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。
www.certpro.jp/dxconsulting/
情報を「知ってる」で止めない大人の学び方
インターネットと生成AIによって、私たちはかつてないほどの情報に触れられるようになりました。Google検索、YouTube、X(旧Twitter)、ChatGPT…。調べれば何でも出てきます。そう、「知る」こと自体は驚くほど簡単になったのです。
でも――
知って満足していませんか?
「あ、それ知ってる」で終わっていませんか?
行動に、変えてますか?
この問いにギクッ!とした方。この記事は、まさにあなたのための「大人の勉強会」です。単なるインプットから抜け出し、行動に結びつける“アウトプット型リテラシー”へ。その方法を、現役DX人材育成のプロとして、私・近森満が語っていきます。
なぜ人は「知ってる」で止まるのか
まず最初に押さえておきたいのは、
「なぜ私たちは知識で満足してしまうのか?」という構造的な問題です。
インターネット社会では、次から次へと情報が流れてきます。そして、脳は知識を得ることで「達成感」を得るという性質を持っています。つまり、行動に移す前に、すでに報酬(ドーパミン)が出てしまうわけです。
この状態が続くとどうなるか?
「インプット症候群」になります。
学んでも、読んでも、聞いても、行動しない、知識がたまるだけ。
思い当たる人、多いんじゃないでしょうか?
さらに、生成人工知能(生成AI)が登場して以降、「調べる・まとめる・要約する」ことはAIが代行してくれるようになりました。その結果、人間側の「考える」「実践する」力が求められるようになったのです。
ーーが、…
知ってるだけでは“損”する時代に突入している
ここでお伝えしたいのは、「知識の蓄積が悪い」という話ではありません。むしろ大切です。でも、それが自分の人生や仕事にどう活かされているか。そこが問題です。
たとえば、ChatGPTの左側の履歴、どんどん積読(つんどく)のように溜まっていませんか?
私も山のようになってました(笑)。
そして、ある時、エクスポート機能を使って出力してみたら、なんと!
アクセスできなかったタイトルが復活したんです。
ここに重要なヒントがあります。
「出力(アウトプット)」は、情報を復活させ、再構成し、行動に導くプロセスそのものなんですね。
知行合一:「知ること」と「行うこと」は一つである
ここで少し哲学的な視点も紹介します。
「知行合一(ちこうごういつ)」という言葉をご存知でしょうか?
これは、明代の思想家・王陽明が提唱した概念で、
「真に知るということは、必ず行動が伴っている」という意味です。
「わかってるけど、やってない」なら、それは本当は“わかっていない”のと同じなのです。
現代で言えば、「ダイエットには運動が大事」と知っていながら何もしていないなら、それは“知っている”とは言えない、ということですね。
この考え方は、まさにDX推進やリスキリングにも通じます。
情報を行動に変える3つのステップ
それでは、「知ってる」から「やってみた」へと移行するには、どうすればいいのか?
私が実践してきた、アウトプット力を育てる3ステップをご紹介します。
1. 学んだら人に話す
最も簡単で、かつ効果的な方法。それは「人に話す」ことです。
私の場合は、ポッドキャストで発信しています。
誰も聞いていなくてもOK。仮想のリスナーを想定し、語りかける。それだけで、思考が整理され、記憶に定着し、理解が深まります。
SNSでもいいし、友人や同僚とのランチでもOK。
大切なのは、口に出すことです。
2. 書いてみる(SNS・ブログ・ノート)
「話す」ことが難しい人は、まずは書くことから始めましょう。
手帳、メモ帳、note、X(旧Twitter)、フェイスブック、なんでもかまいません。書くことで、情報が頭の中で組み替えられ、言語化され、自分のものになります。
特におすすめなのは、140文字以内でアウトプットする習慣。
短い文章でまとめるには、「何を伝えるか」を意識しなければなりません。これが論理的思考力や伝達力を高めてくれます。
ちなみに私はフェイスブック派です。
3. 小さく試す(行動に落とし込む)
最後にやってほしいのが、小さなアクションへの変換です。
「情報を知る」→「興味を持つ」→「やってみる」
この最終ステップこそ、知識を資産に変える分岐点です。
ブログを書く、資料を1ページ作る、チーム内で試す…。ほんの些細なことでOK。
ChatGPTのMy GPTを作成するというのも良いでしょう!
小さな一歩が、未来を変えるのです。
行動に移す環境をつくろう
では、どうすれば行動に移しやすくなるのか?
そのカギは「環境設計」にあります。
私がおすすめするのは以下の3つ:
A:タスクを小分けにする
たとえば、資料作成を「50ページ作る」ではなく、
・既存資料から使える20ページを再利用
・残り10ページは外部資料を引用
・新規作成は1〜2ページ
このように分けるだけで、心理的ハードルがぐっと下がります。
B:締切をつくる
人間は締切があると動きます。
「〇月〇日までにブログ1本書く」
「火曜の社内MTGまでに3案提案する」など、自分なりに期限設定しましょう。
C:仲間と共有する
「これ、今週中にやるから見ててね」
「Slackで成果シェアするね」
こうした宣言効果は抜群です。
誰かに見られている、という意識が行動の起爆剤になります。
アウトプットの場を「意図的につくる」
コロナ禍以降、リモートワークが浸透し、人と話す機会が激減しました。
だからこそ、自らアウトプットの場を設計する必要があります。
私にとっては、
・ポッドキャストで毎日発信
・営業先での商談
・ブログ/SNSで都度発信
・勉強会を主催し発表
・講演会/セミナー講師
これらがすべて、実践的アウトプットの場です。
ぜひ皆さんも、「この場で共有してみよう」という自分だけのステージをつくってください。
「行動」を生むマインドチェンジ
最後に、改めてお伝えしたいのは、行動とはマインドのトランスフォーメーション(MX)であるということです。
「めんどくさい」を「やってみよう」に変える。
「失敗が怖い」を「試してみよう」に変える。
この小さなマインドの転換が、大きな成長を生むのです。
生成AI時代には、「考える力」「発信する力」「行動する力」がより一層問われます。
いまこの瞬間から、“知識を採算化”する第一歩を踏み出しましょう。
まとめ:情報は使ってこそ意味がある
情報を「知ってる」で止めない。
この言葉の裏には、「自分を動かす責任は、自分にある」という強いメッセージがあります。
知識は、行動してこそ意味がある。
行動は、習慣化してこそ成果になる。
習慣は、未来を変える。
ぜひ、あなた自身の行動スイッチを押してみてください。
私も、あなたのその一歩を応援しています。
いかがでしたでしょうか?
すこしでもみなさまの気づきになれたのであれば幸いです。
IT・DX教育サービスについてお悩みがある方は、ぜひ初回無料のオンラインコンサルティングをご利用ください。必ずお役に立ちます。
www.certpro.jp/dxconsulting/
生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。
セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。
certpro-generationaiservice.sfsite.me/
キーワードの解説
知行合一(ちこうごういつ)
「知っていること」と「行うこと」は本来一体であり、行動を伴わない知識は真の知ではないという思想。中国・明代の思想家、王陽明が提唱した哲学で、現代の自己啓発やビジネスシーンでも注目されています。特に、リスキリングやDX推進の文脈では、「学びを行動に変える」重要性を説く上で極めて有効な概念です。
インプット症候群
現代において、情報過多の状態に陥り、知識を得ること(インプット)に満足してしまい、実際の行動(アウトプット)に結びつかない現象。特に生成AIや検索技術の進化によって、「知ってるだけ人間」が増加していることが懸念されており、「知識偏重社会」の落とし穴として警鐘が鳴らされています。
アウトプットの場づくり
知識や情報を行動に移すには、それを発信・共有できる「場」の存在が不可欠です。これはオフィスのMTGルームに限らず、SNS、ブログ、ポッドキャスト、営業先など、どこでも構築可能。自らアウトプット環境を設計し、習慣化することで、行動力が飛躍的に高まります。
【著者紹介】
近森 満(ちかもりみつる)
■株式会社サートプロ 代表取締役CEO
IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。
■所属・役職
・IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定、+DX認定、超知性ASI検定)
・一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)
・電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)
・NPO 組込みソフトウェア管理者技術者育成研究会 メンバー(組込み)
・ET教育フォーラム合同会社 代表(コンテンツ制作)
・経済産業省地方版IoT推進ラボ ビジネス創出事業メンター(IoT支援)
・経済産業省地域DX推進ラボ ビジネス創出事業メンター(DX支援)
・デジタル庁デジタル推進委員(デジタル化支援)
・DX事業共同組合 設立理事(DX推進)
・一般社団法人日本サステナブルビジネス機構 幹事(SDGs認証)
・”一億総活躍社会を実現する”共生日本協議会 理事(DEI支援)
・アジャイル開発技術者検定試験コンソーシアム 事務局長(Agile検定)
・一般社団法人国際サイバーセキュリティ協会 事務局長(IACS認定)


