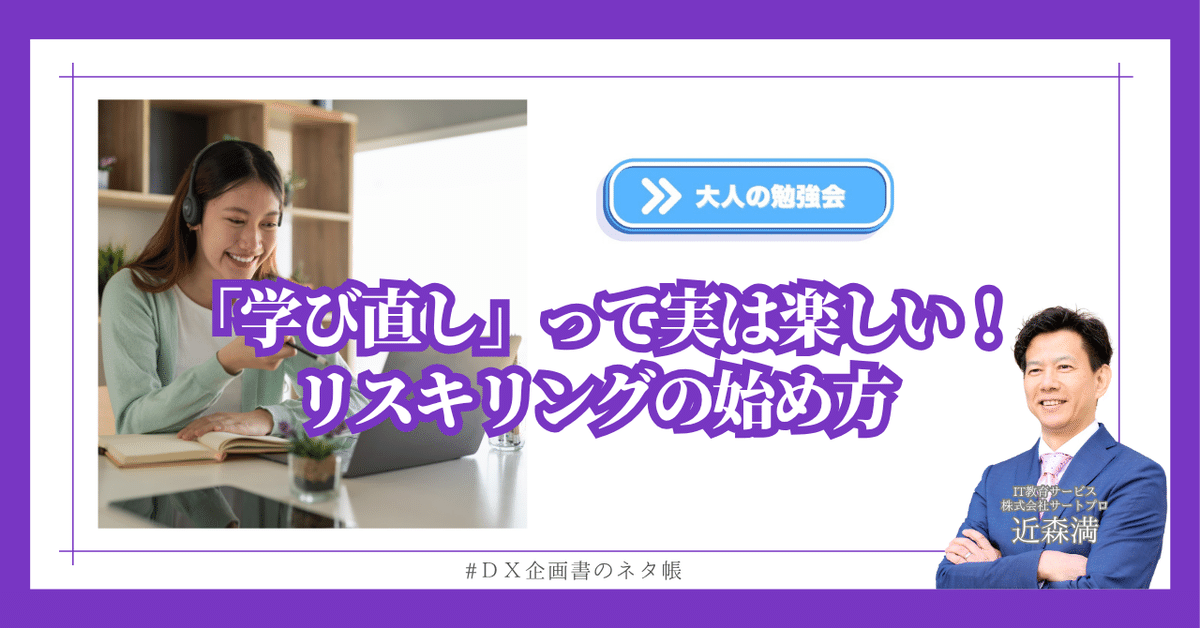
【記事概要】
本エピソードでは、近森満氏が「大人の学び直し=リスキリング」をテーマに、その楽しさと始め方を具体例とともに解説しています。
従来、学び直しは義務感や苦痛を伴うものと思われがちですが、氏は「小さな単位でコツコツ積み上げる」「仲間と一緒に学ぶ(ペアラーニング)」「実践とアウトプットを重視する」など、モチベーションを保ちながら成果を出す方法を提案。生成AIやChatGPTを使った即時アウトプット、短時間集中学習、オンライン・オフラインでの勉強会活用、東京都の無料リスキリング講座(Udemy Business利用)などの具体事例も紹介しています。
また、学び直しの本質を「これまでの職やスキルを手放してでも新たに挑戦する行為」と定義し、アウトプット量をインプット量以上にすることの重要性を強調。ビジネスや社会貢献につなげる視点、夏の時期を活かした室内学習のすすめ、そして「マインド・トランスフォーメーション」による自己変革の必要性を熱く語ります。
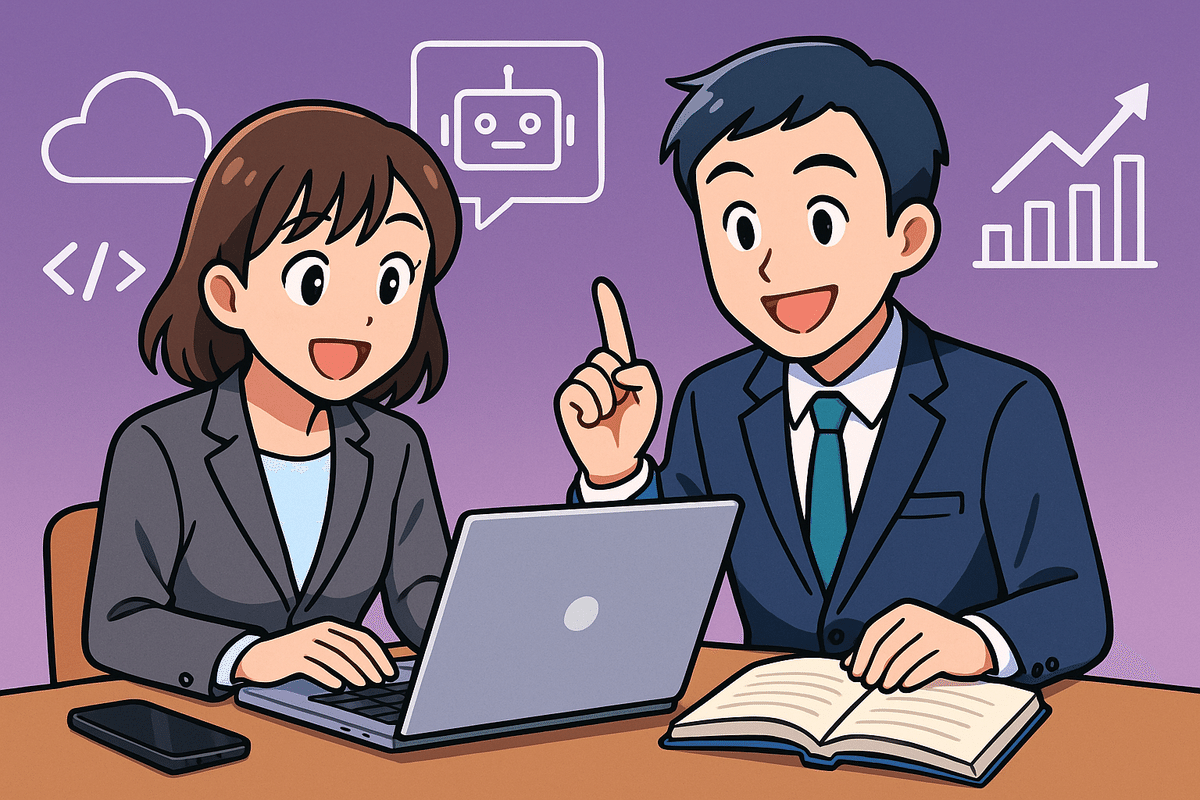
【著者情報】
こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。
www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/
当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。
www.certpro.jp/dxconsulting/
学び直しは苦行じゃない、大人だからこそ楽しめる
「学び直し」と聞くと、なんだか肩に力が入る人も多いでしょう。かつての私もそうでした。学生時代は勉強嫌いで、机に向かう時間は苦痛そのもの。しかし社会に出てからの学びは、義務ではなく自己投資。しかも、やり方次第でめちゃくちゃ楽しくなるのです。最近では経済産業省や総務省が推奨する「リスキリング」という言葉が定着し、DX推進やデジタル人材育成の文脈で使われる機会も増えました。
特に大人の学びは「やらされ感」では続きません。自分が心から面白いと思えるテーマを選び、小さく始めて積み上げることが大切です。興味のある分野は自然と調べたくなり、日常の中で思考が巡ります。これは脳のアドレナリン効果ともいえる現象。ビジネスにも直結する知識やスキルなら、なおさら身につきやすくなります。
ペアラーニングでモチベーションを保つ
一人で黙々と学ぶのも悪くありませんが、人間は社会的な生き物。仲間と一緒に学ぶ「ペアラーニング(ピアラーニング)」は、学びの質と継続力を大きく引き上げます。ソフトウェア開発の現場では「ペアプログラミング」として定着していますが、この考え方は業種や職種を問わず活用可能です。
ペアや小チームで進めると、分からない点を即座に質問できたり、お互いに怠けないよう刺激し合えます。特に若手社員や入社数年目のエンジニアにとっては、社内勉強会やプロジェクト共有会がスキルアップの加速装置になります。責任感の共有、達成感の共有、そしてマインドチェンジを促す相互作用。これは大人にも効果絶大です。
事例: ソフトウェア開発チームのモクモク会
ある開発チームでは、週1回の「モクモク会」を実施。2人ペアでコードレビューや実装を進め、困ったときは即座に相互サポート。結果としてコード品質の向上だけでなく、若手の定着率アップにもつながりました。
小さな単位で積み上げる成功体験
大きな目標をいきなり掲げると、多くの場合は三日坊主になります。例えば「半年で英語のTOEIC満点を取る!」は立派ですが、初動の負荷が高すぎて挫折しがち。おすすめは「5分でできること」を積み重ねることです。
短時間・明確な目的・気軽に取り組める環境があれば、学びは日常に溶け込みます。
例えば私の場合、ChatGPT-5の新機能を試すときは、朝5分で簡単なゲームを生成し、次の10-15分でブログにまとめる。これだけで学びの循環が回り始めます。
生成AIでアウトプットを加速
生成AIは、大人のリスキリングにおける強力なブースターです。特に「インプット即アウトプット」の習慣化がしやすく、試したことを即座に形にできます。私は朝20分でブロック崩しゲームを作り、その制作過程をnoteに投稿するという実験を繰り返しました。これにより、理解が深まるだけでなく、自分の発信がネット上の資産となり、検索エンジンでの存在感も高まります。
オンラインとオフライン勉強会の活用
リスキリングを楽しくするもう一つの鍵は「学びの場」の選び方です。オンライン会議ツール(Zoomなど)を活用すれば、地理的制約なく学べます。逆にオフライン勉強会は、人間関係の構築や偶発的な情報交換に最適です。
事例: 柏市の定期勉強会
私は柏市で2カ月に1回開催される勉強会にオブザーバー兼講師として参加しています。AIや生成AIの最新情報、参加者のプロジェクト事例などを共有。夜は懇親会で交流し、普段接点のない業界の人ともつながれます。ここで得られる学びや刺激は、オンラインでは得がたいものです。
公的リスキリング支援の活用
東京都では、中小企業や個人を対象にした無料のリスキリング講座を提供しています。DX実践人材リスキング支援事業として、Udemy Businessを半年間使い放題で利用でき、AIエージェントや最新DX事例など、数千種類のEラーニングコースを学べます。こうした公的支援は「使えるうちに全力で使う」が鉄則です。
リスキリングの本質は「手放す勇気」
私が考えるリスキリングの本質は、既存のスキルや職を手放してでも、新しい領域に挑むことです。単なる知識の蓄積ではなく、「何かを捨ててでも得る」覚悟が伴う挑戦。それこそがマインド・トランスフォーメーションです。(これは私の勝手な持論です)
アウトプット重視の学び設計
学び直しの成果は、行動として外に出して初めて価値を持ちます。インプット量よりもアウトプット量を多くすることで、知識が実践知に変わります。SNS投稿、社内共有会、ブログ記事、動画解説…手段は何でも構いません。
まとめ:学びを社会価値に転換する
学び直しの最終ゴールは、自分の成長だけでなく、ビジネスや社会への貢献です。得た知識を社内改革に活かし、プロジェクト成功の糧にし、さらには同僚や次世代の人材育成に還元する。これが大人のリスキリングの醍醐味です。
この夏、外出が億劫になる暑い日こそ、室内で新しいことに挑戦してみませんか?学び直しは楽しい、自分を変えるチャンスです。マインドを変え、小さな一歩を積み上げ、そしてアウトプットを社会に投げかける。必ずや未来が開けます。
いかがでしたでしょうか?
すこしでもみなさまの気づきになれたのであれば幸いです。
IT・DX教育サービスについてお悩みがある方は、ぜひ初回無料のオンラインコンサルティングをご利用ください。必ずお役に立ちます。
www.certpro.jp/dxconsulting/
生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。
セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。
certpro-generationaiservice.sfsite.me/
キーワードの解説
リスキリング
リスキリング(Reskilling)は、既存の業務スキルを刷新し、新しい分野や技術に適応するための学び直しを指します。特にDX推進やデジタル人材育成の文脈で重要性が高まっており、AI・クラウド・データ分析などの新技術に対応するために必要です。単なる知識習得ではなく、業務変革やキャリアチェンジを視野に入れた学習が特徴で、公的機関や企業による支援プログラムも増加しています。
マインド・トランスフォーメーション
マインド・トランスフォーメーション(Mind Transformation)は、考え方や価値観を根本から変える意識改革を意味します。新しいスキルを学んでも、従来の発想や行動様式のままでは変革は進みません。DXやリスキリングの成功には、変化を受け入れ、挑戦を恐れない心構えが不可欠です。これは個人だけでなく組織全体の文化改革にも直結します。
生成AI
生成AI(Generative AI)は、文章、画像、音声、プログラムコードなどの新しいコンテンツを自動生成するAI技術です。ChatGPTや画像生成モデルが代表例で、学習や業務効率化、創作活動に広く活用されています。リスキリングの現場では、生成AIを使った実践的アウトプットが短期間で成果を出す鍵となります。特に、インプット直後にアウトプットを行う「即時実践」型学習との相性が良いのが特徴です。
【著者紹介】
近森 満(ちかもりみつる)
■株式会社サートプロ 代表取締役CEO
IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。
■所属・役職
・IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定、+DX認定、超知性ASI検定)
・一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)
・電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)
・NPO 組込みソフトウェア管理者技術者育成研究会 メンバー(組込み)
・ET教育フォーラム合同会社 代表(コンテンツ制作)
・経済産業省地方版IoT推進ラボ ビジネス創出事業メンター(IoT支援)
・経済産業省地域DX推進ラボ ビジネス創出事業メンター(DX支援)
・デジタル庁デジタル推進委員(デジタル化支援)
・DX事業共同組合 設立理事(DX推進)
・一般社団法人日本サステナブルビジネス機構 幹事(SDGs認証)
・”一億総活躍社会を実現する”共生日本協議会 理事(DEI支援)
・アジャイル開発技術者検定試験コンソーシアム 事務局長(Agile検定)
・一般社団法人国際サイバーセキュリティ協会 事務局長(IACS認定)


