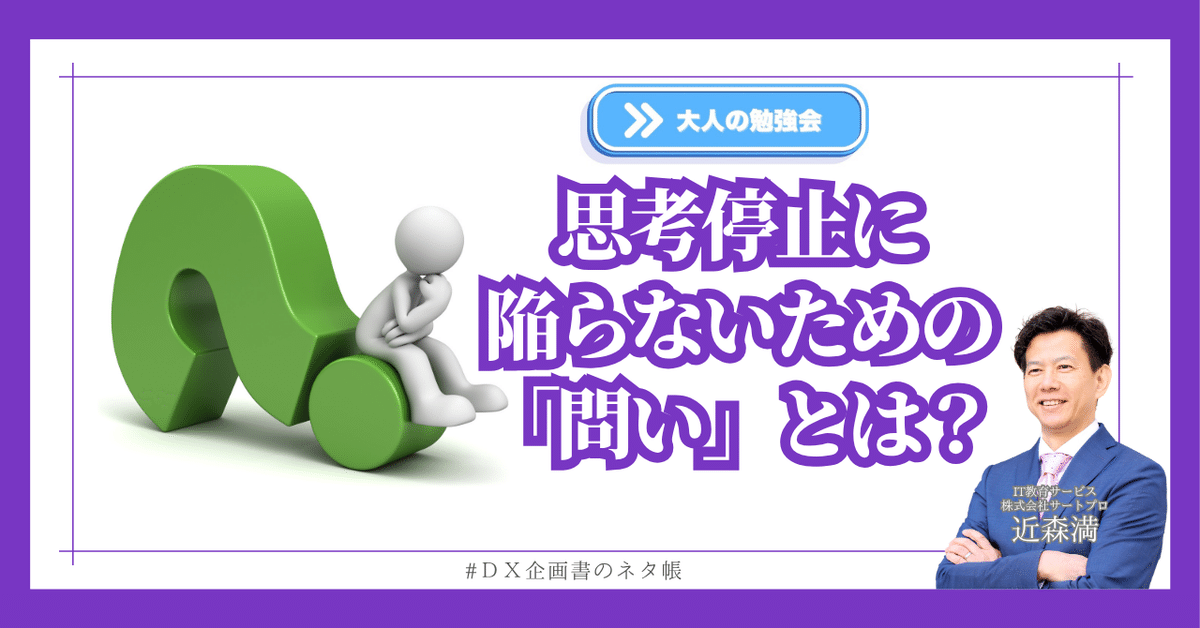
【記事概要】
この記事は、近森満氏による「大人の勉強会:思考停止に陥らないための問いの立て方」という講話を基に、生成AI時代に求められる思考力と問いの技術についてまとめたものです。
生成AI(ChatGPTやGeminiなど)の活用において、適切な問いの設定が成果を大きく左右することを強調します。問いとは単なる質問ではなく、自らの仮説思考を促し、答えのない状況でも思考を止めないための出発点です。幼少期からの「なぜなぜ」や5W1Hの応用、そして雑談や言葉遊びを通じた思考訓練の重要性が語られます。
また、QCサークルやフィッシュボーン分析など製造業で培った分析手法、相手の意見に対して別ルートの仮説を立てる習慣、そして教育モード付きAIとの対話による訓練方法が紹介されています。結論として、思考停止を防ぐ鍵は、唯一絶対の答えに固執せず、多様な視点と仮説を持ち続けるマインドセットの醸成にあるとしています。
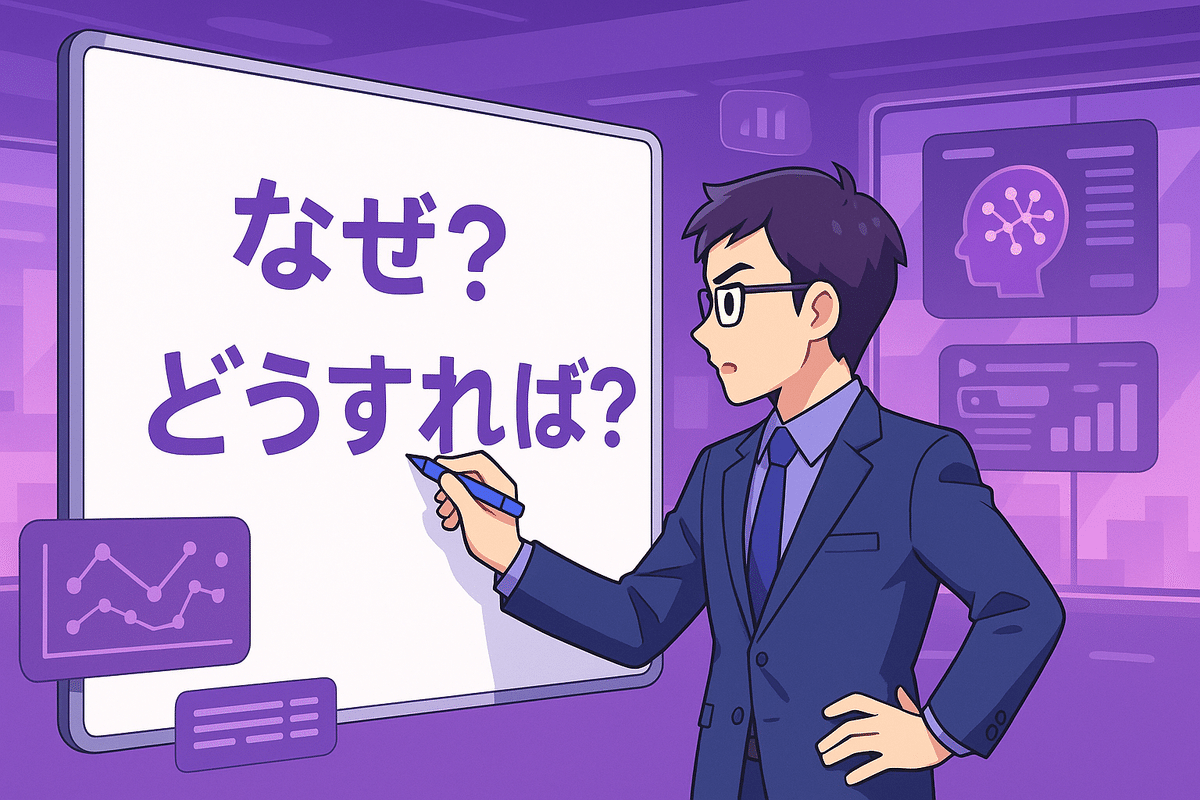
【著者情報】
こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。
www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/
当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。
www.certpro.jp/dxconsulting/
問いが未来を切り開く:生成AI時代の思考停止防止法
私たちが生きるこの時代は、生成AIの急速な進化によって、知識や情報へのアクセスがかつてないほど容易になりました。検索エンジンにキーワードを打ち込めば、答えは瞬時に提示されます。しかし、この便利さの裏には落とし穴があります。それが「思考停止」です。答えをただ受け取るだけの習慣が続くと、自分で考える力が鈍り、いつの間にか「AIに聞けばいいや」という依存状態に陥ります。
ここで重要になるのが「問いの立て方」です。問いは、私たちの思考を動かすエンジンです。良質な問いがあれば、情報探索の質もアウトプットの深さも変わります。
問いの力を理解する
問いは単なる「質問」ではありません。課題を特定するための出発点であり、未来の可能性を開く扉です。例えば「なぜこの課題が発生しているのか?」という問いは、現状の原因を探る思考を促します。一方で「この先、どんな可能性があるのか?」という問いは、未来志向の発想を引き出します。
生成AIを活用する場合、この問いの精度が結果を大きく左右します。AIはあくまで指示に忠実ですから、漠然とした問いには漠然とした答えしか返せません。プロンプトエンジニアリングが重視されるのは、まさにこの理由です。
事例: 麻雀と雑談で磨かれた思考力
私自身、若い頃に麻雀を通じて「問い返す力」と「切り返す力」を鍛えました。牌を選びながら、同時に仲間との会話で笑いを取りに行く。この同時並行のやりとりは、相手の集中を削ぐ戦術であると同時に、瞬時の判断力を養う場でもありました。「こう来たら、こう返す」という訓練の積み重ねは、後のビジネス場面での即応力や仮説構築にも役立っています。
思考停止を防ぐための習慣
人は予期しない状況に直面すると、脳が真っ白になりがちです。これが思考停止の典型です。防ぐためには、日常的に以下の習慣を持つことが有効です。
①多角的な仮説を立てる
相手の意見に同意する前に、「他のルートはないか?」と自問する。
②5W1Hや5W3Hで問いを細分化
誰が、いつ、どこで、なぜ、何を、どうやって、そしていくらで――この整理だけでも問いの質は格段に上がります。
③AIとの対話で壁打ちする
ChatGPTやGeminiの教育モードを使えば、無限に問い返してくれる相手が手に入ります。
製造業で学んだ問いの型
私は製造業出身で、QCサークルやフィッシュボーン分析などの品質改善活動に携わってきました。これらの手法は、本質的には「問いの型」の集積です。原因を徹底的に洗い出し、仮説を検証する。このプロセスは、ビジネスやDX推進にも応用可能です。
事例: QC七つ道具の応用
フィッシュボーン図で要因を分類し、原因を深掘りしていくと、単なる表面的な解決策ではなく、根本的な改善案にたどり着けます。生成AIに問いを投げる際も、この構造的アプローチは非常に有効です。
答えのない世界で生きるために
現代は「答えがないこと」が前提の時代です。VUCAの時代とも言われています。唯一絶対の正解に固執すると、変化に対応できず思考停止に陥ります。だからこそ、自分なりの仮説を持ちつつ、それが間違っている可能性も受け入れる柔軟さが必要です。
マインドセットを変える:マインド・トランスフォーメーション
問いの立て方を変えることは、単なるスキル習得ではなくマインドセットの変革です。特にDX推進に関わる現場では、「前例がないからできない」ではなく、「どうすればできるか」を問い続ける姿勢が求められます。これを私はマインド・トランスフォーメーションと呼びます。
変化に柔軟に対応できる組織は、この問いの文化が根付いています。逆に、問いを立てず、与えられた情報だけで判断する組織は、変化の波に押し流されます。
事例: DX推進プロジェクトでの問い直し
ある製造業クライアントのDXプロジェクトでは、初期設計段階で「本当にこのプロセスは必要か?」という問いを投げかけました。結果、既存業務の30%を削減し、AI活用による自動化の余地を広げられました。問い直しがなければ、そのまま非効率な業務をシステム化してしまうところでした。
デジタル3兄弟とマインド3姉妹
私は講演や研修でよく「デジタル3兄弟とマインド3姉妹」というフレーズを使います。これは、デジタル人材育成に必要なスキルとマインドの両輪を示したものです。
・デジタル3兄弟:DX推進力、AI活用力、データ分析力
・マインド3姉妹:問いを立てる力、仮説を持つ力、柔軟に修正する力
この両方が揃ってこそ、生成AI時代の競争力を持った人材になれるのです。
リスキリングで問いの筋肉を鍛える
リスキリング(学び直し)は単に知識を詰め込む作業ではありません。新しい知識や技術を身につけながら、それをどう使うかを考える――ここに「問いの筋肉」を鍛えるポイントがあります。
例えば生成AIのプロンプト設計を学ぶときも、「どう指示すればAIがより良いアウトプットを返すか?」を自分で試行錯誤する。この試行錯誤こそが、思考停止を防ぐ最大の武器です。
事例: 教育モード付きAIの活用
最近では、GeminiやChatGPTの一部に教育モードが搭載されています。これは、あえて深掘り質問や逆質問を返す機能です。大人の学びにこれを使うと、会議や戦略策定のシミュレーションにもなり、短期間で思考力を磨くことができます。
行動のすすめ:明日からできる問い習慣
①会議で必ず1つは「なぜ?」を投げる
②AIに指示を出す前に、5W3Hで問いを整える
③相手の意見を聞いたら、別ルートの仮説を立てる
④週1回、自分の業務を「ゼロから再設計するならどうするか?」と問い直す
まとめ:答えより問いが価値になる時代
生成AI時代は、「正しい答え」を出す力より、「価値ある問い」を立てる力が評価されます。答えはAIが持ってきますが、その答えの質を決めるのはあなたの問いです。だからこそ、思考停止を防ぎ、問いを鍛え続けることが、DX推進の成功と自分自身の成長のカギなのです。
いかがでしたでしょうか?
すこしでもみなさまの気づきになれたのであれば幸いです。
IT・DX教育サービスについてお悩みがある方は、ぜひ初回無料のオンラインコンサルティングをご利用ください。必ずお役に立ちます。
www.certpro.jp/dxconsulting/
生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。
セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。
certpro-generationaiservice.sfsite.me/
キーワードの解説
生成AI
生成AI(Generative AI)は、テキスト・画像・音声・動画などのコンテンツを自動的に生成できる人工知能の総称です。ChatGPTやGeminiはその代表例で、自然言語処理技術を用いてユーザーの指示(プロンプト)に応じた出力を行います。ビジネスでは文章作成やデータ分析、顧客対応の自動化など幅広い分野で活用が進んでおり、問いの精度がアウトプットの質を大きく左右します。
マインドセット
マインドセットとは、物事の捉え方や考え方の傾向を指します。固定的な思考に固執する「固定マインドセット」と、学びや挑戦によって成長を信じる「成長マインドセット」があり、DX推進やAI活用の現場では後者が不可欠です。新しい技術や変化を前向きに捉え、「どうすればできるか」という問いを持ち続ける姿勢が、変化の時代での競争力を高めます。
リスキリング
リスキリング(Reskilling)は、時代や技術の変化に対応するための学び直しを意味します。新しい知識やスキルの習得だけでなく、それを活用する方法を考える力の醸成も重要です。特に生成AIやデジタル技術分野では、単なる習得ではなく、問いを立て試行錯誤する過程が、思考停止を防ぐ最大の訓練となります。
【著者紹介】
近森 満(ちかもりみつる)
■株式会社サートプロ 代表取締役CEO
IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。
■所属・役職
・IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定、+DX認定、超知性ASI検定)
・一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)
・電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)
・NPO 組込みソフトウェア管理者技術者育成研究会 メンバー(組込み)
・ET教育フォーラム合同会社 代表(コンテンツ制作)
・経済産業省地方版IoT推進ラボ ビジネス創出事業メンター(IoT支援)
・経済産業省地域DX推進ラボ ビジネス創出事業メンター(DX支援)
・デジタル庁デジタル推進委員(デジタル化支援)
・DX事業共同組合 設立理事(DX推進)
・一般社団法人日本サステナブルビジネス機構 幹事(SDGs認証)
・”一億総活躍社会を実現する”共生日本協議会 理事(DEI支援)
・アジャイル開発技術者検定試験コンソーシアム 事務局長(Agile検定)
・一般社団法人国際サイバーセキュリティ協会 事務局長(IACS認定)


