
【記事概要】
本記事は、総務省『情報通信白書』と経済産業省『ものづくり白書』を基に、2025年の日本におけるデジタル活用と製造業の現状・課題・展望を近森満氏の視点で分析した内容です。
前編ではインターネット端末利用やクラウド活用の浸透、端末保有数の増加、シニア層のSNS利用拡大を紹介しつつ、情報信頼性やリテラシー向上の必要性を指摘。中編では生成AI利用率の急増、特に20代の就活・企業調査での活用事例、企業の透明性強化の必要性を論じ、併せて経済安全保障の観点から製造業の国際競争力低下や知財流出リスクを解説。
後編では人材育成・産業融合の重要性を説き、スポーツの世界基準を例にDX推進とマインド・トランスフォーメーション(MX)の必須性を強調。インバウンドを活用した製品・サービス輸出やコンテンツ産業の可能性にも触れ、日本的な「マイペース」型成長戦略と生成AI活用による持続的競争力向上の道筋を提示しています。
【著者情報】
こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。
www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/
当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。
www.certpro.jp/dxconsulting/
デジタル活用の現在地と課題
2025年の日本、インターネット端末利用やクラウド利用は着実に伸びています。SIMフリー端末やWi-Fi専用機の普及で一人当たりの端末保有数は増え、シニア層のSNS利用も拡大しました。
しかし、ネット情報の信頼度はテレビ・新聞を下回り、情報リテラシーやファクトチェック力が求められます。これは単にツールの問題ではなく、使い手のマインドセットの課題でもあります。
令和7年版情報通信白書(概要版)
www.soumu.go.jp/main_content/001019264.pdf
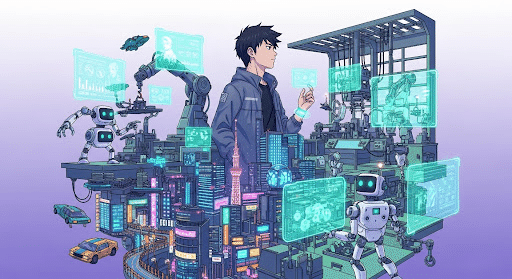
生成AI活用の急伸
生成AIの活用が一気に広がっている――これはもはや“静かなる革命”とも言えます。総務省が2025年7月8日に公表した「令和7年版 情報通信白書」によれば、2024年度に「生成AIを使ったことがある」と回答した日本の個人の割合は26.7%。前年度の約9.1%からほぼ 3倍に増加した衝撃の伸びです。
しかし、この数字を世界と比べると話は別です。中国では81.2%、米国は68.8%、ドイツは59.2%と、日本の数倍という状況。もちろん、20代に限れば日本でも44.7%が生成AIを使っており、世代による温度差が浮き彫りです。
一方、企業の動きを見てみると、導入方針を定めている企業は約50%(2023年の約43%から上昇)にのぼります。それでも、中国や米国、ドイツの水準(活用方針策定率は80–90%以上)には届いていません。特に中小企業ではまだ3割前後にとどまるため、産業規模での温度差が課題です。
このように、日本における生成AIの普及は「急激である一方、依然として慎重」といった二律背反した状態にあります。背景には、「使い方がわからない」「生活や業務に必要性を感じない」といった心理的なハードルも影響しているようです。
事例: 就活生と企業の情報戦
ある大学生は志望企業を生成AIに入力し、評判や社員のSNS投稿、ニュース記事を横断分析。結果、公式サイトにないネガティブ情報も掴み、面接で逆質問としてぶつけました。企業側は回答に窮し、結果的に辞退されるというケースも。情報の非対称性はもはや存在しません。
製造業と経済安全保障
「令和7年版・2025年版ものづくり白書(概要版)」によると、世界の地政学リスクやエネルギー供給不安定化が深刻化する中、日本の製造業は、産業競争力強化・脱炭素・経済安全保障という三本柱を統合して追求する重要性が強調されています。特に「複合的な中長期投資戦略」が不可欠とされているのです。
一方で、経済安全保障への理解はあるが、具体的な取り組みには及ばないという製造事業者が依然として多数を占めます。「聞いたことはあるがイメージできない」という回答が約70%、「実際に取り組んでいない」とする回答も約60%にのぼります。
ただし、いったん取り組みを進める企業では、重点領域として「サイバーセキュリティの強化」「部素材調達先の多元化・変更」が挙げられており、半数以上の企業が対応を開始しています。また、リスク分析の対象も、「自社関連のサプライチェーン」が7割を占め、「自社技術の優位性分析」はまだ少数にとどまっているとの指摘もあります。
こうした状況を受けて、経産省は2025年3月に「民間ベストプラクティス集 第2版」を公表しました。そこでは、経済安全保障対応の好事例として、
①組織体制構築
②技術流出対策
③サプライチェーンリスク対応
という三つの軸で分類し、対応の難易度ごとに整理しています。
また、GX(グリーントランスフォーメーション)の文脈でも製造業はCO₂排出量の大きな割合を占めており、脱炭素と経済安全保障を同時に追うことが求められています。たとえば、鉄鋼業界では「グリーン鉄研究会」を通じ、グリーン鉄の市場拡大を通じた方向性が定められました。
2025年版 ものづくり白書(概要版)
www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2025/pdf/gaiyo.pdf
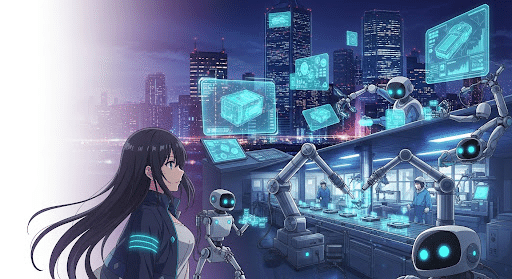
人材育成と産業融合の必要性
スポーツ界が世界基準を意識して育成システムを構築したように、製造業やサービス業もグローバル競争力を前提とした教育が必要です。
インバウンド需要を輸出可能な製品・サービスに転換し、アニメや伝統文化など日本固有のコンテンツをデジタル拡張する動きも重要です。
事例: コンテンツ産業の海外展開
国内で人気の和菓子職人がSNSを通じ海外ファンを獲得。オンライン講座と冷凍配送を組み合わせ、北米や欧州に販路を拡大。単なる輸出ではなく、文化体験を含めたビジネスモデルが成功の鍵となりました。
日本のシティポップが世界で人気
さらに、この文化輸出の潮流は音楽業界でも加速しています。2024年、全世界で日本のシティポップミュージックが再評価され、SpotifyやYouTubeでは70〜80年代の楽曲が国や世代を越えて再生回数を急増させました。海外クリエイターによるリミックスやTikTokでの短尺動画が拡散の起爆剤となり、結果として「日本的ノスタルジア」が世界的なポップカルチャーの一部に組み込まれたのです。
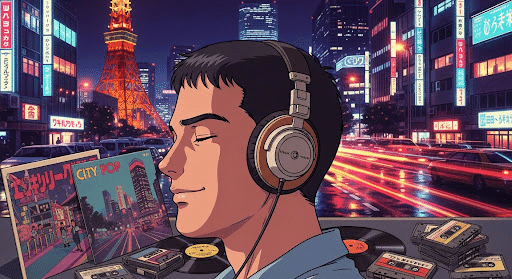
日本のアニメとJーPOPの躍進
そして2025年は、アニメ作品をきっかけに現代のJ-POPが世界的な注目を集めると予測されています。特定のアニメのオープニングやエンディング曲がSNSでバイラル化し、配信プラットフォームでは海外リスナーの比率が過半数を占めるケースも出始めています。音楽単体ではなく、映像・キャラクター・物語と融合した“ジャパンカルチャー・パッケージ”として受容されており、これが日本発ブランドの海外展開に新たな武器となり得ます。

こうした現象は、食品や工芸品、観光業にも応用可能です。音楽と同様に「物」だけでなく、その背景にある物語やビジュアル、体験をセットで届けることで、国境を越えた共感を呼び起こすことができます。
日本的DXの進め方
日本は「二番手・追い込み型」で成果を出す国民性があります。DX推進ではマインド・トランスフォーメーション(MX)が不可欠。生成AIを壁打ち相手に議論力・思考力を鍛え、AGIやASI時代にも対応できる超知性リテラシーを養う必要があります。
まとめ:緩やかでも確実に進むDX
デジタル浸透、製造業再構築、人材育成、国際競争力強化。この4本柱を意識し、企業も個人もスキルチェンジとキャリアパスの再設計を進めるべきです。リスキリングとマインドチェンジが、日本型デジタル・トランスフォーメーションを支える土台です。
いかがでしたでしょうか?
すこしでもみなさまの気づきになれたのであれば幸いです。
IT・DX教育サービスについてお悩みがある方は、ぜひ初回無料のオンラインコンサルティングをご利用ください。必ずお役に立ちます。
www.certpro.jp/dxconsulting/
生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。
セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。
certpro-generationaiservice.sfsite.me/
重要なキーワード解説
DX推進
DX推進とは、単に業務のデジタル化を進めるだけでなく、組織文化やビジネスモデルそのものを変革する取り組みを指します。データとテクノロジーを活用して価値創造を行い、市場や社会の変化に迅速かつ柔軟に対応することが目的です。DX推進には、経営層のコミットメント、現場レベルでのデジタル人材の育成、そして既存業務フローの大胆な見直しが不可欠です。また、進捗を測定するためのKPI設定と成果の可視化が成功の鍵となります。
生成AI
生成AI(Generative AI)は、文章・画像・音声・動画など、多様なコンテンツをAIモデルが自動的に生成する技術です。近年はChatGPTなど自然言語処理モデルの高度化により、ビジネス文書作成やプログラミング補助、マーケティング用クリエイティブ制作まで幅広く活用されています。生成AIを業務に組み込むことで、生産性の向上や新規事業のアイデア創出が可能になる一方、著作権・情報漏洩・倫理面のリスク管理も重要です。適切なガイドライン策定が必須です。
マインド・トランスフォーメーション(MX)
マインド・トランスフォーメーションは、DXや新技術の導入を成功させるために、従業員一人ひとりの意識や価値観を変革するプロセスです。新しいツールやプロセスを導入しても、マインドセットが旧態依然のままでは変化は定着しません。MXでは「変化を恐れず挑戦する文化」「失敗から学ぶ姿勢」「自己成長を続ける意欲」が重視されます。特に生成AIやAGI時代には、柔軟な思考力と学び続ける力が組織競争力の源泉となります。
【著者紹介】
近森 満(ちかもりみつる)
■株式会社サートプロ 代表取締役CEO
IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。
■所属・役職
・IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定、+DX認定、超知性ASI検定)
・一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)
・電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)
・NPO 組込みソフトウェア管理者技術者育成研究会 メンバー(組込み)
・ET教育フォーラム合同会社 代表(コンテンツ制作)
・経済産業省地方版IoT推進ラボ ビジネス創出事業メンター(IoT支援)
・経済産業省地域DX推進ラボ ビジネス創出事業メンター(DX支援)
・デジタル庁デジタル推進委員(デジタル化支援)
・DX事業共同組合 設立理事(DX推進)
・一般社団法人日本サステナブルビジネス機構 幹事(SDGs認証)
・”一億総活躍社会を実現する”共生日本協議会 理事(DEI支援)
・アジャイル開発技術者検定試験コンソーシアム 事務局長(Agile検定)
・一般社団法人国際サイバーセキュリティ協会 事務局長(IACS認定)


