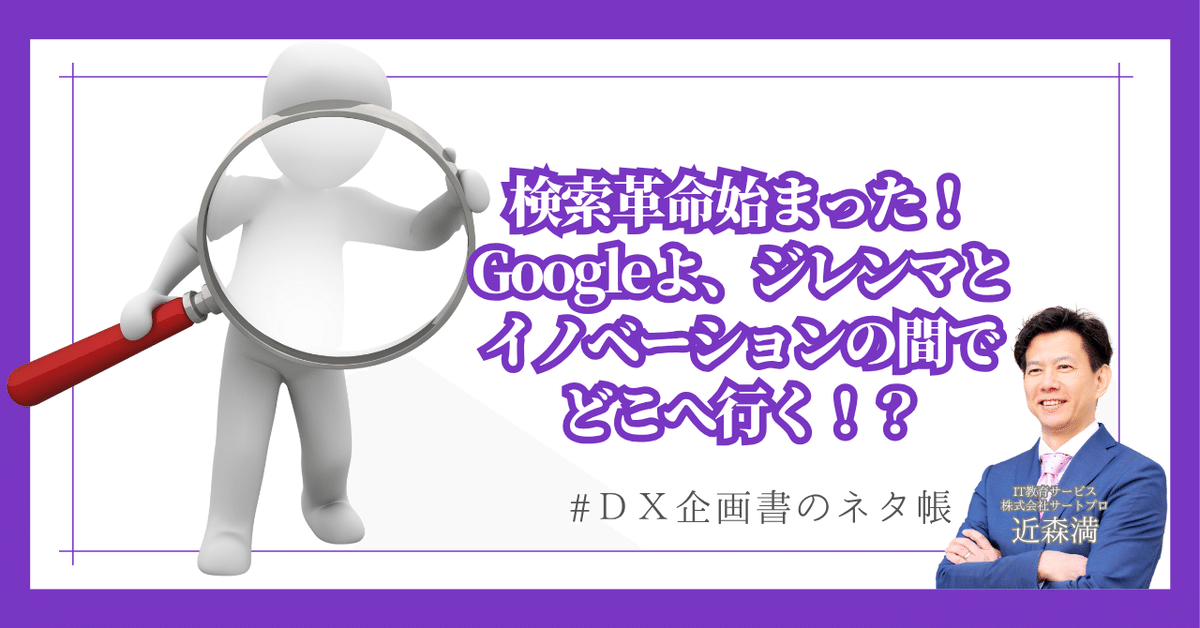
【記事概要】
2025年のGoogle I/Oで発表された最新のAI関連機能を受け、「検索の未来」と「生成AIとの共存」に迫る今回のエピソードでは、Googleの新機能「ジェミニ」と「エージェントモード」などの登場が、従来の検索体験をどう変え、我々の行動様式や情報収集の手段にどのようなインパクトを与えているのかについて、近森満と堀内崇が対談形式で深堀りします。
Googleの検索エンジンにおける生成AIの融合、SEOの在り方の変化、新たな「AIO(AI最適化)」という概念、広告と検索の融合、そして今後のユーザー体験の進化が示唆されており、DX推進やAI活用をテーマとする企業人材戦略における重要なヒントがちりばめられています。
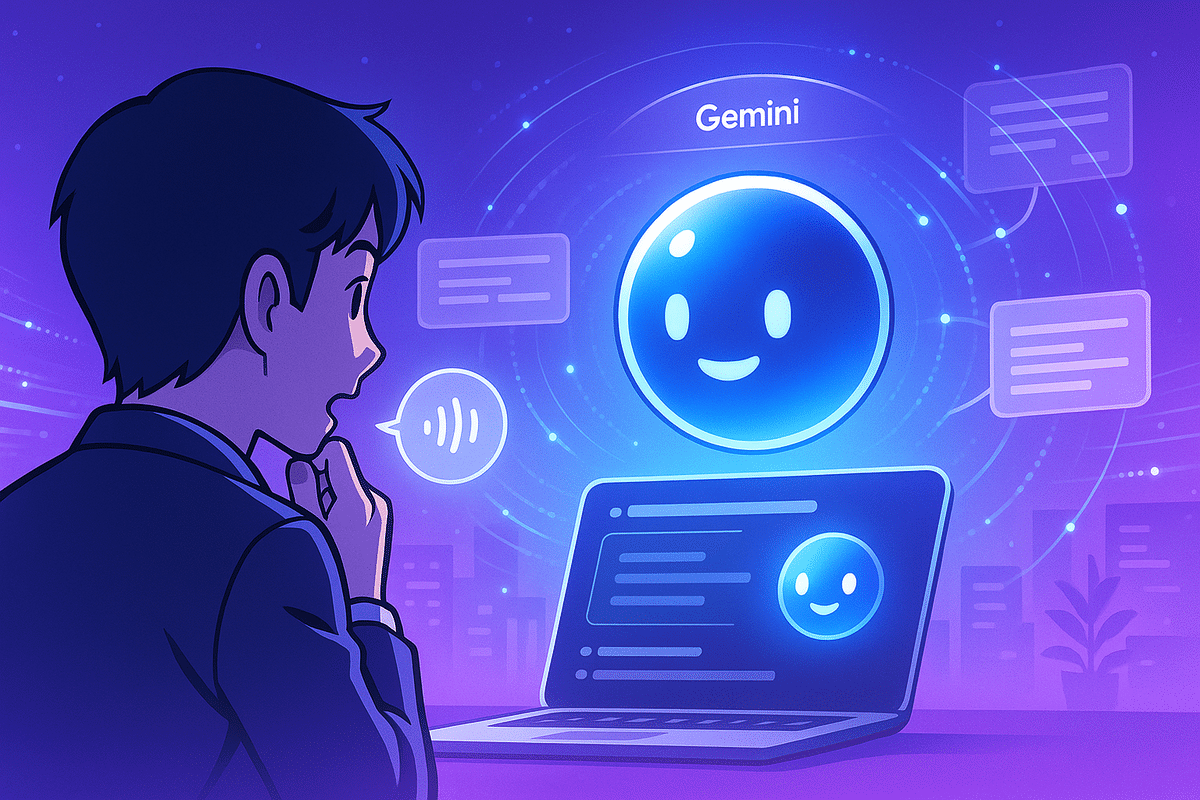
【著者情報】
こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。
www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/
当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。
www.certpro.jp/dxconsulting/
検索から会話へ──GoogleのAI変革は何を意味するのか?
「Googleで検索して調べる」
──この日常が、いままさに変わろうとしています。2025年のGoogle I/Oで発表されたAIエージェント「Gemini(ジェミニ)」や、ユーザーに代わってタスクを実行する「エージェントモード」など、Googleの検索エンジンはかつての“キーワード検索”を超え、“対話による情報探索”のフェーズへと突入しています。
GeminiのAIモードは、従来の検索体験を刷新する可能性を秘めており、ユーザーはもう検索結果一覧をスクロールする必要さえなくなるかもしれません。それは、私たちが慣れ親しんだ検索という行為そのものの再定義を迫る動きなのです。
GoogleとOpenAI──Gemini vs ChatGPTの進化競争
現在、多くのユーザーがChatGPTとGeminiを比較して使うようになっています。私自身も、ビジネス用途ではChatGPT、調査用途ではGeminiを選ぶというように、場面に応じたAIの使い分けが日常となっています。
ChatGPTはカスタマイズの自由度が高く、業務ごとのGPTsの設定が可能な点が魅力です。一方で、GoogleのGeminiはブラウザやGmail、カレンダーといった既存のGoogleサービスと密接に連携しており、自然な形で日常の情報収集を支援してくれます。まるで“人に質問する”かのように、Geminiに話しかけることで必要な情報にたどり着けるのです。
さらに、「エージェントモード」によって、ユーザーの代わりにウェブサイトと対話し、操作まで担うという未来像も実装されつつあります。これはまさに“Webのパーソナル秘書化”であり、AIエージェントが情報検索を代行する時代の幕開けと言えるでしょう。
事例: Google I/Oで発表された「プロジェクトマリナー」
Googleはこの「Project Mariner(プロジェクトマリナー)」において、AIがユーザーの目的に沿ってWebを“自律的に操作”する仕組みを公開しました。単なる検索エンジンではなく、行動支援ツールへの進化です。これはまさに、私たちのDX推進における「業務自動化」や「エージェント思考」と完全に合致するものでした。
プロジェクトマリナー (Project Mariner) とは、Google DeepMindが開発中のAIエージェントで、Chromeブラウザ上でユーザーの代わりにウェブサイトを操作したり、タスクを実行したりする機能を持ちます。
具体的には、以下のような特徴があります。
・ブラウザ操作の自動化:
ユーザーの指示に基づいて、ウェブサイトの閲覧、フォーム入力、クリック、スクロールなど、ブラウザ上での様々な操作を自動で実行します。
・Gemini 2.0基盤モデルの活用:
Googleの最新AIモデルであるGemini 2.0を基盤としており、テキスト、画像、コードなど様々な形式の情報を理解し、処理することができます。
・AIエージェント:
ユーザーの代わりにタスクを実行するAIエージェントとして機能し、複雑なタスクも実行可能です。
・WebVoyagerベンチマーク:
既存のブラウザ操作のベンチマークであるWebVoyagerにおいて、高いスコアを記録しており、実用レベルに達していると評価されています。
・ティーチ&リピート:
ユーザーが一度操作を教えることで、AIがその操作を学習し、類似のタスクを自動で実行できる「ティーチ&リピート」機能を搭載しています。
・同時タスク実行:
最大10個のタスクを同時に実行できるため、複数のタスクを並行して進めることが可能です。
プロジェクトマリナーは、ウェブサイトの操作を自動化することで、ユーザーの作業効率を向上させ、より創造的な業務に集中できる環境を提供することを目指しています。
検索エンジンの終焉?──SEOからAIOへのシフト
これまで、Webマーケティングの世界では「SEO(Search Engine Optimization)」が絶対的な存在でした。しかし今、「AIO(AI Optimization)」という新たな概念が登場しています。
Googleの検索結果では、Geminiが生成するAI要約が一番上に表示されるようになっており、従来のSEO対策によって1位に表示されたコンテンツが実際には“最上段に表示されない”という現象が起きています。結果、検索流入(いわゆるPV=ページビュー)が減少し、サイト運営者にとっては大きなジレンマとなっています。
このような変化は、Google自身が広告モデルの再構築を進めていることとも密接に関係しています。つまり、「検索結果の中でクリックを競う」モデルから、「AIが答える中で“引用される”ことが重要になる」世界へと移行しているのです。
事例: AI要約と引用元リンクの重要性
AIが回答する中で、引用元として取り上げられたサイトは、今後ますます価値を持つようになります。たとえば、医療や法律などのYMYL(Your Money or Your Life)分野では、信頼性と専門性が重要視され、Googleの品質評価ガイドラインでもE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の徹底が求められています。
この引用元への最適化こそが、AIO(AI表示最適化)のコアなのです。
E-E-A-Tとは、Googleの検索品質評価ガイドラインにおける評価基準で、ウェブサイトやコンテンツの品質を評価する際に用いられます。具体的には、「Experience(経験)」「Expertise(専門性)」「Authoritativeness(権威性)」「Trustworthiness(信頼性)」の4つの要素の頭文字を取ったものです。以前はE-A-Tと呼ばれていましたが、2022年12月に「Experience(経験)」が追加され、E-E-A-Tとなりました。
E-E-A-Tは、ウェブサイトやコンテンツが、ユーザーにとって有益で信頼できる情報を提供しているかを判断するための基準です。特に、YMYL(Your Money or Your Life)領域と呼ばれる、お金や健康など、人々の生活に大きな影響を与える可能性のある分野においては、E-E-A-Tが重要視されます。
広告と検索の再定義──マーケティングはどう変わる?
検索がAI要約中心になれば、広告の形も変化します。たとえば、AIが「おすすめのコーヒーメーカー」として紹介する中に「XXメーカーの商品は人気です」と自然に挿入される形での“ネイティブ広告”が増えるでしょう。
また、スマート家電や音声アシスタントが普及するにつれ、ユーザーが声で検索する行動が当たり前になる時代には、視覚的な広告よりも“音声ベースのブランド想起”がより重要になってきます。
このように、企業は広告の「表示順位」を競う時代から、AIが“推薦してくれる”ような情報の構造設計に移行しなければならなくなります。これは、AIに“好かれる”コンテンツ設計の時代です。
事例: Geminiが語る、サートプロの活動
たとえば、「近森満」で検索すると、私の活動内容についてAIが要約で紹介するケースがすでに出始めています。これは検索上位を狙うSEO以上に、「AIに紹介される価値ある情報源」として認識される重要性を示しているのです。
AGI/ASI時代の戦略──企業は何をすべきか?
GoogleがAI技術を検索の中心に据える動きは、単なる技術の進化ではなく、人類全体の知的インフラの進化を示唆しています。AGI(汎用人工知能)やASI(超知性人工知能)の登場が視野に入る今、情報の入口は“人間の問い”から“AIの対話”へと変化しています。
企業にとっては、AIの進化に対して“受け身”ではいられません。
・自社の情報はAIに学習されているか?
・AIに引用されるだけの信頼性があるか?
・AI時代のユーザー体験を設計できているか?
これらの問いに今、真正面から向き合う必要があります。
まとめ:検索革命とAIO戦略
「ググる」から「話しかける」へ。検索という行為は、ただの情報収集から“対話を通じた気づき”へとシフトしています。
そしてこの変化は、企業のマーケティング、コンテンツ戦略、教育、さらにはビジネスモデルそのものをも揺るがす大きな波です。
我々が進めるDX企画においては、
「生成AI時代における検索体験の再設計」
「SEOからAIOへの戦略転換」
「エージェント対応型UX設計」
など、これからのデジタル人材に求められる提案力が問われてきます。
だからこそ今、AIを“使う側”としての発想力とリスキリングが必須なのです。
いかがでしたでしょうか?
すこしでもみなさまの気づきになれたのであれば幸いです。
IT・DX教育サービスについてお悩みがある方は、ぜひ初回無料のオンラインコンサルティングをご利用ください。必ずお役に立ちます。
www.certpro.jp/dxconsulting/
生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。
セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。
certpro-generationaiservice.sfsite.me/
(参考)
Google I/Oにて「AIモード」と呼ぶ機能を検索サービスに追加を発表。これは、いわゆるイノベーションのジレンマなのか?それとも。
日本経済新聞の記事。
Gemini新時代到来。Google I/O 2025 Keynote発表まとめ(ChatGPT研究所)
【キーワードの解説】
AIO(AI表示最適化)
AIO(Artificial Intelligence Optimization)は、従来のSEO(Search Engine Optimization)に代わり注目される新しい最適化手法。GoogleのGeminiなど生成AIが提供する要約コンテンツの中で、いかに自社の情報が「引用元」として選ばれるかを意識した情報設計が求められる。AIOでは、信頼性、専門性、明快な構造、そしてユーザーの検索意図に即した内容が重視される。
ジェミニ(Gemini)
Googleが開発した生成AIで、検索やGmail、ドキュメント、カレンダーなどのGoogleサービスと深く統合されている。会話形式での情報検索や業務補助が可能であり、従来の検索エンジンを拡張する形でユーザー体験を革新している。エージェントモードでは、Web上でユーザーに代わって操作を行う機能も実装予定。
イノベーションのジレンマ
既存の成功モデルに固執する企業が、新しい技術やビジネスモデルを自ら否定してしまうことで成長機会を逃す状況を指す。Googleは検索エンジンという金のなる木を持ちながら、それを破壊しかねない生成AIへ大胆に舵を切っている。この判断は、まさにイノベーションのジレンマに対する正面突破の試みとも言える。
【著者紹介】
近森 満(ちかもりみつる)
■株式会社サートプロ 代表取締役CEO
IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。
■所属・役職
・IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定、+DX認定、超知性ASI検定)
・一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)
・電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)
・NPO 組込みソフトウェア管理者技術者育成研究会 メンバー(組込み)
・ET教育フォーラム合同会社 代表(コンテンツ制作)
・経済産業省地方版IoT推進ラボ ビジネス創出事業メンター(IoT支援)
・経済産業省地域DX推進ラボ ビジネス創出事業メンター(DX支援)
・デジタル庁デジタル推進委員(デジタル化支援)
・DX事業共同組合 設立理事(DX推進)
・一般社団法人日本サステナブルビジネス機構 幹事(SDGs認証)
・”一億総活躍社会を実現する”共生日本協議会 理事(DEI支援)
・アジャイル開発技術者検定試験コンソーシアム 事務局長(Agile検定)
・一般社団法人国際サイバーセキュリティ協会 事務局長(IACS認定)


