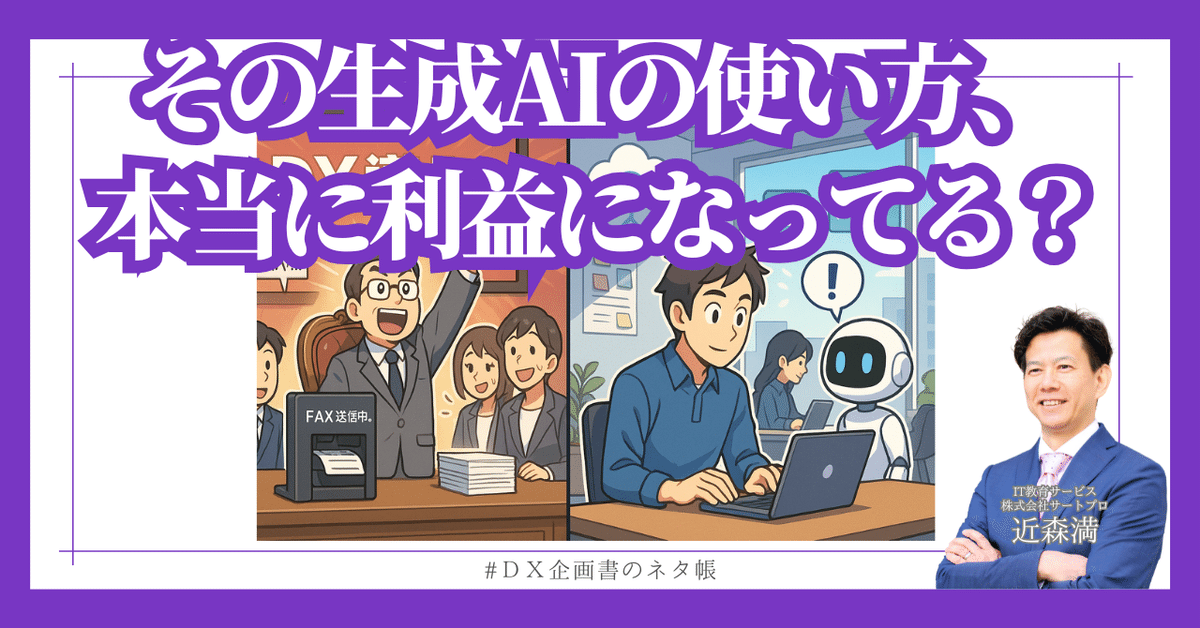
【記事概要】
「生成AIの導入=DX推進」だと勘違いしていませんか?
このエピソードでは、「生成AIの使い方が利益につながっているか?」という挑戦的な問いかけを通じて、形だけの生成AI活用から脱却するためのマインドセットを語ります。ブログや資料作成などの具体的な業務で、生成AIを「自分の不得意を補うツール」として活用し、成果や利益にどう直結させるか。さらに、組織内の関係性や人間性まで含めて、生成AIの“正しい使い方”とは何かを説きます。
「できることをAIに任せて時短」ではなく、「できないことを補完し利益につなげる」発想へ。リスキリングやDXに関心のあるビジネスパーソンにとって、業務改革の視点を大きく変える実践的なヒントが詰まっています。
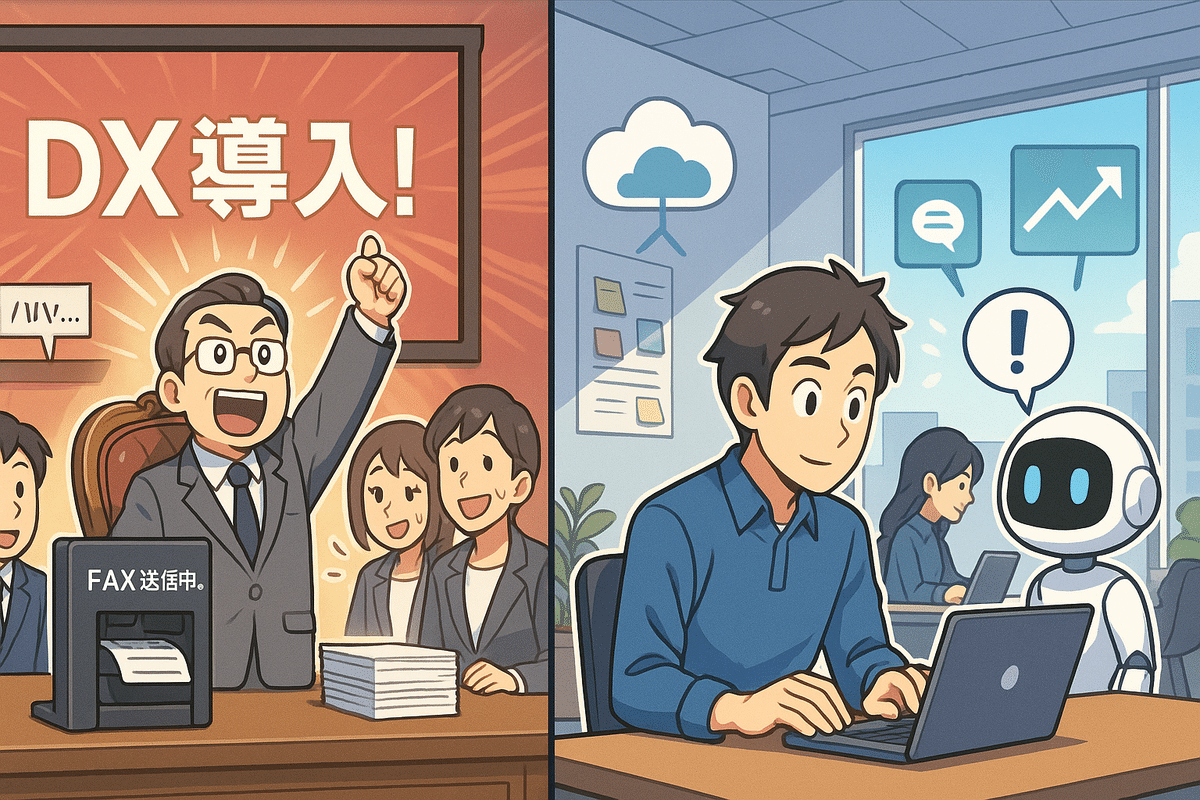
【著者情報】
こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。
www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/
当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。
www.certpro.jp/dxconsulting/
生成AI活用が形骸化していませんか?
「その生成AIの使い方、本当に利益につながっていますか?」
いきなり耳の痛い話からスタートして恐縮ですが、これは今のDX推進現場において非常に重要な問いです。生成AIがもたらす可能性に期待して導入したものの、「便利にはなったけど、結局業績や収益には何も影響していない」という企業、結構多いんじゃないでしょうか?
実際、私の周囲でも「AIに仕事を奪われた」という話を耳にします。でも、本当にAIに奪われたのか、それとも自らAIを活用して利益に変える努力を怠っただけなのか、その点を見直す時期に来ていると感じます。
生成AIは、文章生成や画像作成など、以前なら専門職が担っていた業務(すべてではない)を代替・補完してくれるパワフルなツールです。しかしその力を活かすには、「どう使うか」だけではなく「何のために使うか」まで考えなければなりません。
AIを「自分の不得意を補完する道具」として使う
私はこの音声配信を毎日更新していますが、もともとブログを書くのがとても苦手でした。文字起こしも然り。文章を整えてブログにするには、以前はゴーストライター的な方にお願いしていました。
ですが今は違います。自分の話した音声を文字起こしし、生成AIでリライトし、それを最終的に自分の手で仕上げています。これはまさに、「自分の不得意を補完する生成AIの活用」です。
生成AIの導入で作業効率が上がるのは当然のこと。しかし、単なる「効率化」ではなく、それが実際の成果(売上や受注の増加)につながるかが鍵です。
たとえば、月に1本しか書けなかったブログ記事が、AIのおかげで2本、3本と書けるようになる。結果として、顧客からの問い合わせが増え、新しい案件を受注できる。これこそが「利益を生む活用」です。
事例: 自分が書けなかったブログを生成AIで量産
過去には、音声収録後にそのまま放置していた音源が大量にありました。放置と言ってもインターネット上に置かれた資産として考えればそれで良かった訳ですが、一流の人はその「ネタをコスる」ことで最大化しているのです。それができていないのであれば、いわば“お蔵入りコンテンツ”です。しかし、生成AIを使い出してからは、それらを次々とコンテンツ化できるようになりました。コスれるようになったのです。
その結果、ブログの更新頻度が大幅に上がり、検索流入も増え、講演や研修の問い合わせが倍増しました。これは明確に「利益につながる活用例」だと思っています。
利益とは「数値化できる成果」である
ここであらためて考えたいのは、「利益」とは何かということです。
多くのビジネスパーソンにとって利益とは「売上−コスト」ですよね。生成AIの活用が、コスト削減や業務効率化だけで終わってしまっていては本末転倒です。もちろん「コスト削減や業務効率化で利益はあがるでしょ?」その通りです。これまでであればそれで良かったのですが、生成AIは社会のインフラになりつつ有り、単に「コスト削減や業務効率化で利益はあがる」は競争の源泉ではありません。
AIを課金して使っているなら、その分の投資に対して売上や受注、顧客満足度の向上といったリターンがなければ赤字(と想定)です。
私が以前放送で話したことがあります。
「自分でできる仕事を生成AIにやらせてるのは負け」
「でも、自分ができない仕事を生成AIにやらせないのはもっと負け」
つまり、AIは「自分ができないことを可能にする道具」なのです。
特に教育分野では、講師の方々がAIを使って効率的にテキストや資料を整備することも増えています。大歓迎です。なぜなら、時間をかけずに高品質な教材を作れれば、結果的に受講者の満足度や成果につながり、それが企業の評価・リピート受注につながるからです。
講師は本来の目的として生徒にわかりやすく教える、またわからないところをフォローアップすることに集中し、誰でもできるコンテンツ作りをAIに任せたに過ぎません。
生成AI活用で社内の空気を壊していないか?
一方で、生成AIの導入によって職場に不協和音が生まれるリスクもあります。
たとえば、同僚が時間をかけてやっていた作業を、自分だけ生成AIで効率化して一気に終わらせたとしましょう。それが会社全体の利益になれば良いですが、「出しゃばり」「あの人だけズルしてる」なんて空気が生まれたら、職場の雰囲気は悪化します。
生成AIの活用は、あくまでもチームのパフォーマンスを引き上げる目的で行うべきです。個人の成果だけを追求すると、組織としてのバランスを崩すことになりかねません。
事例: 他人の仕事をAIで奪ってしまった場合の弊害
過去、ある研修現場で、スタッフがAIで自動生成したテキストを提出したところ、他の講師陣から「あれって俺たちの仕事だよね?」と疑念が噴出。
結果として、社内に微妙な空気が流れ、チーム運営に支障が出ました。
生成AIの力は強力ですが、使い方を間違えると信頼関係にヒビが入る。このことは忘れてはいけません。
余談ですが。。。
人がよれば「うらみ つらみ ねたみ そねみ いやみ ひがみ やっかみ」は常についてまわる「職場の花(皮肉)」です。
心理的安全性のため、ぜひコントロールし回避しましょう!
「便利」ではなく「価値」を生む使い方へ
生成AIは間違いなく便利です。しかし、便利なだけでは利益にはならない。価値を生まなければ意味がありません。
ここで言う「価値」とは、
・業務スピードが上がり、案件を複数こなせるようになった
・クオリティが上がって顧客満足度が上がった
・新たなサービスやコンテンツを生み出せるようになった
など、「行動」や「数字」で示せる変化です。
生成AIは「未来を創るための道具」です。「なんとなく使っている」状態から、「目的を持って使い倒す」状態へシフトする必要があります。
自分が変わる。未来が変わる。
「過去と他人は変えられない。自分と未来は変えられる。」
これは私が常に大切にしている言葉です。生成AIがこれだけ身近になった今こそ、「自分がどう変わるか」が問われているのです。
自分が変わらなければ、生成AIを活用しても何も変わらない。変えるのはツールではなく“自分の使い方”なのです。
生成AIを活用するには、単に操作方法を学ぶだけでは不十分です。ビジネス視点で成果を考えられるマインドセット=超知性リテラシーが必要です。
まとめ:生成AI活用=利益創出の公式を持て
今回の内容は、DX企画書のネタにも直結します。以下がポイントです:
・生成AIの活用は「自分が苦手な業務」に使うことで最大化される
・利益とは、「成果が数字として可視化されること」
・AIは便利ではあるが、活用が価値創出に結びついていないなら再考すべき
・社内の信頼関係とバランスも考慮して、戦略的に導入すべし
「便利だった」ではなく「売上が伸びた」「顧客が増えた」というレベルまで使い倒すこと。これが、生成AI時代のDXに求められる姿勢です。
いかがでしたでしょうか?
すこしでもみなさまの気づきになれたのであれば幸いです。
IT・DX教育サービスについてお悩みがある方は、ぜひ初回無料のオンラインコンサルティングをご利用ください。必ずお役に立ちます。
www.certpro.jp/dxconsulting/
生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。
セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。
certpro-generationaiservice.sfsite.me/
【著者紹介】
近森 満(ちかもりみつる)
■株式会社サートプロ 代表取締役CEO
IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。
■所属・役職
・IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定、+DX認定、超知性ASI検定)
・一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)
・電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)
・NPO 組込みソフトウェア管理者技術者育成研究会 メンバー(組込み)
・ET教育フォーラム合同会社 代表(コンテンツ制作)
・経済産業省地方版IoT推進ラボ ビジネス創出事業メンター(IoT支援)
・経済産業省地域DX推進ラボ ビジネス創出事業メンター(DX支援)
・デジタル庁デジタル推進委員(デジタル化支援)
・DX事業共同組合 設立理事(DX推進)
・一般社団法人日本サステナブルビジネス機構 幹事(SDGs認証)
・”一億総活躍社会を実現する”共生日本協議会 理事(DEI支援)
・アジャイル開発技術者検定試験コンソーシアム 事務局長(Agile検定)
・一般社団法人国際サイバーセキュリティ協会 事務局長(IACS認定)


