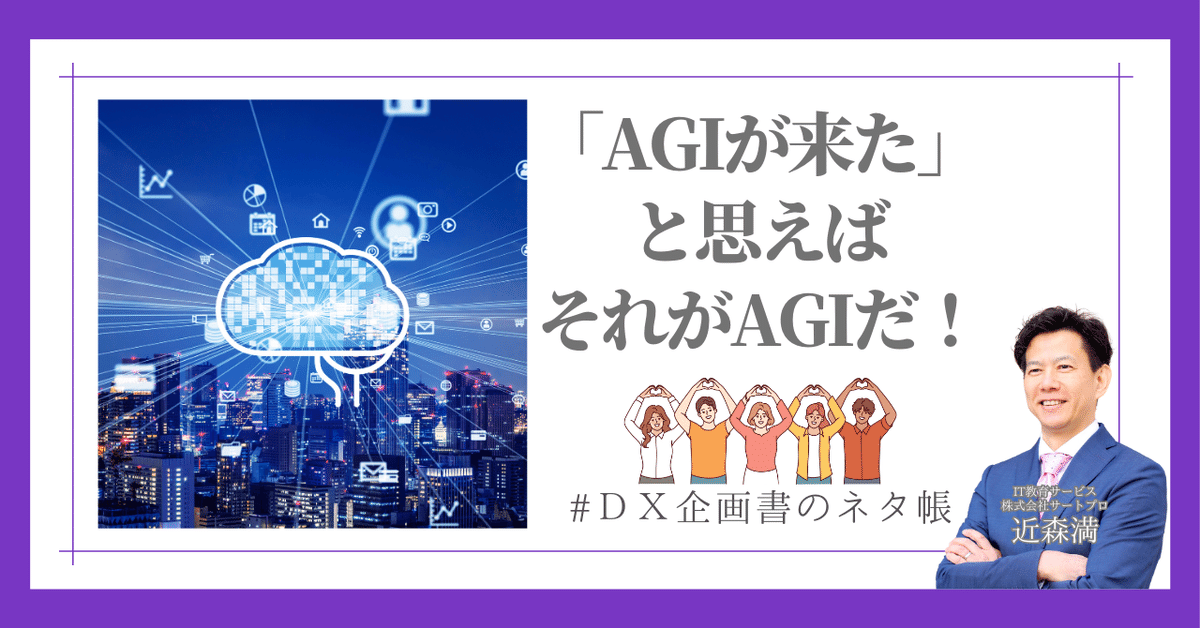
【目次】
- AI研究者24%が「来ると思えば、それはもう来ている」──思考の起点はそこにある
- AGIに対する76%の“懐疑”と、24%の“確信未満”の確信
- 「来るか来ないか」ではなく「もう来たと思うかどうか」が本質
- 超知性ASIの時代をどう迎えるか──リテラシーと準備が鍵
- 人間こそが“アップデートされるべき”である
- まとめ:AGIは「定義」ではなく「受容」の産物
【本文】
こんにちは、IT・DX教育サービスの株式会社サートプロ 近森満です。
www.certpro.jp/blogs/dx_chikamori/
当社では「DX推進人材教育プログラム」として初回無料のコンサルティングを提供しています。DX推進や人材育成のご相談をお待ちしています。
www.certpro.jp/dxconsulting/
AI研究者24%が「来ると思えば、それはもう来ている」──思考の起点はそこにある
「AGI(汎用人工知能)は76%の研究者が“まだ来ない”と言っている──でも24%の人が“もう来ている”と思っていれば、それがAGIなんだ。」
私がこの言葉を口にしたとき、誰もが「ん?」という顔をしました。けれど、これは私の中では確信に近い言葉なんです。未来とは予測するものではなく、受け入れる準備ができているかで決まる。マイノリティや確率ではなく解釈の問題なんです。
先日発表された、国際AI研究団体「AAAI(トリプルAI)」による調査レポート(2025年3月)では、76%の研究者が「現在の生成AI(大規模言語モデル)の延長線上ではAGIは実現しない」と回答しています。しかし、残りの24%は「可能性がある」と考えている。
では、この24%の視点から未来を見てみたらどうなるか? その思考の旅が、この記事のテーマです。
AGIに対する76%の“懐疑”と、24%の“確信未満”の確信
AAAIの調査では、他にも興味深いポイントが示されています。
・回答者の82%が「AGIは公的所有で管理すべき」と主張
・70%が「安全性への懸念があっても開発中止には反対」
・76%が「今の技術のスケールアップではAGIは困難」と回答
これらの数値は、AGIへの慎重論の広がりを示すと同時に、倫理と技術のバランスをどう取るかという命題が、研究者たちの中に明確に根づいている証でもあります。
けれど、私が注目したのはそこではありません。「今の技術でもいける」と考える24%の存在です。この24%は、実現可能性に賭けているというより、すでに“AGI的な存在”を見ている人たちなのかもしれません。
この「見えるか見えないか」「信じるか信じないか」の違いが、人間の創造性の起爆剤になると、私は考えています。
事例: イーロン・マスクの「X」買収は、AGI時代の先手だった?
AGIはモデルの性能だけでなく、情報との接続性が鍵を握る。だからこそ、イーロン・マスクがxAIを立ち上げ、「X」(旧Twitter)を“買収ではなく等価交換”で得たことが象徴的なんです。
ある東京大学の教授に聞いたところ、「人間は常に“最新”を求めている」とのこと。1分前の情報でさえ古い。そんな今において、SNSはリアルタイム情報の供給源であり、生成AIが知性を磨くためのデータ源としては最高です。
つまり、マスク氏は「AGIに必要なのは計算力より情報吸収力だ」と見抜いていたのかもしれません。そしてその情報源を、プラットフォームごと押さえにいった。これはまさにAGIへの布石──そしてASI(超知性)の土台づくりでもあります。
「来るか来ないか」ではなく「もう来たと思うかどうか」が本質
この話、実は量子力学にも通じます。観測することで状態が決まる──つまり、「来た」と思えばAGIは現実化する。
過去を見ても、こういった「未来予測」は常に疑問符がつけられてきました。
・スマートフォンが誰にでも持てるようになる?
・自動運転車が市街地を走る?
・音声だけで文章が書ける?
どれも、10年前なら「そんな未来、来るわけがない」と笑われていたはずです。
でも、いま私たちはその「来るわけがない世界」の真っただ中にいます。
超知性ASIの時代をどう迎えるか──リテラシーと準備が鍵
AGIの先に待つASI(Artificial Super Intelligence=超知性ASI)は、私たちの予想をはるかに超えるスピードで進化していくと考えられます。
ASIとは、人間をはるかに上回る知性を持つAIのこと。
AGIが“人間並み”の知性なら、ASIは“人間超え”の知性です。
この段階で必要になるのが、「超知性リテラシー」。
つまり、AIとどう向き合うか? AIをどう使い、どう共存するか?という姿勢とスキルです。
生成AIやAGIは、技術ではなく社会の受け止め方=文化的合意によって形づくられていく。
だからこそ、今求められているのは技術論よりもマインドセットと準備なのです。
事例: エッジAI×6Gが拓く「分散型知性」の未来
現在進行中の6G(第6世代通信規格)の到来によって、私たちは「どこでも、いつでも、誰でも」超高速・大容量・低遅延で情報を処理・共有できる時代に突入します。
すると、どうなるか?
・IoTデバイスがリアルタイムで知能を持つ
・スマートウォッチやカメラが小さなAIとして判断する
・その情報がクラウドにアップされ、集合知が即時進化
つまり、「集中型AI」から「分散型知性」への移行が起こるわけです。
この流れの中でAGIやASIは、単なる技術ではなく、「社会システムそのもの」になっていくと私は見ています。
人間こそが“アップデートされるべき”である
最後に一番伝えたいことがあります。
**人間は日々進化している。ならば、最も進化するAGIは人間自身ではないか?**ということ。
「生成AIはすごい」
「AGIは来るかも」
「ASIが来たら人間終わるかも」
そうやって怯える前に、人間こそがアップデートされていくべき。
そして、自分自身の行動や学びが「知性」になっていくのだと気づくことが必要です。
私はユーザーであって開発者ではありません。でも、この変化の時代に立ち会えることにワクワクしています。
後悔しないように、備える。
知性を磨く。
変化に柔軟に対応する。
それが、AGI時代を生き抜く人間の“スキルセット”になると信じています。
まとめ:AGIは「定義」ではなく「受容」の産物
・AGIは技術的定義を超えた“社会的合意”で決まる
・イーロン・マスクの動きは、情報プラットフォームの取り込みによるAGI・ASI戦略の先手
・超知性リテラシーがこれからの教育・研修に不可欠
・人間自身が“進化するAGI”として、自らをアップデートするマインドが必要
いかがでしたでしょうか?
すこしでもみなさまの気づきになれたのであれば幸いです。
IT・DX教育サービスについてお悩みがある方は、ぜひ初回無料のオンラインコンサルティングをご利用ください。必ずお役に立ちます。
www.certpro.jp/dxconsulting/
生成AI導入を検討させている方は、こちらもご覧ください。
セキュリティから活用方法まで、サポートさせていただきます。
certpro-generationaiservice.sfsite.me/
【著者紹介】
近森 満(ちかもりみつる)
■株式会社サートプロ 代表取締役CEO
IT技術者の教育支援と人材育成を専門とする事業化コンサルタントとして、2006年に株式会社サートプロを創業し、IoT検定、+DX認定、アジャイル検定などの資格制度を創出。独自の技術者向け教育研修の開発に定評があり、実践的なスキル向上を支援。経済産業省DX推進ラボおよびIoT推進ラボのメンターとして、自治体や中小企業のDX推進を支援。近年は超知性ASIスキル可視化にも取り組み、次世代技術の普及に注力している。
■所属・役職
・IoT検定制度委員会 事務局長(IoT検定、+DX認定、超知性ASI検定)
・一般社団法人 IT職業能力支援機構 理事長(Android資格)
・電気・電子系技術者育成協議会 副理事長(E検定)
・NPO 組込みソフトウェア管理者 技術者育成研究会メンバー(組込み)
・ET教育フォーラム 合同会社 代表(コンテンツ制作)
・経済産業省 地方版IoT推進ラボビジネス創出事業メンター(IoT支援)
・経済産業省 地域DX推進ラボビジネス創出事業メンター(DX支援)
・デジタル庁 デジタル推進委員(デジタル化支援)
・DX事業共同組合 設立理事(DX推進)
・一般社団法人 サステナブルビジネス機構 幹事(SDGs認証)
・”一億総活躍社会を実現する”共生日本協議会 理事(DEI支援)
・アジャイル開発技術者検定試験コンソーシアム 事務局長(Agile検定)


